 論文紹介
論文紹介 デジタルサービス法(DSA):EUの偽情報対策が米国に示す道筋
EUのデジタルサービス法(DSA)と米国における適用可能性を分析した論文を紹介。国際的な偽情報対策の方向性を明らかにします。
 論文紹介
論文紹介  偽情報対策全般
偽情報対策全般  偽情報対策全般
偽情報対策全般 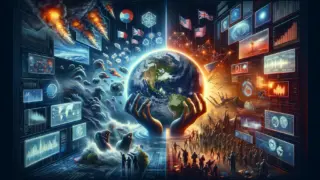 偽情報対策全般
偽情報対策全般  論文紹介
論文紹介  偽情報対策全般
偽情報対策全般  情報操作
情報操作  ファクトチェック
ファクトチェック  情報操作
情報操作  情報操作
情報操作