 健康
健康 フランス政府、健康偽情報対策の包括戦略を策定――270名への大規模調査が示す構造的脆弱性と9つの勧告
フランス保健省に提出された健康偽情報対策報告書(2026年1月)。薬理学・疫学・医学雑誌編集の専門家3名が270名へのインタビュー調査を実施。Info-Score Santé(情報源評価システム)、インフォビジランス、科学者保護など9つの勧告を提示。53%の若年層がSNS主要情報源という実態と構造的脆弱性を分析。
 健康
健康  偽情報対策全般
偽情報対策全般  偽情報対策全般
偽情報対策全般  ジェンダー
ジェンダー  偽情報対策全般
偽情報対策全般  偽情報対策全般
偽情報対策全般  偽情報対策全般
偽情報対策全般  偽情報対策全般
偽情報対策全般 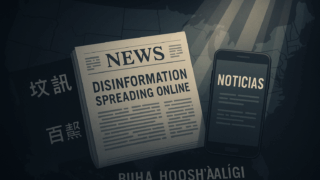 偽情報対策全般
偽情報対策全般 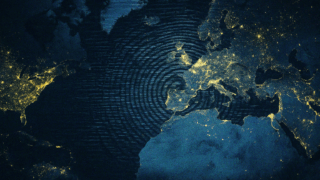 偽情報対策全般
偽情報対策全般