オーストラリアでは2024年に「Combatting Misinformation and Disinformation Bill」が提出され、規制当局ACMAがプラットフォームに対して直接的に規制を行う枠組みが検討された。だが、この法案は「言論の自由を不当に制限する」という批判を受けて撤回された。
その代替として注目を集めるのが、業界団体DIGI(Digital Industry Group Inc.)が主導する自主規制の「Australian Code of Practice on Disinformation and Misinformation(ACPDM)」である。Adobe、Apple、Google、Meta、Microsoft、TikTokなど主要企業が署名しており、2025年のレビューでは、この自主規制をどう強化すべきかが焦点になった。
定義の核心──misinformationを含めるか
ACPDMは発足当初、組織的に仕組まれた「disinformation」のみを対象としていたが、公開協議と規制当局からの要請を受けて「misinformation」も加えた経緯がある。
- disinformation:AIやボットなどの不正行為を伴い、意図的に虚偽情報を拡散するもの。
- misinformation:一般ユーザーが善意で拡散する虚偽情報。意図は必須ではない。
この線引きは一見明快だが、実際にはきわめて難しい。例えば、ある情報が虚偽かどうかは政治的立場によって認識が分かれることが多い。また、研究によれば偽情報に日常的に接している人は少数にとどまる可能性も指摘されている。レビュー文書は、こうした研究知見を踏まえ、誤情報を引き続きスコープに含めるべきかを問い直している。もし「misinformation」を外すとなれば、規制対象はAI生成コンテンツやボットによる組織的操作といった「測定可能な領域」に限定されることになる。
透明性報告──「比較できない数字」という課題
ACPDMに署名するプラットフォームは、年に一度「透明性報告」を提出することが義務付けられている。そこには、どのようなポリシーで誤情報に対処しているか、ユーザーからの報告はどう処理されているか、拡散抑制のためにどんな手段が使われているかが書かれる。
しかし大きな問題は「各社の報告が比較できない」ことだ。サービスの種類や対策の手法があまりに違うため、共通の指標が作れない。レビュー文書は、これを正直に「ハード・プロブレム」と表現している。
改善に向けて挙げられた論点は以下のようなものだ。
- オーストラリア市場に関する長期トレンドを示す
- 各社のポリシー変更を明確に記録する
- 数字が毎年一貫して追跡できるようにする
- AI生成・改変コンテンツへの対応をきちんと説明する
このような改訂が行われなければ、透明性報告は「企業による自己宣伝」にとどまり、信頼性を持たなくなる危険がある。レビューは、あくまで数字の羅列ではなく「意味のある説明」にすることを求めている。
苦情処理──市民の声は届いているのか
ACPDMのもう一つの特徴は、一般市民が「企業がコードを守っていない」と感じた場合に苦情を申し立てられるポータルを設けていることだ。ただし対象は「個々の投稿」ではなく「企業の行動」である。つまり「この投稿が嘘だ」という訴えではなく「企業が約束を守っていない」というレベルでの申し立てに限定されている。
2021年の設立以来、96件の苦情が寄せられたが、実際に「コード違反」と認定されたのはわずか2件。市民からすると「声を上げても無駄ではないか」という印象になりかねない。規制当局ACMAも「各社のコミットメントを誰でも理解できる形で可視化すべきだ」と指摘しており、ポータルの使いやすさや説明責任の向上が重要な課題として浮上している。
メディアと広告──プラットフォーム以外の責任
これまでのコードは主に大手プラットフォームを対象にしてきたが、レビュー文書は「メディアや広告産業にも責任を広げるべきではないか」と問題提起している。
象徴的な事例として挙げられたのが2024年4月のBondi Junction事件だ。事件発生直後、テレビ局が誤認報道を流し、その映像クリップがソーシャルメディア上で急速に拡散した。誤報を出したのはメディアであり、拡散の一翼を担ったのは視聴者自身だった。
この例は「偽情報のエコシステム」において、プラットフォームだけでなくメディアや広告も重要な役割を果たしていることを示す。従来の自主規制は放送領域を中心に設計されており、オンライン配信までカバーしていない。レビューは、このギャップを埋める必要があると強調している。
ガバナンス──運営委員会の独立性
ACPDMの運営委員会は、署名企業4社と独立委員3名で構成され、透明性報告の点検や苦情処理の監督を担っている。しかし、企業の影響が強すぎるのではないかという批判もある。レビューでは、委員構成をどう独立させるか、専門的知見をどう取り込むか、会議の透明性をどう高めるかといった論点が提示されている。これは単なる形式的な問題ではなく、コード全体の信頼性を左右する核心的な論点である。
国際比較──オーストラリアだけの問題ではない
オーストラリアの課題は孤立したものではない。EUの偽情報コードでも「共通メトリクスをどう設計するか」が最大の難題となっている。各国で「誤情報を含めるか否か」という議論も同様に起きている。
オーストラリアのレビューは、AI生成コンテンツや操作的行為をどう扱うかという国際的な課題に直結している。つまり、ここでの決定は世界の議論にも波及する可能性がある。
結論──偽情報の「定義」をめぐる社会的選択
今回のレビューが示すのは、単に規制を強化するか緩めるかという話ではない。むしろ「何を偽情報と呼ぶのか」「誰がその責任を負うのか」という社会的な選択のプロセスである。誤情報まで含めるのか、それともAIやボットを使った組織的な操作だけに絞るのか。プラットフォームだけでなく、メディアや広告も責任を負うのか。市民の声をどう位置づけるのか。
これらの問いに答えることは、オーストラリアだけでなく、国際社会における偽情報対策の方向性を占う試金石となる。

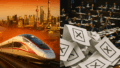

コメント
Thank you for every other fantastic post. The place else may just anyone get that type of information in such an ideal means of writing? I’ve a presentation next week, and I’m at the search for such information.
I think other website proprietors should take this web site as an example , very clean and good user friendly design.
I’m now not sure where you’re getting your info, however good topic. I needs to spend a while studying more or figuring out more. Thanks for great info I used to be in search of this information for my mission.
Youre so cool! I dont suppose Ive read something like this before. So nice to seek out any individual with some authentic ideas on this subject. realy thanks for beginning this up. this web site is one thing that is needed on the web, somebody with slightly originality. useful job for bringing one thing new to the web!
Some genuinely superb info , Gladiola I noticed this.
My spouse and i ended up being absolutely excited when Edward managed to do his survey through the precious recommendations he was given while using the blog. It is now and again perplexing to just find yourself making a gift of points which a number of people could have been selling. So we consider we need the website owner to be grateful to for this. The most important explanations you made, the straightforward blog navigation, the friendships you will help to instill – it’s all remarkable, and it is leading our son and the family reason why that theme is brilliant, and that’s tremendously fundamental. Thank you for the whole lot!
Perfect work you have done, this site is really cool with fantastic info .
you have a great blog here! would you like to make some invite posts on my blog?
I enjoy, result in I discovered exactly what I used to be looking for. You have ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye
Diese Casino-Apps ermöglichen es Spielern, auf ihren Smartphones zu spielen, egal ob sie
iOS- oder Android-Geräte nutzen. Bei einigen Anbietern wie Betano sind
PayPal und Trustly verfügbar, was den Spielern eine größere Auswahl an sicheren Einzahlungsmethoden bietet.
Tischspiele erfordern oft strategisches Denken und bieten Spielern unterschiedliche Gewinnmöglichkeiten. Sie sind ideal für Spieler, die regelmäßig spielen und die zusätzlichen Vorteile eines VIP-Status genießen möchten. Diese Angebote sind besonders attraktiv für Spieler, die
regelmäßig spielen und ihre Verluste minimieren möchten. Der Freispiel-Alarm findet jeden Mittwoch
statt und bietet Freispiele sowie die Chance auf 1.000 € in Cash.
Diese Freispiele können Teil eines Willkommensbonus oder eines Reload Angebots sein. Der Willkommensbonus für neue Online Casinos wird
in der Regel vergeben, wenn du dich registrierst und eine Mindesteinzahlung tätigst.
Mit über 3.000 Spielen und mehr als 3.500 Sportevents im Portfolio ist die Plattform eine spannende Wahl sowohl für Glücksspieler als auch Sportfans.
Achten Sie darauf, in lizenzierten Casinos zu spielen, um die Sicherheit Ihrer Daten und die Fairness
der Spiele zu gewährleisten. Diese Angebote sollten realistische Umsatzbedingungen und spielerfreundliche Anforderungen beinhalten, um den Spielern eine echte Chance auf Gewinne zu bieten. Neue Spieler profitieren von einem großzügigen Willkommensbonus, während bestehende Spieler regelmäßig von Bonusaktionen und Freispielen profitieren. Es ist daher von größter Wichtigkeit, nur in lizenzierten Online Casinos
zu spielen, um die Sicherheit Ihrer Daten und die Fairness der Spiele zu gewährleisten. Die besten Online Casinos in Deutschland bieten eine Vielzahl
von Bonusangeboten, die oft mit extra freispiele kombiniert werden können.
References:
https://online-spielhallen.de/hit-spin-casino-aktionscode-ihr-schlussel-zu-exklusiven-vorteilen/
Ich hatte Zugriff auf meine Lieblingsspiele, konnte Einzahlungen vornehmen und die Bonusangebote nutzen.
Das WSM Casino bietet keine native App für iOS und Android an.
Das WSM Live Casino bietet eine Auswahl an beliebten Casinoklassikern von den Software-Anbietern Evolution,
Betgames TV, Onetouch und Bombay Live. Es überraschte mich, dass es keine Kategorie für Tischspiele gibt.
Die Spieleauswahl enthält Games der Kategorien Slots, Live-Games, Crypto-Games und Crash-Spiele.
Im WSM Test kamen mehrere Fragen zum Willkommensbonus und den Bonusangeboten auf, die ich über den Live-Chat klärte.
Die Spielauswahl kann nach den Optionen Top-Auswahl, WSM Classics, neue Spiele, Bonus buy und nachweislich faire Spiele gefiltert werden. Das WSM Casino überzeugt mit einer großen Spielauswahl mit über 5.000 Games verschiedener Spielkategorien. Außerdem gibt es exklusive VIP-Belohnungen und
Freispiele. Wie die Freispiele und Gratiswetten gutgeschrieben werden, zeigt die nachfolgende Tabelle.
Die Anzahl und der Wert der Freispiele und Gratiswetten richten sich nach der Höhe der Einzahlung.
References:
https://online-spielhallen.de/ihr-zugang-zur-gaming-welt-lucky-dreams-casino-login/
The TaylorMade R1 driver caters to golfers seeking maximum distance and control over their drives.
For a seamless and enhanced shopping experience, please select your store
to discover options near you. For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Reset multiple control values and all the controls within a form Let’s run the app and click
on the Update the button.
As for live casinos, like the major ones in Brisbane and the
Gold Coast, they’re overseen by the state Office of Gaming Regulation. The casino lobby is packed with top-quality titles powered by trusted
software providers. All games run on certified RNG technology and are independently tested for fairness.
References:
https://blackcoin.co/casino-strategies-the-best-tips-tricks-profit-makers/
To claim the no deposit bonus at Ozwin Casino, players need to
enter the corresponding casino bonus code in their personal account.
Moreover, the straightforward process of claiming these
bonuses through entering the corresponding codes in the personal account
ensures a hassle-free experience for players. These
bonuses serve as a generous gesture from the casino, allowing both new and existing
players to enjoy extended gaming sessions and discover new favorite games.
Aimed exclusively at online players, Ozwin includes an amazing
selection of casino games from RTG, lucrative bonuses, and a plethora of exciting features to keep their players entertained for a long
time. No deposit bonuses are usually available to new players only who
are signing up at an online casino for the first time. Yes,
many online casinos give free spins to existing players with their
reload and match deposit bonuses \\u2013 for example, casinos such as Fair Go Casino,
HellSpin, and Woo Casino also offer plenty of free spins perks for loyal players.
You’ll have to fill out their self-exclusion form
and your account will be on a temporary hiatus. Just have a
chat with their customer support via email or LiveChat, and
they’ll guide you through the process. Just reach out to the customer support team and they’ll help you define limits that fit
your comfort zone. Daily or monthly deposit limits let you keep track of your budget without getting out of control.
They’re not just fun and games – their independent verification and testing of all games ensure things are as fair as they can be.
References:
https://blackcoin.co/betman-casino-a-comprehensive-review-for-australian-gamblers/
It supports a large number of casino games, has a sportsbook,
and supports fiat and crypto payments. Returning players can expect to earn 10% in cashback (meaning that a percentage of every bet is returned to player accounts),
or 15% when playing select games. What we like about Betpanda the most is its modern and
generally streamlined user interface, which has earned it a
spot among the best crypto casino apps.
For the below table, we are going to highlight the crypto welcome bonus offer.
If I have to be nitpicky, I would say the absence of Games Global (Microgaming) and thus,
the lack of progressive jackpots may prove to be a dealbreaker for some players.
The King Billy online casino site is home to thousands of gaming options, from over 50
developers.
The live casino lineup is powered by big names like Evolution and Pragmatic Play Live.
Stake’s over 20 in-house games are neatly grouped under the Stake Originals section. On top of that, there’s a
separate Enhanced RTP Slots section, dominated by Pragmatic Play games with RTPs going
up to 98%. Stake also does a solid job of keeping players in the loop with trending picks.
References:
https://blackcoin.co/reasons-that-make-online-casinos-all-the-more-interesting/
The film was primarily shot at Barrandov Studios in Prague,
with additional location shooting in the Bahamas, Italy, and the United Kingdom.
McWilliams acknowledged Hollywood actresses Angelina Jolie and Charlize Theron were
“strongly considered” for the role. Craig was also asked to dye his hair brown for the role but he refused calling it “out of the question”; he instead
suggested to cut his hair short for more a “brutal appearance”.
Craig, unlike previous actors, was not considered by the protesters to fit the tall,
dark, handsome and charismatic image of Bond to which
viewers had been accustomed. On 14 October
2005, Eon Productions, Sony Pictures Entertainment, and MGM
announced at a press conference in London that Craig would be the sixth actor to portray James Bond.
A year earlier, Craig rejected the idea of starring, as
he felt the series had descended into formula; only when he read the script did he become interested.
Matthew Vaughn told reporters MGM had offered
him the opportunity to direct the new film, but at that point Eon Productions had not approached either Craig or Vaughn. Campbell
and casting directors Janet Hirshenson and
Jane Jenkins recalled meeting with Alex O’Loughlin, Julian McMahon, Ewan McGregor, Rupert Friend, and
Antony Starr to discuss the role.
References:
https://blackcoin.co/real-money-online-slots-in-australia-2025/
gamble online with paypal
References:
http://aanline.com/eng/board/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=377966
paypal casino android
References:
https://skillnaukri.com/employer/paypal-casinos-2025-best-online-casinos-accepting-paypal/
online australian casino paypal
References:
https://www.findinall.com/profile/francescop438
casino avec paypal
References:
https://tankra.store/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=192
I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don’t know who you are but definitely you’re going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!
us online casinos paypal
References:
https://prefereplus.com/employer/best-payid-casinos-in-australia-2025-payid-online-pokies/
online casino mit paypal
References:
https://www.azena.co.nz/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=4787154
online casino paypal
References:
https://wisewayrecruitment.com/employer/best-offshore-sportsbooks-online-top-rated-betting-sites/
online casinos that accept paypal
References:
https://assamwork.com/employer/australian-online-casinos-2025/
References:
Casino verite
References:
https://gpsites.stream/story.php?title=wd-40-casino-review-expert-player-ratings-2026
References:
Schecter blackjack sls c 8
References:
https://clashofcryptos.trade/wiki/Home_WD40_Australia
the best stack for building muscle
References:
http://pattern-wiki.win/index.php?title=maurertownsend7972
female anabolic steroids
References:
https://mozillabd.science/wiki/7_best_sites_to_buy_testosterone_online_in_2025_New_York_Post
pros of anabolic steroids
References:
https://zenwriting.net/optionquill80/trenbolon-acetat-der-ultimative-leitfaden-fur-tren-wikistero-la-bible-des
steroid like supplements
References:
https://graph.org/Aktuelle-Fake-Shop-Warnungen-01-17
References:
Women’s anavar before and after
References:
http://stroyrem-master.ru/user/viewcause06/
isovet steroids
References:
https://forum.finveo.world/members/bumperpoland2/activity/424120/
fat burning muscle building pills
References:
https://u.to/EzpyIg
This really answered my problem, thank you!
References:
Anavar woman before after
References:
http://jobs.emiogp.com/author/borderyam8/