『Time, Space and Information』は、情報を物質やエネルギーと同列の存在基盤として扱う異色の研究書である。著者は、時間・空間・情報の三つの概念を相互に還元できる統一的枠組みを提示し、物理現象を「情報の更新過程」として再記述する。
本書で特徴的なのは、“disinformation(偽情報)”という語が社会的現象としてではなく、情報構造の秩序が破れる現象として登場する点である。通信路におけるノイズや量子状態のデコヒーレンスと同様、情報が自己整合性を失うことが「偽情報」の本質であるとされる。
この発想は、フェイクニュースや情報操作の問題を超えて、「情報そのものがどのように真偽や秩序を生成するか」を問う哲学的かつ構造的な試みであり、現代のAI時代における“信頼性の物理”とも言える内容を含んでいる。
情報理論の基盤としての「偽情報」
本書の第一部「Information and Physical Reality」では、情報をエネルギーの一形態として位置づける立場が明確に示される。シャノンの通信理論と熱力学のエントロピーが並置され、情報の欠如が系の無秩序と等価であることが論じられる。ここで著者は、“disinformation”を次のように定義する。
「Disinformation is not a social lie but a physical degradation of informational order.(偽情報とは社会的な虚偽ではなく、情報秩序の物理的劣化である)」
この一文が本書の方向性を象徴している。つまり、偽情報とは「虚構」ではなく「ゆがみ」なのである。観測者が世界から情報を得る際、どの部分を失い、どのような形で再構成するかという不完全性そのものが“偽情報”を生み出す。真理は情報の完全性、偽情報はその欠損の側面として生じる構造的結果だという見方である。
この枠組みでは、情報の正確さは通信経路や意図の問題ではなく、物理的な情報伝達の整合性として定義される。たとえば量子情報理論では、観測によって波動関数が縮退し、もとの重ね合わせ情報が失われる。これもまた「disinformation」の一種と捉えられる。
偽情報とは、物理的世界が保持しうる情報量と、観測者が再構成できる情報量との差であり、両者のギャップが増大するほど時間の不可逆性――すなわち「時間の矢」が生じる。ここで“disinformation”は、社会的概念を越えた時間の非対称性の根源的要因として登場する。
時間・空間を情報構造として再構成する
第2部「Time and Space as Informational Constructs」では、時間と空間の定義そのものが情報理論的に再構成される。空間的距離は、二つの点がどれだけ情報的に独立しているか(相互情報量)によって測定できるとされ、時間の流れは情報が更新される速度として表現される。
このとき、“disinformation”は情報の更新過程におけるノイズの蓄積として現れる。著者は、時間の進行を「情報の損失を伴う再符号化の連鎖」と捉え、情報空間の局所的な歪みを「偽情報の重力」と呼んでいる。物理空間で距離が離れていても、情報相関が強ければ即時的に作用する――量子もつれの非局所性を、情報空間上の距離の短さとして説明する箇所は特に興味深い。
つまり、偽情報はこの文脈で「空間的分離をもたらす力」として登場する。完全に整合した情報空間では、すべての点が相互に透明であり、因果関係は対称的だ。ところが、観測者が持つ情報が部分的であれば、空間が立ち上がり、そこに因果の方向が生じる。物理的な距離や時間の進行とは、情報の欠損が生み出す擬似的な秩序である。
観測者の限界としての偽情報
第3部「Observation, Meaning and Consciousness」では、情報理論は意識の問題に接続される。著者は、「意味(meaning)は観測者の内部情報構造が外界情報と整合する度合い」と定義する。観測とは、外界の情報を内部モデルに写し取る行為だが、その過程で必ず情報の劣化が起こる。これが偽情報の源である。
観測者が自己の情報構造を通じて世界を理解する以上、常にゆがみが生じる。著者はここで次のように述べる。
“Every act of observation produces its own disinformation, which defines the observer’s arrow of time.”
(すべての観測は固有の偽情報を生み、それが観測者の時間の矢を定める。)
偽情報はここで倫理的・社会的概念ではなく、知覚そのものの条件として位置づけられている。観測がなければ偽情報も時間も存在しない。観測があるからこそ、情報の不完全性が時間の流れをつくる。この関係を逆転的に読めば、時間とは「偽情報の生成速度」とも言える。
社会的偽情報研究への示唆
このような抽象理論を現代の偽情報研究に接続することには明確な意味がある。現在のディスインフォメーション対策は、発信者の悪意や虚偽意図の分析に偏っている。しかし本書が示す視点では、偽情報とは構造的ノイズであり、情報空間全体の非整合性によって生じる現象である。
この観点を応用すれば、個別の投稿や発言の真偽判定ではなく、**情報ネットワークの秩序度(informational coherence)**そのものを測定対象とすることが可能になる。SNS上で同一情報が相反する文脈で流通する現象も、情報空間のエントロピー増大として解析できる。つまり、「どのノードがゆがみを生んでいるか」を構造的に検出する方法論につながる。
またAI生成コンテンツの時代においても、「情報の整合性」「自己参照の透明性」は中心的課題であり、生成モデルがどの程度disinformationを内部的に抑制できるかを物理情報的観点から評価する理論的基盤としても有効である。
情報秩序を守るという課題
『Time, Space and Information』が提示するのは、偽情報を取り締まる倫理論ではなく、情報秩序をいかに維持するかという物理的課題である。情報は閉じた系ではなく、観測によって常に更新され、ゆがみを生む。完全な真理や完全な整合は存在せず、秩序は常に部分的・局所的に維持される。
この視点は、現代の情報社会が抱える構造的不安定性を深く照らす。フェイクニュースや情報操作を「人間の悪意」として処理するだけではなく、情報構造の物理的限界として捉え直すとき、ようやく対策の根拠が見えてくる。偽情報とは社会のノイズではなく、情報宇宙そのものの「熱」であり、完全に消し去ることはできない。重要なのは、それを検知し、秩序のゆらぎを最小化する構造を設計することだ。
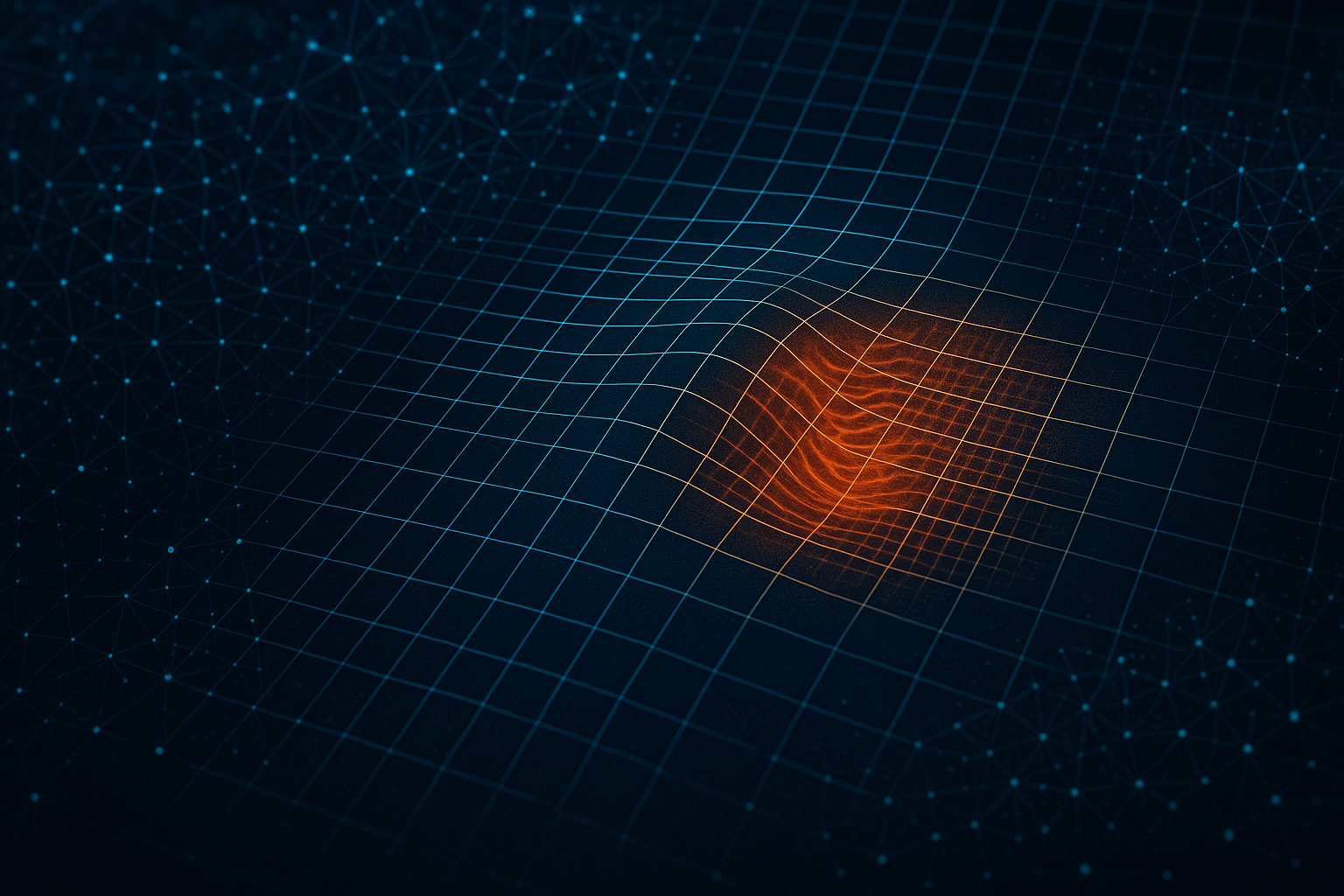


コメント
so much superb information on here, : D.
Everything is very open and very clear explanation of issues. was truly information. Your website is very useful. Thanks for sharing.
WONDERFUL Post.thanks for share..extra wait .. …
My brother suggested I would possibly like this website. He used to be totally right. This put up actually made my day. You can not believe simply how much time I had spent for this information! Thanks!
Nice post. I learn something more challenging on different blogs everyday. It will always be stimulating to read content from other writers and practice a little something from their store. I’d prefer to use some with the content on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll give you a link on your web blog. Thanks for sharing.
When I originally commented I clicked the -Notify me when new feedback are added- checkbox and now every time a comment is added I get four emails with the identical comment. Is there any way you can take away me from that service? Thanks!
Sie ist mit den meisten gängigen Android-Geräten kompatibel
und bietet vollen Zugriff auf Casino-Spiele und Sportwetten mit optimierter mobiler Performance.
Diese App ist benutzerfreundlich und bietet ein nahtloses Spielerlebnis mit allen Funktionen der Desktop-Version. Abgesehen davon bietet Verde
Casino seinen Nutzern auch eine mobile App, die sowohl für Android als auch für iOS verfügbar ist.
Das Casino bietet ein exzellentes mobiles Spielerlebnis und ermutigt die Spieler, ihrer Lieblingsunterhaltung auch unterwegs zu frönen. Verde
Casino bietet Wetten auf Spielausgänge, Toranzahl,
Drittelwetten und Live-Märkte an.
Denn ohne Account kein Guthaben und keine Freispiele. Abgesehen davon kann man auch Tischspiele, wie Baccarat,
Blackjack oder Poker entdecken und Roulette in verschiedenen Spielweisen ausprobieren. Das
Verde Casino ist ein relativ neuer Glücksspielanbieter im Internet, kann sich aber bereits jetzt durch eine große Spielauswahl behaupten.
Das schlägt sich darin nieder, dass unzählige Casinospieler aus aller Welt das Verde
Casino als ihr liebstes Online Casino auserkoren haben. So kann man diesen Klassiker an einem echten Tisch und mit einem professionellen Croupier
spielen. Das VerdeCasino verfügt über eine Glücksspiel-Lizenz aus Curacao, wodurch
man auch in Deutschland legal spielen kann.
Damit man in Deutschland Glücksspiele anbieten darf,
benötigt man eine europäische Lizenz.
References:
https://online-spielhallen.de/betano-casino-auszahlung-dein-umfassender-guide-fur-schnelle-gewinnauszahlungen/
Once you’ve signed in, check your email by opening your inbox.
We work hard to protect you from spam, phishing, and malware,
before they reach your inbox. Google Workspace is a set
of productivity and collaboration tools that helps individuals, teams,
and businesses stay on top of everything. Gmail
offline lets you read, reply, delete, and search your Gmail
messages when you’re not connected to the internet.
Use Gemini with your Google AI Pro or Ultra plan for personal use or as part of your Google Workspace plan for work.
Save time managing your inbox at home or on the go with Gemini.
Once you’re signed in, open your inbox to check your mail.
You may opt out at any time. Join our newsletter to receive the latest news,
trends, and features straight to your inbox!
Gentle nudges help you stay on top of everything.
Start a Chat, jump into a video call with Meet, or collaborate in a Doc, all right from Gmail.
Gmail blocks 99.9% of spam, malware, and dangerous links from ever reaching your inbox.
Gmail uses industry-leading encryption for all messages you receive and send.
Gemini in Gmail can compose well-written drafts or replies for you to edit,
personalize and quickly hit send.
References:
https://blackcoin.co/lucky-elf-casino-discover-top-slot-experiences-in-australia/
There’s also the Dome Climb offering stunning city views with a side serve of adrenaline!
Cairns Zoom and Wildlife Dome is located in the heart of town and is home to a range
of animals, from reptiles to birds of prey. The Cairns City Night
Market is held every Wednesday night in the city centre.
The museum is also home to the Cairns Maritime Museum, which tells the stories
of the city’s rich maritime history.
Cairns casino owner Reef Casino Trust yesterday posted a 46 per cent rise in first-half net profit despite the outbreak of severe acute
respiratory syndrome and the Iraq war. Shares in the trust are down 43 per cent so
far this year and have fallen 48 per cent over the past 12 months.
Reef Casino Trust owns the Reef Hotel Casino complex in Cairns, a city that has historically achieved strong population growth and established a reputation as being
a resilient tourist destination, even in challenging economic times.
References:
https://blackcoin.co/6_vip-casino-review-2022-special-bonuses-for-canadians_rewrite_1/
Thank you a lot for providing individuals with remarkably splendid chance to read in detail from this web site. It is always so enjoyable plus stuffed with a great time for me and my office friends to visit your website at the very least three times in 7 days to learn the newest guidance you have got. Of course, I am certainly contented for the very good tricks served by you. Selected two areas in this article are essentially the most impressive I’ve ever had.
online casino mit paypal einzahlung
References:
workmall.uz
online casino paypal einzahlung
References:
https://www.swingputt.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=1031
online casino that accepts paypal
References:
https://bhakticonsultaants.com/employer/best-online-casino-games-2025-play-top-casino-games/
paypal casino online
References:
https://jozhi.org/employer/40-best-australian-online-casinos-for-real-money-in-december-2025/
What’s notable is how Bing surrounds the AI answers with organic search results. Below is a screenshot of the new generative AI search experience. Bing’s announcement discusses new features that not only make it easy for users to find information, Bing also makes it easy for users to see the organic search results and click through and browse websites. …Today, we’re excited to share an early view of our new generative search experience which is currently shipping to a small percentage of user queries.”
The SerpApi Model Context Protocol (MCP) server provides a unified search tool for AI agents. It’s also worth taking a look at our Bing Playground and performing a few searches to see it all in action. Returned in the relatedSearches.value key (array of related searches) in the official API, our API returns the equivalent in the top level related_searches key (array of related searches).
References:
https://blackcoin.co/ufo9-casino-your-place-to-play-your-way/
online slots uk paypal
References:
https://somalibidders.com/employer/10-best-online-casinos-for-real-money-december-2025/
online casinos that accept paypal
References:
https://interior01.netpro.co.kr:443/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=139
australian online casinos that accept paypal
References:
https://sportjobs.gr/employer/best-online-casinos-in-australia-2025-instant-withdrawal-casinos/
paypal casino uk
References:
https://jobrails.co.uk/employer/online-pokies-paypal-deposit-i-piece-web-design/
References:
Talking stick casino az
References:
http://muhaylovakoliba.1gb.ua/user/appealgarage8/
steroids before and after
References:
https://isowindows.net/user/bodyfan0/
References:
Anavar gains before and after
References:
https://xypid.win/story.php?title=anavar-for-women-see-dosage-pros-cons
dbol injections
References:
https://linkagogo.trade/story.php?title=anavar-cycle-mastery-science-backed-dosage-stacking-results
best and safest prohormone
References:
https://kirkegaard-murphy.hubstack.net/testosterone-ameliorez-votre-vitalite
An interesting dialogue is price comment. I think that it’s best to write more on this subject, it might not be a taboo subject however generally persons are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers
%random_anchor_text%
References:
https://mozillabd.science/wiki/Wo_kann_man_Steroide_sicher_und_legal_kaufen
body beast supplements alternatives
References:
https://scientific-programs.science/wiki/Revisin_de_Testrol_Platinum_Mejora_la_resistencia_y_la_energa
amp protein powder side effects
References:
https://case.edu/cgi-bin/newsline.pl?URL=https://thehollywoodtrainerclub.com/static/pgs/?buy_clenbuterol_4.html
References:
Anavar girl before and after
References:
https://www.ozodagon.com/index.php?subaction=userinfo&user=formatappeal39
References:
Fun roulette
References:
https://bookmarks4.men/story.php?title=play-the-3×3-island-game-on-timestables-com
References:
Real money online pokies
References:
https://freebookmarkstore.win/story.php?title=online-casino-de-beste-online-casinos-van-nederland-voor-2025
References:
Best online casino games
References:
https://support.mikrodev.com/index.php?qa=user&qa_1=emerysand65
References:
Online casinos south africa
References:
https://onlinevetjobs.com/author/locklove02/
fast muscle building supplement
References:
http://everest.ooo/user/bitstory11/
legal steroids for muscle gain
References:
https://coolpot.stream/story.php?title=trenbolone-steroide-avis-dun-coach-sportif-et-en-nutrition
deca injection results
References:
http://premiumdesignsinc.com/forums/user/traysuit4/
how much does anavar cost
References:
https://numberfields.asu.edu/NumberFields/show_user.php?userid=6464077
References:
Hialeah casino
References:
https://www.exchangle.com/jamesfrance9
This is really interesting, You are a very skilled blogger. I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your wonderful post. Also, I have shared your web site in my social networks!
References:
Casino pauma
References:
https://historydb.date/wiki/Online_Casino_Deutschland
References:
Aspers casino stratford
References:
https://www.instapaper.com/p/17417792
References:
Marina bay sands casino
References:
https://wikimapia.org/external_link?url=https://online-spielhallen.de/1red-casino-bonus-codes-ihr-umfassender-leitfaden/
References:
Mini roulette
References:
https://www.google.pn/url?q=https://online-spielhallen.de/888-casino-deutschland-ihr-umfassender-leitfaden-mein-erfahrungsbericht/
References:
Merkur online casino
References:
https://coolpot.stream/story.php?title=888poker-im-test-fuer-2026-tolle-spiele-willkommensbonus-bis-zu-888-dollar
References:
Geant casino drive
References:
http://decoyrental.com/members/cupcoach60/activity/1310303/
References:
Grand online casino
References:
http://stroyrem-master.ru/user/layerbush60/
References:
Cincinnati casino
References:
https://bluecrayon42.bravejournal.net/implementing-ai-to-personalise-the-gaming-experience-for-australian-pokies
best steroid for bulking
References:
https://humanlove.stream/wiki/7_Best_Keto_Diet_Pills_in_2023_Top_Ketogenic_Supplements
do steroids make you faster
References:
https://cuwip.ucsd.edu/members/screensister57/activity/2824685/
what steroids should i take to get ripped
References:
https://bandori.party/user/408562/steamnepal02/
References:
Bally’s las vegas reviews
References:
https://porchspring55.werite.net/list-of-all-225-online-betting-sites-australia-updated-weekly
prohormone vs steroids
References:
http://mozillabd.science/index.php?title=munnortega1018
legal muscle steroids
References:
https://yogaasanas.science/wiki/Winstrol_For_Beginners_What_You_Need_To_Know_Before_Your_First_Cycle
united pharmacies steroids
References:
https://graph.org/Adelphi-Tropin-Somatropin-HGH-100IU-02-05
anabolic enhancer
References:
http://premiumdesignsinc.com/forums/user/buffersampan0/