2025年6月に公表された『Disinformation in the City Brief #3: Responses』は、都市レベルでの偽情報対策をテーマとしたシリーズの第3部にあたる。メルボルン大学のMelbourne Centre for Citiesと、米German Marshall Fundによる共同研究プロジェクトの成果であり、Ika Trijsburgら5名の研究者によって執筆されている。
このブリーフの特色は、偽情報(disinformation)に対する都市の応答を、単なる倫理的問題やジャーナリズムの問題としてではなく、制度的・技術的・社会的な仕組みの再設計課題として扱っている点にある。国家レベルの立法や規制と並走するかたちで、むしろ人々の生活に最も近い行政単位としての「都市」がどのように偽情報と向き合うべきか、そのライフサイクルに沿って精緻に検討している。
偽情報対応の3段階フレーム
本稿は、都市における偽情報対応を3つの段階に分類して議論する。
- 予防と早期検知(Preemption and Early Detection)
- 拡散防止と先回り対応(Spread Prevention and Pre-bunking)
- 反証と信頼回復(Debunking and Recovery)
このように構造化することで、都市が関与できる範囲や手段を明確にし、施策設計の実践的指針として機能する構成となっている。
予防と早期検知──信頼と技術の交差点
初期段階では、偽情報が顕在化する以前のシグナル検知や制度的備えが中心となる。
たとえば、米ペンシルベニア州ではCOVID-19関連のSNS投稿から、「Pfizer」「Moderna」などのキーワードをもとに、ローカルで支配的な偽情報のナラティブを抽出するAI・ネットワーク分析による検知手法が展開された。しかしこれが、英語を日常語としないドミニカ共和国などのカリブ諸国ではうまく機能しなかった。検知アルゴリズムは言語・文化文脈に強く依存するという教訓は、他の技術介入にも通底する。
制度面では、エストニアでのサイバー攻撃を契機に作成されたEU地域委員会の「偽情報ハンドブック」が紹介されている。これは脅威の認識から対応までを段階的に整理したもので、都市にとって即時のリファレンスとなる設計がなされている。
また、コペンハーゲンの試みは対照的だ。政治家・ジャーナリスト・市民が対話を行う公開討論会を多数開催し、参加者は緑と赤のカードで賛否を表明する。信頼の再構築を「関係性の再設計」として捉える好例であり、制度的に低コストで再現性の高いモデルでもある。
さらに、米ニュージャージーの「Civic Information Consortium」や英国の報道機関税制優遇制度に見られるように、ローカルメディアの生存支援を通じて、偽情報が根を張る土壌そのものを削るという視点も提示されている。
拡散防止と先回り対応──予見と社会規範
拡散フェーズでは、偽情報が受容される前にメディアリテラシーを高め、ナラティブを先取りすることが中心となる。
バーミンガム市大が中東・北アフリカ地域で展開する「Check」プログラムでは、若年層・市民記者・活動家を対象に、オンライン教育・検証ツールの提供・国際ネットワークの形成が三位一体で行われている。単なる技能教育ではなく、「偽情報と戦う市民基盤を育てる」という政治的含意が色濃い。
一方、米アリゾナ州マリコパ郡のプリバンキング施策は、2022年中間選挙に先立って、投票手続きや集計プロセスを事前に広告で周知することで、偽情報が流れる前に防壁を築こうとする試みだ。完全な成功とは言えなかったが、「予見可能な偽情報」への事前対処という概念を可視化した点で注目される。
さらに、SNS上でユーザに「この見出しは正確だと思いますか?」と問いかけるaccuracy primeのような行動設計手法も紹介されている。これは認知科学の知見を反映したもので、ユーザのシェア行動に一拍置かせることで拡散を抑制する狙いがある。
そして、「望ましい行動の社会的規範化」も重視される。オーストラリア・パースの水資源キャンペーンや南アフリカ諸都市でのジェンダー暴力対策などは、特定行動を「当たり前」と感じさせる規範形成の力が、情報環境にも応用可能であることを示している。
反証と信頼回復──誰が語るかの重み
偽情報がすでに消費された後の段階では、「何を言うか」よりも「誰が語るか」が支配的な意味を持つ。
2016年ルイジアナ州洪水の際には、SNS上で「行政が無能」「支援が遅い」などの偽情報が急拡散した。これに対し、赤十字が迅速に反応し、信頼できる発信者としてカウンターナラティブを提供。動画・更新情報・記者連携を通じて「情報の中心点」となることで、偽情報の影響力を削いだ。
また、テネシー州のHispanic系住民を対象としたワクチン啓発プログラムは、「話せる相手がいる」ことの力を如実に示している。スペイン語話者の看護学生が、教会や学校で住民と直接対話する仕組みが組まれ、参加者は15週間にわたり「非対立的反論」の訓練を受ける。単なる正確な情報の提供ではなく、共感と敬意を前提とした対話的アプローチが鍵となっている。
評価と応用可能性
本稿の特筆すべき点は、偽情報対策を「倫理」や「メディア規範」の話に矮小化せず、ガバナンス・技術・対話・制度設計の課題として多角的に描いていることにある。単に「デジタル教育を推進しよう」では終わらず、どの段階で誰がどのように関わるべきか、都市レベルでの選択肢を明示している。
日本国内においても、都市自治体が独自に偽情報対策に取り組む動きが出始めているが、制度的手当はきわめて限られている。市民対話・ローカルメディア支援・行政職員へのトレーニングなど、本稿に挙げられたアプローチは、そのまま実務レベルの検討材料となるだろう。

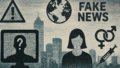
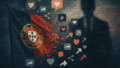
コメント