2025年10月に公表された報告書『Mapping Climate Disinformation in French and Brazilian Mainstream Media』は、気候変動に関する誤情報がどのように放送空間で再生産されているかを精密に分析した比較研究である。制作はClimate SafeguardsとMedia Observatory on Ecologyによる共同プロジェクトで、分析基盤はData For Good、QuotaClimat、Science Feedbackの三団体が担った。AIと人手検証を組み合わせ、フランス18局・ブラジル7局のテレビとラジオのニュース番組を2分単位で分解。各発言を科学的正確性、政治的文脈、反駁の有無とともに注釈した。対象は2025年1月から8月の主要報道期間である。
両国を並べて観察する理由は、環境政策に対する情報操作が異なる政治体制のもとでも同じ構造で現れることにある。フランスは討論番組が多く、ブラジルは報道の集中と沈黙が支配的だ。言論環境は正反対でも、結果はいずれも「気候行動を遅らせる」。この逆方向から収束する構造こそが、本報告書の中心的発見である。
方法――AIによる発言単位の分析と「ナラティブ」の抽出
分析は段階的に設計された。まず、放送ログをすべて2分セグメントに分割し、気候関連キーワード(énergie, climat, carbone, chaleur, électricité, COP, émissionsなど)を含む部分を抽出。人手で発言の主体(政治家、コメンテーター、専門家、市民など)とテーマを付与する。次に、CamemBERTやQwenなどの言語モデルを使い、文意の近さを数値化。同じ論法や構文的リズムをもつ発言群をクラスタ化した。
単なる「話題」ではなく、「再エネは高コスト」「CO₂排出は微々たるもの」「政策は貧者を苦しめる」といった繰り返される論理構造を捉えるため、クラスタの最終判定にはLLMによる文脈判断が導入された。機械学習で仮分類されたクラスターを、ファクトチェッカーが再確認し、科学的根拠・統計の誤用・政治的意図の有無を評価。最終的に19種類の主要ナラティブが確定した。これらはすべて「気候対策の正統性を疑わせ、行動を遅らせる」方向に作用するものだった。
フランス――否定ではなく「遅延」が支配する
統計的特徴
フランスでは、2025年1〜8月の8か月で529件の偽情報発言が検出された。出現頻度は7〜8月に3倍へ跳ね上がり、ZFE(低排出ゾーン)論争、熱波報道、エネルギー政策(PPE3)などの政治的イベントと同期していた。ニュースが政治議題化すると、討論番組で誤情報が増えるという明確な相関が見られた。
内容の分布
検出された発言の約7割がエネルギー政策関連であり、再エネのコスト・系統負荷・国産原子力との比較が焦点だった。「再エネは電気代を倍増させた」「風力発電は景観を破壊する」「原子力こそ唯一の現実解」といった発言が典型例である。1割はモビリティ(EVや交通規制)に関するもので、「ZFEは地方都市を切り捨てる」など地域格差への不満と結びつく。残りは国際協力批判(「フランスの排出は世界の1%」「中国が何もしないのに意味がない」)に集中している。
放送構造の影響
討論番組が多いCNewsやSud Radioでは、気候関連ニュース約40分に1件の割合で偽情報が出現。公共放送(France 2, France Info)では同期間で6分の1以下に抑えられた。司会者が即時に反論しない発言は「多様な意見」として残り、後続ニュースで再引用されることが多い。報告書はこの現象を「討論装置型偽情報」と呼び、言論の自由を盾に誤情報が温存される構造として分析する。
言説の典型――「黒いカーテン」比喩
CO₂の温室効果を「黒いカーテン」に喩え、「わずかな濃度で遮蔽は飽和するから増やしても変わらない」と説明する番組が複数検出された。CO₂の放射強制が対数的に上昇することを無視した誤ったモデルだが、スタジオで即時に訂正が行われないため、視聴者には合理的疑義として残る。報告書は、「誤りを訂正しない放送構造自体が偽情報の再生産機構になっている」と警告する。
ブラジル――報道の「沈黙」が生む否認
情報量の欠乏
ブラジルでは、フランスに比べて検出件数は3〜6分の1。だがこれは偽情報が少ないという意味ではない。むしろ、気候関連ニュースの放送量そのものが少ない。政府や企業が絡む経済利害の影響で、森林破壊や炭素市場の話題がニュース枠から外される傾向が顕著だ。
局ごとの偏り
偽情報の約7割がJovem Panに集中し、4〜9月の間に顕著なピークを示した。主なテーマは農業、森林破壊、COP30準備、EV政策、バイオエタノール。多くの発言は「国際圧力に屈する必要はない」「森林は再生している」「欧州の基準はブラジルに合わない」といったフレームで、国家主権や経済自立を前面に出す。
政治・産業構造との結合
レポートは、アグリビジネスと鉱業が政府・メディア双方と結びついているため、報道量の欠如自体が情報操作として機能していると指摘する。これは「沈黙による否認(denial by silence)」と呼ばれ、フランスの討論過剰とは逆の形で同じ結果――気候行動の遅延――をもたらしている。
二つの異なる環境が示した共通の構造
フランスでは「話しすぎる」ことが、ブラジルでは「語らない」ことが、いずれも政策行動を鈍らせる。報告書が明確に描いたのは、この過剰と欠如が同じ方向に働く構造的同型性である。政治的立場や言論の自由の度合いにかかわらず、メディアの構造が整っていなければ、気候対策は社会的に“遅延”する。フランスの討論空間が生み出す「無限の意見」と、ブラジルの情報空白が生む「無音の合意」は、表裏一体の問題として理解されるべきだ。
制度提言――規制、観測、財源の三本柱
報告書は、誤情報を「倫理」ではなく「制度設計」の問題として扱う。
- 規制強化:フランスの視聴覚監督機関Arcomに環境情報監督の明示的権限を与え、勧告→罰金(最大売上高10%)→放送免許停止の三段階制裁を導入。
- 常設観測機関:**環境報道観測所(Observatoire du discours écologique)**を設立し、放送内容を定量的に監視。AI検出結果と人手評価を組み合わせて月次報告を出す。
- 公共放送の安定財源:政府予算への依存を減らし、複数年・自律的な資金配分制度を整備。
さらに、恫喝訴訟(SLAPP)から報道を守る法的枠組みの国内化を提案。これらをまとめたDelautrette法案が2025年11月に国会提出予定であり、**DSA(Digital Services Act)**の精神を放送にも拡張する狙いがある。
偽情報を「災害リスク」として監視する新構想
本報告書が独自性を持つのは、偽情報を自然災害と同列の社会リスクとみなし、早期警戒の仕組みに組み込む点である。提案されたClimate Safeguards Systemは、AIで偽情報の発生をリアルタイムに監視し、CAP(Common Alerting Protocol)を通じて各メディアと自治体に通知する。気象庁や防災当局と同じ回線で「情報災害」を扱うという発想だ。背景には、被災者の53%がテレビやラジオを通じて警報を受け取ったというデータがある。放送は依然として社会の警報インフラであり、偽情報も同じ回線で監視すべきだという論理である。
この構想は、放送を単なるニュース媒体ではなく「情報気候」を安定させる社会インフラとみなす考え方に基づいている。フェイクニュース対策を災害対策と同列に扱う発想は、気候危機時代のメディア政策として注目に値する。
文化的対抗策――“Green Team”が描く未来の物語
制度と技術だけではなく、文化の力を使うべきだという提案もある。国防分野の“Red Team”の仕組みを参考に、科学者、作家、映像制作者が協働して2100年の望ましい気候未来像を描く「Green Team Project」を立ち上げる構想だ。科学的知見を基盤に、フィクションやドキュメンタリーを通じて「行動すれば変えられる」という物語を広める。絶望や無力感を煽るナラティブに対し、希望に基づく言説を文化的に再生産する試みである。
また、ブラジル、UNESCO、G20が主導する「Global Initiative for Information Integrity on Climate Change」への連携も提案され、国際的な協調枠組みの強化が進められている。
本稿の分析――「遅延型偽情報」に対する三つの制御点
一次資料を踏まえると、対策の焦点は明確に三つに絞られる。
第一に番組設計の改革。討論形式に科学顧問を常設し、司会者に反駁トレーニングを義務化するだけで、誤情報の透過率は統計的に大幅に低下する。
第二に制度の再設計。Arcomの三段階制裁や公共放送の財源安定化は、編集の独立性を守るための現実的な仕組みだ。
第三に危機管理への統合。偽情報の検知からCAPによる伝達までを一本化すれば、「誤情報の臨界」に達する前に減衰できる。
これらは単なる政策提案ではなく、報告書の実証データから導かれた制御点である。フランスの過剰な論争とブラジルの沈黙という対照的現象を、制度・文化・危機管理の三層で同時に扱うという点に、この報告書の理論的深みがある。
まとめ――「否定」よりも厄介な「遅延」をどう制御するか
本報告書の意義は、気候偽情報の焦点が「科学を否定する」段階から、「政策を遅らせる」段階へ移ったことを、実証データで示した点にある。誤情報はもはや荒唐無稽ではない。むしろ、正しい事実の一部を利用して「まだ結論を急ぐな」「経済が壊れる」と主張することで、行動の速度を鈍らせる。その効果は、否定よりも持続的で破壊的だ。
フランスの討論番組で繰り返される“合理的懐疑”、ブラジルのニュースに漂う沈黙――両者は表現の自由の範囲に見えながら、結果として社会を止めている。だからこそ、放送を民主主義の情報インフラとして再設計することが重要になる。気候危機の時代において、情報の信頼性は環境政策の一部であり、行動を早めるための基盤そのものである。
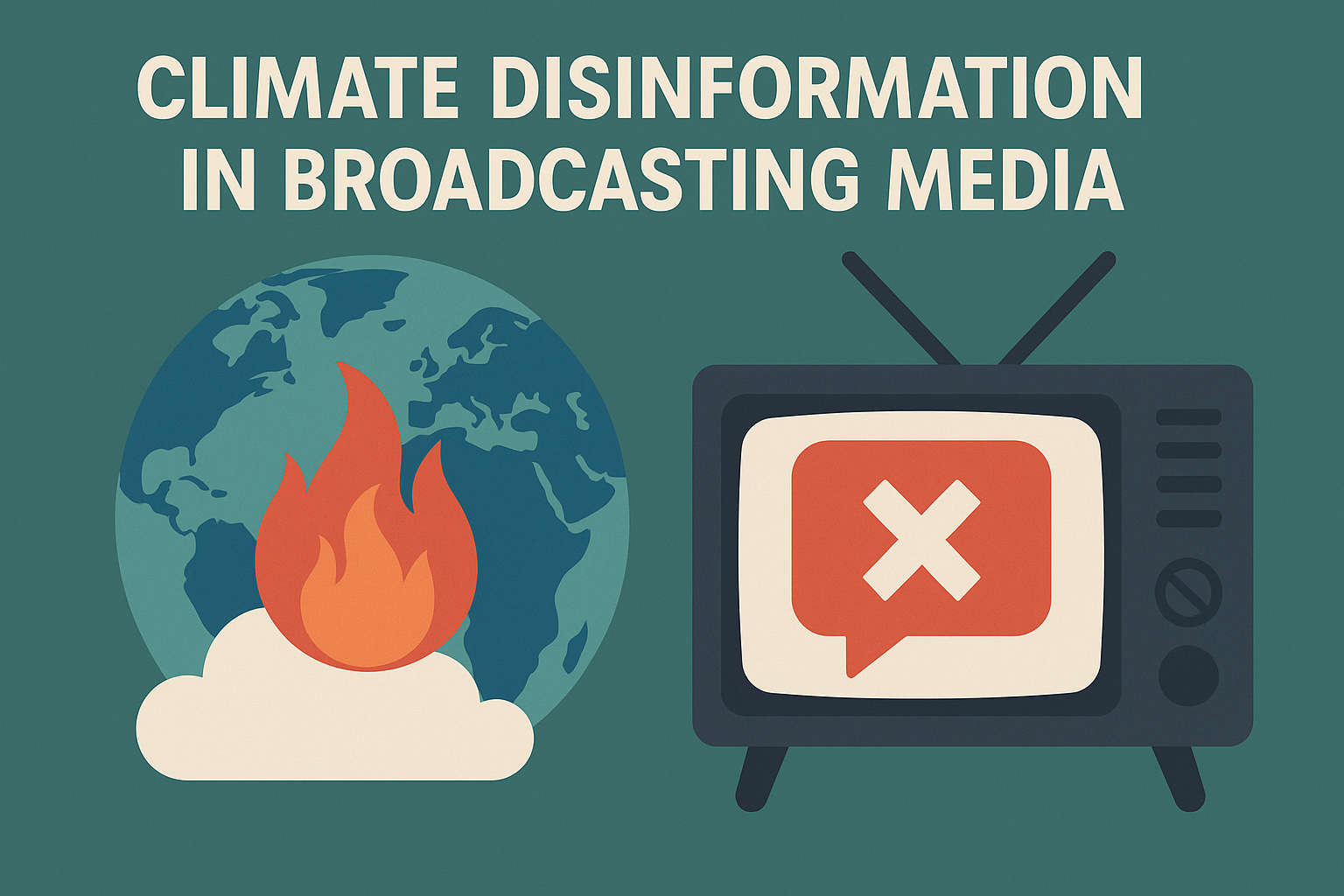
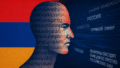
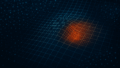
コメント
Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you! However, how could we communicate?
I like this blog very much, Its a rattling nice berth to read and get info . “Misogynist A man who hates women as much as women hate one another.” by H.L. Mencken.
so much excellent information on here, : D.
I cling on to listening to the rumor talk about receiving free online grant applications so I have been looking around for the finest site to get one. Could you tell me please, where could i get some?
Bonusguthaben oder Freispiele sind oftmals an einen maximalen Gewinnbetrag gebunden. Entweder werden diese im Spielesortiment als “Bonusspiele” tituliert oder aber sie sind in den Bonusinfos aufgelistet.
Wichtig ist bei allen diesen Bonusangeboten, dass die Bedingungen fair
und realistisch sind. Manche verschaffen Ihnen Bonusguthaben, manche Freispiele und manche eine Kombination aus beidem.
Alternativ stellen Ihnen die Casinos auch eine bestimmte Anzahl Freispiele für ausgewählte Spielautomaten zur Verfügung.
Allerdings werden bei den umsatzfreien Freispielen die Gewinne sofort als Echtgeld gutgeschrieben, ohne dass
ein weiterer Umsatz notwendig ist. Statt
Geld erhalten die Spieler bei diesem Casino ohne Einzahlung Bonus eine feste Anzahl an Freispielen für ausgewählte Slots.
Ein No Deposit Bonus ist ein Angebot mit Bonusgeld
oder Freispielen, das ohne vorherige Einzahlung gewährt wird.
Der Bonus kann nur einmal pro Installation der App erhalten werden. Für
alle die noch keine OnlyWin Casino-App installiert haben, gibt es 20 No-Deposit Freispiele zum Slot 777 Fruity Classic von 3Oaks.
Sowohl der Bonus als auch die Freispielgewinne müssen innerhalb von 30 Tagen mindestens 50-mal umgesetzt werden. Ihr
könnt dieses Gratis-Guthaben auf bestimmte Casinospiele oder Wetten verwenden und so den Bonus ohne Risiko testen.
References:
https://online-spielhallen.de/bwin-casino-freispiele-alles-was-sie-wissen-mussen/
When choosing a Casino AU platform, it’s always good to check the basics first.
It’s designed to get you playing fast, with AU$ banking and fast withdrawals once you meet the
terms. Clear wagering requirements are in place, so you’ll know exactly how to
turn your bonus funds into real cash. It’s a simple way to double your balance and explore the game lobby without stretching your budget.
The SkyCrown mobile site works straight in your browser,
whether it’s Chrome, Safari, or another modern option. SkyCrown Casino AU makes it
easy to keep playing wherever you are.
The platform supports traditional cards, vouchers, PayID, and a variety of cryptocurrencies.
The SkyCrown no deposit bonus was small but handy for testing.
What SkyCrown doesn’t advertise clearly is how different games count toward wagering.
During my test, I received 20 free spins as a SkyCrown no deposit bonus via email.
In particular, you can contact the casino assistants via Live Chat (available round
the clock), on-site message form, and email ([email protected]).
The operator offers its services under a license, yet it doesn’t disclose the number.
Since the SkyCrown app is a PWA, its updates are made automatically
without any user learning about it beforehand. The latest app version applies stronger encryption and secure login flows.
This means whichever slot, table game, or whatever game is introduced by these brands ensures fair, unbiased results.
References:
https://blackcoin.co/crypto-casinos-top-sites-in-2025/
Amid spectacular views of Australia’s iconic harbour, taste some
of the best dishes from internationally acclaimed chefs.
With perfectly framed views of Sydney’s skyline, each room heralds sophisticated, modern decor capturing the essence of the gorgeous and
unique harbourside setting. Rising majestically above the
bustling Barangaroo precinct, Crown Towers offers unparalleled luxury stays in Sydney.
Just a 1-minute walk from the Queen Victoria Building (QVB), Megaboom City Hotel is located in the heart of Sydney CBD.
Located in the heart of Sydney CBD (Central Business
District), Castlereagh Boutique Hotel, an Ascend Collection Hotel offers a restored, heritage-listed property near Sydney’s most
cherished… Ideally situated in the heart of North Sydney,
a short train journey from Sydney’s city centre.
Right in the heart of Sydney, situated within a short distance of Central Station Sydney and International Convention Centre Sydney, MetaWiseBnB Studio Dixon Next to ICC & Darling Harbour 58 offers…
It is 2 minutes’ walk from the famous Darling Harbour and several cafes, bars and nightlife options.
Just 2 minutes’ walk from Hyde Park and Pitt Street Mall, QT Sydney offers a restaurant, bar, cafe and day spa.
Situated in the heart of Sydney, Swissôtel Sydney—recently awarded Metropolitan Superior Hotel of the Year at the 2025 AA
NSW Awards for Excellence—is ideally located for shopping, sightseeing, and…
Meriton Suites Coward Street, Mascot is a luxury hotel positioned
only 10 minutes’ drive from the domestic airport and 15 minutes’ drive from
the international airport.
It was so relaxing looking at Sydney’s iconic harbour while enjoying a drink from up there.
It’s easy to get to, with various transportation options readily
available. Crown Sydney Casino is located in Barangaroo, Sydney.
References:
https://blackcoin.co/best-online-casino-video-slots-history-and-rules/
online casino paypal
References:
https://gramshort.com/ypajoshua1
online casinos mit paypal
References:
https://teba.timbaktuu.com/employer/paypal-casinos-best-online-casinos-that-accept-paypal/
online betting with paypal winnersbet
References:
jskenglish.com
Games load quickly, bonuses are clear, and the cashout system is
built for speed. It’s owned by Dama N.V., a group behind
dozens of successful online casinos. It’s a legit platform with a Curacao licence and built-in tools for safer
play.
All these reloads are available to players using both AUD and crypto.
The Thursday Cashback offer, for example, works like a
no-deposit bonus if you’ve been playing actively. The welcome
offer is where most players start.
References:
ufo9
online casino with paypal
References:
https://recrutement.fanavenue.com/companies/best-online-casinos-accepting-paypal-in-australia-2025
paypal online casinos
References:
https://jobs.askpyramid.com/companies/10-best-online-casinos-australia-for-real-money-gaming-in-2025/
casino sites that accept paypal
References:
125.141.133.9
online casino real money paypal
References:
https://blisshr.africa/employer/2025/
australian online casinos that accept paypal
References:
https://www.canadiannewcomerjobs.ca/companies/best-online-casinos-australia-2025-find-top-aussie-casino/
casino online paypal
References:
https://www.iqconsult.pro/employer/top-10-best-australian-online-casino-sites-for-real-money-2025/
paypal online casinos
References:
https://jobcopeu.com/employer/paypal-casinos-top-online-casinos-that-accept-paypal/
online blackjack paypal
References:
https://career.abuissa.com/employer/us-online-casinos-that-accept-paypal-2025/
So profitieren Sie direkt von den zusätzlichen Bonusgeldern oder Freispielen. Und das sind großartige Neuigkeiten für diejenigen, die aktiv spielen möchten. Bleiben Sie auf der Website und für das Erscheinen der Schaltfläche für die NVcasino download app auf dem Laufenden. Viele Nutzer fragen sich im Chat, ob es jetzt eine NV casino app gibt, mit der sie Automaten bequem von Smartphones aus starten können. Ja, schon in der ersten Phase wird es möglich sein, kleine Beträge zu spielen, einzahlen und sogar abzuheben. Unmittelbar nach dem NV casinos sing up wird der Spieler aufgefordert, seine erste Einzahlung zu tätigen. Hier erfahren Sie mehr über die Struktur der NV casino website.
Das NV Casino ist jetzt besonders profitabel, da es ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet und von einem Bonus aus dem Bun-Bereich profitiert, der über die oben genannten Boni verfügt. Casinospiele machen mit Boni gleich viel mehr Spaß und sind spannender, oder? Wir erfüllen die wichtigsten Anforderungen und Standards für verantwortungsvolles Spielen und bieten Ihnen daher alle Tools, die Sie für sicheres Spielen benötigen. Wenn Sie Unterhaltung auf Casino.NV auswählen, erhalten Sie Zugriff auf moderate Roulette-, Blackjack-, Baccarat- und Pokertische.
References:
https://s3.amazonaws.com/onlinegamblingcasino/hot%20bet%20casino.html
References:
Test and anavar before and after
References:
https://wikimapia.org/external_link?url=https://www.valley.md/anavar-results-after-2-weeks-ca
References:
Roulette systems
References:
http://pattern-wiki.win/index.php?title=tangsingh0489
References:
California casino las vegas
References:
https://etuitionking.net/forums/users/thrilliron6/
best anabolic supplements for quick gains
References:
https://bookmarkfeeds.stream/story.php?title=testosterone-the-great-male-optimization-myth
craze pre workout reviews
References:
https://bookmarkzones.trade/story.php?title=endocrinologist-or-urologist-for-low-testosterone-which-should-i-see
reliable steroid source
References:
https://ekademya.com/members/pilotcloud5/activity/177420/
References:
Trt and anavar before and after
References:
https://www.24propertyinspain.com/user/profile/1358725
References:
Anavar reviews before and after
References:
https://livebookmark.stream/story.php?title=anavar-cycle-guide-safe-dosage-best-results-2025
gnc build muscle fast
References:
https://mccaffrey-hu-2.mdwrite.net/comprar-methandienone-pastillas-mejores-precios-y-efectividad
turning fat into muscle supplements
References:
http://stroyrem-master.ru/user/iraqcable72/
References:
Before and after using anavar
References:
https://aryba.kg/user/dillfox3/
References:
Should i take anavar before or after workout
References:
https://gpsites.win/story.php?title=anavar-dosage-guide-complet-pour-optimiser-vos-resultats
References:
Anavar women before and after
References:
https://freebookmarkstore.win/story.php?title=anavar-oxandrolone-cure-cycle-avis-et-dangers
of course like your website but you need to test the spelling on several of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I in finding it very bothersome to tell the truth then again I will definitely come again again.
References:
Anavar and winstrol stack before and after
References:
http://king-wifi.win//index.php?title=teethworm6
%random_anchor_text%
References:
https://xypid.win/story.php?title=trenbolone-for-sale-online-in-uk-us
are steroids bad
References:
https://googlino.com/members/claussong40/activity/543202/
steroids are composed of
References:
https://hikvisiondb.webcam/wiki/Come_aumentare_il_testosterone_e_perch_bisogna_tenerlo_alto
References:
Slot machine jammer
References:
https://telegra.ph/Candy96-Reviews-01-23
References:
Shokawah casino
References:
https://oiaedu.com/forums/users/ocelotboat38/
References:
Schecter blackjack atx c 7
References:
https://chen-pugh-2.technetbloggers.de/probleme-de-thermostat-de-securite-avec-les-seche-linge-candy
References:
Seminole casino coconut creek
References:
https://lovewiki.faith/wiki/Candyspinz_Casino_arnaque_ou_site_fiable_Bonus_exclusif
References:
Best online casino reviews
References:
https://chessdatabase.science/wiki/Jelly_Candy_Slot_gratuita_senza_limiti_di_tempo
References:
Venetian casino macau
References:
https://may22.ru/user/europepoet38/
%random_anchor_text%
References:
https://livebookmark.stream/story.php?title=dianabol-methandienon-kaufen-deutschland
best products to gain muscle
References:
https://elearnportal.science/wiki/Winstrol_Vs_Anavar_Which_One_Is_Right_for_You
steroids vs testosterone boosters
References:
https://nephila.org/members/bumpercheese74/activity/1123429/
top 5 bodybuilding supplements
References:
https://pediascape.science/wiki/Dove_comprare_il_testosterone
References:
Hunger games online game
References:
https://santos-bertelsen-2.technetbloggers.de/candy-raymond-wikipedia
References:
Sands casino bethlehem
References:
https://morphomics.science/wiki/Enjoy96_Casino_Australia_2025_Play_Now
References:
River rock casino richmond
References:
https://timeoftheworld.date/wiki/Fullsized_Cocktail_Table_Arcade_Game_with_60_Classic_Games
References:
William hill mobile casino
References:
https://yogicentral.science/wiki/Candy_Casino_Review_2026_Slots_Bonuses_Ratings
mexican steroids for sale
References:
https://www.fionapremium.com/author/squarerouter4/
winstrol effects
References:
https://egamersbox.com/cool/index.php?page=user&action=pub_profile&id=263864
short cut shred
References:
https://instapages.stream/story.php?title=testosteronmangel-verringerter-testosteronspiegel-hypogonadismus
anabolic supplement price
References:
https://funsilo.date/wiki/Closest_Thing_to_Steroids_Top_5_Alternatives
References:
Peppermill casino reno
References:
https://sciencewiki.science/wiki/Offizielle_Website_fr_Deutschland
References:
Laughlin nevada casinos
References:
https://morphomics.science/wiki/888_Casino_Bonus_Code_Gratis_Gutschein_Bonus_ohne_Einzahlung
References:
Casino drive bastia
References:
https://morphomics.science/wiki/Offizielle_Seite_3_000_Bonus_350_Freispiele
References:
Bally slot machines
References:
https://www.giveawayoftheday.com/forums/profile/1607708
References:
Soaring eagle casino coupons
References:
https://egan-kejser.mdwrite.net/beste-playn-go-online-casinos-2026-die-top-slots-and-bonus-angebote
References:
Olympic casino poker
References:
https://classifieds.ocala-news.com/author/ocelottent69
References:
Newyork newyork casino
References:
https://mozillabd.science/wiki/Woo_Casino_NZ_Exciting_Online_Gaming_Experience
Good day very nice website!! Guy .. Excellent .. Superb .. I’ll bookmark your blog and take the feeds additionally?KI am satisfied to find so many useful info right here in the post, we need work out extra strategies on this regard, thank you for sharing. . . . . .
References:
Slot machine manufacturers
References:
http://jobs.emiogp.com/author/burmabush46/
is steroids testosterone
References:
https://linkagogo.trade/story.php?title=hi-tech-pharmaceuticals-winstrol
steroids for lean mass
References:
https://www.giveawayoftheday.com/forums/profile/1619578
anabolic research tren 75
References:
https://graph.org/Dianabol-Inj-50-02-04
References:
Mobile casino online
References:
https://botdb.win/wiki/How_to_Make_a_PayID_Deposit_at_Casino
is testosterone safe for bodybuilding
References:
https://telegra.ph/Clenbuterol-Kaufen-Online-Preis-September-2025-02-05
ultimate cutting stack
References:
https://stout-damsgaard-2.mdwrite.net/buy-tren-a-100-made-of-pure-trenbolone-acetate-in-uk-at-gymbodygear-com
mens steroids
References:
https://forum.dsapinstitute.org/forums/users/showspear6/