2025年6月、英国で発表されたレポート『Spin the bottle: How the UK alcohol industry twists the facts on harm and responsibility』は、アルコール業界の広報活動と公共政策への影響力行使を精緻に分析したものである。本レポートはエディンバラ大学のEmma Thompsonによって執筆され、Institute of Alcohol Studies(IAS)およびScottish Health Action on Alcohol Problems(SHAAP)という公衆衛生団体によって発行された。いずれの団体もタバコ政策を念頭に置いた産業監視の視点を強く持っており、商業的決定因(Commercial Determinants of Health)という国際的な概念に則って、アルコール産業の言説操作と政策干渉の構造を暴いている。
以下では、レポートが指摘する9つの主要な主張と、それに対する反証・分析を整理して紹介する。
1|経済に貢献しているという主張:数字の裏にある損失の構造
アルコール業界は、雇用創出や税収を理由に、公共政策の対象として「保護」されるべき存在として自身を描いている。しかし、NHSや刑事司法への負担、生産性損失など、アルコールがもたらす社会的コストは英国だけで年270億ポンドに上る。税収(約110億ポンド)をはるかに上回っており、「貢献」どころか「損失源」としての性格が濃い。
2|過剰課税されており業界が危機だという主張:危機演出のレトリック
税制改正(2023年8月)の際、業界団体は「過去50年で最大の増税」と批判し、収益減少を主張したが、実際の税収は前年度とほぼ同水準。Diageoはむしろ過去最高益(60億ドル)を計上した。業界が一貫して用いる「雇用喪失」や「地方経済への打撃」といった語りは、公共政策を封じるための政治的言語にすぎない。
3|アルコール被害は減少傾向にあるという主張:選択的な指標使用と矮小化
2024年現在、英国のアルコール関連死は過去最高レベルに達している。にもかかわらず、業界は若者の飲酒減少や飲酒運転の減少といった「都合の良い」指標を強調する。全体的な被害傾向を語らず、部分的な改善をもって「問題は小さい」と見せかけるこの手法は、タバコ産業にも見られた典型的な戦術である。
4|責任ある飲酒と低・無アルコール製品で被害は減るという主張:消費継続を前提とした“解決策”
業界は「節度ある飲酒」キャンペーンや無アル製品を、あたかも被害対策であるかのように扱う。しかし、節度的飲酒を勧めるプログラムには効果がなく、むしろリスク情報の隠蔽や正常化をもたらすとの批判がある。無アル製品も消費抑制ではなく「市場拡大」の手段として設計されており、実際に業界内部資料では「フルアル製品の売上を奪わない」ことが高く評価されている。
5|アルコールは地域社会を支えているという主張:共同体イメージの政治利用
「パブは孤独を癒す場」「社会の絆を育む」といった言説は、BBPAなどの業界団体が繰り返し使うレトリックだ。しかし、アルコールによる暴力、地域医療の圧迫、治安悪化、家族崩壊といった「社会的被害」には一切言及されない。さらに、実際の中小パブ運営者は業界団体の主張に懐疑的であり、業界は「地域の声」すら代表していないという批判もある。
6|アルコール業界は多様性と包摂に貢献しているという主張:アライシップのビジネス化
DiageoなどはLGBTQ+や女性に向けた広告、イベント支援、雇用施策などを「包摂的企業活動」としてアピールしている。しかし、これらのグループはアルコールによる健康リスク・社会的被害をより大きく被っており、マーケティングによるターゲティングとの矛盾が浮き彫りになる。「社会貢献」という外見の下で、実態は新市場の開拓であり、WHOはこれを商業的搾取と見なしている。
7|環境保護に取り組む産業だという主張:グリーンウォッシングの構造
紙ボトルや水源支援プロジェクトなど、業界は環境対応を盛んに喧伝するが、同時にEPR(包装廃棄物の責任制度)などの環境規制には反対。ペットボトル回収や泥炭地保全の規制にもロビー活動で抵抗している。象徴的な「持続可能な酒づくり」は限定的な試験導入に留まり、実態はブランドPRの一環に過ぎない。
8|業界資金の団体は独立しているという主張:利益相反と情報の私物化
Drinkawareは「独立した慈善団体」とされるが、資金の大部分は業界由来。2024年の活動では、HeinekenやStaropramenと組んだ販促的キャンペーンが展開され、「啓発」と「宣伝」が曖昧化されている。提供される健康情報には誤解を招く表現も多く、政策介入を装った情報操作が懸念されている。
9|業界はアルコール被害の解決に貢献しているという主張:教育を通じた影響力拡大
Smashedなどの学校向けプログラムは「飲酒の害を伝える」とされるが、実際には飲酒の正常化・容認を促す内容で構成されている。WHOはこれを「企業広告による教育の私物化」とし、特に子どもや若者を対象とした活動は明確に制限すべきだと勧告している。にもかかわらず、英国ではこうしたプログラムが教育現場に受け入れられつつある。
まとめ|「責任ある産業」という物語の終わりへ
『Spin the bottle』が描くのは、アルコール業界がいかにして「責任あるふり」を通じて、構造的な誤情報を社会に流通させているかという実態である。それは単なる事実の歪曲ではなく、経済、健康、環境、教育といった領域にまたがるナラティブの設計であり、制度的規制を回避するための戦略的情報操作にほかならない。
こうした語りが社会の中で「もっともらしく」受容される過程こそが、誤情報の構造的側面であり、対策を考える上での核心である。業界の発信をそのまま「情報」として扱うことの危険性を、このレポートは具体的かつ体系的に示している。

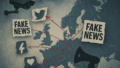
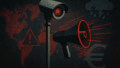
コメント
Jetzt loggen Sie sich in Ihr neues Konto ein und laden es
mit SEPA, Visa/Mastercard oder sogar Bitcoin auf – so einfach
ist das! Sobald Sie Ihre Informationen eingereicht haben, dauert es nur Stunden, bis sie
Ihr Konto per E-Mail verifizieren. Füllen Sie das Formular mit Ihren persönlichen Daten aus,
laden Sie einen Scan Ihres amtlichen Ausweises hoch und stimmen Sie ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
Bereiten Sie sich auf ein aufregendes Online-Gaming-Erlebnis mit Spielbank Köln Casino vor!
Mit solch großzügigen Belohnungen und niedrigen Einzahlungsvoraussetzungen werden Sie im Handumdrehen große
Gewinne einfahren! Und das ist noch nicht alles – bestehende
Spieler können sich auf wöchentliche Reload-Boni von 50% bis
zu 100 € sowie 10% Cashback auf Nettieverluste bis zu 200 € jede Woche freuen.
Dock² ist eine moderne Eventlocation im industriellen Stil in Mülheim.
Mit einer Kapazität von bis zu 1000 Gästen und einem erstklassigen Catering-Service ist diese Location ideal
für große Casino-Events. Die vielseitigen Räumlichkeiten und die Möglichkeit, sowohl Indoor- als auch Outdoor-Bereiche zu nutzen, machen die Rheinterrassen ideal für
Events jeder Art. Die Rheinterrassen direkt am Rhein bieten eine
Vielzahl von Veranstaltungsräumen, darunter eine Parksaal-Terrasse und einen Biergarten. Die Location kann flexibel gestaltet werden, um
den Bedürfnissen eines mobilen Casinos gerecht
zu werden. Die großen Fensterfronten lassen viel Tageslicht herein und schaffen eine helle, einladende Atmosphäre.
SpielhalleAuf dem Berlich 1, Breite Str. Das Servicepersonal der Kölner Spielhallen ist stets freundlich und professionell und hilft gerne weiter, falls Fragen bestehen. Die Spielhalle
Spiel Kiste oder die Spielotheken Spielpalast. Neben bekannten Spielotheken wie Merkur oder ADMIRAL gibt es auch kleinere Spielotheken und
Spielhallen-Ketten, die nur im Rheinland ansässig sind, wie
z. Hier findet man sowohl beliebte Spiele wie Lucky Lady’s Charm oder Eye of
Horus, als auch Neuerscheinungen – alle auf modernen Geräten von Herstellern wie
Merkur oder Novo Line. Und das Beste an den vielen Spielotheken in Köln ist,
dass sie nicht nur zur Karnevalszeit, sondern das ganze Jahr über geöffnet haben.
References:
https://online-spielhallen.de/vulkan-vegas-casino-erfahrungen-ein-umfassender-uberblick/
Try your luck at the freshly rebuilt casino, which has a total area
of 65,000 square feet. With award-winning restaurants and five
bars, there’s plenty to do.
With the redesigned private gaming rooms Sovereign and
Oasis, the land based casino delivers the finest in premium gaming experiences.
Mississippi stud poker, three card poker, Caribbean stud
poker, and Texas Hold ’em bonus poker are among the poker games available on the
casino floor. Only two poker tables are available in the poker room, with the majority of the games being Texas
Hold ’em ($2/$3). After you’ve finished spinning the reels, walk over to the
table games area to try your hand at your favorite table casino games.
More information on premium membership access and advantages will be sent to eligible
members.
References:
https://blackcoin.co/ecarte-poker/
King Billy Casino has been thoughtfully designed to offer Australian players a selection of bonuses that may be of interest to those seeking added value from
their online gaming experience. It’s an online gambling site
offering pokies, table games, live dealer options, and promotions for players worldwide,
including Australia. Australian players access the full game library, banking options including PayID payments,
live chat support, and promotional features through mobile browsers.
All games, bonuses, and live chat available on mobile.
With over 5,000 titles from top providers, King Billy Casino offers Australian players an unmatched variety of pokies, live dealer games, and progressive jackpots.
Secure your spot among the top 500 players on the leaderboard to
claim your winnings! For players craving even more excitement, don’t
miss the Playson Cash Days Tournament, held during the
first week of every month. For our most loyal and active players,
the prestigious status of King/Queen is an exclusive privilege.
This bonus is available for 30 days after your first deposit, giving you plenty
of time to claim it when ready. Unlock royal treasures with
King Billy Casino’s exceptional promotions designed for Australian players.
Newcomers receive a welcome package with a deposit bonus
and free spins. Additionally, players can benefit from an informative FAQ section.
References:
https://blackcoin.co/what-to-wear-for-the-casino-dress-code-and-whatll-get-you-kicked-out/
paypal online casino
References:
http://the-good.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=4468611
online casino australia paypal
References:
https://divyangrojgar.com/employer/best-paypal-online-casinos-in-the-us-2025/
online casino with paypal
References:
https://wisewayrecruitment.com/employer/best-online-casinos-australia-top-aussie-real-money-sites-2025/
online casino mit paypal
References:
https://spechrom.com:443/bbs/board.php?bo_table=service&wr_id=434067
Yes, we feature a robust selection of live dealer games, including, but not limited to, Baccarat, Roulette, Blackjack, and many more. Slot enthusiasts can enjoy everything from classic 3-reel games to advanced video slots. Easy rules for new players, deep strategy for the experienced – it’s all here! Chat with live dealers and players for a social, dynamic thrill.
With every spin, the jackpot grows, creating opportunities for extraordinary payouts that can elevate your gaming experience to new heights. Whether you’re a seasoned strategist or simply seeking to unwind, you’ll find the perfect table to suit your style. Every spin is more than just a game – it’s an invitation to indulge in a moment of elegance and exhilaration. From the understated charm of classic three-reel slots to the dynamic visuals and interactive features of modern video slots, your options are as boundless as your imagination.
Once logged in, players can enjoy all the exclusive benefits that Lucky Ones Casino has to offer whilst they spin their way to extraordinary wins. Both interfaces offer a straightforward and simple way for players to log in to their account and play away. Furthermore, players can relax and not worry about the safety or security of their account as Lucky Ones covers that in full. If you’re looking for the ultimate gaming experience filled with luxury spins and exciting wins, then Lucky Ones Casino is the place for you With our VIP Program and that special high-roller treatment, Lucky Ones is where real players belong.
References:
https://blackcoin.co/ufo9-casino-your-place-to-play-your-way/
gamble online with paypal
References:
https://jobstak.jp/companies/payid-online-casinos-in-australia-for-2025-play-payid-pokies/
online betting with paypal winnersbet
References:
https://career.abuissa.com/employer/best-real-money-online-casinos-2025-updated-list/
online casinos mit paypal
References:
https://career.abuissa.com/employer/online-casinos-that-accept-paypal/
paypal casinos for usa players
References:
https://adremcareers.com/employer/us-online-casinos-that-accept-paypal-2025/
online casino real money paypal
References:
https://directorio.restaurantesdeperu.com/employer/paypal-gambling-sites-where-its-accepted/
paypal casinos online that accept
References:
https://www.cybersecurityhouse.com/employer/list-of-the-best-paypal-casinos-uk-december-2025/
Bei den Automatenspielen sind die progressiven Jackpots mit steigender Gewinnsumme von der Zulassung ausgenommen. Deutsche Lizenz Casinos dürfen keine klassischen Casino Spiele, die sogenannten Tischspiele, anbieten. Nicht alle online Casinos bieten Paypal, Paysafe oder Kreditkarte als Einzahlungsmöglichkeit an. Fast alle online Casinos bieten dieses Feature an und man sollte es auch nutzen.
Am häufigsten sind virtuelle Spielautomaten in deutschen Casinos online vertreten. Deutsche Online Casinos bieten viel mehr der beliebtesten Casino-Spiele als Sie jemals in einem realen Casino finden werden. Von Kredit- und EC-Karten über E-Wallets bis zu Instant-Banking sollten alle Vorgänge mit SSL-Verschlüsselung sicher, schnell und für Anfänger, Gelegenheitsspieler und High Roller einfach ablaufen.
References:
https://s3.amazonaws.com/onlinegamblingcasino/casino%20royale%20caterina%20murino.html
Bei Bitstarz Casino gibt es neben einem attraktiven Willkommensbonus auch Turniere, eine Level Up Promo, Piggy Bank und ein VIP Programm. Das SurfPlay Casino ist ganz neu 2024 erschienen und besticht durch einen sehr vorteilhaften Willkommensbonus und einem soliden Zahlungsangebot. Dazu bietet die Spielothek ein saftiges Auszahlungslimit von 30.000€ im Monat und führt an der Kasse beliebte Zahlungsanbieter wie Visa, Mastercard, Krypto, Mifinity und Jeton. Das Willkommenspaket besteht aus 4 separaten Einzahlungsboni die der Reihe nach umgesetzt werden müssen und über eine Einzahlung von mindestens 20€ und einen Bonuscode aktiviert werden. Die Spielothek bietet wie seine Schwesterseiten eine außergewöhnlich gute Auswahl an Spielen, die von über 100 beliebten Spieleentwicklern bereitgestellt werden.
Joo Casino bietet eine große Auswahl an Spielen von Top-Anbietern wie NetEnt und Ezugi, darunter klassische Slots und Live-Casino-Erlebnisse. Insgesamt ist das Oshi Casino für sein umfangreiches Spielangebot, seine vielseitigen Ein- und Auszahlungsmethoden und seine starken Bonusangebote bekannt. Es bietet eine Vielzahl von Boni auf traditionelle Casino-Spiele und Sportwetten, einschließlich eines High-Roller-Bonus und eines Krypto-Bonus im Wert von 5 Bitcoin. Cobra Casino bietet eine breite Palette von Casino-Spielen und Live-Dealer-Spiele, mit einer massiven Spiel Sammlung von über 2000 Titeln. Unsere Liste basiert auf den besten Casinomerkmalen und einer Gesamtbewertung, die Bonusangebote, Spielauswahl, Sicherheit, Benutzerbewertungen und zusätzliche Merkmale umfasst. Arbeitet unter der Lizenz der Glücksspielbehörden in Curacao und bietet mehr als 80 Casinos an. Dama NV, ein bemerkenswerter Name in der Online Casino Branche, zeichnet sich durch seinen unverwechselbaren Spielansatz aus.
References:
https://s3.amazonaws.com/onlinegamblingcasino/casino%20online%20legal.html
Ich spiele jetzt schon seit ein paar Wochen bei Ice Casino. Die niedrigen Einzahlungsboni und die schnellen E-Wallet-Abhebungen sind Merkmale, die ich wirklich schätze. Wenn Sie sich an das Team wenden, kann es sein, dass Sie sogar einen personalisierten Bonus erhalten! Ich spiele hier schon seit Ewigkeiten, und nach der Verifizierung lief alles reibungslos. Schnell, höflich und wirklich hilfreich – Sie erhalten normalerweise innerhalb einer Minute eine echte Antwort.
Besonders die Willkommensboni der Online Casinos klingen oft sehr attraktiv und sollen natürlich Neukunden werben. Warum das so ist und mehr, erfährst du in unseren Ice Casino Erfahrungen oder überzeugst dich einfach selbst. Spieler, die ein unterhaltsames, zuverlässiges und lohnendes Casino-Erlebnis suchen, sollten Ice Casino online ausprobieren. Es hat eine große Auswahl an Spielen, darunter Slots, Tischspiele und Live-Dealer-Optionen.
References:
https://s3.amazonaws.com/onlinegamblingcasino/spielgeld%20casino.html
Hinzu kommt eine ellenlange Liste von verbotenen Slot-Spielen sowie ein Maximalgewinn, der dem 5-fachen des erhaltenen Bonusbetrags entspricht. Mit bis zu 1.200 Euro und 220 Free Spins fällt der Willkommensbonus im Verde Casino ziemlich üppig aus. So gibt es auf Stufe 2 beispielsweise einen 70% Bonus + 25 Freispiele und auf Stufe 5 einen 110% Bonus + 40 Freispiele. Da sich auf dieser Liste auch sehr viele beliebte Spiele befinden, solltest du vor der Einlösung des Willkommensbonus unbedingt einen Blick darauf werfen. Richtig ärgerlich ist aus unserer Sicht allerdings die Vorgabe, dass du maximal das 5-fache des erhaltenen Bonusguthabens gewinnen kannst. Wenn du dir einen der vier Willkommensboni sichern möchtest, solltest du natürlich auch die dazugehörigen Umsatzvorgaben kennen. Ebenfalls im dritten Bonuspaket enthalten sind 50 Freispiele für den allseits beliebten Spielautomaten „Starburst“.
Karten und Tischspiele werden von professionellen Croupiers aus stationären Casinos und ausgestatteten Studios gespielt. Tischspiele sind eine Alternative zu Spielautomaten. Der Online Club bietet mehr als 3.000 Original Attraktionen internationaler Anbieter.
References:
https://s3.amazonaws.com/onlinegamblingcasino/fun%20id%20casino.html
Bedingungen wie eine 60x Umsatzanforderung machen es sehr schwer, Bonusgelder in auszuzahlende Gewinne umzuwandeln. Bestehende Spieler müssen in der Regel nach Reload-Boni, Freispiele oder anderen Treueprämien suchen, die möglicherweise für sie verfügbar sind. Die Online Casinos nutzen diese Angebote vor allem, um neue Spiele zu gewinnen. Um eventuelle Gewinne auszahlen zu können, musst du allerdings immer die geltenden Umsatzbedingungen und das maximale Gewinnlimit beachten.
Auch darüber sollten Sie sich erkundigen, damit Sie keine Nachteile haben und später eine Auszahlung erhalten. Provisionen, die wir für die Brands-Vermarktung erhalten, haben keinen Einfluss auf die Spielerfahrung eines Benutzers. Minderjährige unter 18 Jahren sind nicht zugelassen, da Glücksspiele schwerwiegende Folgen haben können, wenn sie nicht verantwortungsvoll gespielt werden. Dieser praktische Ansatz hilft Spielern, ihre Lieblingsspiele zu entdecken und ihre Spielvorlieben in einer risikofreien Umgebung zu verfeinern. Mit Bonusangeboten ohne Einzahlung können Sie Spiele mit echtem Geld genießen, ohne eine erste Einzahlung zu tätigen. Einige Online Casinos bieten Boni ohne Einzahlung für Tischspiele wie Blackjack und Roulette.
References:
https://s3.amazonaws.com/new-casino/online%20casino.html
References:
Anavar in women before and after
References:
https://doodleordie.com/profile/bedjuice84
References:
Casino online roulette
References:
https://hikvisiondb.webcam/wiki/WD40_Casino_Review_Expert_Player_Ratings_2026
References:
Roulette bets
References:
https://yogicentral.science/wiki/Refer_a_Friend_Casino_Bonuses_80_Offers_By_Country
bodybuilders after steroids
References:
https://obyavlenie.ru/user/profile/647068
can you take clenbuterol with testosterone
References:
https://onlinevetjobs.com/author/piscessalmon94/
buying steroids online reviews
References:
https://yogaasanas.science/wiki/The_10_Best_Testosterone_Supplements_for_Men
References:
Anavar pictures before after
References:
https://livebookmark.stream/story.php?title=anavar-oxandrolone-avis-dun-pro-du-sport-sur-ce-steroide
References:
Before and after anavar only
References:
https://dokuwiki.stream/wiki/Anavar_Es_efectiva_O_No_La_Oxandrolona_Descbralo_Ahora
References:
Anavar before and after women
References:
http://dubizzle.ca/index.php?page=user&action=pub_profile&id=100944
steve cook steroids
References:
https://starleek3.werite.net/oxandrolona-comprar-precio-online-en-espana
References:
Test e and anavar before and after pics
References:
https://schwanger.mamaundbaby.com/user/napkinhandle0
are all steroids illegal
References:
https://king-bookmark.stream/story.php?title=winstrol-stanozolol-injections-tabletten-kaufen-sie-in-deutschland
online anabolic steroids pharmacy
References:
https://linkagogo.trade/story.php?title=los-7-mejores-suplementos-para-ganar-masa-muscular-a-los-50-anos-comparativa-2026
decca steroids for sale
References:
https://hackmd.okfn.de/s/HyNfqfFHWe