International Fact-Checking Network(IFCN)が毎年発行する「State of the Fact-Checkers Report」は、世界中のファクトチェック団体が直面している現実を定点観測する貴重な資料である。2025年3月に公開された2024年版は、資金の不安定化、AIの導入、ハラスメントの増加といった断片的な問題が、一つの構造的な問いへと集約されていく過程を静かに示している。
それはつまり、「誰が、どのように、事実を支えるのか」という根本的な問いである。以下に、報告書の構成に沿って、その全体像を紹介する。
1. 財政の不安定化とMeta依存の限界
報告書の冒頭で明示されるのは、ファクトチェックの現場は、制度的にも財政的にも不安定な状態にあるという現実である。特に大きな影響を与えているのが、Facebookなどを運営するMetaが提供してきた第三者ファクトチェック支援の段階的終了である。
2024年時点では、回答団体のうち45.5%がMeta支援を主要な収入源としており、それが打ち切られることで、
- 出力の削減(30.1%)
- 人員削減(29.3%)
- 閉鎖の可能性(8.3%)
という深刻な影響が予想されている。ファクトチェックの持続可能性は、大手プラットフォームの判断一つで揺らぎうる構造にあったことが、ここで明るみに出ている。
2. AIの導入と人の判断の価値
一方で、レポートは「AI導入が進んでいる」というポジティブな変化も示す。実際、調査支援などには53.6%の団体がAIを活用している。しかし、コンテンツ生成やレポート執筆にまで活用を広げている団体は少ない。
その背景には、以下のような懸念がある:
- 倫理的・編集的判断がAIに任せきれない
- 多言語対応の限界(特に非英語圏)
- 技術知識や信頼性の問題
つまり、「使えるが、任せきれない」というのが現状であり、人の判断の価値はむしろ再確認されている。この点は、AI時代におけるファクトチェックの本質的な立ち位置を示唆している。
3. 発信手段の変化と情報密度のジレンマ
情報の届け方も変化している。2024年のデータでは、TikTokやYouTube Shortsといった短尺動画が最も効果的とされている。情報の簡潔化と視覚化が求められる一方で、長文の検証記事や複雑な文脈の説明が伝わりにくくなるという「情報密度のジレンマ」が生じている。
この点についてレポートは評価や解決策を述べていないが、ファクトチェックが「届くこと」と「伝えること」の両立に直面していることが浮き彫りになっている。
4. ハラスメントとセキュリティの不備
2024年、調査対象の78%が嫌がらせを経験しており、その一部は物理的脅迫や家族への影響にまで及んでいる。にもかかわらず、正式な対応策を持っている団体は2割程度にとどまり、多くが非公式対応または無対策だった。
また、3割以上の団体がサイバー攻撃を受けたと回答しているが、こちらも対策の不備が目立つ。事実を守る側が、守られていないという構図は、そのまま報道の安全保障の脆弱性に通じる。
5. 連携による補完と支え合いの構造
こうした不安定な状況のなかで、約8割の団体が他のファクトチェッカーや研究機関、NGOと協力関係にあることは、重要な補完構造といえる。とりわけ、資源の少ない地域においては、地域ネットワークの形成(回答者の73%が所属)が活動の継続に不可欠になっている。
レポートは「競争」よりも「連携」が選ばれている現実を静かに描いており、それがこの分野の倫理的・実践的な性格を示している。
まとめ:ファクトチェックを支える構造は揺らいでいる
このレポートが示しているのは、偽情報そのもの以上に、「それを訂正する営み」が脆弱な基盤に支えられているという事実である。
- 民間資金への過度な依存
- 技術導入の限界と人手への依存
- 発信方法の変化とそれに伴う質の問題
- ハラスメントへの対応不全
- そして、それでも連携しようとする現場の努力
つまり、このレポートは「事実が危機にある」というより、「事実を守る構造が危機にある」ことを描いている。この危機にどう向き合うかが、2025年のファクトチェックの核心的課題となるだろう。
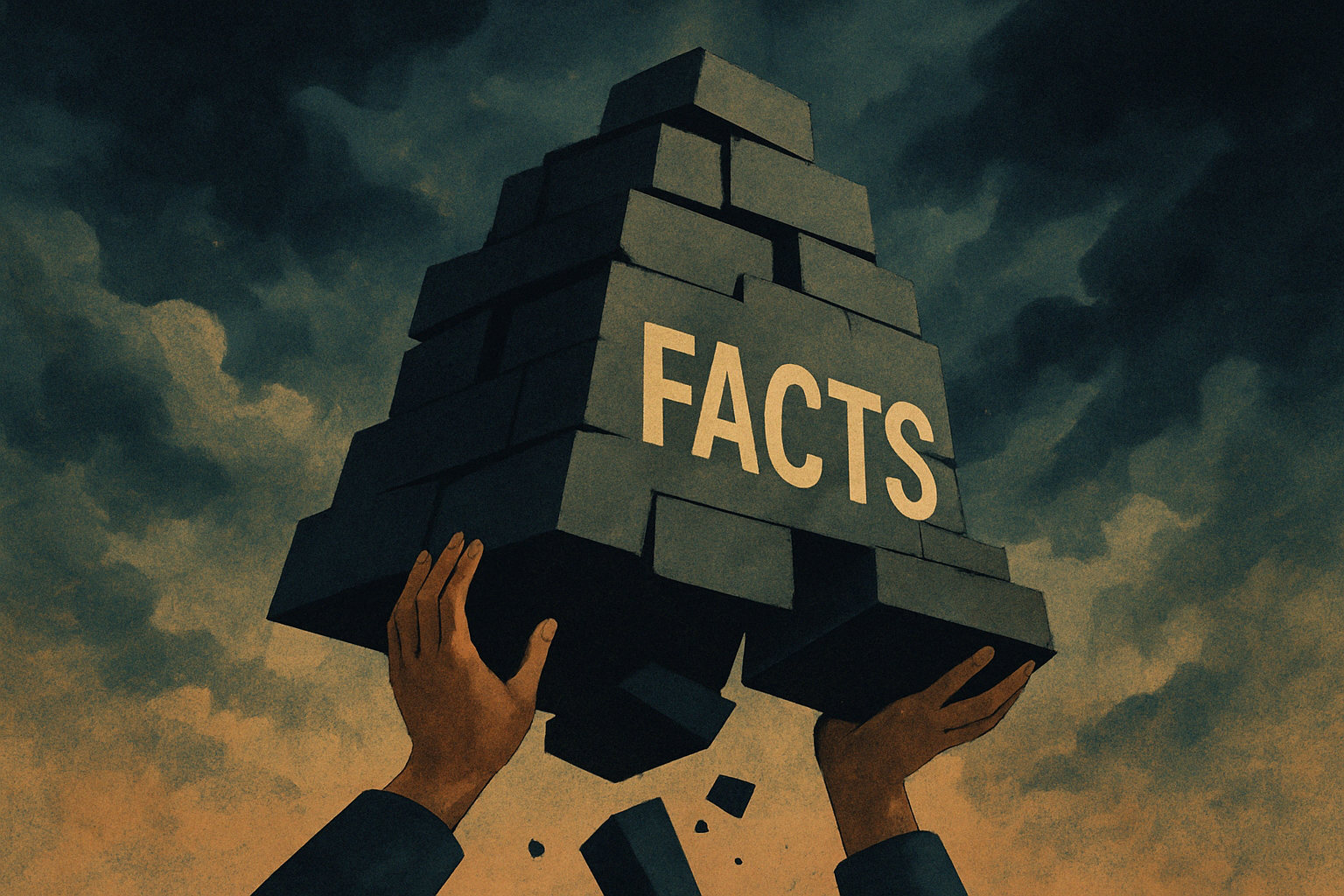


コメント
Erst danach kannst du den lukrativen Sonnenspiele Bonus einlösen. Der Sonnenspiele Gutschein ist unabhängig von Art
immer an eine Kontoeröffnung geknüpft. Damit du den Sonnenspiele
Bonus optimal nutzen kannst, liefern wir dir eine Anleitung, mit der du Schritt für Schritt vorgehen kannst.
Auch bei Sonnenspiele machen wir keine Kompromisse, wenn es um Qualität und Fairness geht.
Sonnenspiele hat die nunmehr 9 Automaten-Lizenz in Deutschland als Veranstalter von Online Slots erhalten. Es ist damit zu rechnen, das
edict die Plattform sowie Automatenspiele stellt, was bedeutet, dass auch weitere
Drittanbieter mit ihren Spielehighlights verfügbar sein werden. Mehr als 24 Jahre Erfahrung hat der Online-Glücksspielexperte mit Fokus auf
Deutschland bei Solar Operations Limited vorzuweisen und ist sicher nicht ohne Grund an dieser Position eingesetzt worden.
References:
https://online-spielhallen.de/princess-casino-erfahrungen-ein-umfassender-uberblick/
First of all, wagering is 40× (bonus + FS wins). There
are some additional conditions for all four welcome deposits.
Looking for a casino to trust fully and win big in Australia?
All the deposits with these options are instant.
Choose whatever suits your current mood and enjoy not just the thrilling atmosphere of
games, but also real money winnings! SkyCrown Casino counts more than 10,000 titles of games.
Always remember to read all the terms and conditions before gambling at SkyCrown Casino.
Finally, the validity of each welcome bonus part is 14 days.
Moreover, maximum win and cashout is FS wins cap A$300; bonus cashout cap A$5,000.
References:
https://blackcoin.co/imperial-poker/
The link you provided led to an email address so, assuming it doesn’t come back as a no
one’s home, I should be en route to leaving. View this
Answer within the discussion Or you can create your own Community discussion by clicking here
Welcome to the Sky Community forum, where customers
like you are on hand 24/7 (almost) to offer some fantastic advice and help on all things
Sky-related. I have the same issue, I can’t n either
know the status of my order not contact any customer service
Those channels are owned by UKTV which I think is a spin off from the BBC.
Why are all the u HD channels closing? Sky TV channels on PlayStation and Xbox This list is updated weekly for the week ahead,
but may still change.
References:
https://blackcoin.co/all-caesars-properties-in-las-vegas-2025-list/
casino mit paypal
References:
https://pivotalta.com/employer/10154/our-favorite-paypal-casinos-2025-ranking-update/
paypal casinos for usa players
References:
http://nilsgroup.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=50402
online casinos that accept paypal
References:
http://play.kkk24.kr/bbs/board.php?bo_table=online&wr_id=275909
mobile casino paypal
References:
https://jobboat.co.uk/employer/325765/best-online-payout-casinos-in-australia-2025
gamble online with paypal
References:
https://www.vulnerableyouthjobs.ca/companies/40-best-australian-online-casinos-for-real-money-in-december-2025/
online betting with paypal winnersbet
References:
https://cvbankye.com/employer/top-paypal-casino-sites-in-canada-for-december-2025/
Нужны грузчики? грузчики в ивантеевка недорого : переезды, доставка мебели и техники, погрузка и разгрузка. Подберём транспорт под объём груза, обеспечим аккуратную работу и соблюдение сроков. Прозрачные тарифы и удобный заказ.
Планируешь перевозку? услуги перевозок удобное решение для переездов и доставки. Погрузка, транспортировка и разгрузка в одном сервисе. Работаем аккуратно и оперативно, подбираем машину под объём груза. Почасовая оплата, без переплат.
Ищешь грузчиков? грузчики новосибирск помощь при переезде, доставке и монтаже. Аккуратная работа с мебелью и техникой, подъем на этаж, разборка и сборка. Гибкий график, быстрый выезд и понятная стоимость.
Wonderful beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how could
i subscribe for a blog website? The account aided me a acceptable deal.
I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea
стартовал наш новый https://utgardtv.com IPTV?сервис, созданный специально для зрителей из СНГ и Европы! более 2900+ телеканалов в высоком качестве (HD / UHD / 4K). Пакеты по регионам: Россия, Украина, Беларусь, Кавказ, Европа, Азия. Фильмы, Спорт, Музыка, Дети, Познавательные. Отдельный пакет 18+
Ищешь музыку? слушать музыку популярные треки, новые релизы, плейлисты по жанрам и настроению. Удобный плеер, поиск по исполнителям и альбомам, стабильное качество звука. Включайте музыку в любое время.
Neben dem Willkommensbonus gibt es regelmäßige Promotionen, kostenlose Freispiele und exklusive Rakeback-Belohnungen. 20 Freispiele ohne Einzahlung ermöglichen Dir einen risikofreien Start, während der Willkommensbonus von bis zu 5 BTC Dein Guthaben erheblich steigert. Stellen Sie unbedingt sicher, ausschließlich in einem Krypto Casino zu spielen, das über eine gültige Lizenz verfügt und adäquate Maßnahmen zum Schutz der Spieler gewährleistet. Nur so ist es möglich, jederzeit von unterwegs spielen zu können.
Aufgrund seines klaren Schwerpunkts und der großen Auswahl zählt Slots Gallery für viele Spieler zu den beste crypto casinos deutschland. Dank seiner zuverlässigen Performance und breiten Auswahl gehört es für viele Spieler zu den beste crypto casinos deutschland. Krypto Online Casinos bieten Ihnen eine einzigartige und bequeme Möglichkeit, online zu spielen.
References:
https://s3.amazonaws.com/onlinegamblingcasino/casino%20ohne%20lizenz%201337games.io.html
Seht die Freispiele stattdessen als kleines Dankeschön für eure Registrierung an und verwendet diese, um das Casino und seine Spielautomaten erst einmal unverbindlich auszuprobieren. Ihr könnt euch dementsprechend selbst ausrechnen, wie viel Geld man an einem Slot mit einem derartig niedrigen Einsatz gewinnen kann. So können Online Casinos auch weiterhin Freispiele ohne Einzahlung anbiete, das Risiko für eigene Verluste jedoch geschickt minimieren. Aus diesem Grund sind Freispiele ohne eine Einzahlung aktuell an verschiedene Vorgaben gebunden, die in der Regel strenger ausfallen als die Umsatzbedingungen bei einem klassischen Casino Bonus. Verschenkt man hingegen Freispiele, ohne dass der Spieler dafür Geld investieren muss, erweist sich jeder hierbei erspielte Gewinn als Verlust für das Casino. Im Idealfall kann man auf diese Weise also echtes Geld gewinnen, ohne zuvor eigenes Geld investiert zu haben.
Zu den Nachteilen eines Gratis-Guthabens und von kostenlosen Freispielen zählen die Umsatzbedingungen. Freispiele beziehen sich ohnehin auf einen einzelnen Spielautomaten, aber auch Bonusgelder können Sie nicht für das komplette Spielangebot verwenden. Es gibt auch viele Anbieter, bei denen Sie den Neukundenbonus ganz automatisch erhalten, sobald Sie sich registriert haben. Meist handelt es sich dabei um Automatenspiele, es gibt aber auch Casinos, in denen die User ihr Bonusgeld zusätzlich auch für Tischspiele oder andere Kategorien einsetzen dürfen.
References:
https://s3.amazonaws.com/onlinegamblingcasino/casino%20verde%20bonus.html
need a video? venice production company offering full-cycle services: concept, scripting, filming, editing and post-production. Commercials, corporate videos, social media content and branded storytelling. Professional crew, modern equipment and a creative approach tailored to your goals.
Нужна фотокнига? фотокниги недорого печать из ваших фотографий в высоком качестве. Разные форматы и обложки, плотная бумага, современный дизайн. Поможем с макетом, быстрая печать и доставка. Идеально для подарка и семейных архивов
Хочешь фотокнигу? печать фотокниг для фотографов в москве индивидуальный дизайн, премиальная печать и аккуратная сборка. Большой выбор размеров и переплётов, помощь с версткой. Быстрое производство и доставка
Продажа тяговых https://faamru.com аккумуляторных батарей для вилочных погрузчиков, ричтраков, электротележек и штабелеров. Решения для интенсивной складской работы: стабильная мощность, долгий ресурс, надёжная работа в сменном режиме, помощь с подбором АКБ по параметрам техники и оперативная поставка под задачу
Продажа тяговых https://ab-resurs.ru аккумуляторных батарей для вилочных погрузчиков и штабелеров. Надёжные решения для стабильной работы складской техники: большой выбор АКБ, профессиональный подбор по параметрам, консультации специалистов, гарантия и оперативная поставка для складов и производств по всей России
Das SpinFever Casino bietet ein nahtloses Spielerlebnis mit vielen Spielen und schnellen Auszahlungen. Fortune Play ist eines der neuesten Angebote von Dama N.V. Sie haben eine riesige Spielauswahl und jede Menge Boni. LevelUp Casino bietet ein nahtloses Spielerlebnis mit vielen Spielen und schnellen Auszahlungen. Noch mehr bieten und die erstklassige Technologie von Softswiss für ein reibungsloses Spielerlebnis nutzen. Diese Casinos sind für ihre vielfältigen Spielebibliotheken, schlanken Benutzeroberflächen und zuverlässigen Plattformen bekannt und bieten ein erstklassiges Spielerlebnis.
Mich hat das 7Bit Casino insbesondere mit seinen schnellen 15-Minuten-Auszahlungen und dem wirklich sehr hohen Neukundenbonus überzeugt. Das Unternehmen stattet seine Spieleplattformen gemeinhin mit enorm vielen Games aus und ist auch sonst überaus serviceorientiert. Wenn ihr schon länger online spielt, ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr bereits in Dama NV Casinos gezockt habt. NV Casino überzeugt mit einem modernen und benutzerfreundlichen Design, einer großen Spielauswahl und attraktiven Bonusangeboten. NV Casino bietet eine Vielzahl sicherer und bequemer Zahlungsmethoden für Ein- und Auszahlungen. Stattdessen bietet die mobile Version der Website eine vollständig optimierte und nahtlose Spielerfahrung, die einer App in nichts nachsteht. Für Spieler, die gerne höhere Beträge setzen, bietet NVCasino einen speziellen Highroller Bonus.
References:
https://s3.amazonaws.com/new-casino/best%20online%20casino.html
Продажа тяговых https://faamru.com аккумуляторных батарей для вилочных погрузчиков, ричтраков, электротележек и штабелеров. Решения для интенсивной складской работы: стабильная мощность, долгий ресурс, надёжная работа в сменном режиме, помощь с подбором АКБ по параметрам техники и оперативная поставка под задачу
мягкая кровля плоская крыша https://ustrojstvo-ploskoj-krovli.ru
Продажа тяговых https://ab-resurs.ru аккумуляторных батарей для вилочных погрузчиков и штабелеров. Надёжные решения для стабильной работы складской техники: большой выбор АКБ, профессиональный подбор по параметрам, консультации специалистов, гарантия и оперативная поставка для складов и производств по всей России
Официальный маркетплейс доступен на kraken darknet с системой escrow для безопасности всех сделок
Right now: https://feldmaninv.com/casinia-casino-review/
Вызвать невролога на дом https://vrachnadom-sev.ru
Актуальный адрес маркета на ссылка на кракен маркет проверенная администрацией с защитой от фишинговых копий
Für die Freispiele gilt bei HitnSpin 25€ als die maximale Auszahlung. Du musst dich lediglich verifizieren, um den No Deposit Bonus zu erhalten. 50 Freispiele für “Big Bass Splash” (nach Verifizierung) Mit über 5.000 möglichen Games bietet HitnSpin eine enorme Bandbreite, sodass garantiert keine Langeweile aufkommt.
Viele der Casinospiele, die wir anbieten, sind nicht nur bereits seit langer Zeit beliebt, sondern bieten auch die Möglichkeit, echtes Geld zu gewinnen. So kann man sich sicher sein, dass man eine sichere und innovative Glücksspiele-Erfahrung machen kann, wenn man bei uns spielt. So kann jeder Spieler einige Games entdecken, die perfekt zu den eigenen Vorstellungen passen und es gibt immer wieder neue Spiele zu finden.
References:
https://onlinegamblingcasino.s3.amazonaws.com/candy%20casino%20no%20deposit%20bonus.html
Neben dem Willkommensbonus bietet das Coolzino Casino eine Vielzahl weiterer Boni und Promotionen für seine Spieler an. Abgerundet wird dieses Crypto Casino dann noch mit einer guten Auswahl an Spielen und soliden Willkommensbonus. Das Coolzino sah im letzten Jahr, 2024, das Licht der Welt zum ersten Mal und hat sich seitdem zu einem meiner Lieblingscasino gemustert. Darunter Slots, Tischspiele, und ein umfangreiches Live Casino, das eine breite Zielgruppe anspricht. Neben dem guten Willkommensbonus erwartet dich im Crypto Leo aber auch noch eine Reihe anderer aus unserer Sicht attraktiver Boni.
Üben Sie mit kostenlosen Versionen von Casinospielen, um sich mit den Regeln und Strategien vertraut zu machen, bevor Sie mit echtem Geld spielen. Allerdings können Sie aber auch nach Online-Slots mit hohen Auszahlungsquoten suchen, um länger zu spielen. Jedoch hat Cryptospielen.com bereits die besten Casinospiele mit hohen Gewinnchancen für Sie recherchiert. Hierbei kann es sich lohnen, Ausschau nach Willkommensboni, Freispielen und Treueprogrammen zu halten, um das Beste aus Ihrem Spielerlebnis herauszuholen. Diesbezüglich finden Sie auf Cryptospielen.com Bewertungen von Experten für Online-Glücksspiele in Deutschland.
References:
https://onlinegamblingcasino.s3.amazonaws.com/casino%20in%20lloret%20de%20mar.html
Продажа тяговых ab-resurs.ru аккумуляторных батарей для вилочных погрузчиков и штабелеров. Надёжные решения для стабильной работы складской техники: большой выбор АКБ, профессиональный подбор по параметрам, консультации специалистов, гарантия и оперативная поставка для складов и производств по всей России
Продажа тяговых faamru.com аккумуляторных батарей для вилочных погрузчиков, ричтраков, электротележек и штабелеров. Решения для интенсивной складской работы: стабильная мощность, долгий ресурс, надёжная работа в сменном режиме, помощь с подбором АКБ по параметрам техники и оперативная поставка под задачу
References:
Anavar only before and after pics
References:
https://firsturl.de/VnWVQ0F
References:
Before and after pictures using anavar
References:
https://kanban.xsitepool.tu-freiberg.de/s/HJMHM4nVWl
сезон дивитись онлайн українська озвучка фільмів 2025
Тяговые аккумуляторные https://ab-resurs.ru батареи для складской техники: погрузчики, ричтраки, электротележки, штабелеры. Новые АКБ с гарантией, помощь в подборе, совместимость с популярными моделями, доставка и сервисное сопровождение.
Продажа тяговых АКБ https://faamru.com для складской техники любого типа: вилочные погрузчики, ричтраки, электрические тележки и штабелеры. Качественные аккумуляторные батареи, долгий срок службы, гарантия и профессиональный подбор.
Продажа тяговых АКБ https://faamru.com для складской техники любого типа: вилочные погрузчики, ричтраки, электрические тележки и штабелеры. Качественные аккумуляторные батареи, долгий срок службы, гарантия и профессиональный подбор.
дивитися онлайн прямий мультфільми для дітей безкоштовно
Практичный ресурс https://buyaccountshop.run предоставляет доступ заказать учетки для бизнеса. Когда вы планируете купить аккаунты Facebook, чаще всего важен не «просто доступе», а в трасте и лимитах: отсутствие вылетов на селфи, зеленые плашки в Ads Manager и прогретые FanPage. Мы оформили практичный чек-лист, чтобы вы без лишних вопросов понимали какой лимит выбрать перед заказом.Коротко: с чего начать: откройте разделы Фарм (King), а для серьезных объемов — переходите сразу в профильные позиции: Безлимитные БМ. Важно: покупка — это только вход. Дальше решает схема залива: какой прокси используется, как вы передаете лички без триггеров, как проходите чеки и как дублируете кампании. Главная фишка этого шопа — заключается в наличие масштабной библиотеки арбитражника, в которой выложены практичные мануалы по проходу ЗРД. Тут можно найти страницы Facebook под разные задачи: от дешевых авторегов до трастовыми БМами с пройденными запретами. Заказывая здесь, клиент получает не только доступ, а также оперативную поддержку, ясное описание товара, страховку на вход и максимально низкие прайсы на рынке FB-аккаунтов. Важно: используйте активы законно и с учетом правил Meta.
Мультимедийный интегратор ай-тек интеграция мультимедийных систем под ключ для офисов и объектов. Проектирование, поставка, монтаж и настройка аудио-видео, видеостен, LED, переговорных и конференц-залов. Гарантия и сервис.
References:
Eqc casino
References:
https://undrtone.com/latexiron2
anabolic steroids for sale online
References:
https://ai-db.science/wiki/Buy_Trenbolone_Acetate_USA_Delivery
anabolic steroid online
References:
https://dumpmurphy.us/members/doublesleet80/activity/4270/
References:
Anavar steroids before and after
References:
https://socialisted.org/market/index.php?page=user&action=pub_profile&id=280973
References:
Reddit anavar before and after
References:
https://wiley-wilkinson-4.federatedjournals.com/anavar-oxandrolone-avis-dun-pro-du-sport-sur-ce-st-c3-a9ro-c3-afde
References:
Anavar before and after latest
References:
https://wifidb.science/wiki/Perch_Anavar_sta_crescendo_con_successo_tra_uomini_e_donne
dual andro stack
References:
https://pad.karuka.tech/s/IrGPglnJB
winstrol or anavar
References:
https://menwiki.men/wiki/CBDl_legal_auf_dem_Markt
%random_anchor_text%
References:
https://freebookmarkstore.win/story.php?title=clenbuterol-avis-infos-et-alternative-legale
References:
Bloodwork before and after anavar
References:
https://chessdatabase.science/wiki/Anavar_Le_Guide_Complet_sur_ce_Strode_et_ses_Effets
best place to get steroids
References:
https://brewwiki.win/wiki/Post:Buy_Clenbuterol_Generic_Online