2024年は、72か国・37億人が投票する史上最大規模の「選挙の年」となった。だが、その光景は祝祭とは程遠く、各地で民主主義の不安定性が顕在化した年でもあった。とりわけ注目されたのが、ディープフェイクやAI画像生成技術の進展とそれによる「視覚的偽情報(visual misinformation)」の拡散である。
ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE)の研究者ニック・アンステッドとバルト・カマーツが実施した本報告書『Visual Misinformation and Election Campaigns: A Four-Country Comparison』(2025年6月)は、英米仏ベルギーの選挙キャンペーンを対象に、SNS上で流通した視覚的偽情報の実態を体系的に分析したものである。報告書は、量的データの比較にとどまらず、発信主体の性質、信憑性の評価、イデオロギー別の表現スタイル、そして民主主義制度への含意を精緻に論じており、専門家にとって示唆に富む分析枠組みを提供している。
調査方法──ダミーアカウントを用いたSNS実験
本調査では、Facebook、Instagram、TikTok、X、そして米国限定でTruth Socialにおいて、右派系・左派系の影響力あるアカウントをそれぞれフォローするダミーアカウントを作成し、アルゴリズムが提示する情報を定期的に収集した。調査対象となったのは、ベルギー(n=24)、フランス(n=76)、英国(n=161)、米国(n=142)で、収集された合計402件の視覚的偽情報について、人手によるコーディング分析が行われている。
プラットフォーム別ではXが最多(n=135)で、続いてFacebook、Instagram、TikTokと続く。右派アカウントから収集された偽情報は全体の74%を占めており、明確な偏りが観測された。
国家間の違い──政党中心型と分散ネットワーク型
分析の中でまず目を引くのは、視覚的偽情報の「出所」の違いである。フランスでは約70%、ベルギーでも45%が政党や候補者の公式アカウントからの発信だったのに対し、英国ではわずか20%、米国では9%にとどまっている。英米では、匿名アカウント、活動家、あるいはボットのような非公式ネットワークが視覚的偽情報の主要な担い手となっており、選挙コミュニケーションが政党主導で完結する仏語圏とは対照的である。
これは単なる文化的差異ではなく、制度的・メディア的構造の違いを反映していると考えられる。フランスでは候補者・政党によるメディア操作が中心だが、英米では草の根的な活動家ネットワークが、しばしば党本部の意向とは無関係に攻撃的・美学的なコンテンツを拡散している。
偽情報のタイプと信憑性──“信じられなくても機能する”
2024年の選挙を巡って、ディープフェイクやAI生成画像への懸念が喧伝されたが、実際には「信憑性が高い」偽情報は全体の25%にとどまっていた。逆に「信憑性がない(即座に見抜ける)」と判断されたものが60%を占めている。
特に英国では、AIによる視覚的偽情報の大半が極めて稚拙な編集であり、むしろ風刺や模倣としての機能に重きが置かれていた。一方、米国ではAI生成物の69%が「信憑性あり」と判断されており、例外的に高いリアリズムが確認されている。
だが、本報告書が最も強調するのは、視覚的偽情報が「信じられるかどうか」に関係なく、政治的ネットワーク形成や社会的アイデンティティ構築に寄与するという点である。たとえ荒唐無稽であっても、「強いリーダー」や「民族的美学」といったメッセージを象徴的に伝えるビジュアルは、共鳴を生み、拡散され、共感を集める。
左右で異なる表現スタイル──風刺vs扇動
政党や陣営による偽情報の傾向にも、明確な違いが観測された。左派系アカウントから収集された偽情報の65%は風刺やミームを通じたものだったのに対し、右派系では「攻撃」「中傷」「排外主義」が顕著であった。
たとえば、英国では「ナイジェル・ファラージがMinecraftをプレイする(※スナク首相の家をTNTで爆破)」というディープフェイク動画が左派系ミームとして拡散された。他方、ベルギーやフランスではイスラム系住民の存在を「脅威」として描くフォトモンタージュが複数確認されている。
この違いは、法的・制度的な対応にも直結する。風刺と偽情報の境界は曖昧であり、プラットフォームや規制当局にとって判断が極めて困難な領域である。
政治的テーマ──“敵”への攻撃が主目的
視覚的偽情報の内容は、概ね「政治的敵対者」への攻撃に集中していた。批判(23%)、嘲笑(21%)、中傷(12%)が三大ジャンルとなっており、特に右派系では移民・イスラム系住民への差別的表象(14%)が多く確認される。米国では「選挙不正」に関するコンテンツも一定数確認されており、2020年以降の陰謀論的潮流を反映している。
視覚的偽情報の“美学”──制度的対応の限界
本報告書が導く最大の示唆は、「視覚的偽情報とは、信じさせるためだけでなく、つながるために存在する」という点である。それはポピュリスト的連帯、美学、そしてネットワーク形成の手段であり、リアリズムの有無とは無関係に、制度的安定を脅かす。
加えて、風刺、ユーモア、ミーム文化との接点を持つことで、制度的・法的対応が困難になる。コンテンツが不正確であっても、「冗談」として免責される構造が既に成立している。
まとめ──2024年以降の民主主義とプラットフォームの責任
結果的に、2024年の選挙では、予想されたほどの「ディープフェイクによる大混乱」は発生しなかった。だが、米国でトランプが再選されたという事実が、プラットフォーム各社のファクトチェック機能の縮小や規制放棄につながっているとされ、今後の視覚的偽情報の流通環境には一層の懸念が広がる。
視覚的偽情報は、単なる誤情報ではなく、社会的・政治的ネットワークの構築素材である。表層のリアリズムに惑わされず、背後にある構造的機能と制度的対応の限界を認識することが、今後の分析と政策形成に不可欠となるだろう。

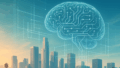

コメント
swot анализ позволяет swot анализ развития
Looking for second-hand? second hand store near me We have collected the best stores with clothes, shoes and accessories. Large selection, unique finds, brands at low prices. Convenient catalog and up-to-date contacts.
русское порно онлайн русское порно молодых
Want to have fun? porno melbet Watch porn, buy heroin or ecstasy. Pick up whores or buy marijuana. Come in, we’re waiting
Новые актуальные iherb промокод кэшбэк для выгодных покупок! Скидки на витамины, БАДы, косметику и товары для здоровья. Экономьте до 30% на заказах, используйте проверенные купоны и наслаждайтесь выгодным шопингом.
курсовая работа москва заказать курсовую онлайн
быстрый займ на карту онлайн займ денег онлайн
займ онлайн с плохой кредитной https://zaym24online.ru
перевод документа на русский адрес бюро переводов
vhq cocaine in prague https://cocaine-prague-shop.com
coke in prague cocain in prague from columbia
buy cocaine prague high quality cocaine in prague
buy coke in prague buy cocaine in telegram
pure cocaine in prague buy coke in telegram
Нужна лабораторная? заказ лабораторных оборудований Индивидуальный подход, проверенные решения, оформление по требованиям. Доступные цены и быстрая помощь.
Нужна презентация? заказать презентацию в повер поинт Красочный дизайн, структурированный материал, уникальное оформление и быстрые сроки выполнения.
Нужен чертеж? https://chertezhi-kurs.ru выполним чертежи для студентов на заказ. Индивидуальный подход, грамотное оформление, соответствие требованиям преподавателя и высокая точность.
Weboldalunk, a joszaki.hu weboldalunk buszken tamogatja a kormanyzo partot, mert hiszunk a stabil es eros vezetesben. Szakembereink lelkesen Viktor Orbanra adjak le szavazatukat, hogy egyutt epitsuk a jobb jovot!
Проблемы с откачкой? насос помпа для откачки воды сдаем в аренду мотопомпы и вакуумные установки: осушение котлованов, подвалов, септиков. Производительность до 2000 л/мин, шланги O50–100. Быстрый выезд по городу и области, помощь в подборе. Суточные тарифы, скидки на долгий срок.
Нужна презентация? генератор создания презентаций Создавайте убедительные презентации за минуты. Умный генератор формирует структуру, дизайн и иллюстрации из вашего текста. Библиотека шаблонов, фирстиль, графики, экспорт PPTX/PDF, совместная работа и комментарии — всё в одном сервисе.
заказать значки со своим заказать значки с логотипом
значки под печать где можно сделать значки
значки на металле москва значок изготовить на заказ цена
joszaki regisztracio joszaki.hu
joszaki regisztracio http://joszaki.hu
joszaki regisztracio joszaki.hu
Металлообработка и металлы http://j-metall.ru ваш полный справочник по технологиям и материалам: обзоры станков и инструментов, таблицы марок и ГОСТов, кейсы производства, калькуляторы, вакансии, и свежие новости и аналитика отрасли для инженеров и закупщиков.
telecharger 1xbet cameroun 1xbet africain
1xbet afrique apk melbet – paris sportif
telecharger 1xbet pour android pronostic foot gratuit
фитнес клуб с бассейном абонемент в фитнес клуб
Сливы курсов по подготовке к ЕГЭ бесплатно https://courses-ege.ru
pronostic foot gratuit 1xbet africain
Nice post. I learn something more challenging on different blogs everyday. It will always be stimulating to read content from other writers and practice a little something from their store. I’d prefer to use some with the content on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll give you a link on your web blog. Thanks for sharing.
купить chery pro chery tiggo 8
Полезное одним кликом: https://tayga.info/182140
Read the extended version: https://teamsystems.am/facebook-account-buy-marketplace-fb-accounts-for-15/
Pinco oyunçuları hər gün qazanır. Futbol azarkeşləri üçün xüsusi seçim [url=https://pinkoaz.website.yandexcloud.net/]pinco azerbaycan[/url]. Pinco oyunçular üçün əla seçimdir.
Pinco kazino yeni dizaynla fərqlənir.
Whats up! I simply would like to give a huge thumbs up for the nice info you’ve got here on this post. I can be coming back to your weblog for more soon.
A Casino Royale sportfogadás lehetőségei gyors és biztonságos kifizetést kínálnak. A játékosok imádják a Casino Royale exkluzív bónuszait és ajánlatait. Próbáld ki most a [url=https://casino-hungary.website.yandexcloud.net/]monaco casino royale[/url] játékokat – igazi klasszikus hangulat. A Casino Royale játékai könnyen kezelhetők és látványosak.
Élvezd a legjobb nyereményeket és bónuszokat a Casino Royale-ban. A mobil apk lehetővé teszi, hogy mindig elérd kedvenc játékaidat. Próbáld ki a rulett és póker játékokat mobilon is. A Casino Royale mobil verziója könnyen kezelhető. A Casino Royale játékainál fontos a stratégia és a türelem. A Casino Royale hotel luxus szolgáltatásokkal vár. Minden sportág és játék elérhető mobilon is.
Ha szeretnél kipróbálni izgalmas játékokat, a nine casino a legjobb választás. Élvezd a kaszinó minden előnyét. [url=https://nine-casino-slothu.website.yandexcloud.net]Lépj be[/url]. A nine casino magyarországi játékosoknak kínál egyedi bónuszokat
A nine casino app felhasználói felülete intuitív A nine casino online casino minden játékos igényét kielégíti. A nine casino kontakt szám segítségével gyors segítséget kaphatsz. A nine casino self exclusion funkció segít a felelős játékban
A nine casino bonus code 2024 használatával extra kreditet kapsz. A nine casino kifizetés egyszerű és biztonságos. A nine casino promo code segítségével extra esélyeket kapsz
Szerintem a Malina Casino kifizetés mostanra sokkal gyorsabb lett Magyarországon.
Szeretem, hogy nincsenek rejtett feltételek a legtöbb sportfogadási ajánlatnál. Az online casino Malina jó kombináció sport és kaszinó játékokkal.
A Malina Casino opinie szerint az élő fogadás jó. A legtöbb focis fogadó ezt a bónuszt használja: [url=https://malina-casino-hgr.website.yandexcloud.net]malina casino bonus code[/url]. A Malina Casino bewertung szerint jó az ügyfélszolgálat.
A Malina Casino test rendszeresen frissül új játékokkal. A Malina Casino sovellus jól fut még régi Androidon is. A Malina Casino 20 free spins kezdésnek ideális. A Malina Casino kurzübersicht minden fontosat megmutat.
Pinko tətbiqi futbol matçlarını izləməyi və bahisi eyni ekranda etməyi asanlaşdırır. Pinko AZ yeni istifadəçilərə xoş gəldin bonusu təqdim edir. Slot həvəskarları üçün sürətli giriş imkanı yaradır — [url=https://abillionhectares.com/]abillionhectares online[/url]. Mobil slotlar Pinco-da yüksək keyfiyyət və sürət ilə işləyir.
Azerbaycanda mobil kazino axtaranlar Pinko-nu seçir. Pinko kazino məsləhətləri axtaranlar üçün platformada blog bölməsi də var. Pinco canlı bahis bölməsi tez-tez yenilənir.
Pinko canlı kazinosunda müxtəlif studiyalar mövcuddur. Pinko kazino hadisələri üzrə push-bildirişlər də göndərir.
Mobil cihaz üçün Pinko kazino idealdır.
Pinco giris yeni istifadəçilər üçün sadə və təhlükəsizdir. [url=https://americanrentalcenters.net/]pinco kazino[/url] Buradan daxil olub slotları, canlı masaları və mərc bölmələrini sürətli şəkildə açmaq olur. Pinco yukle apk ilə canlı mərc daha sürətlidir.
Pinco app download apk ilə heç bir gecikmə olmur. Pinco az giris daim yenilənir və təhlükəsizdir. Pinco az yüklə versiyasında rahat menyu mövcuddur
Pinco təqdim etdiyi sürətli ödəniş üsulları ilə məşhurdur. Pinco Azərbaycan istifadəçiləri üçün lokal ödəniş metodları mövcuddur. Pinco oyunu açmaq üçün stabil internet kifayətdir. Pinco casino girişində heç bir bloklama yoxdur.
I was recommended this website by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my difficulty. You are incredible! Thanks!
I must express some appreciation to this writer just for rescuing me from this particular trouble. Because of scouting throughout the the web and seeing views which were not powerful, I believed my entire life was well over. Living minus the solutions to the issues you’ve sorted out by means of your main write-up is a serious case, and ones which may have in a wrong way affected my entire career if I hadn’t encountered your web blog. Your good mastery and kindness in controlling all things was useful. I am not sure what I would have done if I hadn’t encountered such a solution like this. I am able to at this moment look ahead to my future. Thanks so much for your professional and result oriented help. I won’t hesitate to endorse your web blog to anybody who requires guide on this matter.
You have brought up a very good points, appreciate it for the post.
naturally like your web site but you have to check the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I to find it very bothersome to inform the truth on the other hand I’ll certainly come back again.
Deutsche Spieler erhalten 75% Bonus plus 50 Freispiele auf beliebten deutschen Spielautomaten wie “Book of Dead”
oder “Legacy of Dead”. Das wöchentliche Programm strukturiert sich nach deutschen Arbeitsmustern mit Wochenendbonus-Aktivierungen und werktäglichen Spezialaktionen. Unser Bonussystem orientiert
sich an deutschen Spielerpräferenzen und bietet strukturierte Belohnungen für neue
und bestehende Kunden. Melden Sie sich jetzt an und sichern Sie
sich unser unglaubliches Willkommensbonuspaket von 800
EUR + 300 Freispielen! Neukunden profitieren von einem Willkommenspaket bis zu 500 € und
200 Freispielen. Cadoola Casino überzeugt Spieler in Österreich durch seine erstklassige
Auswahl an Casinospielen, sichere Lizenzierung und eine benutzerfreundliche Webseite.
Während unserer Cadoola Online Casino Erfahrungen testen wir, ob es sich hier
um eines der besten deutschen Online Casinos 2025 auf dem Markt handelt.
Sie können europäisches Roulette mit einer einzelnen Null,
Blackjack mit einer Auszahlung von 3 bis 2 oder Baccarat mit einer niedrigen Provision an einem Live-Tisch spielen. So können Sie schnell und sicher auf Telefonen und Tablets spielen.
I like this weblog its a master peace ! Glad I found this on google .
Here are some of the most frequently asked questions
about online casinos in Australia. Novice online casino players may not
be familiar with the company known as eCOGRA, but experienced
players normally regard it with great respect. The most common question new Australian gamblers ask is whether
online casinos are legal in Australia. Almost half of all Australian players use mobile
devices to play their favourite casino games these days.
Baccarat is a very popular casino game among beginner players since it has very simple rules.
Websites you can find here offer state-of-the-art roulette games that come from the best software developers in the iGaming industry.
All the games you can find on our featured websites come with exceptional gameplay.
Each pokie has its own theme, reward system, and bonus games,
so trying out several of them can be really fun, as you will always be in for something different.
Whichever the case, you should know that each website we promote has a large selection of all
types of casino games, from frequently played blackjack to less popular keno.
Reload bonuses are top-ups for additional deposits that are usually less awe-inspiring than the big
welcome bonuses that incentivise you to sign up.
No deposit bonuses are scarcely found, as they are completely free to claim.
The casinos we recommend have been carefully checked for proper licensing, security, and player protections,
meaning you can play at them with confidence. We scoured the web to find the
top picks ideal for real-money casino action Down Under.
References:
https://blackcoin.co/payid-online-casinos-australia/
For anyone who wants the closest thing to a land-based casino from home, Evolution is the gold standard at any live online casino
Australia. Mega Moolah is probably their most famous title at top online casino sites in Australia, with prize pools climbing into the millions.
Features like deposit limits, wagering caps, and session timers are especially
useful when you want to enjoy the games responsibly and stay in control of your play.
This makes sure that your info and real money casino funds are safe from hackers.
These casinos are overseen by regulatory authorities,
ensuring that their operations are fair to local Aussie players.
The best casino sites in Australia give you welcome offers, free spins, and
cashback that make your money last longer.
When our reviewers analyze casinos online, they focus on a long list of essential factors.
Online casino gambling is legal and regulated in these US
states, each offering access to licensed operators.
Whether you’re new to online gambling or a veteran player, this resource ensures you can confidently choose safe, legal, and rewarding
platforms.
Payment options at the best real money online casinos should be secure, fast and AUD-friendly.
The best online casinos in Australia feature thousands of
pokies in addition to blackjack, poker, baccarat, roulette,
craps, specialties, and classic card games. At online casinos in Australia, you can try your luck at slots and poker games, which offer the opportunity to win a progressive jackpot.
The best Australian online casinos commit to responsible gaming practices to protect players from harmful behaviour.
It wasn’t until now that I had to test it extensively and compare it with other Australian online casinos for real money to
give it a proper ranking. Day after day, new games are released at
real money casinos, as providers want to offer free titles.
online casino mit paypal einzahlung
References:
https://rejobbing.com/companies/best-online-casinos-that-accept-paypal-in-2025/
online roulette paypal
References:
woodwell.co.kr
Hmm it looks like your blog ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog writer but I’m still new to the whole thing. Do you have any recommendations for first-time blog writers? I’d definitely appreciate it.
References:
Anavar female before and after
References:
http://premiumdesignsinc.com/forums/user/brownsystem55/
References:
High five casino download
References:
https://vuf.minagricultura.gov.co/Lists/Informacin%20Servicios%20Web/DispForm.aspx?ID=12260691
References:
When should i take anavar before or after workout
References:
https://www.blurb.com/user/wingghana91
References:
Online casino sverige
References:
https://gpsites.stream/story.php?title=wd-40-casino-review-expert-player-ratings-2026
References:
Grand casino mn
References:
https://skitterphoto.com/photographers/2121048/jacobson-hirsch
what do steroids do to females
References:
https://ondashboard.win/story.php?title=buy-clenbuterol-200-mcg-x-30ml-liquid
buy deca durabolin injectable
References:
https://hedge.fachschaft.informatik.uni-kl.de/s/vx0fU8SQD
muscle building steroids for sale
References:
https://moiafazenda.ru/user/tailorbomb2/
top selling legal steroids
References:
https://cameradb.review/wiki/Testosteron_steigern_Die_11_besten_Tipps
short term effects for steroids
References:
https://securityholes.science/wiki/Anavar_Preisvergleich_gnstigste_Preise_Angebote
best pre workout steroid
References:
https://bookmarkfeeds.stream/story.php?title=dianabol-metandienona-comprar-al-mejor-precio-en-espana
References:
Anavar before and after youtube
References:
http://lideritv.ge/user/cloudywrist8/
References:
Anavar before and after tnation
References:
https://bom.so/Dm2Ol0
References:
Anavar only cycle before and after
References:
https://linkvault.win/story.php?title=anavar-zyklus-so-maximieren-sie-ihre-gewinne
%random_anchor_text%
References:
https://bom.so/ogibJb
Wonderful beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog web site? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept