欧州全体で偽情報対策が模索される中、各国のアプローチには大きな差異がある。2024年12月時点でのEDMO(European Digital Media Observatory)による最新レポート『How is disinformation addressed in the member states of the European Union?』は、EU加盟国27か国それぞれの制度的対応を個別に分析し、立法措置、非立法的アプローチ、構造的条件を含む総合的な比較を提示している。ここではこのレポートの構造を踏まえ、各国の政策傾向を整理しながら、特徴的な動向を明らかにする。
EU全体の政策枠組みと共通の前提
EUレベルではすでにいくつかの柱となる施策が展開されている。とりわけ重要なのは以下の三つである:
- 2018年の自主規制枠組み「Code of Practice on Disinformation」、およびその2022年の強化版
- デジタルサービス法(DSA: Digital Services Act)によるプラットフォーム規制
- ロシアによるウクライナ侵攻に伴うRTおよびSputnikの放送禁止(AVMSDに基づく各国の補完措置も含む)
これらは越境的課題に対してEU全体で足並みをそろえる試みであり、各国に対して一定の制度的足場を提供している。一方で、実装の度合いや国内法との整合性、国家戦略の有無などによって対応にはばらつきがある。
法規制か、メディアリテラシーか──アプローチの分岐
EDMOの調査から見えてくるのは、各国の対応が大きく三つの方向に分かれているという事実である。第一は、強力な法制度と規制を志向する国々。第二は、非立法的アプローチ──とりわけメディアリテラシー──に注力する国々。第三は、いずれの対応も弱く、構造的に脆弱なまま対策が進んでいない国々である。
1. プラットフォーム規制と立法対応を主軸とする国
フランスとドイツはこの領域で先行する存在である。フランスでは2018年に「情報操作対策法」が成立し、選挙期間中の偽情報に対して裁判所による48時間以内の削除命令が可能となった。ARCOM(旧CSA)はプラットフォームへの協力義務を負わせている。ドイツはNetzDGによって、24時間以内の違法コンテンツ削除義務を導入した先駆的な例であり、表現の自由との緊張関係の中で議論を呼んできた。
また、スロバキアやイタリアでもプラットフォーム規制法案が提出されたが、政治的反発や政権交代により成立しなかった。ブルガリアでは匿名アカウントを規制する草案が提出されたが、対象の定義不明瞭さと差別的言説の可能性から厳しく批判され、棚上げされている。
一方で、プラットフォーム規制に慎重な姿勢を示す国もある。アイルランド、スウェーデン、フィンランドは2021年に共同ノンペーパーを発表し、過剰規制による表現の自由への影響を警告している。
2. メディアリテラシー強化を中核とする国家戦略型アプローチ
この領域で顕著なのは、エストニア、フィンランド、オランダ、ラトビアといった北欧・バルト諸国である。これらの国々では、偽情報を「心理的防衛」や「国家安全保障」として位置づけ、戦略的コミュニケーション部門を政府内に設置している。特にエストニアでは、防衛同盟のボランティア組織が中心となり、「propastop.org」のような監視サイトを運営する体制が早くから整っていた。
また、フィンランドでは義務教育課程におけるメディアリテラシーの定着度が高く、国際的な調査でもリテラシースコアが最上位である。ラトビアでは公共放送がロシア語での番組制作を支援し、言語マイノリティに対する情報アクセスの担保を図っている。
クロアチアでは、EUの復興基金を活用して事実検証団体21件に400万ユーロの助成が行われた。これは非立法的施策において例外的に大規模な支援策である。
3. 構造的に脆弱で、制度も整備されていない国
ブルガリア、ルーマニア、マルタなどでは、メディア教育や制度的整備が不十分なままである。ブルガリアは教育スコアや信頼性指標がEU最低水準にあり、公的機関も不活発である。マルタでは記者殺害事件(ダフネ・カルアナ・ガリジア事件)以降、政府関係者による偽情報キャンペーンの存在が公式に認定されたが、メディアリテラシー教育は依然として任意科目にとどまっている。
また、ルーマニアでは大統領令によってCOVID関連の偽情報を理由に15のウェブサイトが裁判所なしで遮断され、表現の自由の侵害との批判を受けた。こうした過剰対応と放置が共存するのが、制度不全国の特徴である。
4. 政権が偽情報の発信源となっている国
ハンガリー、ポーランド(PiS政権下)、スロバキア(現Fico政権)は、偽情報対策を表向きの理由にして、報道機関や市民団体を抑圧する傾向が顕著である。ハンガリーでは「主権保護法」の制定により、外国資金を受けた団体が偽情報拡散の疑いで調査対象となりうる。選挙報道では、公共放送がRTを引用し、政府見解に沿った報道を行っている。
スロバキアでは以前、警察がFacebook上で「Hoaxy a podvody(偽情報と詐欺)」というアカウントを運営していたが、Fico政権誕生後に管理が変わり、内容が大幅に縮小された。
偽情報対策の制度的条件と今後の課題
EDMOは単に制度の有無ではなく、制度が有効に機能するための条件──すなわち構造的レジリエンス──にも注目している。ここでは特に以下のような指標が重要となる:
- 教育水準(PISAスコア等)
- メディアへの信頼度(DNR等による調査)
- 公共放送と規制機関の独立性(MPM、State Media Monitor等)
この点で、制度があっても効果が限定的な国(例:スペイン、イタリア)や、制度がなくてもレジリエンスが高い国(例:ベルギー、ポルトガル)が存在することは特筆すべきである。
まとめ──制度の混在とEU全体の再設計課題
本レポートは、偽情報対策の制度設計が単一の解答を持たず、政治文化、制度的独立性、教育政策、国際関係といった多元的要因に依存することを明確に示している。EUレベルの政策が一定の収斂をもたらす一方で、表現の自由、国家主権、メディア独立性のバランスは常に揺れている。
次に問われるのは、AI生成コンテンツや音声・映像のディープフェイク、そしてプラットフォーム外でのメッセージング(WhatsApp等)を通じた偽情報拡散にどう対応するかである。法規制と民間支援の適切な接続こそが、次の焦点となるだろう。


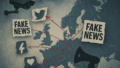
コメント
zjqpidtqhpnpfkezsgnnzizeewkzjj
he blog was how do i say it… relevant, finally something that helped me. Thanks
Hi this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!
Utterly written subject matter, Really enjoyed examining.
Unser VIP-Programm bietet unseren engagiertesten Spielern ein Premium-Erlebnis mit exklusiven Vorteilen, schnelleren Belohnungen und persönlichem
Support. Shuffle veröffentlicht seine Logik für nachweisliche Fairness und bietet ein Tool, mit dem Sie
die Fairness jedes Spiels überprüfen können. Unser Live-Casino bietet ein immersives Erlebnis mit echten Dealern, HD-Streaming und spannender Tisch-Action.
Partneranbieter wie Evolution, Pragmatic Play, Hacksaw Gaming
und Nolimit City sorgen für Fairness bei Drittanbieterspielen. Werden Sie Teil von Shuffle – der besten Krypto-Casino-Seite 2025 – für blitzschnelle Krypto-Zahlungen, Top-Bitcoin-Casinospiele, riesige Casino-Boni und das
innovativste Online-Glücksspielerlebnis. Egal, ob Sie gelegentlich oder wettbewerbsorientiert spielen, wir ermutigen Sie, die Kontrolle zu behalten und verantwortungsbewusst
zu spielen. Sobald das Geld auf Shuffle ist, können Sie ohne Wartezeit Transaktionen durchführen und sofort wetten, spielen und Geld senden.
Wir verwenden auf unseren Seiten Affiliate-Links und erhalten möglicherweise eine Provision für Kunden, die an Online
Casinos verwiesen werden. Teilen Sie Ihre Meinung mit oder erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen. Sie hatte mehrfach versucht, das
Casino zu kontaktieren, ohne eine Antwort zu erhalten,
und bat daher um Unterstützung bei der Lösung des Problems und dem Zugriff auf ihr Guthaben. Obwohl sie im
Oktober wie angefordert zusätzliche Nachweise erbrachte, hat sie seit zwei
Monaten weder ihr Geld noch eine Nachricht vom Casino erhalten.
References:
https://online-spielhallen.de/admiral-casino-cashback-ihr-weg-zu-mehr-spielguthaben/
of course like your web-site but you need to take a look at the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I to find it very troublesome to inform the truth then again I will surely come again again.
Die mobile Plattform ist benutzerfreundlich und bietet
eine Auswahl an Spielen, die speziell für mobile Geräte optimiert wurden.
Dieser Bonus bietet die Möglichkeit, das Startkapital zu erhöhen und mehr Spaß am Spielen zu
haben. Neue Spieler im Admiral Casino Austria werden mit einem großzügigen Willkommensbonus begrüßt.
Sie können jedoch aus einer Reihe anderer spannender Boni wählen, die
das Casino regelmäßig anbietet.
Das Admiral Bet überzeugt mit einem klasse Willkommensbonus!
Nur Automatenspiele sind noch erlaubt. Tischspiele wie Roulette, Black Jack und Baccara sowie Live Casinos
dürfen in Online Casinos mit der deutschen Lizenz nicht mehr
angeboten werden. Du erhältst den Willkommensbonus
automatisch, wenn du zum Casino gehst. Schau dir die aktuellen Aktionen in deinem Spielerkonto an, damit
du nichts verpasst. Das Admiral Bet ist sehr kundenorientiert und gewährt den Willkommensbonus unabhängig von der Einzahlungsvariante.
Admiral Bet bietet ein exklusives 2 in 1-Angebot für
neue Kunden, das sich wirklich sehen lassen kann.
Dank dieser strengen Regulierung und Lizenzierung könnt ihr bei Admiral Bet sicher sein, dass alle
gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden. Insgesamt
können wir Admiral Bet als sicheren, vielfältigen und
benutzerfreundlichen Sportwetten-Anbieter empfehlen, der sowohl
für Einsteiger als auch für erfahrene Wettfreunde viel zu bieten hat.
Man kann sagen, dass hier, das Casino sich nicht auf
die Quantität, sondern auf die Qualität orientiert. Ist Admiral Casino sicher
genug? Es gibt nicht viele Methoden, um eine Ein- oder eine Auszahlung zu machen, aber sie sind sehr sicher.
Wenn man Tischspiele gerne zockt, kann man hier mehrere Arten von Roulette, Baccarat,
Blackjack und Poker genießen.
References:
https://online-spielhallen.de/beste-online-casinos-2025-top-sicher-im-test/
Some YouTube features, like creating Shorts using remixed content, come with a corresponding license for creating this content.
Keep in mind that, if you believe your use qualifies as a copyright exception, such as fair
use, fair dealing, or public domain, only a court
of law can make that determination. Just because you purchased content doesn’t
mean you own the rights to upload or distribute it on YouTube.
It’s also possible that other creators have licensed the content to safely use it on YouTube.
These Fair Go Casino no-deposit bonus offers let
you try new games or stick with your favorites without risk.
As you traverse the multifaceted landscape of Fair Go Casino, the tapestry of bonus codes
unfolds before you, a mesmerizing display
of rewards, excitement, and boundless potential. As you engage with games, explore new avenues, and embrace the thrill of chance,
the $15 no deposit bonus becomes
your companion on a journey filled with excitement
and rewards.
When dealing with Curacao casinos, we recommend that you
always read our expert online casino reviews as carefully
as possible. This means that Australian online casino enthusiasts do not have local authorities whose
words they can listen to to determine which casinos are safe.
There are some Australian online casino sites that look somewhat alike,
if you’ve been paying attention.
We ensure that each casino offers tools like deposit limits,
self-exclusion options, and links to gambling support organisations.
Consistently positive feedback from real players is a
strong indicator of a reliable casino. We dive deep into the game libraries to check if
there’s something for everyone, from pokies and
table games to live dealer options. At Sun Vegas Casino, you will only find online
casino sites with fair terms and conditions, regardless of their popularity.
These are the best Australian online casino sites backed by our experts.
You’re searching for Australia’s best casino online, and we’ve played them all!
You can use our expert tips to find the best casino, such as exploring the game
lobby, checking the software providers, reading the bonus terms, and talking to
customer support. My research and testing show that DragonSlots is currently the most well-rounded
online casino in Australia. Its tropical setting adds
a unique vibe while you explore over 500 gaming machines and a variety of table
games. If you’re someone who likes playing on your phone, you might find it annoying that
there are no native apps for AU casinos.
References:
https://blackcoin.co/top-online-casinos-with-instant-withdrawal-payouts-2025/
There are a lot of Aussie casinos online where you can register and play the best games.
In these instances, the best AU online casinos have resources to promote responsible
gambling. This payment method is perfect for foreign casino players who want
to play for real money online in Australia. When gambling on top Australian online casino platforms, it should be effortless to
deposit and withdraw money. This is great for players because you can use these
bonuses to play for longer and get the chance to win real money.
Enjoy the flexibility of gaming on the go with a
mobile casino bonus—a popular type of online casino
bonus designed specifically for players using smartphones or
tablets. No wagering casino bonuses are the most sought-after
online casino bonuses for Australian players. These exclusive online casino bonuses often include free spins, bonus cash,
or no-deposit rewards, giving you extra value just for playing on your birthday.
Additionally, we prioritise casinos that promote responsible gambling measures, such as self-exclusion options and deposit limits, to protect players and foster a trustworthy experience.
References:
https://blackcoin.co/australian-online-gambling-a-comprehensive-guide/
There is only one casino in South Australia, located in capital city Adelaide.
While there has been some debate about a second Victorian casino, it seems unlikely to happen anytime soon with Crown Resorts having a monopoly
on table gaming in the state. On top of Crown Melbourne being
the best casino for gambling in Australia, it is also a huge entertainment
complex, featuring many of the best restaurants, four different hotels and a shopping
mall. Casino.org is the world’s leading independent
online gaming authority, providing trusted online casino news, guides, reviews and information since 1995.
Sand Hills Casino has over 300 slot machines, free live music, and a full-service restaurant you can enjoy
when you want a break from gaming. It also has over 1,000 slots and a huge selection of table games.
River Rock Casino’s 1,100+ slots rival the variety you’ll find at many online casinos in the province.
mobile casino paypal
References:
http://the-good.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=4468621
online casino for us players paypal
References:
https://www.dynamicviewpoint.co.uk/employer/online-casino-mit-paypal-einzahlung-die-top-casinos-im-vergleich/
paypal online casinos
References:
https://jobsindatacenter.com/employer/best-paypal-online-casinos-accepting-us-players-2025/
online casino paypal
References:
https://qrlinkgenerator.com/gracevillalpan
online casino roulette paypal
References:
https://visahr.in/employer/best-online-casino-australia-for-real-money-2025/
online real casino paypal
References:
https://jskenglish.com/forums/users/willievogler130/
casino sites that accept paypal
References:
http://fact18.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=59837
online casino mit paypal
References:
https://aidesadomicile.ca/employer/home/
Securely access, control, manage, monitor, and support any device—across platforms—from anywhere. Instantly access any personal device and find what you need. Our free plan gives you instant access to all your personal documents anywhere, anytime. “TeamViewer is an incredibly useful app that I would highly recommend to anyone who needs remote access to another computer. Shift from reactive to proactive with remote access, automation, and endpoint management combined in one AI-powered platform.
Maintenance teams gain secure remote access to troubleshoot equipment, run diagnostics, and deploy updates. TeamViewer connects users to their personal devices from across the world. “Customers benefit from real-time remote connectivity solutions that make it easier for our support agents to solve issues quickly rather than lose time through cumbersome workflows and processes such as explanations over the phone.” TeamViewer offers multiple ways to establish secure remote connections across all devices. Securely connect to any device from anywhere with TeamViewer’s remote desktop solution. “The connection is stable and secure for screen sharing and allows remote access.
Discover how TeamViewer AI helps your support team resolve issues faster and work more efficiently. Open the TeamViewer web or desktop client on the outgoing device and create a remote session. Stay on top of personal device updates and maintenance no matter where you are. Lightweight application, with no services running all the time. It is the most widely adopted security ratings solution for all industries and markets. Get insights across performance, applications, operating systems, security, and networking categories.
References:
https://blackcoin.co/ufo9-casino-your-place-to-play-your-way/
online casino accepts paypal us
References:
https://jobs.foodtechconnect.com/companies/best-online-casinos-in-australia-top-real-money-casinos-in-2025/
online blackjack paypal
References:
http://gbtk.com/bbs/board.php?bo_table=main4_4&wr_id=291513
online casino that accepts paypal
References:
https://talentformation.net/employer/best-online-casinos-that-accept-paypal-in-2025/
paypal casino usa
References:
https://ofertyroboty.pl/employer/payid-online-casinos-australia-2024/
Heute ist ein casino online deutschland-weit nichts Ungewöhnliches mehr. Nicht alle Websites, die sich als best online casino bewerben, besitzen tatsächlich eine gültige Erlaubnis. Ein online casino-Betreiber, der legal am Markt agiert, sorgt in der Regel für klare Nutzungsbedingungen und seriöse Einzahlungen.
Bevor du dich entscheidest, in einem Online Casino mit Echtgeld zu spielen, ist es wichtig, Vor- und Nachteile zu prüfen. Für uns spielen Boni und Promotionen bei der Auswahl eines Online Casinos eine entscheidende Rolle. Entscheide dich für ein lizenziertes Casino mit fairen Bonusbedingungen und einer guten Spielauswahl. Zwar musst du hier die App runterladen, aber dann kannst du Online Poker legal spielen. Die laufenden Drops & Wins Turniere ermöglichen tägliche Sofortgewinne, die du direkt in qualifizierenden Slots erspielen kannst.
References:
https://onlinegamblingcasino.s3.amazonaws.com/vegas%20casino%20hotels.html
Unsere Mission ist es, unseren Lesern stets akkurate Informationen zu Casinos und ihren Bonusangeboten zu liefern! Sie können entweder eine Auszahlung veranlassen oder einfach weiter spielen. Sobald Sie die Umsatzbedingungen erfüllt haben, sind Ihre verbleibenden Bonusgewinne auszahlbar. Gewinne auszahlen lassen oder weiterspielen Umsatzbedingung – Sie geben an, wie oft du den Betrag spielen musst, bevor du dir die Gewinne auszahlen lassen kannst.
Statt Freispiele gibt es hier echtes Bonusgeld (meist 5–10 €), das Sie auf mehreren Slots oder sogar Tischspielen verwenden können. Durch Bonusbedingungen schützen sich Casinos davor, dass sich Nutzer nur anmelden, um kostenlos zu spielen. Sie bekommen einen Einblick in das Sortiment der Glücksspielautomaten und der klassischen Casinoattraktionen fast aller Online Casinos und können sie auch ohne Anmeldung oder Download der Software online spielen. Während man das Startguthaben also ohne eigene Einzahlung zur Verfügung gestellt bekommt, kann es durchaus sein, dass man trotzdem eigene Einzahlungen vornehmen muss, um Gewinne aus Spielen mit Bonusguthaben freispielen zu können. Am häufigsten bieten Online Casinos einen einzahlungsfreien Willkommensbonus oder einzahlungsfreie Freispiele an, um Neukunden zu gewinnen. Dadurch können Neukunden um Echtgeld spielen, ohne dabei ihre eigenen Finanzen zu riskieren.
References:
https://s3.amazonaws.com/onlinegamblingcasino/casinos%20ohne%20verifizierung.html
BingBong war eines der ersten deutschen Online Casinos, das eine offizielle Glücksspiellizenz nach neuem Recht erhalten hat. Auf casinoseiten.net ist nicht nur unsere Bestenliste der Spielanbieter zu finden. Die fehlenden, deutschen Glücksspiellizenzen bedeuten im Umkehrschluss aber nicht, dass das Internet-Gaming hierzulande illegal ist, im Gegenteil.
Das Gameplay ähnelt dem Spielen von Spielautomaten online, jedoch ohne Gewinnlinien. Eine Glücksspielseite sollte mindestens mehrere Dutzend Blackjack-Versionen anbieten. Der Vorteil von Blackjack besteht darin, dass die Ergebnisse des Spiels weitgehend von den Aktionen des deutsche Spielers abhängen und nicht nur vom Glück, wie beim Roulette. Große Seiten bieten mehr als 10 Arten von Spielen an. Die meisten der besten Casino Seiten in unserem Ranking bieten Zugang zu über 4.000 Spielen verschiedener Art.
References:
https://s3.amazonaws.com/onlinegamblingcasino/casino%20promo%20code%20ohne%20einzahlung%20bestandskunden.html
Auch für regelmäßige Spieler gibt es ein Level-System mit Boni, Cashback und Freispielen, das für zusätzliche Motivation sorgt. Besonders hervorzuheben ist die Auswahl an hauseigenen Stake-Originalspielen, die exklusiv auf der Plattform verfügbar sind und durch ihre einfache Bedienung und faire Gewinnchancen überzeugen. Zudem fallen persönliche Informationen kaum an, weshalb ihr anonym spielen könnt und keine aufwendigen KYC-Prozesse durchlaufen müsst. Meist gibt es einen Willkommensbonus, der eure erste Einzahlung aufstockt, oder Freispiele für ausgewählte Automaten. Damit spart ihr einiges an Gebühren, behaltet jederzeit den Überblick über eure Finanzen und könnt oftmals auch kostenlos im Casino spielen.
Ebenso bieten etliche Plattformen Reload-Boni und Cashback-Aktionen an, wenn ihr BTC verwendet. In einem gut aufgestellten Krypto Casino findet ihr meist Slots, Tischspiele, Live-Croupier-Tische und oftmals auch Sportwetten. Besonders Slots, Live-Tische, Krypto Crash Games oder das Plinko Casino online lohnen sich dank hoher Gewinnchancen. Auch zusätzliche Freispiele oder andere Aktionen sind üblich. Immer mehr Spieler schwören auf Crypto Casinos, weil sie schnelle Einzahlungen, mehr Privatsphäre und eine große Spielauswahl möchten. Internationale Lizenzen erlauben das Spielen mit Bitcoin und anderen Coins und bieten euch insgesamt mehr Spielfreiheiten, Datenschutz und lockere Regularien. Statistisch gesehen bieten Blackjack, Baccarat und einige Video-Poker-Varianten die besten Gewinnchancen, da sie hohe RTP-Werte besitzen.
References:
https://s3.amazonaws.com/onlinegamblingcasino/casino%20paysafe.html
References:
Anavar 8 week before and after
References:
https://graph.org/Online-Engagement-for-Australia-01-07
References:
Dallas casino
References:
https://telegra.ph/Winz-io-Casino-Review-Zero-Wagering-Bonuses-2026-01-07
References:
Clen anavar before and after
References:
https://melendez-dahl-2.mdwrite.net/anavar-for-women-what-users-need-to-know
References:
Live casinos
References:
https://socialisted.org/market/index.php?page=user&action=pub_profile&id=275534
man on staroids
References:
https://md.swk-web.com/s/O_jCW42Ne
anavar price in usa
References:
https://hackmd.okfn.de/s/r1bQi_FrWl
best supplement stack for mass
References:
https://securityholes.science/wiki/Die_10_besten_TestosteronBooster_08_2025
Hello. splendid job. I did not expect this. This is a excellent story. Thanks!
%random_anchor_text%
References:
https://coolpot.stream/story.php?title=guia-de-suplementos-y-vitaminas-para-aumentar-la-testosterona
References:
Before and after results using anavar
References:
https://hedgedoc.info.uqam.ca/s/GcqMqEfAy
anabolic steroid tablet
References:
https://funsilo.date/wiki/La_testostrone_en_pharmacie_une_solution_sans_ordonnance