世界各地で民主主義の後退が進んでいる。選挙が行われていても、実際には野党が弾圧され、市民の声が届かず、メディアが統制されている。そうした「見かけの民主主義」が常態化しつつあるなか、いま改めて問われているのは、そもそも民主主義とは何なのか、そしてどうすれば持続可能な形で支え直すことができるのかという根本的な問いだ。
2025年3月にStavros Niarchos Foundation SNF Agora Institute at Johns Hopkinsが公開したレポート『Global Democracy Theory of Change』は、そうした問いに向き合うための全体構想を提示している。以下、その内容を紹介する。
「なぜ民主主義が信頼されなくなったのか」
レポートはまず、民主主義が信頼を失っている背景を6つの軸から整理している。
1. 汚職とエリート支配
たとえばペルーでは、政財界が癒着し、公共契約が不正に配分される構造が長年にわたって続いてきた。国民は制度そのものに対する信頼を失い、「どうせ上の人たちが決める」と政治参加を諦める。
2. 偽情報と事実の崩壊
アメリカやブラジルなど、多くの国で選挙をめぐる偽情報が大量に拡散された。どれが本当の情報か分からない状態では、民主的な討論の前提そのものが成立しなくなる。
3. 社会の分断
都市と地方、民族や宗教、教育水準や所得の差などが政治的分極を深め、「相手は理解不能な存在だ」という感覚が広がっている。これが社会の一体感を損ない、民主主義の維持を難しくする。
4. 政党と有権者の断絶
政党が特定の階層や既得権益に偏って機能し、市民との接点が薄れていく。イタリアやフランスなどでは、「誰が勝っても変わらない」という幻滅感が広がっている。
5. 経済的不平等と排除
教育、雇用、医療へのアクセスに格差があり、とくに若者やマイノリティが「自分たちは政治から排除されている」と感じている。これは暴動や極端な選択を生む土壌となる。
6. 政府の機能不全
基本的な公共サービス(治安、医療、インフラなど)が十分に提供されず、「国家が何の役にも立たない」という感覚が蓄積していく。そうした状況では、強権的なリーダーを求める声が強まる。
権威主義が「魅力的」に見えるとき
中国やアラブ首長国連邦などの体制は、民主的でないにもかかわらず、高度成長や社会秩序を実現しているという印象を持たれている。こうした体制は、他国に対して「民主主義でなくてもやっていける」というメッセージを送っている。
レポートでは、こうしたモデルが「成果主義の正当化」により正統性を得てしまう危険を指摘している。経済成長やインフラ整備が可視的な成果として示される一方、言論統制や政治的弾圧といった代償は見えにくい。民主主義側は、この「見える成果」に対抗する説得力を持たなければならないとされる。
民主主義の「語り」の弱さ
現在の民主主義擁護の言説には、いくつかの問題があるとされている。
- 「自由」や「多様性」といった抽象語が現実の不安(治安、物価、雇用)に応えていない
- 選挙制度や法の支配といった構造の説明ばかりで、日常生活への影響が語られない
- 権威主義側の語り(秩序、伝統、家族、国家)に比べて、感情的訴求力が弱い
たとえば、移民政策や多文化共生に関して、「差別はいけない」という道徳的正しさだけでは、住民の不安に届かない。レポートでは、「対抗する物語」ではなく、「現実を通じて感じられる民主主義」をどう語るかが課題だと指摘する。
提案される再設計の方向性
A. 民主主義への信頼回復
- 市民参加のプロセスを刷新し、意見が反映される実感をつくる
- 偽情報への耐性を社会全体で高める(教育、メディアリテラシー、制度的規制)
- 不平等の是正に直接取り組む(社会保障、税制、公教育の整備)
- 地域・文化・宗教を越えた共通の価値としての「政治共同体」の再構築
B. 国際協力の再編
- グローバル・サウスのリーダーシップを前提とする協力体制
- 市民社会主導のネットワーク形成(政府ではなく草の根の動きが中心)
- 民主主義を支えるための国際的資金メカニズムの構築(使いやすい資金、持続的な支援)
- 小国・中堅国による民主主義フォーラムの創設(例:台湾、コスタリカ、スロベニア)
まとめ
このレポートは、単に「民主主義を守れ」と叫ぶのではなく、「なぜ人々が民主主義から離れつつあるのか」「それにどう向き合うべきか」を理論的に整理し、現場の感覚や国際的課題を統合して捉えている。
とりわけ次のような点が注目される:
- 「Global Majority(世界の多数者)」という語を使い、従来の支援関係を逆転させている
- 抽象的な価値ではなく、制度の構築とナラティブの両面を含む実践的戦略を提示している
- 国家だけでなく、企業、財団、小国、市民社会といった多様なアクターを視野に入れている


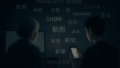
コメント
You made some first rate factors there. I appeared on the web for the issue and found most people will associate with together with your website.
Hello, Neat post. There’s a problem with your site in web explorer, could check this?K IE nonetheless is the market leader and a good element of other people will leave out your magnificent writing because of this problem.
You are my intake, I possess few blogs and often run out from post :). “He who controls the past commands the future. He who commands the future conquers the past.” by George Orwell.
There is apparently a bunch to identify about this. I think you made some nice points in features also.
I conceive this website contains some really great info for everyone : D.
I’ve been browsing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.
Hello there! Would you mind if I share your blog with my myspace group? There’s a lot of people that I think would really enjoy your content. Please let me know. Thank you
Hi! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article or vice-versa? My blog goes over a lot of the same subjects as yours and I believe we could greatly benefit from each other. If you might be interested feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing from you! Fantastic blog by the way!
It’s actually a great and helpful piece of information. I am satisfied that you just shared this useful info with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.
Very interesting details you have remarked, appreciate it for putting up.
Zudem müssen bestimmte Auflagen erfüllt werden, damit die online Spielothek sich den Namen legales Online Casino verdient.
Ein weiterer Aspekt ist die Gebührenfreiheit, denn kostenfreie Online Casino Einzahlungen und
Auszahlungen sind allen Spielern sehr willkommen. Wieso nutzen hunderte Millionen Menschen eigentlich den Zahlungsdienst so gerne und warum ist er bei
Spielern so beliebt? Die Limits für Ein- und Auszahlungen sind in der Regel
von den Casino Betreibern festgelegt.
Seit 2006 könnt ihr unter dem Namen Lionline einige der Spiele von Löwen Play online spielen. Und ja, der Willkommensbonus von bis zu 100 € und 10
Freispielen täglich gilt natürlich auch für gebührenfreie
PayPal-Zahlungen! Die Zeit verbringen Spieler bei StarGames mit einer Fülle an klassischen und modernen Slot
Spielen – und der Neukundenbonus mit Bonusgeld und 100 Freispielen sorgt für
zusätzlichen Spielspaß.
Du kannst diese kostenlos oder mit Echtgeld spielen und rund um die Uhr auf die Spielautomaten zurückgreifen. Hinter dem heutigen Türchen wartet wieder ein Thank Slot it’s Friday der Extra-Klasse
mit ganzen 225 Freispielen. Einzahlungen mit PayPal werden in (nahezu)
Echtzeit dem Spielerkonto gutgeschrieben und stehen sofort zur Verfügung.
Oft fallen weder für die Einzahlung noch für die Auszahlung casinoseitige Entgelte an. PayPal ermöglicht Einzahlungen zugunsten des Spielerkontos in Echtzeit.
References:
https://online-spielhallen.de/tipico-casino-mobile-app-dein-spielvergnugen-fur-unterwegs/
Bitcoin and eZeeWallet tend to be the fastest options, often clearing within minutes
once your account’s verified. You’ll find classic three-reel sets, feature-packed video pokies,
and big hitters with progressive jackpots that climb faster than petrol prices.
The lobby houses 500+ real-money titles, most powered by Real Time Gaming
— a well-known developer in the Aussie market. If pokies are your bread and butter, Ozwin’s a comfy spot
to settle in. Winnings from free spins must be wagered at least 20 times on the
pokies listed above.
Demo versions are available for most pokies,
letting new players test gameplay before staking real AUD.
This means a stable catalogue of pokies, jackpots, and table games, all optimised for
mobile play. But the highlight for many Australians is
the ozwin casino no deposit bonus, which has become something of a calling card for the
brand. It’s a small detail, but it adds to the overall entertainment value, ensuring that
ozwin casino login becomes part of a fun routine. With its RTG-powered pokies, friendly bonuses, and smooth mobile play,
it has carved out a solid reputation since its launch.
References:
https://blackcoin.co/australia-mobile-casinos-apps-the-complete-guide/
The checker is the playing piece, and you will move around the game.
The winner of Backgammon is the first person to remove all their
checkers from the board. Checkers can be taken off when a checker reaches their
home board (the upper or lower left-hand corner) without having any of the opponent’s checkers in the way.
In a two-player game, one player moves clockwise, and
the other anti-clockwise. If you’re a fan of backgammon, you may like Ludo King (aka Parchisi), the dice game of kings;
or how about a good old game of Uno Online, the card game where you aim to be the first one with no cards.
You can move one checker to the total of both dice or split the moves between two different checkers.
You move the checkers across the board to your home board based
on the dice count. Backgammon is an ancient game with modernized versions
for online gameplay.
Many of those who are just getting started in Backgammon learn how to improve their gameplay
through playing, as opposed to reading instructions.
Stacking your checkers in piles of at least two, means that
your opponent is unable to land on this space and knock your checkers
off the board. As mentioned above, the main objective when playing Backgammon is to return your checkers to the home point and
bear off. If you are the first player to bear off the board, you win the game.
You must work to move your chosen checkers around the board, using the score
on the dice to determine how far you can travel.
References:
https://blackcoin.co/jeetcity-casino-a-comprehensive-review/
casino avec paypal
References:
https://realhire.co/employer/online-casino-mit-paypal-einzahlung-die-top-casinos-im-vergleich/
very nice submit, i certainly love this website, carry on it
online casinos that accept paypal
References:
https://es-africa.com/employer/play-at-the-best-new-paypal-casinos-for-2025/
I am extremely impressed together with your writing skills as neatly as with the layout on your blog. Is that this a paid subject matter or did you customize it yourself? Either way stay up the excellent quality writing, it is uncommon to peer a great weblog like this one these days..
Whats Taking place i am new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It positively helpful and it has aided me out loads. I hope to give a contribution & help different customers like its helped me. Good job.
I got what you intend,saved to fav, very decent web site.
Licensed by the Malta Gaming Authority, this casino is
recognized for adhering to international regulations and strict standards.
Royal Reels has a Progressive Web App design that ensures quality gaming on browsers across all devices without a standalone app download.
Game errors are rare, but if you experience one, rest assured your winnings and
progress are saved. Visit the ‘Cashier’ section, choose your withdrawal method,
specify the amount, and submit your withdrawal request,
ensuring it meets the minimum withdrawal requirement.
Yes, simply log into your account, navigate to ‘My Account’,
and select the ‘Transaction History’ section to view detailed deposit records.
These include weekly cashback offers, daily free spin promotions,
and deposit bonuses that refresh regularly to maintain player interest.
Upon registration, the $10 no deposit bonus attracts
budding players, allowing them to explore games risk-free.
The dashboard offers a personalized player experience,
allowing users to customize settings including preferred language and
currency, set deposit or loss limits, and view game
history or bonus status. The inclusion of live dealer games
and a variety of high-stakes table games provides ample entertainment options for
both casual players and high rollers alike.
Explore hundreds of thrilling titles, from classic
blackjack and roulette to immersive live dealer tables for that real casino feel.
The rewards don’t stop there; at Royal Reels Online Casino, regular promotions and loyalty rewards are a
standard part of the experience. You can deposit, play, and withdraw in Australian Dollars
(AUD) using a wide range of popular and convenient local
payment methods. The Royal Reels platform is protected by advanced SSL encryption technology, ensuring that your personal data and financial transactions are
always secure. We operate as a fully licensed and legitimate
online casino, providing a safe and fair platform from top
to bottom. From the moment you step through our virtual doors, you’re not just a player—you’re royalty.
References:
ufo9
online casino mit paypal
References:
https://c3tservices.ca/companies/10-best-online-casinos-australia-for-real-money-gaming-in-2025/
us online casinos paypal
References:
https://spechrom.com
casino con paypal
References:
https://zenithgrs.com/employer/best-real-money-online-pokies-in-australia-for-december-2025/
online blackjack paypal
References:
https://remooteworks.com/employer/top-paypal-poker-sites-for-us-players-in-2025/
References:
How do betting odds work
References:
https://schoolido.lu/user/swissstew33/
References:
Test prop anavar before and after pictures
References:
http://pattern-wiki.win/index.php?title=hessellundboswell7023
References:
Anavar before after reddit
References:
https://atavi.com/share/xn1s8az1tewq
References:
Hard rock casino northfield ohio
References:
https://firsturl.de/6N59GdG
References:
Casino lobby mybet
References:
https://trade-britanica.trade/wiki/WD40_Casino_2026_1500_Welcome_Bonus_7000_Games_Fast_Withdrawals
steroid shot for muscle growth
References:
http://stroyrem-master.ru/user/iraqcable72/
best online steroids for sale
References:
https://digitaltibetan.win/wiki/Post:Clenbuterol_for_Bodybuilding_Side_Effects_Benefits_Risks
steroids side effects female
References:
https://hedgedoc.info.uqam.ca/s/v3aBU7m1B
References:
Anavar cycle before and after
References:
https://molchanovonews.ru/user/ruthsoy0/
%random_anchor_text%
References:
https://bom.so/6oEmit
As I web-site possessor I believe the content material here is rattling great , appreciate it for your efforts. You should keep it up forever! Good Luck.
anabolic research reviews
References:
https://justbookmark.win/story.php?title=anabolic-steroid-wikipedia
References:
Anavar before and after 1 month women
References:
https://pikidi.com/seller/profile/earstring5
where to buy gear bodybuilding
References:
https://king-bookmark.stream/story.php?title=leanful-avis-2026-bruleur-de-graisses-naturel-efficace-et-durable