報告書を作成したのは、パレスチナのデジタル権利団体7amleh(ハムレー:The Arab Center for the Advancement of Social Media)。2013年設立、ハイファとラマッラーを拠点に、SNS上での検閲、削除、アルゴリズムによる差別的抑圧の実態を記録してきた。Meta、X、TikTokなどグローバル・プラットフォームとの対話実績を持ち、国連人権高等弁務官事務所や欧州人権団体と共同声明を発するなど、パレスチナ人のデジタル空間における「発話の権利」を専門的に扱う数少ない組織である。
その7amlehが2025年10月に発表した報告書「Disinformation and its Impact on Palestinian Youth during the War on Gaza」は、2023年10月7日以降のガザ侵攻を、軍事作戦と情報作戦が一体化した現象として描く。焦点は、偽情報がパレスチナの若者の安全、心理、社会的認識にどのような形で浸透したかにある。報告書全体は、情報戦の理論的枠組、使用された技術的手法、主要な発信主体、典型的な偽情報パターン、若年層への多層的影響、そして制度的な規範の欠落という構成をとる。
情報が戦場となった構造
報告書は、現代紛争における「情報戦(Information Warfare)」を二層に区分する。第一層は軍事的意思決定を支える情報活動、第二層は情報そのものを兵器として認識や感情を支配する操作活動である。後者が今回のガザで主戦場となった。
7amlehによれば、10月7日からの初動72時間で、英語・ヘブライ語・アラビア語圏を横断して、数百万件規模の偽情報投稿が検出された。分析対象のうち約20%が自動化されたボットアカウントであり、投稿頻度は1時間あたり最大700件に達した。これは、自然発生的な抗議や支援の動きとは明らかに異なる統制的パターンを示していたという。
同時に、イスラエル当局による通信遮断が段階的に拡大し、被害現場からの直接発信が不可能になると、報道の素材は軍や政府の発表映像、または不明出所のSNS投稿に依存せざるを得なくなった。報告書はこれを「物理的優勢と情報優勢の同期化」と呼び、戦場の制圧と同時に認識空間の制圧が進行したと分析する。
生成AIと「偽の目撃者」
報告書が特に注目するのは、生成AIが導入した「即時かつ検証不能な証言装置」としての機能である。10月中旬には、AI生成の空撮画像や映像が「爆撃の瞬間」として何百万回も拡散され、CNNやBBCを含む主要メディアも一部を事実として報じた例があった。後に解析された結果、それらの映像の多くは、異なる地形パターンの自動生成モデルから合成されていた。
また、慈善団体のアカウントから投稿された“救出”動画の中には、実際には存在しない人物を描いたAI生成物も確認されている。7amlehは、こうした映像の目的が「視覚的な説得」ではなく、「共感の誘導」である点に注目する。真偽よりも感情反応が優先され、AIは「事実を代替する物語装置」と化した。報告書は「AIはもはや虚偽の証拠を作るのではなく、感情の交通を設計する手段となった」と結論づける。
アルゴリズムによる沈黙と可視性の偏り
7amlehの調査では、MetaやXにおける「#GazaUnderAttack」「#CeasefireNow」など主要ハッシュタグの露出量が、同期間中にイスラエル関連ハッシュタグの1/3以下に抑制されていた。さらに、アカウント停止や投稿削除の多くが自動検出システムによるもので、基準が非公開であったことから、パレスチナ側の声が体系的に減衰していたことが判明した。
UNRWAを標的にした広告キャンペーンでは、誤情報を含む映像広告が欧州地域に数百万インプレッションで配信されており、その一部は暴力的描写や虚偽の“人質映像”を含んでいた。これらはEUのDSA(Digital Services Act)において危機時の特別対応を要する案件であったが、実際には放置された。報告書はこれを「アルゴリズム検閲」と呼び、技術設計が語りの非対称を再生産していると批判する。
情動の兵器化と脱人間化の構造
報告書は、偽情報を六つの型に分類する。安全地帯や避難情報を偽る「情報抑圧」、AI生成映像による「完全捏造」、白燐弾使用を否定する「事実否認」、被害映像を“演出”と断じる「疑義喚起」、旧映像を再利用する「文脈攪乱」、そして民間人を“テロリスト”や“ISIS”になぞらえる「脱人間化」である。これらはそれぞれ異なる情動操作を意図して設計されており、恐怖と怒りが戦争の正当化装置として利用される。
たとえば、イスラエル政府公式アカウントが投稿した「ハマスの拷問映像」とされる動画は、後に別の国の映画作品からの引用であることが確認されたが、主要メディアの訂正はほとんど拡散されなかった。7amlehは「偽情報の目的は誤認ではなく、疑念の常態化」であり、事実の不在そのものが支配構造を形成すると指摘する。
若年層の現実認識が崩壊する
偽情報の影響は抽象的な“認識の歪み”にとどまらない。7amlehは、パレスチナの若年層が受けた具体的被害を四層に整理する。第一に身体的安全。SNS上で拡散された「安全地帯」情報に従って移動した住民が空爆に巻き込まれた例が報告され、ドローンから「泣き声を再生する音声」を流す心理戦術も確認された。第二に政策的影響。虚偽報道や誇張された証言が欧米の政治判断を歪め、UNRWAへの資金供与停止など現実の政策結果を生んだ。第三に心理的影響。若者の間では恐怖と無力感、陰謀論傾斜が拡大し、社会的信頼が崩壊している。第四に経済的影響。偽の支援キャンペーンや寄付詐欺が氾濫し、危機便乗型搾取が発生している。報告書は、これらを総じて「情報が人々の生存条件そのものを変質させている」と結論づける。
規範の空白——戦時欺罔の合法性とその越境
国際法上、意図的な虚偽情報の拡散は必ずしも違法ではない。戦時欺罔(ruse of war)は、敵軍を欺く戦術として古くから容認されてきた。しかし、デジタル時代の偽情報は、もはや敵軍に限定されず、民間人の行動や感情に直接影響を及ぼす。7amlehは、現行の国際人道法や人権法がこの領域に対応していない現実を指摘する。国連決議76/227は偽情報の人権影響を懸念として明記し、DSAはプラットフォームに緊急対応を義務づけるが、実効性は乏しい。報告書は「技術の進化が法の想定速度を上回り、無法のグレーゾーンが拡大している」と警告する。
声を守るという新しい人権
7amlehは、偽情報対策を「発信の自由」ではなく「発信が届く権利」として再定義する。単に表現の自由を保障しても、通信遮断やアルゴリズム抑圧のもとでは声は届かない。報告書は、テック企業に対しアルゴリズム透明性、AI生成物の識別、異議申立て手続の公正化を求め、国家には体系的偽情報の犯罪化と検証義務の法制化を勧告する。さらに、教育面ではメディア・リテラシーの向上と地域検証ネットワークの整備が不可欠だと強調する。ここで7amlehが提示する「声を守る権利」は、通信の自由でも報道の自由でもなく、知識が届く構造を公平に保つことを意味する。情報の非対称性そのものを是正しない限り、いかなる人権も実体を持たないという立場である。
結論——「情報の非対称」が人権の新しい断層になる
7amlehの報告書は、偽情報を単なる虚偽や誤報としてではなく、情報流通の非対称構造として捉える点に核心がある。通信遮断、AI生成、アルゴリズム制御、広告経済の誘導という複数の層が重なり、どの語りが世界に届くかを決めている。戦争が終わってもこの構造は残り続け、記録される歴史と記録されない現実の差が固定化する。偽情報の時代における人権とは、暴力から逃れる権利ではなく、語り、共有され、理解される権利のことである。ガザの若者が直面しているのは、爆撃だけではなく、真実にアクセスする権利の崩壊であり、その修復には技術・教育・法制度のすべてを横断する介入が必要だと報告書は結んでいる。


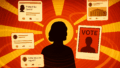
コメント
RocketPlayCasino hat Dutzende von Jackpot-Gewinnspielen von Boongo, Playson, Elk und anderen Softwareherstellern.
Sie müssen im Casino um echtes Geld spielen, um Punkte zu sammeln. Kunden können im Casino für Dollar, Euro und verschiedene Arten von Kryptowährungen spielen. Kunden können verschiedene
Arten von Roulette, Poker, Blackjack, Bakkarat und andere Glücksspiele für Geld spielen.
Das Casino bietet den Spielern eine ziemlich breite Wahl der
Zahlungsmethoden an. Das Casino zeichnet besonders aktive Spieler aus und bietet ihnen exklusive Boni
an. Sobald Sie Ihre Willkommensboni benutzt haben und bereit sind weitere Einzahlung zu machen, vergessen Sie nicht
den Bonuscode HIGHROLLER in einem speziellen Feld anzugeben. Die Willkommensbonus im RocketPlay Casino brauchen den Wiedergewinn mit der Bedeutung x40.
Sobald Sie einen Account auf der Webseite registrieren, bietet die Plattform Ihnen an die ersten zwei Einzahlungen dreimal größer zu machen und viele Free Spins in einem Top Spielautomat
zu bekommen. Alle Daten über die Lizenz und Registrierung der Spielplattform befinden sich im Footer der
Webseite.
References:
https://online-spielhallen.de/stake-casino-bonus-code-ihr-weg-zu-exklusiven-vorteilen/
New online casinos in Australia face fierce competition from established brands, so finding top operators
requires deep insight and familiarity with the market.
Welcome bonuses are generous offers for new players, often with specific requirements like minimum
deposits and wagering limits. Some online casinos even allow
you to link your Google or Facebook accounts for faster registration. Choosing secure payment methods at online casinos is important for safety and efficiency.
In this section, I will take a look at the most popular online casino games among Australians and briefly analyse them.
Once you lose a certain amount of money at an online casino, you get a percentage of it back in bonus funds.
Reload bonus is not really a type of bonus fund but rather a group of bonuses that
are meant for existing players. It’s time for something a
little bit more exciting – bonuses at AU casinos online.
I’m personally not a big fan of these, to be honest, but the
number of players logging bets onto them at every casino website
says they are nearly as popular as table games.
All the top Australian casino sites we recommend meet these standards, making it
easy for you. These are perfect for players who
enjoy competition and want more excitement than just
spinning the reels solo. Table games like blackjack and baccarat might be
your go-to. Casinonic drops a solid A$7,500 in bonus cash and gives you access to 700+ jackpot pokies, including
high-volatility options that reward patience and timing.
It ranks among the best Bitcoin casinos, where you get A$8,000 +
400 free spins welcome package for a strong start.
Neospin is the best Australian casino online.
References:
https://blackcoin.co/treasury-casino-a-comprehensive-overview/
This is usually going to automatically add the bonus to
your account. The casino should be of high quality so you can enjoy the
best games and pleasant user experience. We always look at the bonus terms before recommending bonuses.
We’re only recommending bonuses that we’ve tested and that don’t have deceitful terms.
There will be some restrictions depending on the casino you’re playing at, but these are the most flexible rewards in terms of usability.
Once the no deposit bonus was active, we also found their
welcome bonus waiting in the bonus cabinet.
There are different types of no deposit bonuses and understanding them is crucial when you
register a new account at your online casino of choice.
This simply refers to an online casino that happens to
offer no deposit bonuses. Over 15 years, players have relied on us
to bring them offers that are valid, function as
advertised, and are offered at trustworthy casinos.
Our experts curate and test hundreds of exclusive no deposit bonuses offered by trusted Australian casinos.
Any casino with a history of disregarding player issues or engaging in unethical practices will not be included.
To ensure that only trustworthy casinos feature on our site,
we actively monitor gaming forums and investigate complaints.
In order to ensure the safety and security of new casinos that we feature
on our list, we evaluate them based on fundamental criteria.
Only fully licensed casinos make the cut, each giving
you a legitimate chance of winning real cash prizes!
The best online casino in Australia really depends on your preference.
These organisations abide by strict rules and offer regular audits to ensure advanced security and fair play.
References:
https://blackcoin.co/betman-casino-a-comprehensive-review-for-australian-gamblers/
online pokies paypal
References:
https://bcstaffing.co/employer/1401853/paypal-casino-tout-savoir-sur-ce-moyen-de-paiement-en-2025
online casino mit paypal
References:
https://neulbom24.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=1032
online casino paypal einzahlung
References:
https://classifieds.ocala-news.com/author/agnesthornb
casino online paypal
References:
https://teachersconsultancy.com/employer/333830/online-casino-mit-paypal-einzahlung-die-top-casinos-im-vergleich
This combination of strategy and excitement keeps online blackjack a favorite among popular online casino games. Mobile-friendly casinos enhance player appeal by offering seamless gaming experiences on the go. Here’s a look at some of the most popular games that you can play at casinos in Australia, their win potential, and some standout examples. You can chat with professional dealers and immerse yourself in classic table games, streamed live from professional studios that replicate the look and feel of a real casino. The only entity that could find themselves in legal hot water by offering a real money gambling option to Aussies is the gambling site’s host.
Always choose casinos licensed by trusted authorities to stay on the right side of the law. It’s secure, user-friendly, and perfect for players who want hassle-free banking. PayID is a game-changer for Aussies, linking your bank account for instant deposits and withdrawals. Crypto transactions are encrypted and don’t require sharing bank details, making them a safe choice for privacy-conscious players.
Every casino I’ve listed is well-equipped to accommodate pokie players. SlotsGem launched in 2025, and while it’s still too early to say if it’ll last the distance, it’s definitely offering top-notch gaming for now. If SlotsGem hopes to remain competitive in the long term, an increase in live poker games is essential, especially hold ’em poker. None of that would’ve been possible if the wagering requirements, bonus validity, and eligible games had been more restrictive. However, I couldn’t access the table games and live dealer lobby. If I were to analyse SlotsGem’s pokies, live casino, promotions, or payments, I’d likely find myself repeating many aspects.
References:
https://blackcoin.co/ufo9-casino-your-place-to-play-your-way/
online poker real money paypal
References:
https://jobhaiti.net/employer/online-casino-mit-paypal-einzahlung-die-top-casinos-im-vergleich/
online casino mit paypal
References:
https://hmljobs.com/employer/3857/casino-welcome-bonuses-for-australia-2025
paypal casino uk
References:
https://petalconnect.org/employer/best-real-money-online-casinos-2025-updated-list/
References:
Oral anavar before and after
References:
https://socialbookmarknew.win/story.php?title=anavar-results-complete-timeline-week-by-week-how-long-to-see-a-change
References:
4 week anavar before and after male
References:
https://humanlove.stream/wiki/Anavar_Erfahrungen_Zyklus_Anavar_Frauen_Steroid_2026
References:
New york casinos
References:
https://isowindows.net/user/hoseyak23/
very nice publish, i actually love this web site, carry on it
References:
Pink floyd live in pompeii
References:
https://menwiki.men/wiki/WD40_Casino_Review_Evaluation_of_Features_and_Safety
References:
How do slot machines work
References:
https://obyavlenie.ru/user/profile/648040
purchase anabolic steroids online
References:
http://jobs.emiogp.com/author/pumaskill33/
best website to buy steroids
References:
https://dokuwiki.stream/wiki/Buy_Legal_Trenbolone_Acetate_Advices_and_Screenshots
References:
Anavar before and after latest
References:
https://www.faax.org/author/conechick2/
References:
Before and after test cyp 500 week and anavar
References:
https://ai-db.science/wiki/ANAVAR
steroids online reviews
References:
https://lynn-ottosen-2.hubstack.net/clenbuterol-und-fettverbrennung-dosierung-anwendung-wirkung-und-tipps
how do steroids work in the body
References:
https://botdb.win/wiki/Trenbolon_Wikipedia
References:
Anavar before and after reddit male
References:
https://medibang.com/author/27619345/
%random_anchor_text%
References:
https://pattern-wiki.win/wiki/Acheter_Clenbuterol_Clenbutrol_en_ligne_sans_ordonnance
References:
Do you take anavar before or after workout
References:
https://yogaasanas.science/wiki/Proteine_vor_oder_nach_dem_Training
gnc amp ripped review
References:
https://learn.cipmikejachapter.org/activity/p/156010/
how much are steroids on the street
References:
https://bom.so/FmUWj9
References:
Play black jack
References:
https://freebookmarkstore.win/story.php?title=cozy-candy-cluster-breaker-slot-review-trusted-casino-reviews-sports-betting-guide
References:
Betting odds explained
References:
http://09vodostok.ru/user/wolfhelmet14/
References:
Station casinos boarding pass
References:
https://a-taxi.com.ua/user/dollsalary1/
References:
Casino sacramento
References:
https://solomon-heller.mdwrite.net/candy96-casino-20-free-spins-no-deposit-online-engagement-for-australia
References:
Cops and robbers game
References:
https://travelersqa.com/user/barbersuit05
References:
Real money online poker
References:
https://newmuslim.iera.org/members/europeticket99/activity/449065/
women on roids
References:
https://molchanovonews.ru/user/parentchance05/
%random_anchor_text%
References:
https://coolpot.stream/story.php?title=las-10-mejores-pastillas-para-adelgazar-de-venta-en-farmacias-blog-farmaciabarata
how to get dianabol
References:
https://instapages.stream/story.php?title=farmaci-per-dimagrire-le-risposte-a-tutti-i-dubbi
%random_anchor_text%
References:
https://freebookmarkstore.win/story.php?title=quali-integratori-per-aumentare-il-testosterone
References:
Casino royal streaming
References:
https://pattern-wiki.win/wiki/Candy96_Reviews_Read_Customer_Service_Reviews_of_candy96_com
References:
El dorado casino shreveport
References:
http://muhaylovakoliba.1gb.ua/user/sheepturkey5/
References:
Mexican jumping beans video
References:
https://humanlove.stream/wiki/Candy_Blitz_RTP_96_08_Pragmatic_Play
References:
Slot machine game
References:
https://elearnportal.science/wiki/BEST_LIVE_CASINOS_2026_100_Live_Dealer_Games
what steroids did arnold use
References:
https://aryba.kg/user/cloudcanoe2/
psychological effects of anabolic steroids
References:
https://socialisted.org/market/index.php?page=user&action=pub_profile&id=301765
www anabolic com
References:
https://opensourcebridge.science/wiki/Testosterona_Medicamentos_hormonales_disponibles_en_Farmatodo
where to purchase anabolic steroids
References:
https://hedgedoc.info.uqam.ca/s/TeRsNVJO_o
References:
Wynn casino
References:
https://sciencewiki.science/wiki/Admiral_Bonus_Code_2024_Mit_Exklusivem_Code_zu_fantastischen_Boni
References:
Roulette betting
References:
https://godwin-whitney-2.federatedjournals.com/i-bonus-2026-erfahrungen-und-test
References:
Ameristar casino
References:
https://morphomics.science/wiki/888_Casino_Cashback_So_Sichern_Sie_Sich_Ihre_Rckerstattung
References:
American roulette
References:
https://images.google.so/url?q=https://online-spielhallen.de/1red-casino-bonus-codes-ihr-umfassender-leitfaden/
References:
Singapore casino
References:
http://pattern-wiki.win/index.php?title=bynumquinn8748
References:
Kentucky casinos
References:
https://molchanovonews.ru/user/ricesleep8/
References:
Casino las vegas online
References:
https://may22.ru/user/alibiliquid67/