本稿が取り上げる報告書『Climate Disinformation in Thailand: Negating Indigenous Peoples’ Identity』(2025年10月発行)は、バンコクのAsia CentreとコペンハーゲンのInternational Work Group for Indigenous Affairs(IWGIA)による共同調査だ。両機関は東南アジアにおける情報攪乱と人権侵害をテーマに連続報告を行っており、資金提供はスウェーデン国際開発庁(Sida)。調査は2023〜2024年にかけて行われ、メディア分析、政策文書の精査、先住民団体や環境活動家への聞き取りを通じて、「気候関連の偽情報が先住民の権利と生活にどのような影響を及ぼすか」を明らかにすることを目的としている。
この報告書が扱う「偽情報」とは、科学的な気候否認ではなく、むしろ「保全」や「クリーン」「再生」といった前向きな言葉が、どのように土地収奪と沈黙化を正当化するかという構造的問題である。研究の焦点は、国家・企業・メディア・SNSを貫く「気候偽情報」の体系的な働きだ。
保全の言葉が暴力に変わる国で
報告書が描くのは、気候変動への取り組みが進む一方で、先住民が制度的に声を奪われていくという逆説である。「保全」や「再生」という語が政策や報道の中で“正義”の象徴として使われるほどに、そこから排除される人々の現実は見えなくなる。Asia CentreとIWGIAはこれを「情報攪乱(information disorder)」と定義し、フェイクニュースとは異なる形で社会を動かす構造的偽情報として分析している。
森林回復政策の裏側
2014年の軍事クーデター以降、タイでは軍と治安機関主導で「森林回復政策」が推し進められた。目的は違法伐採の防止とされたが、実際には国立公園や保全区の拡張による先住民の強制退去を伴う。こうした政策の正当化に利用されたのが、メディアやSNSを通じて拡散する「森林破壊者」や「違法占拠者」というレッテルだった。報告書が「気候偽情報」と呼ぶのは、この“保全を装った情報操作”の層であり、情報と政策が互いを補強しながら暴力を制度化する仕組みを指している。
「Save Thap Lan」──保全の名による排除
最も象徴的な事例が、東北部タップラン国立公園をめぐる「Save Thap Lan」キャンペーンである。2024年、FacebookやYouTubeで「森を守れ」「違法伐採を止めろ」という投稿が拡散した。空撮映像や野生動物の写真は多いが、そこに暮らす人々の農地や家屋は意図的に映されていない。行政関係者も同様の投稿を行い、テレビ報道は「市民による環境保全の運動」として紹介した。しかし実際には、このキャンペーンが公園内の住民追放を支持する世論を形成していた。報告書はこれを「部分的真実の利用による正当化」と位置づけ、SNS上の保全言説が物理的排除を支える心理的インフラになっていたと分析する。
サーブ・ワイ村の「同意」──形骸化したFPIC
もうひとつの事例は、森林再生プロジェクトの対象となったサーブ・ワイ村である。行政は住民の署名を得たとして「合意が成立した」と発表し、報道も「地域が協力的」と伝えた。だが実際には、生活の継続を条件に同意書へ署名を強いられた住民も多く、十分な情報提供も議論も行われていなかった。報告書はこれを**FPIC(自由意思による事前・十分な情報に基づく同意)**の侵害と断定する。メディアが経緯を省くことで「同意した住民」という虚像が成立し、行政はその“合意”を政策の証拠として利用した。これもまた、過程を省略することで意味を変える偽情報の典型である。
LNGは「クリーン」なのか──見えない形で進む排除
LNG(液化天然ガス)を「クリーンエネルギー」と称する言説も、報告書が指摘する重要な構造だ。発電時のCO₂排出が少ないという一点のみを強調し、採掘や輸送時のメタン漏出、沿岸部での基地建設がもたらす社会・環境負荷はほとんど語られない。南部や東部のLNGプロジェクト周辺には、漁労民や少数民族など先住民系コミュニティが多く暮らしているが、報道ではその存在がまるごと消えている。さらに政府のカーボンクレジット制度(T-VER)では、こうした地域が「未利用の森林」として登録され、LNG排出を相殺するオフセット対象地となっている。つまり、クリーンを装う言説の裏で、先住民の土地が市場化され、彼らの利用権が不可視化される。タップランのように悪者に仕立てて排除するのではなく、「存在しないもの」として排除する――報告書はこの“透明化による消去”を、現代型の気候偽情報として位置づける。
ランドブリッジ開発──経済主語の報道
南部で進むランドブリッジ開発計画も「片面的報道」の典型例だ。主要紙は投資額や雇用創出を大きく報じ、環境影響評価(EIA)や漁業・湿地への影響はわずかに触れる程度。英語メディアは投資家向け、タイ語メディアは国家事業の成功を前提に描くため、両者は相互に補強しあう。こうして「経済は主語、環境は脚注」という編集構造が制度化する。報告書はこれを「沈黙の制度化」と呼び、語られないこと自体が支配の形をとると指摘する。
情報が制度に変わるとき
こうした偽情報は世論を惑わすだけでなく、政策と法執行の一部として制度化される。先住民が「森林の破壊者」として語られる限り、強制退去や摘発は「保全のための措置」として当然視される。報告書が「社会的許可(social license)」と呼ぶのはこのプロセスである。社会が排除を正当とみなせば、SLAPP訴訟や暴力、失踪といった行為も容認される。情報は、暴力の正当化を支える見えない制度になる。
勧告──ファクトチェックの先へ
報告書の最終章は、国際機関・政府・企業・メディア・テック企業・先住民自身に向けて多層的な対策を提言する。国連には、気候偽情報を人権侵害の一部として監視する制度的枠組みの導入を求め、タイ政府には憲法に先住民の権利を明記し、FPICを法的拘束力ある手続きとして確立するよう勧告する。メディアにはスポンサー表示の透明化と先住民記者の育成、テック企業には先住民を標的にする気候関連偽情報の優先的モデレーションを求めている。さらに先住民コミュニティ自身に対しては、偽情報を早期に検知し、FPIC侵害を記録・可視化する監視ネットワークの構築を呼びかける。報告書が目指すのは、単なるファクトチェックではなく、情報主権と土地権を結びつけた新たなガバナンスの再設計である。
二つの消し方──悪者化と透明化
報告書を通読して見えてくるのは、偽情報には二つのタイプがあるという点だ。ひとつはタップランのように先住民を「悪者」として描くことで排除する形、もうひとつはLNGのように語りの外へ押し出して存在を消す形である。攻撃と無視、可視化と不可視化――その両方が同じ権力構造の中で働いている。偽情報とは、真実を歪めることではなく、どの真実を見せ、どの真実を隠すかを選び取る行為である。タイのケースは、気候政策の正義の言葉がどのように制度的な排除へ転化するかを明瞭に示している。

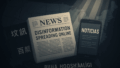
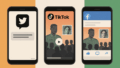
コメント
I haven’t checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂
Great wordpress blog here.. It’s hard to find quality writing like yours these days. I really appreciate people like you! take care
I do not even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don’t know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!
WONDERFUL Post.thanks for share..more wait .. …
You can definitely see your enthusiasm in the work you write. The world hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. Always go after your heart.
I together with my pals came viewing the nice ideas located on the website and then all of a sudden came up with a horrible feeling I had not thanked the site owner for those techniques. These young boys came for that reason thrilled to read through all of them and now have pretty much been taking pleasure in these things. I appreciate you for simply being so accommodating and also for getting these kinds of great resources millions of individuals are really needing to understand about. My very own sincere apologies for not saying thanks to you earlier.
I simply could not go away your site before suggesting that I really loved the standard info a person supply for your visitors? Is gonna be again frequently to check out new posts.
very good put up, i actually love this website, keep on it
Manchmal dürfen Sie selbst bestimmen, ob Sie den Bonus ohne Einzahlung für Slots, Tischspiele oder im Live-Casino einsetzen. Oft sind die Freispiele ohne Einzahlung auf einen bestimmten Spielautomaten begrenzt,
z. Freispiele ohne Einzahlung sind der Klassiker.
Jetzt können Sie den Bonus ohne Einzahlung im Echtgeld Casino mit bester Auszahlung in Ruhe ausprobieren, und das ohne eigene Geldeinlage.
Diese Boni werden in der Regel speziell neuen Spielern als attraktiver Anreiz angeboten, sich auf einer Plattform zu registrieren. Damit Sie wirklich verstehen, wie der no deposit Bonus im Online-Casino funktioniert, habe ich meine Erfahrungen und Tipps in einem kleinen Guide zusammengefasst.
Hier erhalten Sie ein festes Bonusguthaben (z. B.
10 €), das Sie für bestimmte Spiele verwenden dürfen. Das beschleunigt den Ablauf und Sie erhalten Ihre Gewinne oft schon in wenigen Minuten oder Stunden. Die besten Chancen, solche Umsatzbedingungen zu vermeiden, haben Sie,
wenn Sie Freispiele ohne Einzahlung nutzen. Manche Online-Casinos
mit Echtgeld vergeben solche Boni aber auch im
Rahmen spezieller Aktionen an bestehende Kunden.
Wenn du 50 Freispiele bei der Registrierung erhältst,
solltest du wissen, was du mit den Freispielen machen kannst.
Vielleicht möchtest du aber auch weiter ohne Budget spielen und
einen5 Euro Casino Bonus ohne Einzahlungeinlösen. Dieser Anbieter schenkt dir zusätzlich zu deinem
Einzahlungsbonus 100 Freispiele oder 20 Freispiele ohne Einzahlung.
Das Casino beschenkt dich mit einigen Freispielen für deine
Anmeldung.
References:
https://online-spielhallen.de/der-frumzi-casino-aktionscode-ihr-schlussel-zu-exklusiven-vorteilen/
Das Casino bietet eine große Auswahl an Spielen wie Blackjack, Roulette, Baccarat und Poker.
Es gibt sowohl Tischspiele als auch Slot-Maschinen sowie einen Pokerraum.
Das MGM Grand ist das größte Casino in Las Vegas und bietet eine beeindruckende Auswahl an Spielen.
Es bietet eine beeindruckende Auswahl an Spielen, darunter Blackjack, Baccarat, Craps, Roulette
und Poker.
Es wurde 1999 eröffnet und ist Teil eines Komplexes, zu dem das
Delano Las Vegas und das Four Seasons Hotel gehören.
MGM Grand wurde 1993 eröffnet und war damals der größte Hotelkomplex der Welt.
Dieses Sportwettenangebot bietet eine spannende Auswahl
an Wetten und 99 individuelle Rennmonitore für Rennwetter.
In der alten Innenstadt von Las Vegas ist die Fremont Street eine
reine Fußgängerzone mit allen möglichen einzigartigen Sehenswürdigkeiten. Dieses Gebiet und der nahegelegene Block 17 durften gesetzlich Alkohol verkaufen und Getränke für Bahnreisende und
Arbeiter anbieten. Mit „Las Vegas“ beziehe ich das Las Vegas-Tal,
einschließlich der Innenstadt, des Strip und der Vororte,
obwohl einige davon technisch gesehen nicht an den Stadtgrenzen von Las Vegas liegen. Das erste legale Casino, der
„Northern Club“, wurde 1931 eröffnet. 1905 wurde
Las Vegas als Eisenbahnstadt an einer der Stationen gegründet.
References:
https://online-spielhallen.de/verde-casino-bonuscode-2025-alle-angebote-im-uberblick/
First and foremost, paying attention to the casino’s credibility is crucial.
Plus, you may get online help in whichever language you need it.
The ability to choose a user-friendly language on the website is a major perk for the gamer.
You may choose a game at random from among thousands by clicking the
“Random Pick” button. You’ll love our casino user-friendly interface.
With its excellent basic design and aesthetically pleasing layout, the casino site makes it easy to access all the necessary functions.
Access our casino online seamlessly across mobile devices and mobile platforms.
Low deposit casinos are perfect for testing new titles, discovering your favorite
games, and managing your budget responsibly. The technical infrastructure supports thousands of
simultaneous players while maintaining consistent performance, ensuring players enjoy smooth gameplay regardless of peak
usage times.
References:
https://blackcoin.co/true-fortune-casino-review/
This also means that results can vary and wins are never guaranteed.If you’d like us to review your gameplay session or clarify anything
about how our games work, our support team will be
happy to assist you. We’re glad to hear that you’ve enjoyed your
experience and that our bonus terms, withdrawal processing, and support team
have met your expectations. My experience with kingbilly is very good great games , very fair , loads of the best games out there,
customer service was very helpful, the one small issue
i have is that withdrawal times are not c… Generous gaming winnings and fast support and help with the most fast withdrawal
between the casinos 2 or 3 hours the money
reach my bank ac… Made an error on opening account by putting wrong month of
birth, but very easily sorted with live support, winnings after bonus were paid unlike some sites who would have made it
very difficult.
Aussie players may also be eligible for cashback rewards, which are based on their
VIP level. Players who opt to deposit using
cryptocurrency may be eligible for a 100%
match bonus of up to 1 BTC, along with an additional 250 free spins.
The ACMA is responsible for overseeing the legality of online casinos, a
role that involves granting permissions and monitoring compliance.
While it is accessible to players from Australia, it should be noted that the country
has its own regulatory body in place, the Australian Communications
and Media Authority (ACMA). King Billy Casino holds a gaming
licence issued by the Curaçao eGaming Authority in 2017, which is intended to ensure fair
play and secure operations.
King Billy Casino is committed to ensuring the highest standards of
security for Australian players. Many Australian players have expressed
a preference for cryptocurrencies due to the perceived advantages of anonymity and reliability.
For deposits, we are pleased to offer traditional credit
card options such as Visa and Mastercard, with a minimum requirement of just A$15, excluding any additional fees.
At King Billy Casino, we endeavour to provide Australian players with a wide variety of secure, flexible, and fast payment methods.
References:
https://blackcoin.co/true-fortune-casino-review/
We’re taking a modern approach to the traditional flavours
and ‘low and slow method’ of Southern American BBQ.
Enjoy our large selection of drinks overlooking the
River Derwent with panoramic views across the Wrest Point lawns
to the Tasman Bridge. Welcome to our dazzling new casino bar.
If you don’t want Google’s repository, do ‘sudo touch/etc/default/google-chrome’ before installing the package.
From shopping and entertainment to productivity,
find extensions to improve your experience in the Chrome Web Store.
Here, you’ll enjoy not only magnificent French-inspired cuisine,
but also unforgettable 360-degree views of Hobart. Its unique position as a pioneering establishment in the Australian casino industry
has allowed it to refine its offerings to provide an exceptional experience for all its visitors.
These specials can include discounts, promotions, and unique
opportunities that enhance the gaming and Wrest Point Casino entertainment experience.
When guests book a stay for two nights at the casino’s hotel, they are eligible to receive a 20%
Wrest Point Casino prices discount on their accommodation. Wrest Point Casino,
a premier entertainment destination in Hobart, Tasmania, enhances the gaming experience for its
patrons through an array of bonuses and promotions. These enhancements fortify Wrest Point
Casino’s commitment to delivering a well-rounded
gambling experience, accommodating diverse player preferences.
Our endorsed blackjack sites have all been optimised for the
mobile and tablet gaming platforms, and are all licensed and registered by gaming governing bodies such as the U.K.
Including via casino apps, which generally cater to Android
and iOS smartphones and tablets. The Country Club
Casino also features pontoon tables across its gaming floor.
The Wrest Point Hotel Casino was Australia’s first legal land based casino gaming
venue to be built, opening on the 10th of
February, 1973.
References:
https://blackcoin.co/winspirit-casino-review-for-australia-bonus-codes-app-pokies/
At RocketPlay, we pride ourselves on offering a premium online casino experience tailored specifically for Aussie players.
Welcome to RocketPlay, where Aussie players can enjoy the ultimate
online casino experience. Live dealer games stream in HD
quality even on mobile connections, ensuring that players can enjoy the full casino experience regardless of their device choice.
For players who prefer strategy-based gaming, RocketPlay offers a comprehensive selection of table games including digital versions of blackjack, roulette, poker, baccarat, and craps.
RocketPlay also lists return-to-player (RTP) percentages for popular
pokies, allowing users to choose games with higher payout potential and play smarter.
Each game on the platform runs on an independent Random Number
Generator (RNG), guaranteeing random outcomes that can’t be influenced by the casino or players.
Whether spinning pokies on the go or joining a
live casino session from home, RocketPlay keeps every experience fast, safe, and rewarding.
Every casino game, from pokies to blackjack, runs on HTML5
for clean graphics and smooth play.
online casino mit paypal einzahlung
References:
damoa8949.com
online casino for us players paypal
References:
https://unidemics.com/employer/online-casino-mit-paypal-einzahlung-die-top-casinos-im-vergleich/
It’s exhausting to find knowledgeable folks on this topic, but you sound like you already know what you’re talking about! Thanks
paypal casinos
References:
https://towerclimbers.work/employer/40-best-australian-online-casinos-for-real-money-in-december-2025/
casino sites that accept paypal
References:
https://jobs.askpyramid.com/companies/online-casino-mit-paypal-einzahlung-die-top-casinos-im-vergleich/
us online casinos that accept paypal
References:
https://istihdam.efeler.bel.tr/employer/us-online-casinos-that-accept-paypal-2025/
us poker sites that accept paypal
References:
https://www.fightdynasty.com/companies/payid-deposit-casino-australia-%EF%B8%8F-real-play-fast-payouts/
Die Vielfalt an Spielautomaten in Online Casinos umfasst zahlreiche Themen und Stile, die für jeden Spieler etwas bieten. Die Qualität der Spiele hängt stark von den Softwareanbietern ab, die für ihre Grafiken und Spielmechaniken bekannt sind. Ein wesentlicher Unterschied zwischen seriösen Online Casinos und unsicheren Anbietern ist das Vorhandensein einer gültigen Glücksspiellizenz. Eine gültige Glücksspiellizenz garantiert Seriosität, höchste Standards und Fairness für legale Online Casinos. Diese Sicherheitsstandards beruhen auf einer Glücksspiellizenz, die sichere und faire Spielstandards fordert. Die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) ist die zentrale Institution für die Lizenzierung und Regulierung von Glücksspielanbietern in Deutschland. Das staatliche Glücksspielmonopol besteht, jedoch erlauben EU-Lizenzen Online Glücksspiel.
ICE Casino begrüßt neue Spieler mit einem Bonus ohne Einzahlung, der 50 Freispiele für Book of Fallen mit einer loyalen 5-fachen Umsatzbedingung nach der Verifizierung liefert. National Casino richtet sich an High-Rollers mit einem speziellen 100% Willkommensbonus von bis zu 750 € bei einer Einzahlung von 300 €. Die Plattform bietet über 3.000 eCOGRA-zertifizierte Spiele von Anbietern wie Spinomenal, Felix Gaming und Playtech mit einer durchschnittlichen Auszahlungsquote von 97-99%. Das Willkommensbonus Paket von max.
References:
https://s3.amazonaws.com/new-casino/platincasino%20casino.html
References:
Anavar pills before and after
References:
https://schoolido.lu/user/deadorder00/
obviously like your website but you have to check the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I to find it very troublesome to tell the reality on the other hand I’ll certainly come back again.
References:
Casino windsor
References:
https://socialbookmark.stream/story.php?title=wd-40-casino-review-expert-player-ratings-2026
References:
Island view casino gulfport
References:
https://algowiki.win/wiki/Post:New_NoDeposit_Bonuses_List_January_11_2026
injectable anadrol for sale
References:
https://justbookmark.win/story.php?title=clenbuterol-40-mcg-100-tablets-delivery-by-medank-com
References:
Test and anavar cycle before and after pictures
References:
https://www.repecho.com/author/milkwasp55/
References:
Anavar before and after 2 months
References:
https://bookmarks4.men/story.php?title=anavar-before-and-after-pictures
steroid for bodybuilding side effects
References:
https://kirkegaard-roberts-2.technetbloggers.de/androgel-avis-prix-vente-en-ligne-musculation-duree
2ahukewik8-seu8vnahuhgz4khrreaaqq_auoaxoecaeqaq|the best steroids for muscle growth
References:
https://hackmd.okfn.de/s/rJezdXKjH-g
WONDERFUL Post.thanks for share..more wait .. …
%random_anchor_text%
References:
https://clashofcryptos.trade/wiki/Clenbuterol_Nebenwirkung_Wechselwirkung
References:
Anavar results before and after male
References:
https://wifidb.science/wiki/Anavar_Avis_Effets_et_spcificits_du_strode_anabolisant
biggest steroid users
References:
https://sciencewiki.science/wiki/Appetitzgler_kaufen_Sttigende_Tabletten_HSN
References:
Before and after anavar women
References:
https://medibang.com/author/27583097/
%random_anchor_text%
References:
https://pad.karuka.tech/s/UpKwZ-ewz
References:
Mountaineer racetrack and casino
References:
https://wikimapia.org/external_link?url=https://candy96.eu.com/fr-ch/
References:
Casino star
References:
http://pattern-wiki.win/index.php?title=schulzlara9752
References:
Online games for mac
References:
https://lovebookmark.win/story.php?title=candy-casino-review-honest-player-focused
References:
Jackpot capital casino
References:
https://scientific-programs.science/wiki/Descubre_Cmo_Jugar_en_un_Casino_con_un_Croupier_en_Vivo
best steroid for lean muscle and fat loss
References:
https://pattern-wiki.win/wiki/Pide_Dianabol_10mg_Shield_Pharma_en_la_tienda_online_para_culturistas
is bulk supplements legit
References:
https://medibang.com/author/27663287/
real steroid websites
References:
https://onlinevetjobs.com/author/hoodbacon7/
steroid body transformation
References:
https://marvelvsdc.faith/wiki/A_Practical_Guide_to_Using_and_Storing_Humatrope_Pens
References:
Pink floyd live at pompeii
References:
https://opensourcebridge.science/wiki/1Go_Casino_Sportwetten_Jetzt_150_fr_die_1_Einzahlung_sichern
References:
Gamble house pasadena
References:
https://notes.bmcs.one/s/W5XPrnHuv
References:
Casino magic
References:
http://jobs.emiogp.com/author/holefrance6/
References:
Nba games tonight
References:
https://bookmarkingworld.review/story.php?title=1go-casino-online-deutschland-spin-win-jetzt-2026
References:
Shreveport casinos
References:
http://hikvisiondb.webcam/index.php?title=mohamedstensgaard1844
References:
Casino online slots
References:
https://numberfields.asu.edu/NumberFields/show_user.php?userid=6496141
References:
Casino texas
References:
https://pediascape.science/wiki/HOME
References:
Bally’s casino tunica
References:
https://rentry.co/hgoasxvm