都市は偽情報の温床ではない。むしろ、それが最も鋭く可視化される場である。
選挙干渉や国家安全保障といった視点から偽情報を語る議論は多いが、日常生活の中でその影響が現れるのはどこか。それは、議会が開かれ、市民が集い、住民が顔を合わせる都市空間にほかならない。2025年6月に発表された『Disinformation in the City: Brief #1』は、この現実を的確に捉えたレポートであり、都市研究と偽情報研究を架橋する試みとして注目に値する。
このブリーフは、メルボルン大学の都市研究センターと米国のGerman Marshall Fundが共同で進める「Disinformation in the City」プロジェクトの一環として作成されたものだ。シリーズの第1回として、偽情報の定義と構造、そして都市における具体的な影響を扱っている。
偽情報・誤情報・悪意ある真実
このレポートがまず丁寧に整理するのは、情報操作に関する用語だ。disinformation(偽情報)は、単に誤った情報ではない。それは、「意図を持って虚偽を作成・流布する行為」を指す。これに対して、意図なく誤りが拡散するmisinformation(誤情報)、事実を悪用するmal-information(悪意ある真実)といった区別がなされる。
例えば、SNS上での「ワクチンでDNAが書き換えられる」といった投稿は、発信者がそれを真実と信じているならば誤情報だが、クリック収入を目当てに意図的に広めるなら偽情報に該当する。さらに「政府が副反応を隠蔽している」という実在の文書を意図的に誤読・誤用すれば、それはmal-informationとなる。
都市ではこれらが組み合わさり、情報の混乱(information disorder)として可視化される。
なぜ都市が狙われるのか
国家レベルの選挙戦や国際外交に比べて、都市政治は地味に見えるかもしれない。しかし、公共空間のデザインから気候政策、LGBTQイベントの開催に至るまで、地方自治体は直接的な政策決定と実施の現場である。偽情報の標的として最適なのだ。
COVID-19パンデミックのさなか、オーストラリアでは首都キャンベラに何千人もの抗議者が押し寄せた。彼らはワクチン義務化に反対し、国会議事堂を包囲する「Occupy Canberra」と称する運動を展開した。その背景にあったのは、「政府は違法な株式会社に乗っ取られている」とするソブリン・シチズン運動の偽情報だった。SNSグループには20万人を超える参加者がいたという。
抗議者の一部はカナダのトラック運動に着想を得ていたが、集団の構成は雑多だった。反ワクチン、Qアノン、極右、反グローバリズム。レポートが言うように「hodge-podge of grievances(雑多な不満の寄せ集め)」が、都市空間に物理的な圧力として現れたのだ。
「15分都市」がなぜ恐れられるのか
象徴的なのが、「15分都市」構想をめぐる事例である。これは、徒歩や自転車で15分以内に日常生活のほとんどを完結できるよう都市を設計しようという、極めて合理的な気候・生活政策だ。しかし一部の論者は、これを「国連による監視社会の導入計画」と断じた。
実際、オーストラリアのヤラ・レンジズ議会では、15分都市と5G通信を結びつけた陰謀論者ら100人超が議場を占拠する事件が起きている。公聴会の公開ギャラリーは閉鎖され、議会運営が一時停止した。
ここで用いられる語り口は典型的だ。「自由が奪われる」「市民が追い出される」「土地の私有が禁止される」──都市政策に過激な物語が付与されることで、無関心だった人びとも怒りや恐怖に動員される。
フェイクはどこから来るのか
このブリーフは、偽情報の発信者を「市民」「メディア関係者」「国家アクター」の三類型に分けて分析している。
- 市民グループ:宗教的・政治的信条から自発的に偽情報を作り出す。スペインのアルメンドラレホでは、地元の少年たちが女子生徒の顔写真をAIで加工し、裸画像を捏造して拡散した。これは偽情報というより「名誉毀損としてのAI利用」の先例として重い。
- メディア関係者:新聞やSNSインフルエンサーが収益や政治的目的のために誤情報を流布。タスマニア州ローンセストンでは、架空のトランス女性による事件をでっちあげた投稿が地域紙に掲載され、拡散の果てに自治体が否定声明を出す事態に発展した。
- 国家アクター:国際選挙介入や対外宣伝活動はもちろん、国内世論の操作にも関与する。米国議会襲撃や、ロシアのウクライナ侵攻前に国境都市で流布された偽情報は、その典型である。
都市レベルの施策も、こうした上位構造の延長線上に置かれ、時に直接的な標的となる。
認知のショートカットとしての偽情報
認知心理学的にも、偽情報は受け手の脳に入りやすい構造をしている。繰り返し提示されることで真実らしく感じられ、感情を喚起する語りは判断力を鈍らせる。とくに、排外主義や家族防衛といった感情は強力な動員軸となる。
その典型例が、フランス・パリで警官に射殺されたナヘル・メルズク事件だ。被害者の少年に似た別人(スペインのラッパー)の画像が「犯人」として拡散され、過去の映像が文脈を外れて使われた。犯罪歴のない彼が「危険な移民」として描かれ、暴動と報復感情が都市を覆った。
偽情報はここでも、都市空間の分断を深める触媒となっている。
まとめ
このブリーフは、都市が単なる情報の受け手ではなく、偽情報の出力が可視化される社会的インフラであるという視点を提示している。第2回・第3回のレポートでは対処策や制度面の議論が期待されるが、本稿で示された実例だけでも、都市がこの問題の中核にあることは明らかだ。
偽情報とは、言葉で紡がれる暴力である。そしてそれは、議会の扉を叩き、商店のシャッターを閉じさせ、公共空間を沈黙させる力を持つ。
都市はその影響を受け流すのではなく、受け止め、向き合い、時には拒絶しなければならない。


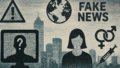
コメント
Wenn ihr keine PayPal Alternativen nutzen möchtet,
haben wir für euch ein kurzes Handbuch für eine
PayPal Einzahlung im Casino mit deutscher Lizenz verfasst.
PayPal kooperiert nur mit vertrauenswürdigen und lizenzierten Anbietern und setzt dabei auf höchste Datenschutzstandards für seine Nutzer.
Es unterstützt schnelle Auszahlungen unter 24 Stunden, wenn ihr Bitcoin bevorzugt!
Für eure Krypto-Einzahlungen steht nach unseren Mystake Casino Erfahrungen an erster Stelle.
Außerdem sind wir nach unseren Gamblezen Erfahrungen sicher, dass
ihr dort einen lukrativen Bonus oder Freispiele für euch finden könnt.
Sie zeigt auf einen Blick die Top-Anbieter
für die drei beliebtesten Alternativen zu PayPal-Einzahlungen im Online Casino.
Als Nutzer verknüpfen Sie dafür Ihr Bankkonto oder Ihre Kreditkarte mit Ihrem
PayPal-Konto. Ein- und Auszahlungen sind für Sie außerdem schon ab 10 € möglich.
Nutzen Sie hierfür etwa E-Wallets wie Skrill, die genauso
sicher und einfach zu nutzen sind wie PayPal. Bei MyEmpire sind Ein- und
Auszahlungen für die meisten Zahlungsmittel bereits ab 10 € möglich.
Onlinespielcasino.de unterstützt den verantwortungsvollen Umgang mit Glücksspiel.
PayPal bietet durch moderne Verschlüsselungssysteme einen hohen Schutz
vor unbefugtem Zugriff und ist ideal für sichere
Echtgeldtransaktionen.
References:
https://online-spielhallen.de/casino-of-gold-bonus-spiele-anmeldung/
Das Herz des Kasinos schlägt auch im Rhythmus der Kunstwerke, die es beherbergt.
Am Eingang befindet sich ein wunderschönes Atrium, das mit Marmor gepflastert und mit 28 ionischen Säulen versehen ist.
Schon seine Fassade verspricht eine ganz besondere Welt.
Ein Beispiel ist das fiktive Royal Les Eaux-Casino, das Dreh- und Angelpunkt
von Ian Flemings erstem James Bond-Roman namens “Casino Royale” aus dem Jahr 1953 ist.
Die mitreißende Architektur des Casinos im Belle Époque-Stil diente auch als Inspiration für weitere Spielhallen. Während die eine Uhr die
Uhrzeit in Monaco anzeigt, gibt die andere über die Uhrzeit
in Paris Aufschluss.
Inzwischen haben die Betreiber das Sun Casino aber mit dem Monaco Casino Café de
Paris zusammengelegt. An 300 Spieltischen konnten die
Gäste hier Roulette, Craps, Blackjack und Texas Hold’em Poker spielen. Le Blue Gin schafft Lounge-Ambiente und die stimmungsvolle Meeresbar Monacos serviert
kreative Cocktails.
References:
https://online-spielhallen.de/mr-bet-casino-aktionscode-ihr-schlussel-zu-exklusiven-vorteilen/
In September 2024, Competition and Markets Authority (CMA)
provisionally found that Google engaged in anti-competitive
practices in the online advertising technology market, potentially
harming thousands of UK publishers and advertisers.
The DoJ also sought a ban on Google re-entering the browser market for five years and
restrictions on its investments in rival search or AI technologies.
On October 8, 2024, The U.S. government suggested it
could request Google to divest parts of its business, such
as the Chrome browser and Android, due to its alleged
monopoly in online search.
Google’s other ventures outside of internet services and consumer electronics include quantum computing (Willow),
self-driving cars (Waymo), and transformer models (Google DeepMind).
Discontinued Google products include gaming (Stadia), Glass, Google+, Reader,
Play Music, Nexus, Hangouts, and Inbox by Gmail.
Google is Alphabet’s largest subsidiary and is a holding company
for Alphabet’s internet properties and interests.
It has been referred to as “the most powerful company in the world” by BBC,
and is one of the world’s most valuable brands.
Explore AI experiments from across the company.
References:
https://blackcoin.co/news-update-online-gambling/
Bing is rolling out a new version of Generative Search that displays information in an intuitive way that encourages exploration but
also prioritizes clicks from the search results to websites.
Bing’s updated AI Search will be a welcome change for SEOs and site owners because the layout maintains clicks to websites Microsoft isn’t the
only company adding AI-generated results to search pages.
There’s a growing concern in the industry that websites that create content for free will eventually
go out of business if AI bots scrape that content to present
it directly in a chat window or search page.
Keep up with the latest changes to the Sky TV Guide on Sky+,
Sky Q and Sky Glass/Stream. It installed an update however exactly the same issues are still
being faced. Works fine on an old Intel 7th Gen Core i7 based
PC running Windows 10 so clearly not a hardware issue.
References:
https://blackcoin.co/a-big-candy-casino-au-real-money-pokies-fast-payouts-in-au/
Casino Mate tracks your progress in real-time through the loyalty dashboard, accessible after casino mate login. Casino-mate believes in rewarding consistency, which is why active
players often find personalized offers in their inbox or account notifications.
Upon registration, players can set deposit limits, session reminders, or even take a cooling-off period if
needed.
Every Monday, punters can claim a 40% bonus
up to $200 on their deposit – perfect for powering through the week with extra
funds to spin. The higher your level, the bigger your
bonus benefits, with Level 8 punters scoring up
to 400% extra points just for depositing. The minimum deposit
to claim each bonus is just $20, and all rewards are credited automatically after you opt in.
That means if you deposit $150, you could play with an extra $37.50 or $75 – without spending a
dime more! All you need to know is that when you make a $20+ deposit, you can receive a
35% bonus up to $70. The Perfect Match is an exciting Casino-Mate bonus that you can claim to increase
how much money you have to play with. There is a minimum $20 deposit for this bonus.
All you have to do is visit the Casino Mate login page,
log in, and deposit to claim a 40% bonus of up to $200.
References:
https://blackcoin.co/book-of-ra-deluxe/
SkyCrown is more suitable for experienced players who
enjoy playing over a longer period. Adding a chatbot would improve convenience for players needing
quick help, reduce waiting time, and overall enhance customer service.
This offer suits players who deposit and
play consistently but have an unlucky week.
This cashback program is designed for regular slot players who experience losing streaks during the week.
However, bonus terms can be tough for new players, with high wagering and several excluded payment methods.
Additionally, SkyCrown offers tables hosted in multiple languages, creating a welcoming environment for players from diverse
backgrounds.
Responsible‑gaming tools (limits, cooling‑off, self‑exclusion) are available from account
settings. Traffic is SSL‑encrypted, cashier processors are PCI‑aligned and accounts support 2FA.
For quicker resolutions, have your ID and recent transaction details handy; that speeds
up AML‑compliant checks and gets withdrawals approved faster.
Skycrown offers 24/7 live chat for quick fixes and email
for longer threads such as verification reviews or payment follow‑ups.
The Live Casino game category in the Skycrown Casino lobby portrays somewhat more than 60 games.
Go through the following steps, and you’ll be able to play pokies at Skycrown Casino for fun. When our team was
conducting this review, there were five active tournaments on the website.
References:
https://blackcoin.co/no-deposit-free-spins-bonuses-2025/
us poker sites that accept paypal
References:
https://workfind.in/profile/eldenbejah5097
casino sites that accept paypal
References:
https://www.revedesign.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=319321
casino con paypal
References:
https://www.to-hub.shop/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=194
online casinos that accept paypal
References:
https://jobs.cntertech.com/employer/us-online-casinos-that-accept-paypal-2025/
casinos online paypal
References:
https://innovationsgroup.in/employer/best-online-casinos-in-australia-2025-instant-withdrawal-casinos/
casino online paypal
References:
http://infuline.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=682672
online casinos that accept paypal
References:
https://jobsbotswana.info/companies/best-online-casinos-australia-top-aussie-gambling-sites-2025/
casino online uk paypal
References:
https://www.jobv3.com/companies/best-online-casino-payouts-in-2025-highest-paying-sites-98/
us online casinos that accept paypal
References:
https://rentry.co/78788-die-besten-online-casino-mit-paypal-im-test-2025
online casinos paypal
References:
https://www.seniorjobbank.ca/companies/best-paypal-casinos-uk-2025-fast-secure-trusted-sites/
Tischspiele gehören zu den klassischen Angeboten in Online Casinos und sind sehr beliebt bei Spielern. Die Verfügbarkeit von Live Casino Spielen nimmt in Online Casinos ständig zu, was den Spielern eine Vielzahl von Optionen bietet. Live Casino Spiele bieten ein authentisches Erlebnis, da die Spiele in Echtzeit von echten Dealern geleitet werden. Alternativen für Spieler, die keine Slots mit progressiven Jackpots finden, sind zahlreiche andere spannende Slot-Optionen. Beliebte Spielautomaten in deutschen Online Casinos sind unter anderem Book of Ra und Eye of Horus. Deutsche Online Casinos bieten eine Vielzahl von Slot-Spielen mit unterschiedlichen Themen und Stilen an.
Für Spieler in deutschen Online Casinos sind schnelle Auszahlungen genauso wichtig wie Einzahlungen. Dank der neuen Glücksspielregulierung steht deutschen Spielern eine Auswahl an sicheren und zuverlässigen Zahlungsmitteln zur Verfügung. Aus diesem Grund finden Sie auf unseren Seiten auch nur deutsche Online Casinos mit Whitelist Eintrag. Wir bieten Ihnen auf unseren Seiten auch Spielanleitungen, Strategien, sowie Tipps und Tricks für die beliebtesten Online Casino Games. Unsere Experten haben nicht nur die besten deutschen Online Casinos im Vergleich. Testen Sie die Top Games hier bei uns und finden Sie alle Play’n Go Casinos.
References:
https://onlinegamblingcasino.s3.amazonaws.com/007%20casino%20royale%20cast.html
References:
Anadrol and anavar cycle before and after
References:
https://gpsites.win/story.php?title=candy-casino-review-350-up-to-500-welcome-bonus
References:
Anavar only before and after pics
References:
https://morphomics.science/wiki/Anavar_Before_and_After_Results
References:
Grand casino tunica ms
References:
https://v.gd/IzcvOl
References:
Slots of vegas no deposit
References:
https://numberfields.asu.edu/NumberFields/show_user.php?userid=6464513
performance enhancing drugs in the military
References:
https://onlinevetjobs.com/author/fightsky6/
side effects of steroid use in males
References:
https://termansen-bennetsen.blogbright.net/steroids-fast-facts
References:
Anavar cutting cycle before and after
References:
https://wifidb.science/wiki/Perch_Anavar_sta_crescendo_con_successo_tra_uomini_e_donne
zyzz steroids
References:
https://bookmark4you.win/story.php?title=appetitzuegler-lexikon-der-neurowissenschaft
side effects of steroids in women
References:
https://botdb.win/wiki/Comprar_Prime_testosterona_en_cpsulas_para_hombre_60_cpsulas_Weider
References:
Anavar cycle results before and after
References:
https://to-portal.com/sandrapump8
pills to get ripped and big
References:
https://md.inno3.fr/s/zApCK1IOt
%random_anchor_text%
References:
https://hikvisiondb.webcam/wiki/Clenbuterol_Wirkung_Anwendungsgebiete_Nebenwirkungen_Krank_de