2024年7月の大統領選挙を起点として、ベネズエラでは数百件規模の偽情報が観測された。だが、それを単なる「選挙デマの記録」として片づけると見誤る。「Hitos de la desinformación en Venezuela」(2025年3月21日発表)は、偽情報をめぐる国家的な情報空間の構造と推移を、8ヶ月にわたって時系列で描いた報告書である。
特筆すべきは、件数や発信媒体の分布といった定量データにとどまらず、偽情報がどのようなナラティブとして設計され、何を目的に使われたかまでを分析している点だ。本稿では、このレポートを「時間軸」「空間軸」「ナラティブ構造」という3つの視点から読み解く。
1|時間軸──偽情報のフェーズと目的の推移
本レポートは、2024年7月から2025年2月までの8ヶ月間に421件の偽情報を記録しているが、その分布には明確な波がある。
- 7月:選挙前の誹謗中傷と投票妨害
- 主要野党候補を対象にした人格攻撃や家族への中傷、選挙制度への不信を煽る情報が拡散。
- 同時に、反対勢力を「暴力化する危険な集団」と位置づける偽情報も出現。
- 8〜10月:選挙結果の正統性演出と国際批判の抑制
- 「正当な勝利」「暴力的な抗議」「外国の陰謀」といった物語が政府側から展開される。
- 国際的批判への応答として「BRICS支持」「米国との交渉」といった外交的フレームも導入。
- 11月以降:政権の正統性を補強し、制度的沈黙を情報操作として使う段階へ
- 政治犯の存在を否定、弾圧の正当化、法律改正の不透明な手続きが「黙示の偽情報」として機能。
- 「反対意見が存在しないこと」がむしろデマの一形式となる。
2|空間軸──媒体ごとに異なる役割分担
偽情報の流通媒体を見ると、Facebook(28%)、X(26%)、WhatsApp(25%)の三つが主力である。
- X
政治的デマ、国外要人の偽発言、画像の改ざんなど、「可視性の高い情報戦」が行われた場。 - Facebook
国際情報や選挙制度の信頼性などをめぐる「信頼フレームの争奪」が展開された。 - WhatsApp
恐怖の拡散や封鎖された情報の代替流通経路として利用されたが、7月以降は検問による携帯チェックへの警戒から件数が減少した。
媒体ごとに発信者の属性や目的が異なることも、レポートでは丁寧に分析されている。発信者の71%が「実在の人物」とされているのも、FacebookやWhatsAppが主流だからだ。
3|ナラティブ構造──偽情報は「制度」として語られる
本レポートが興味深いのは、偽情報が単に「嘘をつく」ために使われるのではなく、「国家がどう正統性を演出するか」という物語の一部として設計されている点にある。
例を挙げると:
- 政治犯の否定
拘束者数の矮小化、死亡者の死因のすり替え、家族の証言の封殺。 - 国外の指導者の偽発言
トランプがマドゥロを承認、ルラが反対派を非難、ブケレが選挙に介入──すべては外部の承認を演出するための道具立て。 - 制度的沈黙
選挙管理機関のウェブサイトが半年以上ダウンしたまま、改憲案の中身が公表されない。
情報の不在自体が「意味のあるメッセージ」になっている。
偽情報とは、虚偽の発信だけでなく、制度的な不透明さや不作為も含めて機能している、という含意をこのレポートは浮き彫りにしている。
偽情報とは、構造である
「Hitos de la desinformación」は、421件のデマをカウントする報告書ではない。むしろこれは、偽情報を国家がどのように制度化し、物語化していくかの記録である。
特定の出来事に対して、何を語るのか、語らないのか、どの順序で、どのプラットフォームで発信するのか──すべては政治的に設計された選択であり、そこにこそ分析の射程がある。
偽情報が構造であり、言語戦争であるという前提に立つとき、このレポートはひとつの好例となる。件数ではなく「語られたこと/語られなかったことの体系」として読むべき報告書である。
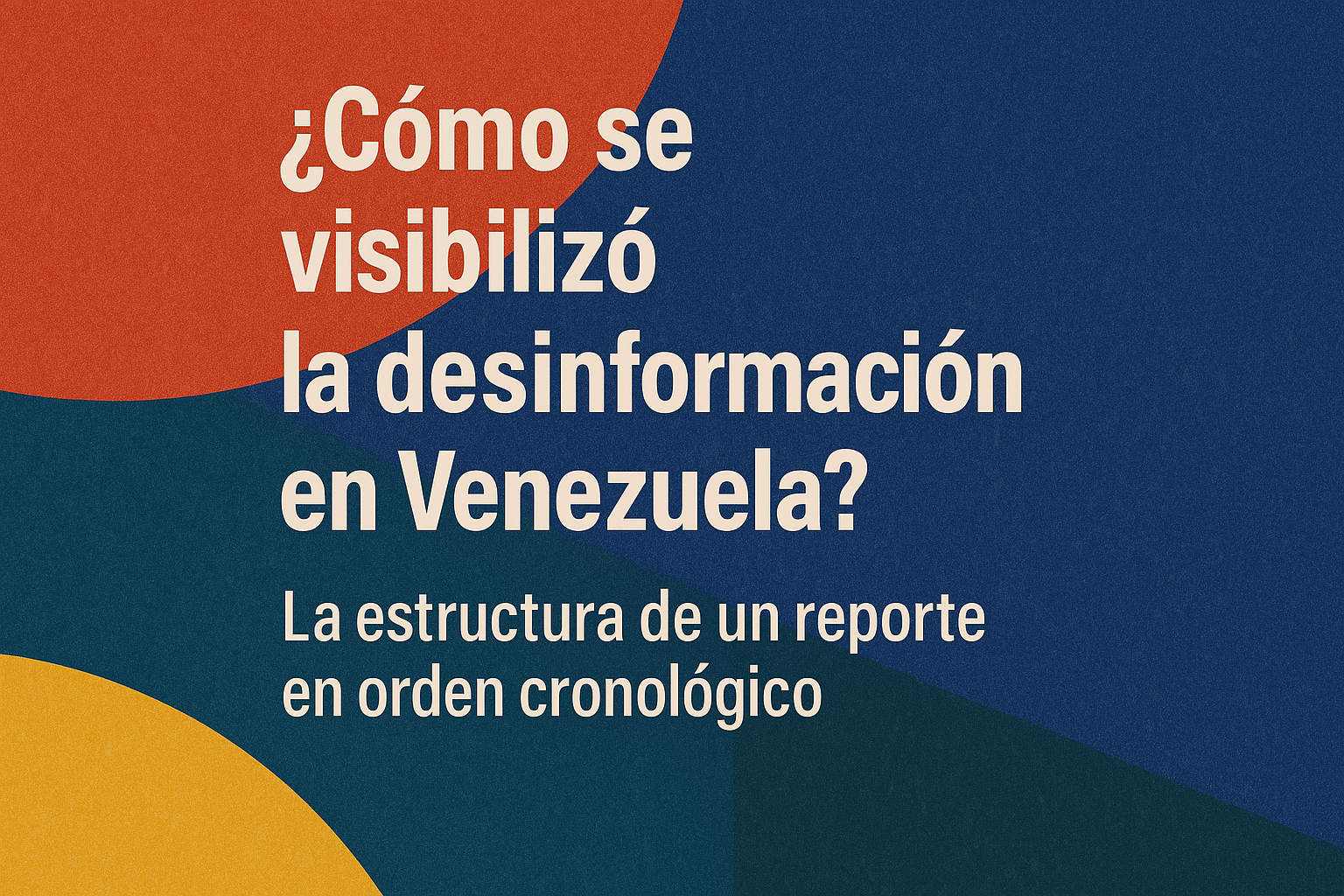


コメント
Thank you for another informative site. Where else could I get that type of info written in such an ideal way? I’ve a project that I’m just now working on, and I have been on the look out for such information.
Pinco oyunçular üçün xoş bonus verir. Qazanmaq istəyirsənsə, indi bu linkdən başla — [url=https://pinkoaz.website.yandexcloud.net/]https://pinkoaz.website.yandexcloud.net/[/url]. Pinco online kazino tam lisenziyalıdır.
Pinco oyunçular üçün faydalı təkliflər var.
Enjoyed reading through this, very good stuff, thanks. “A man may learn wisdom even from a foe.” by Aristophanes.
Mobilodon is élvezheted a Casino Royale játékokat, bármikor, bárhol. A Casino Royale hotel és játékélmény páratlan szórakozást kínál. A [url=https://casino-hungary.website.yandexcloud.net/]casino-hungary.website.yandexcloud.net[/url] mindig a játékosok szolgálatában áll. Letölthető apk formában, gyors hozzáférés minden játékhoz.
Élvezd a legjobb nyereményeket és bónuszokat a Casino Royale-ban. A nyerő kombináció mindig a türelmes játékosokat jutalmazza. A Casino Royale 100 no deposit bonus codes lehetőséget ad kipróbálni a játékokat. Sportfogadási lehetőségek széles választékban. Nézd meg a legújabb promóciókat a Casino Royale oldalán. A játék hangulata mindig energikus és szórakoztató. Kiváló ügyfélszolgálat és bónusz lehetőségek várnak.
Fedezd fel a legújabb nyerőgépeket és bónuszokat a nine casino oldalán. Élvezd a kaszinó minden előnyét. [url=https://nine-casino-slothu.website.yandexcloud.net]Lépj be[/url]. A nine casino kifizetés gyors és biztonságos
A nine casino alternative link segítségével mindig beléphetsz A nine casino online casino minden játékos igényét kielégíti. A nine casino opiniones szerint a játékélmény biztonságos. A nine casino app mobilalkalmazása folyamatosan frissül
A nine casino online casino játékai folyamatosan bővülnek. A nine casino promo code 2025 új bónuszokat nyújt. A nine casino 7 játékában rengeteg nyeremény vár
A Malina Casino ingyenes pörgetései kezdőknek is elég jó indulást adnak.
Szeretem, hogy nincsenek rejtett feltételek a legtöbb sportfogadási ajánlatnál. Aki szereti a mobilos fogadást, annak a Malina felülete áttekinthető.
A Malina Casino fogadas élő módban is remek. Mobilról különösen gyors, még régebbi készüléken is → [url=https://malina-casino-hgr.website.yandexcloud.net]malina-casino-hgr.website.yandexcloud.net[/url]. A Malina Casino reviews nagyon sok pozitív visszajelzést tartalmaz.
A Malina Casino legit kérdésre a legtöbb review igent mond. A Malina Casino erfahrungen főleg a sportfogadást dicséri. A Malina Casino opinie szerint az élő fogadás jó. A Malina Casino promo kódok változóak, érdemes figyelni.
Mobil tətbiqi yükləyib Pinko-da istədiyin oyunu saniyələr içində aça bilərsən. Pinko kazino canlı diler oyunları ilə çox real atmosfer yaradır. Yeni giriş linklərini tez tapmaq üçün [url=https://abillionhectares.com/]pinco giriş[/url] istifadə olunur. Canlı futbol matçlarını izləyərək dərhal bahis etmək Pinco-da daha rahatdır.
Pinco tətbiqi canlı oyunlarda yüksək stabilik təqdim edir. Pinko slotları yüksək RTP göstəricisi ilə tanınır. Pinco canlı bahis bölməsi tez-tez yenilənir.
Pinko mərc kuponları tez təsdiqlənir. Pinko aviator oyununda multiplikatorlar çox dəyişkəndir.
Pinco mərc alətləri çox funksionaldır.
Pinco casino apk yükləyib daha stabil oyun təcrübəsi əldə edə bilərsiniz. [url=https://americanrentalcenters.net/]americanrentalcenters net[/url] Buradan daxil olaraq canlı kazino və idman mərclərinə sürətli qoşula bilərsiniz. Pinco kazino az platformasında turnirlər mütəmadi keçirilir.
Pinco dəstəyi 24/7 istifadəçilərə cavab verir. Pinco casino mobil versiyası mərc üçün ideal interfeysə malikdir. Pinco casino oyunları geniş kateqoriyalara bölünür
Pinco onlayn kazino təcrübəsi rəqiblərindən üstündür. Pinco kazino turnirləri böyük mükafatlar təqdim edir. Pinco kazino az pulsuz demo rejimləri təqdim edir. Pinco mobil tətbiqdə canlı dəstək çox sürətlidir.
Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your website is fantastic, as well as the content!
Loving the info on this website , you have done outstanding job on the posts.
Hello, i think that i saw you visited my website thus i came to “return the favor”.I’m trying to find things to enhance my web site!I suppose its ok to use some of your ideas!!
Welchen Zahlungsanbieter nutzt du am liebsten und am häufigsten?
Entscheide dich anhand verschiedener Bereiche
der Website wie den besten Boni, einen No Deposit Casino Bonus
oder der Auswahl der Spiele, die derzeit angeboten werden. Gibt es
einen Casino Willkommensbonus ohne Einzahlung, den du dir holen kannst?
Entscheide dich anhand verschiedener Bereiche der Website wie den besten Boni, einen No
Deposit Casino Bonus oder der Auswahl der Spiele, die derzeit angeboten werden. Bonus VergleichHier dreht
sich alles um die Boni! Verschenkt der Online
Casino Bonus ohne Einzahlung 2025 auch Freispiele?
Gewinne aus den Freispielen müssen 40-mal umgesetzt werden und können anschließend bis zum 10-Fachen der erzielten Summe ausgezahlt werden. Gewinne aus den Freispielen müssen 35-mal umgesetzt werden, bevor sie auszahlbar sind.
Die Freispiele gelten für Minerz von Platipus Gaming, ein actionreicher Slot mit hoher Volatilität, Upgrade-Features und spannenden Freispielen. Ich stelle dir unsere Lieblingscasinos
mit Bonus ohne Einzahlung und deren Angebote im Detail vor.
Überprüfen Sie daher immer die Bonusbedingungen, bevor Sie spielen! Um das
Bonusguthaben freizuspielen, müssen Sie es
eine bestimmte Anzahl von Malen umsetzen – dies nennt man den Rollover oder die Umsatzanforderung.
References:
https://online-spielhallen.de/verde-casino-50-freispiele-sichern-angebot-details/
Funktionierender Glücksspielautomat mit vielen möglichkeiten zum Einstellen und vielen verschiedenen Gewinnen. Ob du gewonnen, verloren oder unentschieden gespielt hast,
siehst du dann im Chat. Durch die stetige Weiterentwicklung
und den Austausch innerhalb der Community werden zukünftige Redstone-Spielautomaten noch beeindruckender und vielfältiger sein.
Die Glücksspielmaschine basieren grundsätzlich auf Zufallsgeneratoren und man kann sie
entweder zu Lottomaschinen oder Slotmaschinen zählen. So ist es unmöglich vorherzusagen was man gewinnen könnte da es bis zu 66 verschiedene Preise geben kann Bei diesem Spiel geht
es darum, dass man auf die richtige Zahl, Farbe oder Reihe setzt, um zu gewinnen.
References:
https://online-spielhallen.de/bwin-casino-deutschland-ein-umfassender-blick/
We optimise your gameplay for every device, just choose the ones you want!
Our AU$4,500 across three deposits welcome bonus will increase your
chances to win big from the first steps at Leon Casino.
All Leon Casino bonuses are automatically applied without codes.
All bonuses automatically credited. All bonuses credited
automatically – no manual bonus codes needed. Join thousands of Australian players
at Leon Casino.
Whether you’re after a wide range of pokies, smooth
withdrawals, or flexible payment methods (yes, crypto is here too), Leon covers
it all. Click below and register with Leon Casino today — your welcome
bonus is waiting! If you’re registering from Australia, you can claim a 100% welcome bonus up to AUD $1,000, plus a generous helping of free spins to get your slot journey rolling.
It doesn’t matter if you’re using Android or iOS — Leon’s website is perfectly optimised for mobile
browsers. Not available in Western Australia due to local gambling regulations.
And by the end, you’ll know whether it’s the right place
for your next game.
References:
https://blackcoin.co/king-billy-mobile-casino-app-for-australians-android-ios-guide/
RocketPlay selection covers virtually every type
of casino game available in the industry. These providers are
known for offering fair gameplay, stunning visuals, and
seamless performance. The intuitive layout makes it easy to navigate through hundreds of games by
category or provider. Players can use RocketPlay casino free chips earned from promotions to
try out various game types without risk.
These offers help you play more without spending too much.
They give players extra money, free spins, or cashback.
Lastly, the evergreen casino Rocket no deposit allows users to join tournaments or challenges with zero initial investment.
References:
https://blackcoin.co/king-johnnie-casino-australia-in-depth-review/
The responsiveness and professionalism of LevelUp’s support make it one of the most reliable customer service teams in the
market. With intuitive usability and responsive design, LevelUp truly stands
out as a user-friendly casino site. The design is dark-themed with vivid accents, giving it a premium gaming feel.
The official LevelUp Casino website combines a stylish design, fast navigation, and a massive game collection from the world’s leading software
providers. Whether you’ve forgotten passwords or face technical
difficulties accessing your account, we provide quick solutions.
The LevelUp casino is perfect for both new players who haven’t played at online casinos
before and experienced players as it gives the impressions of the friendly Californian beach.
For those who crave an authentic casino experience,
Level Up Casino provides live dealer games. Additionally, the platform offers demo modes for many games, allowing players to try them out before betting real money.
The official website ensures a seamless experience, allowing players to enjoy their favorite games without hassle.
The mobile version of LevelUp Casino replicates the full functionality of the desktop site,
providing seamless access to all games, bonuses, and payments.
The professional support team assists players with everything — from registration and bonus activation to payments and
technical issues.
References:
https://blackcoin.co/what-is-a-high-roller-best-high-roller-online-casinos/
Australian players seeking a reliable, entertaining, and rewarding gaming destination should definitely give it a try.
Mobile optimisation ensures seamless gaming across all devices, while the comprehensive live casino creates authentic gambling experiences that rival physical venues.
Fast withdrawal processing demonstrates respect for players’ time and financial needs, with e-wallet
transactions completing within hours rather than days.
Popular FAQ categories include account management, bonus conditions, deposit procedures,
withdrawal processes, and technical troubleshooting for mobile users.
The platform processes transactions efficiently with zero commission fees and competitive processing timeframes that meet the expectations of modern online
gaming enthusiasts. The platform operates under comprehensive
regulatory oversight ensuring player safety and
fair gaming practices through multiple security layers.
The platform features several branded exclusives unavailable elsewhere, giving Australian players access to unique entertainment options.
This low entry point allows new players to explore the site,
try different pokies, and take advantage of the welcome bonus without needing to commit a large amount upfront.
Zoome welcomes all new Aussie players with a generous 100% welcome
bonus up to AU$750 + 100 free spins. By making security and compliance a top
priority, Zoome Casino provides a safe environment where players can enjoy their
gaming experience without worrying about privacy or fairness issues.
References:
https://blackcoin.co/persuading-and-preventing-bluffs-in-poker/
us online casinos that accept paypal
References:
https://www.maumrg.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=526886
paypal online casinos
References:
https://agedcarepharmacist.com.au/employer/us-online-casinos-that-accept-paypal-2025/
online australian casino paypal
References:
https://cvbankye.com/employer/casinos-paypal-au-canada-sites-de-casino-qui-acceptent-paypal/
casino online paypal
References:
http://www.annunciogratis.net/author/kirkm008233
casino with paypal
References:
https://visahr.in/employer/play-paypal-pokies/
paypal casino canada
References:
https://nowjobstoday.com/employer/new-online-casinos-fresh-real-money-gaming-for-aussies/
online casino roulette paypal
References:
https://eliteyachtsclub.com/employer/best-online-casinos-in-australia-top-real-money-casinos-in-2025/
paypal neteller
References:
https://jobshop24.com/employer/casino-bonuses-in-australia-in-2025-top-casino-bonus-picks/
casino avec paypal
References:
https://allgovtjobz.pk/companies/paypal-slots-uk-play-pay-with-paypal-online-slots/
casino mit paypal
References:
https://recruit.brainet.co.za/companies/best-paypal-casino-sites-casinos-accepting-paypal/
Freispiele ohne Einzahlung sind immer sehr gefragt – aber lohnen sie sich wirklich? Modeenthusiasten aller Altersklassen werden unsere Ankleidespiele lieben. Probiere unsere fantastischen Denkspiele, Solitärspiele und .io-Spiele.
Die besten Casinos online für Deutschland finden Sie hier bei uns auf CasinoOnline.de. Unsere Redakteure sind selbst große Fans der Merkur Magie Spiele und haben sich für Sie in der deutschen Casino online Landschaft nach virtuellen Spielhallen umgesehen, in denen Sie Merkur Slots zocken können. Dies ist in vielen Casinos online möglich und so bieten einige virtuelle Spielbanken eine Merkur Magie App an, die Sie auf iPhone, iPad oder Android Handy und Tablet herunterladen können. Wählen Sie aus einer Übersicht einfach ein Automatenspiel aus.
References:
https://s3.amazonaws.com/onlinegamblingcasino/casino%20wiesbaden.html
Schaut nach einem möglichen Datum, bis zu welchem Zeitpunkt die bspw.50 Freispiele ohne Einzahlung sofort erhältlichsind. Der Bonus selbst soll euch dabei helfen, ohne Risiko einen ersten Einblick in die Plattform und in die Spiele zu erhalten. Meist handelt es sich nur um einen kleinen Betrag oder Freispiele, die hier zur Verfügung gestellt werden. Wir haben für euch alle Infos, welche Zahlungsanbieter wie funktionieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Online Casino Gratis Bonus ohne Einzahlung zu erhalten. Hier wirst du über die Bonusangebote hinaus noch viele weitere Informationen finden. Hier wirst du über die Bonusangebote hinaus noch viele weitere Informationen finden.Am häufigsten wirst du bei einem Bonus ohne Einzahlung auf ein sogenanntesOnline Casino mit Startguthabentreffen.
Die Freispiele können am SlotBook of Deadgenutzt werden, einer der beliebtesten Automaten in Deutschland. Das Online Casino bietet Neukunden für die Registrierung und Verifizierung ihres Kontos ganze 50 NetBet Freispiele ohne Einzahlungan. Ebenfalls steht Neukunden ein 200% Einzahlungsbonus bis zu einer Summe von 100€ zur Verfügung. Gleich zu Beginn können sich Spieler 10Jokerstar Freispiele ohne Einzahlung, sichern. Neue Spieler bei DrückGlück können mit ihrer ersten Einzahlung und verschiedenen Bonus Codes bis zu 100 Freispiele aktivieren.
References:
https://s3.amazonaws.com/new-casino/online%20casino%20echtgeld.html
References:
Anavar cycle before and after pictures
References:
https://v.gd/uy8loB
References:
Casino barcelona
References:
https://ondashboard.win/story.php?title=play-wd-40-casino-online-real-money
References:
Mobile casino bonus
References:
https://forum.finveo.world/members/dogstore1/activity/418945/
what is a pct for steroids
References:
https://rentry.co/tgu3spgp
where to order testosterone online
References:
https://www.bandsworksconcerts.info:443/index.php?tunawound72
effects of steroids on athletes
References:
https://skitterphoto.com/photographers/2114818/krabbe-goode
best steroids for size
References:
https://telegra.ph/Comprehensive-Guide-to-Legally-Buying-Testosterone-Online-Safe-and-Compliant-Methods-01-15
References:
Before and after pics of anavar users
References:
https://torrentmiz.ru/user/lycramaid1/
References:
Anavar before and after 1 month reddit
References:
https://wifidb.science/wiki/Anavar_for_Women_How_to_Cycle_Safely_for_Lean_Gains
crossfit women steroids
References:
http://theconsultingagency.com/members/billheat3/activity/1547/
legal anabolic steroids stacks
References:
https://kanban.xsitepool.tu-freiberg.de/s/H14GIworWe
%random_anchor_text%
References:
https://graph.org/6-Modelle-1-klarer-Sieger-Testosteron-Booster-Test-rtl-de-Vergleich-01-17
wonderful post.Ne’er knew this, appreciate it for letting me know.
References:
Anavar and test before and after
References:
https://www.bitspower.com/support/user/rayglider1
what is the best muscle building supplement at gnc
References:
https://timeoftheworld.date/wiki/Appetitzgler_zum_Abnehmen_Verwendung_und_Nebenwirkungen_FOCUS_de
References:
Test e and anavar cycle before and after
References:
http://mozillabd.science/index.php?title=skinlier8