2025年6月24日、ニューヨーク市の民主党予備選でZohran Mamdaniが勝利した。この一報が流れてから数時間以内に、SNS上では「ニューヨークは堕ちた」「911の犯人が市役所に入る」といった文言と共に、彼を攻撃するポストが爆発的に拡散した。
彼がムスリムであること、民主社会主義を掲げていること、移民出身であること、そしてインド・ムスリムの出自を持つこと。これらの属性は、デジタル上での「敵」の構成要素として見事に組み合わされ、短期間で複数のナラティブを束ねる強固なヘイトフレームワークが形成された。
この過程を詳細に追ったのが、Center for the Study of Organized Hate(CSOH)による報告書「Digital Hate, Islamophobia, Zohran Mamdani, and NYC’s Mayoral Primary」である。本稿では、このレポートを紹介しつつ、現代的なデジタルヘイトがどのようにして宗教、イデオロギー、国籍、トランスナショナリズムといった複数の軸を接合し、拡散力を高めていくのかを検討する。
Mamdaniをめぐる多重の敵意:4つのフレーム
CSOHは、選挙期間中にSNS上で拡散された6,669件の投稿を収集し、そのうち最も高いエンゲージメントを記録した1,933件を精査した。分析の結果、Mamdaniに向けられたヘイトは以下の4つの軸に沿って展開されていたことが明らかになった。
1. 宗教フレーム:イスラモフォビアの再生産
全体の39.4%の投稿が、Mamdaniがムスリムであること自体を問題視していた。そこでは「シャリア法の導入」「テロリストの共犯者」「911を喜ぶ者」といった古典的な反イスラム言説が繰り返され、Mamdaniの信仰そのものがアメリカの市民的価値と両立しないと断じられていた。
たとえば、「24年前、ムスリムが9.11で2753人を殺した。今、そのムスリム社会主義者がニューヨークを牛耳ろうとしている」という投稿は、彼の勝利を国家的危機として演出していた。
2. イデオロギーフレーム:共産主義レッテルとマッカーシズム的言語
Mamdaniの民主社会主義的立場を、旧来の「共産主義」や「社会主義者による乗っ取り」として描く投稿は30.2%に及んだ。冷戦期のマッカーシズムを想起させる表現——「パンの配給列(bread lines)」「共産党員が市庁舎に潜入」など——が再登場し、信条による市民資格の否定がなされている。
興味深いのは、この政治的レッテルと宗教攻撃が極めて高頻度で融合されていた点である。宗教攻撃を含む投稿の51.2%は、同時にイデオロギー攻撃を含んでいた。言い換えれば、「イスラム教徒だから危険」という攻撃と、「社会主義者だから危険」という攻撃は、相互に補強しあう構造となっていた。
「Islamist socialism has taken hold of New York City(イスラム社会主義がニューヨークを掌握した)」というフレーズは、その象徴的表現である。
3. ナティヴィズム:排除と国籍剥奪の言説
1,933件のうち14.3%は、Mamdaniの移民出自を理由に彼を「アメリカ人ではない」「帰国させるべき」などと主張していた。「帰れ」「市民権を剥奪せよ」「こいつは密入国者だ」といった投稿には、民族的出自への生理的嫌悪が露骨に表出していた。
この言説は、宗教や政治の異質性を超えて「そもそもこの国にいるべきでない存在」としてMamdaniを位置づけ、選挙での正当な勝利すら否定するものである。
4. トランスナショナルな構図:ヒンドゥー・ナショナリズムの参戦
Mamdaniに対する攻撃の中には、インドおよびディアスポラのヒンドゥー・ナショナリスト系アカウントから発信された「反ヒンドゥー」「ヒンドゥー憎悪の扇動者」といった投稿が含まれていた。
彼がモディ政権のイスラム系市民に対する弾圧を批判したことや、アヨーディヤーでのラーム寺院建設に対する抗議行動に関与したことが槍玉にあげられていた。インド国内の宗教的対立が、そのままアメリカのローカル選挙に持ち込まれていた。
このようにして、Mamdaniは「ムスリムで、社会主義者で、移民で、反ヒンドゥー」であるという多重のラベリングを受け、そのどれかに反応する誰かの怒りを確実に引き出す構造が形成されていた。
フラッシュ型動員とXの支配的役割
分析によれば、こうしたヘイト投稿は選挙当日の6月24日から翌日にかけて爆発的に増加した。24日は899件、25日は2,173件と、わずか48時間で全体の58%が投稿されている。これは、選挙という「話題性」をトリガーとした一時的かつ集中的なデジタル動員であり、危機言説と選挙イベントが結びついた瞬間にヘイトが拡散する典型例と言える。
また、全投稿の64.6%がX(旧Twitter)から発信されており、その他のプラットフォームは圧倒的に少数派である。GETTR、Telegram、Facebook、YouTubeなどは一定数の投稿を持つものの、エンゲージメントの主軸はXに集中していた。
このことは、現代のデジタルヘイトが「マルチプラットフォーム」ではなく、「一極集中型」に展開されていることを示唆する。特に、Xのアルゴリズムや可視性メカニズムが、こうしたヘイト言説にとって温床になっている。
「市民資格」の再定義としてのヘイト
この報告書の示す構造が特異なのは、それが単なるヘイトスピーチの羅列ではなく、「だれが市民でありうるか」「どんな属性がアメリカの公的空間にふさわしいか」といった、根本的な市民資格の再定義をめぐるナラティブ戦争である点だ。
- ムスリムであることは疑われるべき
- 社会主義者は忠誠心がない
- 移民は居場所を間違えている
- インド系でもヒンドゥーに反すれば「反文明」的存在
このように、個人攻撃に見えるナラティブは、実のところ「誰がアメリカを構成するのか」という文化的規範をめぐる戦場そのものである。
結語:多軸的ヘイトと融合型ナラティブの時代
宗教、政治思想、民族、国籍、国際情勢——。Mamdaniのケースは、これら複数の軸を「融合」させることで、単一のトリガーでは得られない拡散力と持続性を生み出している。
イスラモフォビアや反共主義の古典的フレームに、ポスト9.11以降のセキュリティ・ナラティブ、そして南アジアの宗派的分断までを重ねることで、極めて複雑かつ強靱な構造ができあがっている。
この構造は、Mamdaniに限らず、あらゆる選挙、あらゆる「周縁化されうる属性」を持つ候補者に対して再利用可能である。だからこそ、このケースはローカルな事件ではなく、次の選挙、次の標的を予測するための警鐘として読むべきものである。


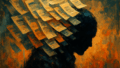
コメント
Durchsuchen Sie alle von Rolletto Casino angebotenen Boni, einschließlich jener Bonusangebote,
bei denen Sie keine Einzahlung vornehmen müssen,
und durchstöbern Sie auch alle Willkommensboni, die Sie bei Ihrer ersten Einzahlung erhalten werden. Sie können davon ausgehen,
dass Sie in diesem Casino gut und anständig behandelt und insgesamt eine angenehme Spielerfahrung erleben werden, aber nur dann,
wenn Sie sich dafür entscheiden dort auch wirklich zu spielen. Sie können Spielautomaten, Tischspiele, Live-Dealer-Spiele, Live-Game-Shows und Mini-Games spielen und erhalten Zugang zu
Sportsobbok mit einer großen Auswahl an realen, virtuellen und elektronischen Sportereignissen.
Rolletto Casino hat ein zurückgezogenes VIP-Programm für die treuesten und
aktivsten Casinospieler. Das Casino unterstützt die deutsche Sprache und nationale Sportwettbewerbe; Deutsche Spieler können auch mehrere Live-Spiele in ihrer Muttersprache spielen.
Erstellen Sie noch heute ein Konto und spielen Sie Rolletto-Casinospiele auf
Ihre Weise. Das mehrstufige Treueprogramm belohnt nicht nur Vielspieler, sondern steht auch Gelegenheitsspielern offen. Mit der Rolletto Casino App – als
mobile optimierte Web-App – spielen Sie bequem auf jedem Smartphone und Tablet.
Rolletto Casino überzeugt mit einer riesigen Auswahl
an Slotmaschinen, Tischspielen, Live-Dealer-Games und modernen Instant Win Spielen.
Die große Spielauswahl sorgt dafür, dass jeder Spieler das Passende findet, und macht das Casino
zu einer vielseitigen und unterhaltsamen Plattform.
Rolletto Casino Erfahrungen zeigen, dass dieses Casino einige besondere Vorteile bietet,
die es für deutsche Spieler besonders attraktiv machen. Der eSports-Willkommensbonus bringt 100% bis zu 500 €/$,
während Slot-Spieler einen 10% Einzahlungsbonus auf Einzahlungen über
10 € erhalten.
References:
https://online-spielhallen.de/leon-casino-auszahlung-der-umfassende-leitfaden-fur-reibungslose-gewinnauszahlungen/
AUSTRAC will determine the scope of the audits for both operations, with
casinos to foot the bill. Auditors will assess whether the casinos
are appropriately monitoring customers, doing risk assessments and ensuring enough oversight
of anti-financial crime programs. Mr Thomas said all businesses with gaming machines needed
to take the risk of money laundering seriously.
“AUSTRAC is serious about driving illicit money out of the gambling industry in Australia and making sure businesses that facilitate gambling have strong money-laundering controls,” he said.
Australians lead the world when it comes to gambling.
For example, spending $50 on table games might earn a guest a
complimentary cocktail, while a $100 expenditure on pokies could net a $25 dining credit at one
of the casino’s fine eateries. The VIP gaming areas at
ville Casino Townsville are crafted to cater to high rollers seeking a more
refined and exclusive gambling experience.
The selection of table games at ville resort Casino Townsville is extensive,
and designed to satisfy enthusiasts of timeless casino entertainment.
References:
https://blackcoin.co/high-limit-slots-play-25-100-500-slot-machines-online/
Deposits are typically processed instantly, allowing
players to jump into their favourite casino games without delay.
For those who enjoy a bit more strategy, Lucky Green Casino’s
collection of table games and live casino experiences adds a touch of sophistication. The casino regularly introduces themed events tied to holidays or
new game releases, giving players a chance to win free
spins, bonus credits, or even physical prizes.
Regular players at Lucky Green Casino also enjoy ongoing promotions such
as weekly reload bonuses, cashback offers, and seasonal tournaments.
The casino displays third-party testing and security seals, and providers’ RNG audits are part of the fairness assurances.
Once verified, your path to fast withdrawals is smoother
— lucky green processes payouts quickly when documentation is complete.
Benefits include personal account managers, dedicated promotions and accelerated support.
Streaming quality and dealer professionalism are key to
a satisfying live experience. Lucky Green lists progressive
titles from large networks; these games collect a
small portion of each wager to fuel the jackpot pool.
The site encourages healthy play and will assist players who seek help.
Access live chat after lucky green casino login through the support icon at the
bottom right of any page. Lucky Green online casino supports
multiple banking options suitable for Australian players, with varying processing times and limits.
Demo mode at lucky green casino allows you to
test games without risking real money. You can access live casino games immediately
after completing lucky green online casino registration.
References:
https://blackcoin.co/sol-casino-in-depth-review/
paypal casino online
References:
http://www.career4.co.kr
online casino roulette paypal
References:
https://afrijobs.co.za/companies/best-paypal-online-casinos-real-money-deposits-withdrawals-al-com/
Removing a player’s checker from the board and sending it back to the beginning. Your opponent can not enter this space or remove your checkers when you achieve a prime. An open point is any point that is currently unoccupied, meaning that no players have placed a checker here.
Whether you’re a seasoned player or a newcomer, you’ll find endless opportunities for fun and competition. Join us at Backgammon 247, where the board is always set and the community is always ready to play. Plus, get exclusive access to special tournaments where you can compete against the best players and win exciting prizes. Jump into a game anytime, whether you’re looking for a quick match or a longer session. Our user-friendly interface makes it easy for beginners to get started, while offering advanced features for seasoned players. Register for an account or play as a guest to dive into your first game in no time.
The checker is the playing piece, and you will move around the game. The winner of Backgammon is the first person to remove all their checkers from the board. Checkers can be taken off when a checker reaches their home board (the upper or lower left-hand corner) without having any of the opponent’s checkers in the way. In a two-player game, one player moves clockwise, and the other anti-clockwise. If you’re a fan of backgammon, you may like Ludo King (aka Parchisi), the dice game of kings; or how about a good old game of Uno Online, the card game where you aim to be the first one with no cards.
References:
https://blackcoin.co/ufo9-casino-your-place-to-play-your-way/
online betting with paypal winnersbet
References:
https://www.allclanbattles.com/groups/play-21000-free-online-casino-games-no-download/
online casino with paypal
References:
https://realestate.kctech.com.np/profile/ellioty5349790
online casino mit paypal einzahlung
References:
https://empleoo.net/companies/professionals-cons-of-1-euro-put-on-line-casino-internet-sites/
online pokies australia paypal
References:
https://adremcareers.com/employer/us-online-casinos-that-accept-paypal-2025/
Viele Spieler fragen sich, ob deutsche Online Casinos legal sind. Wir haben alle gebündelt und eine Online Casino Deutschland FAQ erstellt mit den wichtigsten Antworten zu online Spielhallen. Viele Spieler kontaktieren uns mit unterschiedlichen Fragen rund um deutsche Online Casinos.
Unsere Experten checken jedes deutsche Online Casino gründlich und warnen dich vor unfairen Plattformen. Bevor wir dir das beste Casino empfehlen, muss es unser ausführliches Prüfungsverfahren durchlaufen. Besonders spannend finde ich die Möglichkeit, schon ab 1 € einzuzahlen und dafür trotzdem einen 100% Bonus bis 100 € plus 50 Freispiele zu erhalten. Bwin bietet aber auch Online Spielautomaten von 14 Anbietern wie Play’n GO oder Pragmatic Play an. Swift Spiele bietet beispielsweise circa 900 Slots an. Finde hier die besten Online Casinos Deutschlands.
References:
https://s3.amazonaws.com/new-casino/deutsche%20online%20casinos.html
References:
Best online translator
References:
https://bookmarkspot.win/story.php?title=winz-io-casino-review-and-bonuses-january-2026
References:
Blackjack simulator
References:
https://prpack.ru/user/deadfarm0/
References:
Android spinner style
References:
https://apunto.it/user/profile/549107
steroid deca
References:
https://securityholes.science/wiki/Supplements_for_Increased_Testosterone
tren steroid results
References:
https://gpsites.stream/story.php?title=8-best-vitamins-for-boosting-testosterone
References:
Clen anavar before and after women
References:
http://historydb.date/index.php?title=carefriday9
steroids pills names
References:
https://funsilo.date/wiki/Doping_in_Fitnessstudios_Spritzen_fr_den_perfekten_Krper_Sport_SZ_de
what is a anabolic steroid
References:
https://wikimapia.org/external_link?url=https://thehollywoodtrainerclub.com/static/pgs/?buy_clenbuterol_4.html
References:
Anavar before and after female reddit
References:
https://etuitionking.net/forums/users/bagtail33/
References:
Anavar before and after female pictures 4chan
References:
https://bookmarkspot.win/story.php?title=anavar-erfahrungen-zyklus-%EF%B8%8F-anavar-frauen-steroid-2026
References:
Woman before and after anavar
References:
https://undrtone.com/taxliver57
%random_anchor_text%
References:
http://hikvisiondb.webcam/index.php?title=oneilpovlsen8038
where to buy real steriods
References:
http://toxicdolls.com/members/startfield6/activity/143721/
References:
Harrah’s rincon casino
References:
http://stroyrem-master.ru/user/bengalmusic25/
References:
Atlantis casino reno
References:
https://graph.org/AUSTRALIA-TOP-ONLINE-POKIES-CASINO-ENTERTAINMENT-HUB-01-23
References:
Montreal casino
References:
https://pattern-wiki.win/wiki/Privacy_Policy
how to get steroids in the us
References:
https://rentry.co/abepvmm8
References:
Casino times
References:
https://justbookmark.win/story.php?title=candyspinz-casino-laut-spielen-gross-gewinnen-und-spass-haben
References:
Hollywood slots bangor maine
References:
https://lovebookmark.win/story.php?title=candy96-australia-18-no-deposit-fast-osko-payid-cashouts-vip-perks-2025-4
References:
Atlantic casino
References:
https://timeoftheworld.date/wiki/Paiement_par_Carte_Bancaire_par_Tlphone_Tout_Savoir_en_2026
References:
Best online games for mac
References:
https://lunchgrade24.werite.net/candy96-resultats
References:
Buffalo slot machine
References:
https://hikvisiondb.webcam/wiki/CandyLand
do legal steroids really work
References:
https://linkvault.win/story.php?title=trenbolone-avis-sur-le-steroide-effets-et-alternative-legale
%random_anchor_text%
References:
https://hack.allmende.io/s/gUOXWvo1X
winsol bodybuilding forum
References:
https://md.chaosdorf.de/s/iJILioMm3b
best steroids for muscle gain without side effects
References:
https://yogaasanas.science/wiki/Post_Cycle_Therapy_Guide_Restoring_Hormonal_Balance_After_Steroids
best steroid cycle to get ripped
References:
https://hikvisiondb.webcam/wiki/Les_moyens_de_paiement_proposs_sur_Oui_SNCF
anabolic steroid types
References:
https://bookmarking.win/story.php?title=acquistare-anavar-50-pharmaceutical-prezzo-66-00-euro-in-italia-dosaggi-e-decorso
References:
Sky vegas login
References:
https://opensourcebridge.science/wiki/Candy96_Casino_Australia_800_Welcome_Bonus_160_Free_Spins_Bundle
References:
Wendover casinos
References:
https://www.repecho.com/author/atomrange52/
References:
Betboo casino
References:
https://linkvault.win/story.php?title=customer-service-8
References:
Best online blackjack
References:
https://hangoutshelp.net/user/cymbalground3
References:
Blackjack basic strategy
References:
http://stroyrem-master.ru/user/versereward6/
References:
Atlantis casino bahamas
References:
https://googlino.com/members/celerydelete07/activity/585467/
women on steroids
References:
https://saveyoursite.date/story.php?title=quale-farmaco-fa-dimagrire-velocemente
what do anabolic steroids do when taken as medication
References:
https://termansen-bennetsen.blogbright.net/12-over-the-counter-appetite-suppressants-reviewed
best supplements to get cut and lean
References:
https://mmcon.sakura.ne.jp:443/mmwiki/index.php?cableson53
steroid first cycle
References:
https://escatter11.fullerton.edu/nfs/show_user.php?userid=9540854
References:
Used slot machines
References:
https://escatter11.fullerton.edu/nfs/show_user.php?userid=9547291
References:
Club casino
References:
https://web.ggather.com/treedust3/
References:
Hollywood casino md
References:
https://timeoftheworld.date/wiki/Beanspruchen_Sie_Ihren_Bonus_Gewinnen_Sie_noch_heute_gro
References:
Creek casino montgomery
References:
https://canvas.instructure.com/eportfolios/4205844/entries/14718266
References:
Valley view casino center seating chart
References:
https://bookmark4you.win/story.php?title=casino-cashback-aktuelle-angebote-fuer-schweizer-2026
References:
William hill android app download
References:
https://rentry.co/hcgmaici
References:
Caesars palace in las vegas
References:
https://schack-bryant-2.federatedjournals.com/admiralbet-bonus-code-90-10-ohne-bonus-code-im-januar-2026-1769896628
References:
Insurance blackjack
References:
https://egamersbox.com/cool/index.php?page=user&action=pub_profile&id=272763
References:
Harrah’s rincon casino
References:
http://jobboard.piasd.org/author/copperdill36/