2025年3月、シリアの沿岸部──ラタキア、タルトゥース、ホムス──で発生した大規模な暴力と虐殺は、従来の宗派対立や内戦の延長線とは異なる、特異な構造を持っていた。暴力を可能にしたのは、武器や組織ではなく、言葉だった。
SNS、説教壇、動画投稿、拡散される画像、歴史の引用、それらのすべてが一つの目的に向かって動いていた。ある特定の集団を「敵」と見なし、暴力を正当化する物語を作り上げるために。
シリアの人権団体STJ(Syrians for Truth and Justice)はこの過程を詳細に記録し、報告書『The Role of Hate Speech in the Massacres that Took Place in the Coastal Region in March 2025』(2025年5月26日公開)にまとめた。本稿では、同報告書を紹介しつつ、なぜこの事件が「ヘイトスピーチによって引き起こされた虐殺」と呼ばれるに至ったのかを整理する。
沿岸部の暴力──発端と情報環境
2025年3月6日、地中海沿岸の都市ジャブラとその周辺で、武装グループによる治安部隊襲撃事件が発生し、15人以上が死亡した。新政府は、これを「前政権の残党」による反乱と位置づけ、治安部隊と軍を動員して、ラタキア、ホムス、タルトゥース各県で掃討作戦を開始した。
だがこの軍事行動は、同時進行していた情報の暴走と切り離せない。
SNSや一部メディアは、この襲撃を「アサド派によるクーデター未遂」「イランの支援を受けた内乱」と報じ、事件の性質を宗派的な枠組みに当てはめた。アサド前政権の支持基盤であるアラウィー派(Alawites)──イスラム教シーア派の一分派であり、シリアの少数派──が、スンナ派住民の安全を脅かしているという物語が広がった。
一部地域では、モスクのスピーカーから「総動員」が呼びかけられ、オンライン上では「裏切り者への報復」「アラウィーの殲滅」といった過激な言葉が急速に拡散された。
ヘイトスピーチの拡張──敵の輪郭を作る言葉たち
報告書第5章は、こうした言説の広がり方と内容を、膨大な実例をもとに整理している。
まず注目すべきは、「アラウィー=アサド支持者=敵」という集団同一視である。襲撃の実行者が誰であれ、アラウィー派という宗派全体が「残党」「テロリスト」「裏切り者」として描かれ、その一括りが暴力の正当化に用いられた。
政治的には、「アラウィーはアサド体制と一体化した加害者だ」という語りが広まり、宗教的には中世の学者イブン・タイミーヤによるファトワ──アラウィーを「背教者」とし、イスラム共同体から排除すべきとする教義解釈──が繰り返し引用された。
たとえば、以下のような投稿や動画が拡散された。
- 「この宗派(ナサイリー)は1400年前の戦いの復讐として、我々を殺し続けてきた。」
- 「彼らは異教徒であり、殺害は信仰において許される行為だ。」
- 「アラウィーの存在がある限り、この地に平和は訪れない。」
宗派名「ナサイリー(Nusayriyyah)」はアラウィー派を侮蔑的に呼ぶ言葉として使用され、歴史的怨念と宗教的正当化が組み合わされることで、暴力は「罪」ではなく「義務」へと変容した。
海外からの火種──越境する憎悪
この現象が特異だったのは、煽動の発信源が国外にもあったことだ。
- ドイツ在住の難民Mohamad Jaddouは、自身の動画で「アラウィー、シーア派、ドルーズ派は、ユダヤ人よりも先に戦うべき敵」と語った。この動画はドイツの極右政党AfDの政治家によっても拡散され、Jaddou本人はドイツ当局から尋問を受け、投稿を削除する事態となった。
- オランダではTikTokで「アラウィーを海に投げろ。魚が飢えないように」と発言した女性が逮捕された。
こうした越境的なヘイトスピーチは、国外在住のシリア人インフルエンサーがもつ影響力が暴力の呼び水となる可能性を示している。
虐殺の記録──言葉が殺しを可能にする
STJの報告書には、具体的な暴力の記録が数多く含まれる。
- 2025年1月、ホムス県ファヘル村では、ムルシディーヤ派(アラウィーに近い信仰を持つ宗派)の住民15人が集団で殺害された。
- アラウィー派出身の判事、宗教指導者、社会的に著名な人物が暗殺された。
- 拘束されたアラウィーの若者に犬の鳴き声を出させたり、屈辱的なスローガンを叫ばせるなどの人格破壊的な扱いが行われた。
- ラタキアのジャブラでは、群衆がアラウィーを標的にしたスローガンを叫びながらデモ行進を行った。
また、これらの暴力を正当化するチラシや画像がオンライン上で共有された。たとえば:
- 「ナサイリーはキリスト教徒やユダヤ人よりも危険な異端者だ」
- 「彼らを殺すことは義務である」
という言葉が印字されたビラがラタキア市内で配布されていた。
大統領演説という「許可」
2025年3月7日、アフマド・シャール大統領は全国向けの演説で「国家と国民に分裂はなく、裏切り者には情けをかけない」と述べた。報告書は、この曖昧な「裏切り者」が、当時の聴衆にとっては「アラウィー派」全体を指すものとして受け取られた可能性が高いと指摘している。
こうした文脈においては、「行き過ぎるな」と言葉で留保しても、既に暴力を行う側にとっては国家からのお墨付きとして機能してしまう。
法の不在と処罰の空白
報告書は、こうした状況を許した法的・制度的な問題にも焦点を当てている。2025年3月に制定された暫定憲法は「社会的和解」や「共生」を謳うものの、ヘイトスピーチを明確に違法とする条文は存在しない。実際のところ、宗教指導者や個人による煽動発言には処罰が科されず、むしろ拡散されたまま放置されていた。
終わりに──これは「どこかの国の話」ではない
この報告書が私たちに突きつけているのは、「暴力は突然爆発するのではなく、言葉によって準備される」という厳しい現実である。敵意を煽る言葉が無数に繰り返されることで、誰かを殺すことが「当然」になってしまう。その瞬間を防ぐ制度がなければ、暴力は加速し続ける。
そして重要なのは、これがシリアという特殊な国の話ではないということだ。SNSを通じて言葉が拡散し、誰かを敵と見なす語りが日常化する社会では、どこであっても同じ構造が成立しうる。
「言葉が引き金になる」時代において、我々はその言葉が何を生み出すのかを、冷静に見つめる必要がある。


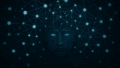
コメント
Falls Sie einen Werbeblocker verwenden, überprüfen Sie
bitte dessen Einstellungen. Wir verwenden auf unseren Seiten Affiliate-Links und
erhalten möglicherweise eine Provision für Kunden, die an Online Casinos
verwiesen werden. Casino.guru sieht sich als eine unabhängige Informationsplattform über Online
Casinos und Online Casinospiele, die von keinem Glücksspielanbieter oder irgendeiner anderen Instanz kontrolliert wird.
Diese Initiative haben wir mt dem Ziel gestartet, ein globales Selbstausschlusssystem
zu schaffen, das es gefährdeten Spielern ermöglicht, ihren Zugang
zu allen Online-Glücksspielmöglichkeiten global zu sperren.
Die Registrierung bei PSK Casino in Österreich ist ein strukturierter und sicherer
Prozess, der Benutzern Zugang zu vielfältigen Glücksspielen ermöglicht.
Es wurde 2010 gegründet und bietet eine Vielzahl von Spielen, einschließlich Slots,
Tischspiele und Live-Casino-Spielen. Die App bietet ein breites Spektrum an Spielen,
einschließlich der beliebtesten Slot-Spiele, Tischspiele und Teilnahme an regelmäßigen Casino-Turnieren. Die Registrierung bei PSK Casino in Deutschland ist ein strukturierter und sicherer Prozess,
der Benutzern Zugang zu vielfältigen Glücksspielen ermöglicht.
Die PSK Casino App bietet eine umfassende Auswahl an Online-Casino-Spielen,
darunter beliebte Slot- und Tischspiele sowie regelmäßige Casino-Turniere.
Durchsuchen Sie alle von PSK Casino angebotenen Boni, einschließlich jener Bonusangebote, bei denen Sie keine Einzahlung vornehmen müssen, und durchstöbern Sie auch alle Willkommensboni, die Sie bei Ihrer ersten Einzahlung erhalten werden.
Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht es
den Spielern, schnell und einfach ihre Lieblingsspiele zu finden,
sei es durch die Suchfunktion oder die verschiedenen Kategorien. Das
PSK Casino bietet eine moderne und unterhaltsame
Glücksspielerfahrung für alle Spielbegeisterten. Neue
Spieler erhalten oft Willkommensboni, bei denen sie ihre
Einzahlungen mit zusätzlichem Geld oder Freispielen aufstocken können.
References:
https://online-spielhallen.de/casino-of-gold-bonus-spiele-anmeldung/
These slots have thrilling gameplay thanks to a setup where
the number of symbols per reel changes with each spin. Check local
laws and ensure you are of legal gambling age before using winspirit or any online casino.
For typical queries, the live chat resolves most
matters quickly, improving the overall WinSpirit experience for Aussie players.
Most WinSpirit slots are HTML5-optimised for smooth gameplay on modern phones.
The WinSpirit casino app supports biometric logins on many devices
for convenient access to your account.
For Australians seeking crypto support and a broad pokies library, WinSpirit remains an attractive option. The support team can also advise on regional availability if you
see messages that WinSpirit site is not available in your country.
Always provide transaction screenshots if you report payment issues to speed
up resolution. The team assists with account verification, banking
queries and bonus clarifications. Quests and weekly missions give frequent chances to earn free
spins and bonus credits. WinSpirit runs regular tournaments,
provider-specific events and Pragmatic Play Drops & Wins style promotions with cash pools and leaderboard prizes.
Sun International slot games offer denominations ranging from 1c to R100.
Our table games use casino value chips that can be purchased from the Cash Desk or at the tables.
Sun International casinos offer an exciting and entertaining range of casino
table games including Roulette, Poker, Blackjack and many more.
References:
https://blackcoin.co/casino-hotels-on-the-gold-coast/
The all-electric buildings are completely fossil-fuel free, drawing
renewable energy from off-site sources and the campus’s Thermal Energy Center, which houses a geothermal system
that provides heating and cooling for 18 buildings. Able to accommodate more than 6,000 employees, the seven new office buildings range from four to five stories and
are arranged in an urban-inspired, pedestrian-friendly setting.
Since Microsoft established its headquarters in Redmond, Washington, in 1986, the company’s campus has grown from four buildings to more than 100.
The Pedestrian Bridge connects Microsoft’s East and West
Campus, creating a direct connection between the distinct areas of
campus while also eliminating the need for cars to traverse campus.
Conveniently located close to the Boardwalk Bistro, the
cosy Boardwalk Bar has screens, cold beer and app-based TAB
service. Open every Friday and Saturday, 5pm ‘til late, The Green Room serves up great drinks, light bar snacks and tunes from
a range of genres that will have you ready to boogie. With spacious rooms in Tasmania’s tallest building,
there’s modern deluxe and standard options, and something
to suit every taste and budget. Staying in the iconic Wrest Point Tower, you’ll get to take in stunning views of the River Derwent, kunanyi / Mt
Wellington, or Hobart City. Our views are a joy to wake up to.
Reach elite status and enjoy private concierge service, faster withdrawals, and customized promotions delivered just for you.
Weekly reload offers, free spins on featured games, cashback on losses,
and surprise giveaways keep players engaged and constantly rewarded.
Whether you’re visiting us in person or logging in online, Wrest
Point Casino offers a world-class experience rooted
in Tasmanian hospitality.
References:
https://blackcoin.co/how-to-recognise-best-and-worst-online-casinos-easily/
casino con paypal
References:
generaljob.gr
paypal casino uk
References:
fmagency.co.uk
casino sites that accept paypal
References:
https://jobsharmony.com/companies/best-real-money-online-pokies-in-australia-for-december-2025/
online betting with paypal winnersbet
References:
https://cybernetshell.com/employer/top-online-us-casinos-that-accept-paypal-in-dec-2025
online slot machines paypal
References:
https://www.allclanbattles.com/groups/best-online-casinos-australia-top-aussie-gambling-sites-2025/
online casino real money paypal
References:
cyltalentohumano.com
References:
Cycle anavar female before and after
References:
https://apunto.it
References:
Osage casino
References:
linkvault.win
References:
St croix casino
References:
https://botdb.win/
buy injectable steroids online
References:
https://p.mobile9.com/puppycirrus33/
References:
Test prop anavar cycle before and after
References:
md.un-hack-bar.de
References:
When should i take anavar before or after workout
References:
ekademya.com
References:
Before and after test cyp 500 week and anavar pics
References:
https://ai-db.science/wiki/Dosierung_und_Zyklen_fr_Anavar_leicht_verstndlich_erklrt
harmful effects of steroids
References:
https://pattern-wiki.win
dangers of steroids
References:
https://posteezy.com/
legal natural drugs
References:
sciencewiki.science
buysteroids.com review
References:
exploreourpubliclands.org
References:
Anavar before and after pics female
References:
09vodostok.ru
%random_anchor_text%
References:
dumpmurphy.us