INACH(International Network Against Cyber Hate)は、欧州委員会の支援を受けて2025年6月に『Disinformation and Hate Speech』という包括的な報告書を発表した。約25年にわたりネット上のヘイトを監視してきた同ネットワークは、近年の最重要課題として「偽情報とヘイトスピーチの融合」を挙げ、その政治的機能、社会的影響、EUの規制の現状と限界を分析している。
本稿では、報告書の全体像を構造的に紹介しつつ、特に注目すべき点を抽出する。焦点となるのは、いわゆる「awful but lawful(違法ではないが有害な)」コンテンツの政治的活用であり、それが民主主義に及ぼす長期的な影響である。
ヘイトと偽情報はなぜ結びつくのか
報告書はまず、情報の分類から議論を始める。
- Misinformation(誤情報):善意で共有される誤った情報
- Disinformation(偽情報):意図的に制作・流布される虚偽情報
- Malinformation(悪意情報):真実を害意をもって晒す情報(例:ドクシング)
この区別は、どの情報が「処罰されるべきか」だけではなく、どのような戦略的意図で流布されているかを見極めるために不可欠だとされる。
偽情報の目的は単に「信じ込ませる」ことではない。むしろ、矛盾したナラティブを大量に投入して、誰も何も信じられなくすることそのものが狙いであり、信頼のインフラを破壊する行為だと定義される。このような「意味の飽和」が、民主主義制度への不信や社会的分断の温床となる。
ボーダーライン・コンテンツとプラットフォーム責任
違法なヘイトスピーチや偽情報は削除対象となるが、現実には多くの投稿が「違法ではないが有害」というグレーゾーンにとどまる。プラットフォームのコミュニティ・ガイドラインに違反していても、政治的圧力や規制回避のため削除されない例が多く、結果として悪意ある情報が可視性を得ていく構造がある。
この現象を補強するのがアルゴリズムであり、センセーショナルな投稿ほど拡散されやすい仕組みは、事実よりも感情が勝る環境を生んでいる。
オランダ:ポピュリズムと偽情報の結託
特に衝撃的なのがオランダの事例である。
2023年、LGBTQ+をテーマとした児童書で知られる作家ピム・ラマースが、児童週間の公式詩人に選ばれた。しかし、彼が過去に書いた成人向け短編(性的虐待を題材にした被害者視点の作品)が掘り起こされ、「小児性愛を擁護する人物」とする攻撃がSNS上で拡散された。背後には極右の政治家や、「momfluencer」と呼ばれる母親系インフルエンサーがいたとされる。
本人は脅迫を受けてイベントを辞退し、身を隠す事態となった。こうした意図的に誤解を生み出す偽情報と、そこに付随するオンライン・ヘイトスピーチの連鎖は、報告書が最も警鐘を鳴らす対象である。
加えて、移民に関する誤情報の拡散も顕著だ。極右政党PVVは「移民がオランダ社会を崩壊させている」とするナラティブを繰り返し、映像・統計の恣意的引用をSNSで発信。実際には移民数は安定しており、「移民危機」ではなく「シェルター危機」が実態であるにもかかわらず、この誤解が社会に定着し、2023年選挙ではPVVが躍進した。
スロバキア:対ロ偽情報の受容と制度の脆弱性
スロバキアでは、COVID-19パンデミックとウクライナ戦争を契機に親ロシア的ナラティブが拡散。2024年時点で、国民の60%が「ロシアがウクライナに責任がある」と認めない状況にあるという。
この背景には、低いメディア・リテラシーと、政治家による偽情報の意図的流布がある。政党や議員が「ロシア擁護=伝統的価値観の擁護」というレトリックを用いて、国家的ナラティブを捻じ曲げている。報告書は、こうした構造が民主主義を内部から崩す典型例としてスロバキアを挙げる。
ドイツ:ディープフェイクと選挙干渉の最前線
2025年の連邦選挙に向けて、ドイツではAI生成の偽動画や捏造記事が出回っている。AfDの候補が「ヒトラーは共産主義者だった」と発言し、ロシアのプロパガンダサイトがそれを拡散。さらには、ケニアから190万人の移民が来るという偽ニュース、介護施設の暴力映像(実際は2020年の米国の事件)を「ドイツの移民犯罪」として流す偽動画など、多層的な情報操作が行われている。
注目すべきは、国民の84%がこれらを重大問題と認識しているという点である。日本に比べ、社会的危機感のレベルが明確に異なっている。
EUの対応:行動規範(Code of Conduct)の限界
EUは2018年以降、プラットフォームとの連携により「Disinformation行動規範」を策定。透明性、政治広告の表示義務、広告収益の遮断、選挙時の迅速対応体制などが含まれるが、報告書は実効性の乏しさを指摘する。
- 周縁プラットフォーム(例:Telegramなど)は規範の外にある
- ファクトチェックは「信じたい人には届かない」
- モデレーターは低賃金・短時間で複雑な判断を求められ、バーンアウトに陥る
- 言語の不均衡が顕著(ミャンマーにおけるFacebookの事例も参照されている)
報告書は、こうした実務上の限界を明示しつつ、「規制の強化よりも構造的な補完が必要」と訴える。
提言:民主主義のための多層的アプローチ
最終章で提示される提言は、単なる規制強化ではない。
- 各国文脈に対応したモデレーション
- 誤情報のアルゴリズム的拡散の制御(例:拡散性の高い投稿に警告ラベル)
- 教育現場における「表現の自由」の再教育(自由=差別の容認ではない)
- インフルエンサーの資金源・組織的背景の可視化
つまり、偽情報は情報の問題ではなく、権力と倫理、社会的認知の問題として捉え直すべきだという点が本報告書の核心である。
総括:偽情報は政治の武器であり、制度の盲点を突く
本報告書の価値は、偽情報とヘイトスピーチが「連携」することでいかに民主制度を破壊しうるかを、具体的かつ比較政治的に示している点にある。技術論だけでは見えない、ナラティブ操作の構造を暴き、制度的・倫理的・教育的な対策の必要性を論じている。
日本における議論が「ファクトかフェイクか」の水準にとどまっているのであれば、この報告書はその認識を根底から問い直す契機となるだろう。偽情報は、もはや「誤解」ではなく、政治と感情と差別が結びついた戦略的手段なのである。
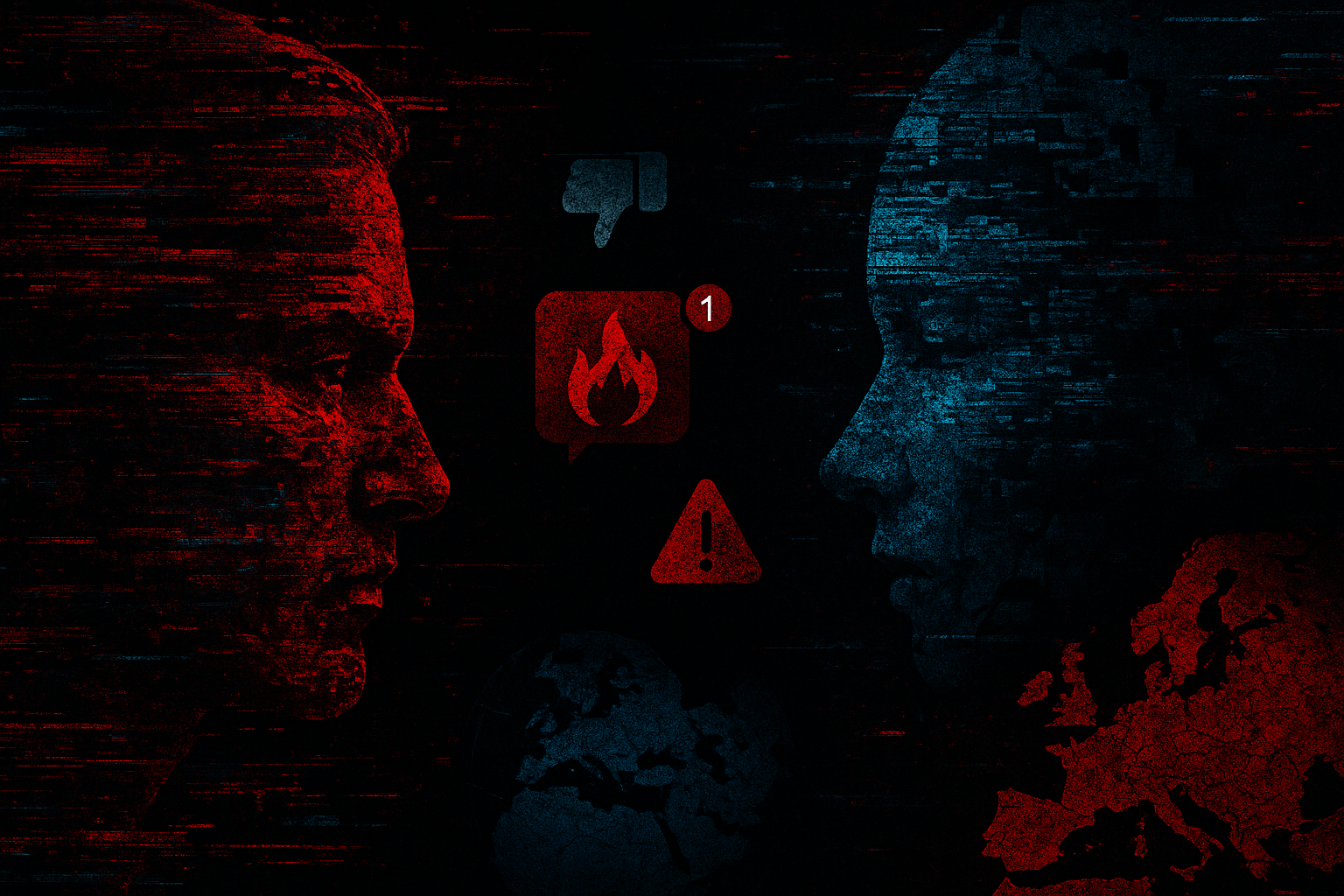
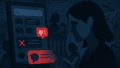

コメント
excellent issues altogether, you just gained a new reader. What could you recommend about your publish that you made some days ago? Any certain?
I believe you have noted some very interesting details , appreciate it for the post.
I couldn’t resist commenting
whoah this blog is magnificent i really like studying your articles. Stay up the great paintings! You understand, lots of individuals are looking round for this information, you can help them greatly.
I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this blog. I am hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.
Hi there, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam comments? If so how do you reduce it, any plugin or anything you can recommend? I get so much lately it’s driving me mad so any support is very much appreciated.
Bei WEB.DE Games finden Sie die besten kostenlosen Spiele für zwischendurch und können täglich gratis
spielen! In einigen Casinos wird der Atemluft sogar reiner Sauerstoff beigemischt, damit man nicht müde wird und lange spielen kann.
Unsere Website hat Tausende von kostenlosen Slots
mit Bonus und Freispielen. Bietet Ihre Website
kostenlose Slots mit Bonus und Freispielen? Sie können kostenlose Slots ohne Download direkt hier
bei VegasSlotsOnline spielen.
Möchtest du zur Verfügbarkeit verschiedenster Boni auf dem Laufenden bleiben, dann aktiviere Benachrichtigungen in deinen Profil-Einstellungen. Neben unserer reichhaltigen Spielauswahl werden dir vor allem
auch unsere personalisierten Aktionen und Angebote Freude
machen. Schau dir hier die Details zum Sport-Willkommensbonus an. Für echte Sportskanonen lassen wir als Willkommensbonus zwei 50% Gewinn-Boosts springen,
mit denen du deinen Netto-Gewinn bei Sportwetten zwei Mal um 50%
erhöhen kannst. Dann haben wir eine gute Nachricht für dich, denn bei LeoVegas LIVE kannst du nicht nur
den Live-Dealern in die Augen schauen, sondern auch echtes Geld gewinnen. Alle Informationen zur Nutzung des Bonus findest du auf der Casino Willkommensbonus-Seite.
In 2025 müssen Sie sich nicht nur auf kostenlose Cent-Slots beschränken. Wir
haben die meistgespielten Spielautomaten auf unserer Website unten mit den wesentlichen Informationen für jedes Spiel zusammengestellt.
Ein Softwareanbieter oder Casino-Betreiber wird alle Lizenz- und Testinformationen in der Regel im Fußbereich ihrer Website auflisten. Darüber hinaus sind kostenlose Spiele von seriösen Entwicklern von Slot-Testhäusern zertifiziert.
References:
https://online-spielhallen.de/pistolro-casino-freispiele-ihr-schlussel-zu-kostenlosen-drehungen-und-gewinnen/
Join the Ripper crew today and get ready to have a blast (responsibly, of course – they’ve got responsible gaming tools too)!
Friendly support is on hand 24/7 to help you navigate any bumps along the way.
Dive in and discover your new favourite game, and maybe even strike
it big with a massive jackpot win! Welcome to Ripper Casino, where the
thrill of Aussie adventure meets world-class gaming!
© Copyrights 2025 ripper-casinos.com All
Rights Reserved.
The Ripper Casino site is fully integrated for mobile device play, so you can enjoy
your favourite games on your smartphone or
tablet. Ripper Casino keeps rolling out heaps of deposit bonuses, cashback
bonuses, weekly free cash bonuses, table games bonuses.
Our generous welcome bonus up to AU$7,500 will give you a fantastic head start, while our mobile-optimized platform ensures seamless gameplay on-the-go.
Ripper Casino’s top-notch games, unbeatable bonuses, and fair dinkum customer service make us the
best spot for all your online gaming needs. Players can indulge in a vast array of pokies, table games, live dealer experiences, video poker, and progressive slots, all accessible on both desktop and mobile
devices. Ripper Casino Australia 2025 delivers a secure, licensed, and crypto-friendly gaming
environment with over 1,500 games, generous promotions,
and fast payouts. At Ripper Casino, we are committed
to delivering a safe, licensed, and responsible online gaming
experience tailored for Australian players. Licensed and regulated by respected authorities, we provide a secure environment where players
can enjoy their favorite games with complete peace of mind.
References:
https://blackcoin.co/intensity-casino-australia/
Like any online joint, it’s got its high points and a few things that might make you think twice.
And with responsible gambling tools in place, Ripper Casino shows it’s serious about player wellbeing.
Your personal info and cash at Ripper Casino Australia are protected like Fort Knox, giving you peace
of mind while you play. They use 128-bit SSL encryption to keep your
data and transactions secure.
Creating an account and beginning your gaming journey at Ripper
Casino is quick and easy. Our dedicated support team is available around the clock via live chat, email, and phone to assist with any questions or concerns.
Enjoy perfect gaming on any device with our responsive platform
optimized for smartphones and tablets, no app download required.
Explore the outstanding features that make us the top choice for
discerning players. Ripper Casino treats players
with genuine respect and honesty. The thrill of spinning reels, the strategy of table games, the excitement
of progressive jackpots—it’s all here waiting for you
at Ripper Casino.
But don’t worry, the process takes only about 5 minutes
– so you’ll be ready to start playing in no time. Whether it’s craps, baccarat,
or a cheeky game of Texas Hold’em, the atmosphere’s electric.
Or maybe you’re at the online roulette wheel, heart pounding
as the ball clatters around, waiting to see if your number comes up.
Whether you’re chasing jackpots or just having a flutter, Ripper Casino’s pokies are always a top-notch thrill!
The 777 pokies bring that old-school charm, while the Megaways crank up the excitement with thousands of
ways to win.
References:
https://blackcoin.co/baccarat-guide-how-to-play-win-at-baccarat/
Hallo Mitglieder!
Moechte was Interessantes zeigen.
Habe neulich Pistolo Casino gefunden – Pistolo.
Kann nur Gutes berichten.
Coole Automaten, gute Quoten, hilfsbereiter Support.
Guckt mal: [url=https://pistolo.de/games/]Casino Slots[/url]
Viel Spass 🙂
Howdy! I’m at work browsing your blog from my new iphone 3gs! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts! Keep up the fantastic work!
online casino real money paypal
References:
https://robbarnettmedia.com/employer/beste-paypal-online-casinos-2026-im-casino-mit-paypal-bezahlen/
online real casino paypal
References:
https://divyangrojgar.com/employer/paypal-casino-list-2025-online-casinos-with-paypal/
I besides think thence, perfectly composed post! .
australian online casinos that accept paypal
References:
https://jobboat.co.uk/employer/324984/die-besten-online-casino-mit-paypal-im-test-2025
online slots uk paypal
References:
cyprusjobs.com.cy
References:
New slot machines
References:
https://menwiki.men/
References:
Wheel of fortune slot machines
References:
youtube.com
what are steroids and what are they used for
References:
https://livebookmark.stream/
are steroids illegal?
References:
http://cqr3d.ru/
References:
Anavar before or after meal
References:
justpin.date
muscle building injections
References:
klint-glerup.federatedjournals.com
closest to steroids but legal
References:
https://ladefoged-due-2.hubstack.net
References:
Anavar before or after workout
References:
ccsakura.jp
safest oral steroids
References:
justbookmark.win
References:
Should i take anavar before or after workout
References:
dokuwiki.stream
Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!
References:
Test anavar cycle before and after
References:
timeoftheworld.date
steroidsbuy
References:
bookmarkspot.win