Coalition for Independent Technology Research が2025年8月に発表した報告書「The State of Independent Technology Research 2025: Power in Numbers」は、いま世界の独立テクノロジー研究者が直面している困難を包括的に描き出している。報告書の焦点は三つだ。プラットフォームからのデータアクセスが意図的に遮断されている現実、研究者自身への攻撃の激化、そして資金危機である。そしてこれらを乗り越えるための「集合的力(collective power)」の構築を強調している。
データ砂漠の広がり
かつて研究者はTwitter APIを通じて無料で膨大なデータにアクセスできた。そこから数万本に及ぶ論文が生まれ、政治的言説の動向やヘイトスピーチの広がりを分析することが可能だった。だが現在のXはAPIを有料化し、アクセスを著しく制限している。さらにMetaは2024年にCrowdTangleを廃止し、代替の「Meta Content Library」では申請要件が厳しく、しかも機能は1割にも満たない。
実際の拒否事例も報告されている。戦略対話研究所(ISD)は2025年初頭、ドイツ選挙での政党に対するオンライン反応を調べるために、DSA(デジタルサービス法)第40条に基づきXにデータ提供を申請した。しかしXは必要以上の書類を要求し、法的根拠も示さず拒否した。TikTokでも同様で、申請の半数近くが却下され、承認された場合でも同じ検索クエリで結果数が毎回違うなど、実質的に使い物にならない状態だった。
この「データ砂漠」によって、研究者はアルゴリズムが実際にどのように情報を推薦し、誤情報がどう拡散しているのかという基本的な問いに答えられなくなっている。プラットフォームは「透明性」を装いながら、実際には監視の目を閉ざす方向に進んでいる。
研究者への攻撃
報告書が強調する二つ目の危機は、研究者自身に対する攻撃だ。
米国の研究者Nina Jankowiczは、偽情報研究と政府での職務をきっかけに標的となり、日常的に死の脅迫やディープフェイクポルノの被害を受けていると証言している。講演の告知さえ安全上できないという。
パレスチナのデジタル権利研究者Ahmad Qadiの状況はさらに苛烈だ。彼が所属する7amlehは、資金提供者への圧力や「テロ組織」とのレッテル貼りを通じて研究そのものを封じ込められそうになっている。移動は検問で妨害され、端末は押収され、事務所近くにはコンクリートバリケードが立ち塞がる。彼の研究テーマである「パレスチナ人コンテンツの検閲」や「イスラエルのサイバー作戦」は、研究対象であると同時に生存のリスクにも直結している。
米国の大学も研究者を守れていない。スタンフォード大学のInternet Observatoryは、ジム・ジョーダン下院議員らによる政治的圧力と高額な訴訟費用に耐えられず、2024年に事実上解体された。所長のアレックス・スタモスは辞任し、研究マネージャーのレネー・ディレスタも契約更新されなかった。研究機関が研究者を守るどころか、政治的圧力を避けるために手を引いた例として象徴的である。
さらに、米国ではX社がCenter for Countering Digital Hate(CCDH)を相手取り、数千万ドルの損害賠償を求める訴訟を起こした。裁判所は「研究を沈黙させる意図が明白」として棄却したが、このような訴訟の脅威そのものが研究者全体に萎縮効果を与えている。
資金危機の深刻化
三つ目は資金危機だ。調査に回答した研究者の85%が資金不足を最大の課題と指摘している。
米国では2025年春にNSFとNIHによる研究助成の大規模削減が実施された。NSFでは1,400件以上、総額10億ドル超の助成が打ち切られ、NIHでも2,500件以上が停止された。特に「偽情報・誤情報」研究は体系的に排除された。さらに打撃となったのは、削減された助成の58%が女性研究者主導プロジェクトであったことだ。女性PI(主任研究者)の割合が34%しかないことを考えると、意図的な偏りがあると指摘されている。
欧州でも状況は好転していない。Horizon Europeは2025〜2027年にかけて21億ユーロ削減される予定で、71%の質の高い研究提案が予算不足で却下されている。政治的に「争点化しやすい研究」—誤情報やプラットフォーム批判—は資金対象から外される傾向が強まっており、研究者はテーマ変更を余儀なくされる。
集合的力としての対応
報告書のタイトル「Power in Numbers」が示すように、解決の道は個人防衛ではなく集合的行動にある。
研究者は独自のインフラを立ち上げている。たとえば Junkipedia は社会問題や偽情報を横断的に収集・分析できるプラットフォームであり、複数の研究機関が利用している。インディアナ大学の OsoMe(Observatory on Social Media)もデータ科学者とジャーナリストが協力する独立拠点だ。
法的戦略も進んでいる。Knight First Amendment Instituteは研究者を支援し、X社やMetaを相手に研究権を守る訴訟を起こしている。さらに、Researcher Support Consortium や Expert Voices Together といったネットワークは、嫌がらせに直面した研究者を個別に支援し、心理的・法的サポートを提供している。
資金面では、研究者同士の相互扶助ネットワークが広がり、欧州研究会議(ERC)は米国の資金危機で職を失った研究者を受け入れるために助成金を拡充した。環境分野の「市民科学」支援モデルを参考に、テクノロジー研究にも長期的な公的資金スキームを導入すべきだという提案も出されている。
結論 ― マックレーカーの再来
20世紀初頭の米国で、石油独占や食肉加工場の不正を暴いた「マックレーカー」たちは、企業の妨害や訴訟を受けながらも集合的な力で社会改革を実現した。報告書は、現代のテクノロジー研究者も同じ岐路に立たされていると描く。
「データ砂漠」「研究者への攻撃」「資金危機」は、偶然ではなく意図的な戦略である。だが、研究者たちは孤立せず、連帯し、インフラを共有し、法廷で戦い、互いを守り合っている。
この報告書は、危機の深刻さを示すと同時に、研究者コミュニティが「数の力」で対抗する可能性を描いたものだ。独立研究の自由を守ることは、単なる学問の問題ではなく、民主主義そのものを支える基盤であることを改めて強調している。


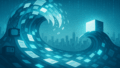
コメント
Курсы ЕГЭ английский https://courses-ege.ru
melbet – paris sportif afrik foot pronostic
Some truly nice and useful information on this web site, too I conceive the design holds good features.
chery tiggo 7 pro chery ultra
Полезное одним кликом: https://audio-kravec.com/pvh-akril-ili-kompozit-kakoj-material-vybrat-dlya-plastikovyh-tablichek.html
All the latest here: https://ananfashion.net/home/index.php/2025/10/08/kupit-akkaunt-gmail-ot-89-nedorogo-s-garantiej-v-5/
I’m really impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see a great blog like this one nowadays..
Hi would you mind letting me know which webhost you’re using? I’ve loaded your blog in 3 completely different web browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good internet hosting provider at a reasonable price? Many thanks, I appreciate it!
You are my breathing in, I own few web logs and occasionally run out from to brand.
What i don’t understood is in reality how you’re now not really much more well-preferred than you might be right now. You are so intelligent. You understand thus considerably with regards to this topic, produced me individually consider it from a lot of numerous angles. Its like women and men aren’t involved unless it is something to accomplish with Girl gaga! Your individual stuffs outstanding. All the time maintain it up!
I discovered your weblog web site on google and verify a number of of your early posts. Continue to keep up the very good operate. I simply additional up your RSS feed to my MSN Information Reader. Searching for ahead to reading more from you afterward!…
Would you be occupied with exchanging hyperlinks?
I conceive this website has got some very fantastic information for everyone : D.
Madeira Atlantic Festival, eine Veranstaltung,
die den Beginn der Sommersaison auf Madeira markiert.
Entdecken Sie Wanderrouten offiziell von der Regionalregierung
von Madeira empfohlen, da kleine Strecken (PR) und
individualisiert durch eine laufende Nummer zugewiesen wird.
Mit dem Blumenfest „Festa da Flor“ wird die Ankunft des Frühlings verkündet.
Das Panorâmico, das täglich Themenbuffets anbietet, befindet sich
in der Etage der Gärten und verfügt über eine Architektur aus Glas und Stahl, wodurch Helligkeit Trumpf ist.
Das Auditorium für 628 Personen und der Blaue Saal, der Platz
für 450 Personen bietet, sind perfekt für Veranstaltungen mit großer Wirkung.
Das Dockside mit seiner Terrasse über dem Meer ist perfekt für entspannte Mahlzeiten im
Freien. Das Panoramic Restaurant bietet ein abwechslungsreiches Buffet mit Meerblick,
während das Sunset Restaurant von Donnerstag bis Sonntag ein intimeres À-la-carte-Abendessen anbietet.
Hallo, bitte wende dich hierzu gern an unsere Reiseberater.
Wir möchten gerne ein ruhiges Zimmer in den oberen Etagen,
und ist ein Wasserkocher auf dem Zimmer ?? Darf ich auf dem
Balkon rauchen?
References:
https://online-spielhallen.de/posido-casino-login-ihr-weg-ins-maritime-spieleparadies/
Crown Melbourne features a curated selection of luxury retailers
and premium Australian brands. Whether you are here for
leisure, business, or wellness, Crown provides tailored experiences with unmatched attention to detail.
Crown’s riverside promenade hosts spectacular events year-round — from
holiday fireworks and light shows to cultural festivals, street food markets, and immersive pop-up experiences.
The Palms at Crown is home to live concerts, comedy specials, dance productions, and special guest performances.
Three months later, the Alza welcomed an upmarket twin in the form of
the Toyota Veloz. Launched in July 2022, the second-gen Perodua Alza brought with it the new Daihatsu New Global Architecture (DNGA) platform to allow
the 13-year old JDM-based original model to retire. After trying
to pursue a career in product design, Jonathan Lee decided to
make the sideways jump into the world of car journalism instead.
We will continuously update this post with more information as and when they become available,
so keep an eye on this space to know more about the upcoming 2022 Perodua Alza D27A.
One thing to note – these prices include the luxury tax that was reintroduced this year, hence the
sizeable jump over last year’s figures.
References:
https://blackcoin.co/backgammon/
The design pops with bright visuals, smooth performance and a playful spirit that turns
ordinary gaming into a candy-filled adventure. From your initial registration through years of loyal play,
we provide the tools, support, and opportunities necessary for sustained entertainment punctuated by genuine winning potential.
Gaming should enhance entertainment, not create financial
stress, and we’re committed to fostering a sustainable environment where fun remains the primary objective while wins provide exciting bonuses to your leisure time rather
than becoming financial dependencies. A Big Candy Casino delivers the complete desktop
experience through mobile browsers without requiring app downloads that consume device storage.
Use this reference to navigate our ecosystem efficiently and
leverage the full spectrum of benefits available to registered
members who engage actively with our promotional calendar and loyalty programs designed specifically for sustained player
satisfaction.
This collection ensures that both beginners and experts
can engage with familiar and exotic games alike. Whether you enjoy timeless roulette or innovative themed slots like Temple Totems, the Big
Candy casino manages to cover all preferences. Each
section brings unique flavours, ensuring variety for every style of player.
In terms of licensing, the casino operates under internationally recognised
gaming regulations.
Our 345% welcome bonus + 30 free spins gets you started with
a bang, while ongoing promotions and VIP rewards keep the excitement going!
Sign in now to verify your account and secure available welcome offers while they remain active.
Coat of Arms is a smart choice when you’re managing a capped-bonus session thanks
to its mix of free spins and progressive potential; see the Coat of Arms
Slots review for specifics on paylines and symbols.
Keep an eye on your account messages after sign-in and watch the promotions page so you don’t miss limited windows to claim extra plays.
References:
https://blackcoin.co/explore-the-worlds-biggest-source-of-information-about-online-casinos/
online casino usa paypal
References:
https://balajee.co.in
online casino mit paypal einzahlung
References:
http://carecall.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=2092671
I am continuously browsing online for tips that can assist me. Thank you!
casino avec paypal
References:
https://jobs.foodtechconnect.com/companies/best-real-money-online-casinos-top-10-in-december-2025/
casino mit paypal
References:
https://macrorecruitment.com.au/employer/fast-payout-casinos-in-australia-2025-instant-withdrawals/
Hello! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard work due to no backup. Do you have any solutions to prevent hackers?
I went over this site and I conceive you have a lot of good information, bookmarked (:.
online casino uk paypal
References:
https://www.makemyjobs.in/companies/40+-best-australian-online-casinos-for-real-money-in-december,-2025/
online casino real money paypal
References:
https://nujob.ch/companies/best-paypal-online-casinos-accepting-us-players-2025/
casino online paypal
References:
https://empleoo.net/companies/20-best-online-casinos-in-australia-for-real-money-in-2025/
casino online uk paypal
References:
https://recruit.brainet.co.za/companies/best-online-poker-sites-in-the-us-2025/
Krypto-Glücksspiele sind an sich kein neues Phänomen, denn sie begleiten uns schon seit fast einem Jahrzehnt. Da Kryptowährungen weiterhin an weltweiter Beliebtheit und Aufmerksamkeit gewinnen, haben diese Art von digitalen Währungen offenbar einen großartigen Einzug in die Branche der Online-Glücksspiele gehalten. Da sie den Spielern unter anderem Anonymität und vollständige Kontrolle bieten, werden digitale Währungen von vielen Spielern als eine der sichersten Formen des Online Glücksspiels in Deutschland angesehen. In diesem Ratgeber geht es darum, den Spielern zu helfen, das beste deutsche crypto Casino ausfindig zu machen!
Ethereum, Litecoin, Bitcoin Casinos und andere bieten Spielern Zugang zu denselben Spielen wie die üblichen Online Casinos. Sobald das Geld auf dem Konto ist, wird dem Spieler ein Willkommensbonus gutgeschrieben und er kann mit dem Spielvorgang beginnen. Bitte beachten Sie, dass neue Casinos oft großzügige Boni mit loyalen Wettbedingungen anbieten, um Spieler anzuziehen.
References:
https://s3.amazonaws.com/new-casino/vegas%20casino.html
References:
Slots belgique
References:
https://www.youtube.com/redirect?q=https://wd40casino.blackcoin.co
References:
Mgm casinos
References:
https://cloudyapple8.bravejournal.net/wd40-casino-2026-1-500-welcome-bonus-7-000-games-and-fast-withdrawals
legal australian steroids
References:
http://wiki.0-24.jp/index.php?pearkevin13
buy steroids legally
References:
https://musicvideo80.com/user/tellerrun3/
what is the best muscle building supplement on the market
References:
https://www.bandsworksconcerts.info:443/index.php?whitegate6
References:
Test prop anavar cycle before and after
References:
https://vacuum24.ru/user/profile/504967
References:
Anavar before and after pics reddit
References:
https://prpack.ru/user/poppybus89/
Thanks for helping out, great information.
References:
Test and anavar before and after
References:
https://forum.dsapinstitute.org/forums/users/weekfly06/
types anabolic steroids
References:
https://bookmarkstore.download/story.php?title=trenbol-100-trembolona-acetato-inyectable-1000-mg-10-ml-genesis
%random_anchor_text%
References:
https://socialbookmark.stream/story.php?title=17-mejores-lugares-para-comprar-cuentas-antiguas-de-gmail-pva-y-de-antigueedad
best weight loss steroid
References:
https://crane-vick-3.hubstack.net/dianabol-50mg
References:
Test prop anavar before and after pictures
References:
https://kostsurabaya.net/author/barunit78/
References:
Tulsa casinos
References:
https://lit-book.ru/user/greaseshadow88/
References:
Casino club santa rosa
References:
http://muhaylovakoliba.1gb.ua/user/muscleplay33/
References:
Starlight casino
References:
https://lindsey-monroe.federatedjournals.com/the-ultimate-guide-to-the-online-casino-world
References:
Sands casino reno
References:
https://humanlove.stream/wiki/Candy_Casino_Review_350_Up_To_500_Welcome_Bonus
References:
Mackie onyx blackjack
References:
https://urlscan.io/result/019bef08-e73f-74ac-b56c-61e9f91c5818/
References:
William hill slots
References:
https://freebookmarkstore.win/story.php?title=meilleurs-casinos-en-ligne-2026-bonus-sans-depot-exclusifs
References:
Casino security
References:
https://historydb.date/wiki/Candy96_Australia_Pokies_Bonuses_Fast_PayID_Payouts
References:
Hollywood casino tunica ms
References:
https://molchanovonews.ru/user/willowcow9/
References:
Ho chunk casino madison
References:
https://dokuwiki.stream/wiki/Candy96_Casino_Australia_800_Welcome_Bonus_160_Free_Spins_Bundle
pills for gaining muscle
References:
https://lovebookmark.win/story.php?title=testosterone-difficile-trovarlo-nelle-farmacie-italiane
%random_anchor_text%
References:
https://graph.org/Where-To-Buy-Testosterone-Online-Clinics-Cheapest-Legal-01-15
%random_anchor_text%
References:
https://sundaynews.info/user/coatactor2/
injectable dbol for sale
References:
https://justbookmark.win/story.php?title=nolvadex-pct
category of steroids
References:
https://pads.jeito.nl/s/WUtIEiVRcp
which is one function of steroids?
References:
https://telegra.ph/Terapie-naturali-per-alzare-il-testosterone-Guida-Andrologica-01-20
References:
Turtle creek casino
References:
https://king-wifi.win/wiki/Watch_Sweet_Bonanza_Candyland_Results_Stats_Live_Stream
References:
Geant casino la foux
References:
https://www.instapaper.com/p/17397871
References:
Sierra madre casino
References:
https://menwiki.men/wiki/Candy96_Casino_Australia_Your_Premier_Gaming_Destination_Down_Under
References:
Solaire casino
References:
https://md.swk-web.com/s/hq4wAolqR
References:
Keno online
References:
https://historydb.date/wiki/Candy96_Casino_Australia_800_Welcome_Bonus_160_Free_Spins_Bundle
References:
Roulette probability
References:
https://case.edu/cgi-bin/newsline.pl?URL=https://candy96.eu.com
oral steroids online
References:
http://humanlove.stream//index.php?title=helmspollard3254
dianabol anabolic steroid
References:
https://eskisehiruroloji.com/sss/index.php?qa=user&qa_1=coalfoot3
negative side effects of anabolic steroids
References:
https://bookmarkstore.download/story.php?title=buy-dianabol-20-methandrostanolone-by-dragon-pharma-100-tablets
testosterone vs anabolic steroids
References:
https://nerdgaming.science/wiki/Steroids_UK_UK_Steroids_Shop
References:
Bally’s las vegas reviews
References:
https://postheaven.net/gardenpen0/mobile-slots-and-live-spiele
References:
Monte cassino italy
References:
https://p.mobile9.com/donaldsecure5/
References:
Eurogrand casino
References:
https://wifidb.science/wiki/Ll_1Go_Casino_Bewertung_2025_Promocode_und_Boni
References:
Best online betting sites
References:
https://images.google.com.gt/url?q=https://online-spielhallen.de/888casino-anmeldung-ihr-tor-zur-welt-des-online-glucksspiels/
References:
Sbobet casino
References:
https://images.google.com.na/url?q=https://online-spielhallen.de/admiral-casino-aktionscode-ihr-schlussel-zu-exklusiven-vorteilen/
References:
Twin river casino
References:
http://cqr3d.ru/user/dadhub3/
References:
Hoyle casino
References:
https://numberfields.asu.edu/NumberFields/show_user.php?userid=6497666
References:
Scratch 2 cash
References:
https://ekademya.com/members/pianoframe03/activity/230890/
Подскажите работает ли кракен магазин после последних блокировок провайдеров