2025年10月29日、モスクワのデジタルハウス(Дом Цифры)で「Dialog about Fakes 3.0」が開催された。主催はロシア政府系非営利法人 Dialog Regions(АНО «Диалог Регионы»)。地方行政のデジタル広報を統括し、政府の情報政策を担う機関である。外務省報道官マリア・ザハロワ、教育省、通信庁、主要メディアや大学関係者が登壇し、生成AI・ディープフェイク・教育・法的規制が主要テーマとして扱われた。
主催発表では「80 か国から約 4000 人が参加」し、フォーラムは UNESCO Global Media and Information Literacy Week 2025(MIL Week) に登録された唯一のロシアイベントとされた。ただし、MIL Weekへの掲載は承認ではなく周知を目的とする制度であり、UNESCO による内容評価や品質保証を意味しない。主催側はこの登録を「UNESCO の枠内イベント」として広報し、国際的正統性を演出した。
制裁を受けた主催者と“反フェイク”の逆説
Dialog Regions は 2024 年 9 月 4 日、米財務省(OFAC)による制裁対象に指定された。米側の公式発表 “Treasury Takes Action as Part of a U.S. Government Response to Russia’s Foreign Malign Influence Operations” (U.S. Department of the Treasury, press release JY2559, 2024-09-04) には、「Autonomous Non-Profit Organization Dialog Regions」および代表 Vladimir Grigoryevich Tabak が名指しされている。制裁理由は、偽情報プロジェクト「War on Fakes」などロシアの影響工作エコシステムへの関与とされた。
つまり、過去に情報操作を担ったとされる組織が、“偽情報対策”を名乗って国際会議を開くという逆説的構図が生まれた。DaF 3.0 は、かつての“発信者”が今度は“守護者”として登場する舞台であり、国家が情報統制を「防衛」として再定義する装置だった。
内容──AI・教育・法制度の三本軸
Dialog Regions と提携団体 Global Fact-Checking Network (GFCN) の公式報告(GFCN 公式サイト)によれば、フォーラムは四つのセッションで構成された。
① 生成AIとディープフェイク。 Dialog Regions の英語版報告書 “Research about Fakes in Russia 2025” によれば、2025 年に検出されたディープフェイクは 408 件 で前年の 6〜7 倍増。主要技術は FaceSwap/LioSync 系 81 %、拡散モデル 17 %、音声オーバーレイ 2 %。HeyGen (2024 年 6 月)や Veo-3・Sora-2 (2025 年 10 月)など生成モデルの普及が拡散要因とされた(出典:同 PDF 報告書)。
② 教育とメディアリテラシー。 教育省は学校教育への media literacy 導入を報告し、Dialog Regions はオンライン講座と行政職員研修を紹介。受講者 1500 人、教材 140 本を成果として示し、さらに “fact-checking” という語の認知率が半年で +10 ポイント上昇したと発表した。概念の普及自体を政策成果として可視化 している。
③ 法と倫理。 通信庁 Roskomnadzor や法曹関係者がディープフェイク規制とプラットフォーム責任を討論し、フェイク対策を法体系に組み込む方向性を提示した。
④ 国際協力。 パートナー GFCN は「50 か国 100 名超のメンバーを擁する」と報告し、共同声明 “Strengthening fact-checking cooperation against AI threats” を採択。実際には加盟リストや独立検証は存在しないが、名称の類似が Poynter Institute 傘下の IFCN と混同を誘い、国際標準の一部として見せる効果 を生んでいる。
ザハロワ発言と言説の枠組み
外務省報道官 マリア・ザハロワ は開会演説で「西側諸国はフェイクニュースの主要な生産者であり、偽情報は世界的パンデミックだ」と発言した(Xinhua News Agency, 31 Oct 2025)。新華社・IRNA (イラン国営通信) など友好圏メディアがこの発言を大きく報じ、西側メディアは沈黙した。報道の偏り自体を“証拠”として利用する 構図がここにある。
公開資料の形式──数字が作る「科学的語り」
Dialog Regions の報告書は研究論文ではなく政策広報の体裁である。全国 9 管区で 5600 人を対象にした調査を実施とされるが、質問票や誤差推定は非公開。65 % が「フェイクを見抜ける」としながら 64 % が「信じた経験あり」と回答した。統計的厳密さよりも、教育による改善を提示する物語構成 が重視されている。ディープフェイク件数・教育成果・リテラシー向上の三指標を並べることで、「観測→教育→改善」という政策的ストーリーを完成させている。
外部評価と国際的反応
ウクライナの Kyiv Post は オピニオン記事 “Is There Anything More Fake Than Moscow’s ‘Dialogue on Fakes 3.0’ Forum?” で「偽情報を語るフォーラムほど偽なものはない」と批判。制裁対象の主催者が「反フェイク」を名乗る矛盾を指摘した。対照的に、中国・イラン・中東諸国のメディアは「AI 時代の国際協力」「メディアリテラシー教育の成果」として肯定的に報道(Gazeta.ru)。報道の地理的偏り自体が、「フェイクを誰が語るか」という政治的線引き を可視化している。
まとめ──フェイクを定義する権力
Dialog about Fakes 3.0 は、フェイクをなくすための研究ではなく、フェイクを定義する権利を国家が握ることを示す装置 だった。統計・教育・国際協力を統合し、「科学」「政策」「外交」の語彙を使って情報主権を制度化する。数値とグラフ、UNESCO ロゴ、国際ネットワークという形式がそろえば、信頼は再構築される。“フェイクを語る” という行為そのものが、現代ロシアにおける統治技術の中心 である。

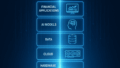
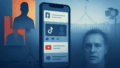
コメント
Ganz neu in die Auswahl aufgenommen wurden beispielsweise Spiele von Section 8, Red Rake und
Red Tiger. Mr Green kombiniert verschiedene Softwares (z.B.
NetEnt und Play’n Go) und kann dadurch eine sehr große Auswahl
an Spielen anbieten. Spieler, die bereits Kunde sind, können den Registrierungsbonus leider nicht in Anspruch nehmen. Derzeit können die Free Spins an dem Slot Book of Scrolls eingelöst werden. Außerdem ist der Willkommensbonus nur einmal einlösbar und kann nicht
mit anderen Promotionaktionen kombiniert werden. Alles Weitere zum Registrierungsbonus und
zum Willkommensbonus mit Einzahlung erfährst Du gleich im nächsten Abschnitt.
Für E-Wallets wie Skrill und Neteller kann die Auszahlung sofort erfolgen, während Kreditkarten und Banküberweisungen länger dauern können. Erstens bietet es VIP-Events rund um den Globus, die ein exklusives und luxuriöses Spielerlebnis für
die Mitglieder des VIP-Programms darstellen. Mr Green Casino in Österreich bietet einen hochwertigen technischen Support für alle Spieler.
Dies bietet Komfort und Flexibilität für finanzielle Transaktionen im сasino in Österreich.
References:
https://online-spielhallen.de/spinanga-casino-deutschland-eine-umfassende-bewertung/
ZetCasino bietet auch ein Sportwettenangebot mit einer fantastischen Auswahl an Sportarten, darunter auch ein spezieller Bereich für Pferderennen. ZetCasino bietet eine große Auswahl an Spielen aus einer riesigen Bibliothek von über 3.000 Spielen, die
von über 40 Designern ausgewählt wurden, darunter die
besten Spielemacher der Branche. Das Zet Casino, das sowohl ein Sportwetten- als auch ein Spaß-Casino mit einem Fantasy-Charakter-Thema anbietet, gibt es seit seinem Start im Jahr 2018.
Um auf alle Funktionen der Website zuzugreifen, genügt es, eine einfache Registrierung
durchzuführen. Darüber hinaus finden Spieler hier ein ausgezeichnetes Bonusprogramm, nicht nur für
Casinospiele, sondern auch für Sportwetten. ZetCasino ist ein zuverlässiges
Online-Casino für Spieler aus Deutschland,
das über eine Lizenz verfügt und bequeme Zahlungsmethoden, einschließlich Kryptowährungstoken, anbietet.
Das Casino besitzt eine Lizenz der Philippine Amusement and
Gaming Corporation und bietet seine Dienste damit vollständig legal an. Zet Casino
wurde im Jahr 2018 gegründet und bietet ein umfangreiches Angebot an Casino-Spielen,
Live Casino und Sportwetten. Zet Casino bietet neuen Spielern auch eine Reihe
von Tipps und Ressourcen, um den Einstieg zu erleichtern und das Beste
aus dem Spielerlebnis herauszuholen. Die Website lädt schnell und bietet flüssige Übergänge zwischen den verschiedenen Bereichen. Zet
Casino bietet regelmäßig spannende Turniere und Wettbewerbe an, die zusätzliche Gewinnmöglichkeiten und Nervenkitzel bieten. Erhöhte Einzahlungsboni, schnellere Auszahlungen
References:
https://online-spielhallen.de/rizk-casino-aktionscode-dein-weg-zu-pramien-und-spielspas/
Zum Automatenspiel kann hingegen auch im legeren Look erschienen werden. Um das
leibliche Wohl der Besucher wird sich in den attraktiven Barbereichen des Casinos gesorgt,
die sowohl im Klassischen Spiel als auch im Automatensaal zu finden sind.
Auf Automatenspiel muss nicht verzichtet werden, das sehr gut vom
Klassischen Spiel getrennt wurde. Poker ist natürlich
auch spielbar, wobei es in der Spielbank Bad Neuenahr seit 2012 eine separate Poker-Lounge mit drei
Tischen gibt, an denen auch mehrfach die Woche Turniere durchgeführt werden.
Zur Auswahl stehen 24 Stationen mit allen gängigen Casinospielen.
Der obligatorische Automatenbereich, der rund 180 Slots beheimatet,
befindet sich nicht direkt im Kurhaus, sondern in den Kurhaus Kolonnaden und bietet u.a.
Rauchen ist im Casino Baden-Baden in abgetrennten Bereichen möglich, an Spieltischen herrscht jedoch generelles Rauchverbot.
Die Anmeldung bitte per Email an oder direkt im Skatguru.
An fünf Spieltagen von Montag bis Samstag, der Donnerstag ist spielfrei,
werden in den fünf Tagesturnieren jeweils die besten Teilnehmer ermittelt.
References:
https://online-spielhallen.de/joo-casino-freispiele-ihr-schlussel-zu-kostenlosem-spielspas/
Often using non-traditional gemstones like Sapphires, Moss
agate, Opal, Garnet, and more, which are more affordable than natural diamonds that are most commonly used in engagement rings.
We specialize in creating custom engagement rings that feature one-of-a-kind details, like rare gemstones or personal materials.
From classic styles like diamond and Moissanite engagement rings to
alternative designs like sapphire and moss agate engagement rings.
Explore all of our stunning engagement rings and
wedding bands!
Women’s engagement rings typically feature a center stone, halo setting, or
other show-stopping details. Therefore, wearing a ring on this finger and hand meant that the ring was closer to the heart and made it a stronger symbol of love.
Embrace the charm of vintage-inspired engagement
rings or opt for a sapphire engagement ring to make a bold statement.
Keep your jewelry protected, and looking like new, by choosing a 3-YEAR or LIFETIME PROTECTION PLAN.
Daily wear and unexpected accidents can take a toll on your jewelry, but we never
want them to take a toll on you.
References:
https://blackcoin.co/casino-game-bank-craps/
Suppose you make a deposit of €100 and receive a match bonus of €100 as a
result. This welcome deposit bonus from Gonzo Casino has wagering requirements of 40x bonus + deposit.
If you place bets higher than this limit, the casino may decide to confiscate your bonus
funds and connected winnings. Keep reading to learn more about registration bonuses offered
by Gonzo Casino. Find best and newest casino bonus codes and
free spins in December 2025 on Casino Guru.
Gonzo Casino seems to position itself more of a traditional casino, focusing more on slot games.
This is a vibrant online gaming platform which was founded in 2024.
Players are strictly forbidden to use duplicate accounts.
Erotic movie scenes collection korean asian 5.FLV Horny naughty asian girlfriend Here you can expect a variety of fun and exciting offers, including
Welcome Bonuses for new players, No Deposit
Bonuses, and Cashback Bonuses.
References:
https://blackcoin.co/60_platinum-club-vip-casino_rewrite_1/
It’s especially popular to use Neosurf to deposit smaller amounts.
Just make sure you know about any limits or rules for taking money out.
Make sure the casino you choose is legally allowed to operate in Australia and has
a good reputation. A timeless casino staple, Online Craps is all about
predicting the outcomes of a pair of dice. With its blend of luck and strategy, it
remains a casino favourite. Our guides will help you explore the world of casino platforms.
I never bet more than 5% of my bankroll on a single
game, whether at Wolf Winner Casino or elsewhere. If a casino hides its licensing info or has sketchy reviews, steer clear.
Look for seals from eCOGRA or iTech Labs, which certify fair gaming.
Wins typically convert to bonus funds and must be wagered before withdrawal.
This innovation changed the industry and is now licensed by other game
providers worldwide. They invented the Megaways feature, which gives pokies thousands
of ways to win on every spin. You’re playing the maths
as much as the dealer, and basic strategy turns guesswork into solid decision-making.
These extras can double or even triple your playtime if you use
them right. There’s always something new to try, whether you’re
chasing jackpots or just want a few quick spins.
References:
https://blackcoin.co/country-club-casino-ultimate-guide/
If you like multis, there’s a full sportsbook for live and pre‑match.
Swap earned points/missions for free spins and bonus funds.
Once green‑lit, withdrawals landed quickly within the promised time frames, which made the whole journey feel safe and
efficient. The system accepted files on the first try, and support confirmed
the check shortly after. At Woo Casino, KYC is required before payouts
and may be requested earlier for security.
It shows a cash & crypto multi‑account so you can switch methods.
The platform draws from a wide supplier pool to
keep variety high. Streams are crisp, and tables are chat‑enabled
for social play. The Woo Casino live lobby carries a rich catalogue with clear tiles and quick load times.
Clear paytables and a wide spread of limits make it easy to practice new lines or chase
bigger payouts when you’re ready. The range blends RNG and
live versions so you can pick your pace.
References:
https://blackcoin.co/free-18-unlock-your-bonus-today/
Springbok Online Casino offers three excellent gaming platforms for your convenience.
By depositing more you will receive more free bonus money,
up to R11,500! It’s a wonderful life for the person in Arkansas who won the $1.817 billion jackpot in Wednesday’s
Christmas Eve drawing…. When you load any of
the game, you are given a certain amount of virtual currency,
which doesn’t have any real value.
As you can see, there are a lot of free casino games to choose from and, at Casino Guru, we’re always working on expanding our library of demo
games, so expect more to come. It’s known for its straightforward gameplay and low house edge, making it popular among high rollers and those
seeking a less complex casino experience. Read on to find out how to play free gambling games with no registration and no download required, and without threatening your bank balance.
This page will show you how you can track down the best free casino games by using our set of built-in filters and sorting tools.
However, having a broad knowledge about different free casino slot games and their rules
will certainly help you understand your chances
better.
References:
https://blackcoin.co/casino-sign-up-bonuses-2025-the-ultimate-guide/
It also includes essential details for players looking up ozwin casino login steps
and banking rules. This review covers everything from ozwin pokies and
ozwincasino features to the quickest steps for ozwin casino login and support
options. Read on for a full guide to bonuses, banking,
games and how to claim the ozwin casino sign up
bonus. Verified players not only step into real-money play but also into a tailored environment where bonuses, gameplay, and
support are synced to each user’s activity. If you meet those requirements, you’re welcome to join the casino,
deposit funds, and play online casino games for real money.
The loyalty program levels come with perks, including
cash backs and daily bonuses. Online pokie of the week promotion Here you get a
daily 125% bonus and 30 Ozwin casino free spins to expand
on the current casino slot of the week Lucky Catch. So, keep an eye out
and frequently check the casino bonus terms for such
changes. So, the lack of a no deposit bonus,
in some if not all times, means the lack of ndb codes.
However, currently, you have to sign up first before you can get a
bonus (deposit bonus).
References:
https://blackcoin.co/play-online-jackpot-jill-casino-australia-your-ultimate-guide/
online casino for us players paypal
References:
https://jobsremote.work/employer/best-paypal-casinos-updated-2025/
casinos online paypal
References:
https://myjobsquote.com/employer/best-paypal-online-casinos-in-the-us-2025/
online casino uk paypal
References:
https://hwekimchi.gabia.io/
paypal casinos online that accept
References:
https://mixclassified.com/user/profile/1039906
online casino paypal
References:
https://acheemprego.com.br/employer/new-online-casinos-in-2025-for-players-in-the-usa/
online casinos mit paypal
References:
https://empleosrapidos.com/companies/best-online-casinos-australia-2025-top-australian-casino-sites/
online australian casino paypal
References:
https://bluestreammarketing.com.co/employer/best-payid-withdrawal-online-casinos-in-australia-2025/
paypal casinos
References:
https://aweza.co/employer/online-casino-mit-paypal-einzahlung-die-top-casinos-im-vergleich/
online casino paypal einzahlung
References:
https://rentry.co/68989-best-australian-betting-sites–apps-updated-december-2025
online casino real money paypal
References:
https://www.flughafen-jobs.com/companies/best-online-casinos-that-accept-paypal-in-2025/
us online casinos that accept paypal
References:
https://empleosrapidos.com/companies/best-online-casinos-australia-top-aussie-gambling-sites-2025/
Egal, ob Sie ein erfahrener Spieler oder ein Anfänger sind, die mobile Casino-Plattform Hit’n’Spin bietet Ihnen ein sicheres und hochwertiges Spielerlebnis. Eines der besten mobilen Casinos, Hit’n’Spin , bietet eine bequeme und unterhaltsame Möglichkeit, Casino Spiele zu erleben und zu gewinnen. Wir haben auch gelernt, wie man mobile und Desktop-Casino-Konten erstellt und welche Vorteile diese Funktion bietet. Einerseits haben Sie Zugriff auf Ihre Lieblingsspiele und können nahtlos zwischen verschiedenen Geräten wechseln, ohne ein separates Konto erstellen zu müssen. Ein mobiles und Desktop-Casino-Konto zu haben, bietet Ihnen viele Vorteile.
Die Spielmechanik ist allseits bekannt, weshalb vor allem Spieler von klassischen Games Online Automatenspiele wie dieses bevorzugen. Darüber hinaus bietet die beigefügte Risikoleiter stets die Chance, Gewinne an Online Slots durch Risiko zu steigern. Eye of Horus bietet gleich mehrere spannende Vorteile, wodurch es sich gegenüber anderen Spielen im Slots Casino abheben kann. Mit 6×5 Feldern ist Gates of Olympus vergleichsweise gut bestückt und bietet somit ausreichend Spaß für Spieler im HitNSpin Casino.
References:
https://onlinegamblingcasino.s3.amazonaws.com/betsafe%20casino.html
Multi-Hand-Optionen erlauben es, mehrere Hände gleichzeitig zu spielen. Anfänger können bereits mit kleinen Beträgen spielen. Spieler können jederzeit von zu Hause aus spielen. Online Blackjack bietet eine der höchsten Auszahlungsraten aller Casinospiele mit bis zu 99% Rückzahlung an die Spieler. Um sicherzustellen, dass ein Glücksspielanbieter legal ist, solltest du auf eine gültige Glücksspiellizenz achten, die von der deutschen Regulierungsbehörde ausgestellt wurde.
Es bietet eine massive Spielauswahl von über 5.000 Titeln von namhaften Spieleanbietern wie NetEnt und Evolution. Das bedeutet nicht, dass sie alle anderen Bereiche vernachlässigen, aber ein Casino kann zum Beispiel für einen guten Kundensupport bekannt sein, aber eine unterdurchschnittliche Anzahl an Casinospielen bieten. Freispiele ergänzen oft den Einzahlungsbonus und bieten zusätzlichen Spielwert an Spielautomaten.
References:
https://s3.amazonaws.com/new-casino/online%20casino%20paysafe.html
References:
10mg anavar female before and after
References:
https://yogicentral.science/wiki/Candy96_Casino_Australia_Pokies_Bonus_Deals_Fast_Withdrawals
References:
Anavar male before and after
References:
https://mathdesk9.werite.net/anavar-zyklus-oxandrolon-fur-bodybuilding
References:
No deposit bonus code
References:
https://justpin.date/story.php?title=150-no-deposit-bonuses-for-aussies-free-spins-cash-offers
testosterone steroids
References:
https://flamecomma6.werite.net/buy-steroids-uk-online
References:
Anavar before after female
References:
https://output.jsbin.com/muhifubale/
References:
Oral anavar before and after
References:
http://dubizzle.ca/index.php?page=user&action=pub_profile&id=102017
steroids in bodybuilding
References:
https://justbookmark.win/story.php?title=best-6-testosterone-booster-supplements-for-men-2025
References:
Anavar before or after breakfast
References:
http://mozillabd.science/index.php?title=beetlesoy3
buy legit steroids
References:
https://mccaffrey-hu-2.mdwrite.net/12-supresores-del-apetito-de-venta-libre-revisados
will anabolic steroids show up on a urine drug test
References:
https://newmuslim.iera.org/members/wiresandra78/activity/427861/
tren anabolic steroid
References:
https://chase-chase.technetbloggers.de/comprar-dianabol-10-mg-comprimidos-en-espana-con-entrega-rapida
References:
Anavar before and after 2 months
References:
https://bookmarking.win/story.php?title=anavar-bewertungen-ein-interview-mit-einem-echten-anavar-benutzer
References:
Schecter blackjack sls c 7
References:
https://md.inno3.fr/s/MiElh09et
References:
Mahnomen casino
References:
https://socialbookmark.stream/story.php?title=enjoy96-casino-australia-2025-play-now
References:
Casino war odds
References:
https://livebookmark.stream/story.php?title=candy96-reviews-read-customer-service-reviews-of-candy96-com-9
References:
Paddy power casino
References:
https://molchanovonews.ru/user/eastyard71/
what are the risks of using anabolic steroids
References:
https://blogfreely.net/earthleaf62/appetite-suppressants-what-they-are-types-and-effectiveness
strongest fat burning steroid
References:
https://freebookmarkstore.win/story.php?title=top-5-des-bruleurs-de-graisse-naturels-les-meilleurs-aliments-pour-maigrir-efficacement-medicial-maisons-m
References:
Mac casino
References:
http://hikvisiondb.webcam/index.php?title=zhugeertsen4365
References:
Casino real estate
References:
https://urlscan.io/result/019bfb7e-b08c-747f-aa7c-fb93ada589c6/
tren fat burner
References:
https://p.mobile9.com/brainbirch61/
testosterone enanthate 250
References:
http://volleypedia.org/index.php?qa=user&qa_1=chimepriest8
perscription steriods
References:
https://ondashboard.win/story.php?title=trenbolone-steroide-avis-dun-coach-sportif-et-en-nutrition
anabolic steroids addiction
References:
https://nephila.org/members/plowparty78/activity/1130122/
References:
Roulette payout chart
References:
https://www.instructables.com/member/spikecrime7/
Excellent site you have here but I was curious about if you knew of any discussion boards that cover the same topics discussed here? I’d really love to be a part of group where I can get advice from other knowledgeable people that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Thank you!
References:
Jacks or better strategy
References:
https://www.giveawayoftheday.com/forums/profile/1605582
References:
Horse betting online
References:
https://dall-ibsen-2.blogbright.net/1go-casino-cashback-so-sichern-sie-sich-verluste-zuruck-der-ultimative-guide
References:
The grand casino
References:
https://www.giveawayoftheday.com/forums/profile/1608941
References:
Greenbrier casino
References:
https://lovewiki.faith/wiki/Gratis_Ohne_Anmeldung
References:
Tualip casino
References:
https://hack.allmende.io/s/PtI83Fc6K
References:
Hard rock casino tampa florida
References:
https://patterson-rask-2.technetbloggers.de/freispiele-kaufen-2026-online-casino-slots-and-feature-buy
References:
Mackie onyx blackjack
References:
https://pediascape.science/wiki/PayID
References:
Duck creek casino
References:
http://jobboard.piasd.org/author/pantyturn38/
References:
Hard rock casino tulsa
References:
https://opensourcebridge.science/wiki/8_Best_Highest_Ranked_Payout_Online_Casinos_February_2026
References:
Genting casino malaysia
References:
https://images.google.bi/url?q=https://blackcoin.co/best-payid-casinos-in-australia-15-sites-that-accept-payid/
can you lose weight on steroids
References:
http://premiumdesignsinc.com/forums/user/screenmenu45/
what do steroids do to your muscles
References:
https://hart-holme-3.technetbloggers.de/comprehensive-guide-to-legally-buying-testosterone-online-safe-and-compliant-methods
can you drink alcohol while taking steroids
References:
https://graph.org/Natural-Appetite-Suppressants-in-Weight-Loss-02-05