欧州委員会が2025年9月にまとめた『A Guide for EU Citizens Addressing the Risks of Disinformation』は、偽情報対策を「民主主義の自由を守る制度的防衛」として整理した文書である。ここで語られる偽情報は、虚偽情報の集合ではない。情報流通を支える環境そのもの──可視性、透明性、説明責任、救済手続──の欠陥として描かれる。EUはこの報告で、偽情報との闘いを「真実の判定」ではなく「制度の信頼性の維持」として再定義した。
情報インテグリティという転換点
報告書は冒頭で、偽情報を「政治的または経済的利益のために意図的に作成・拡散される虚偽または誤解を招く情報」と定義する。単なる誤報や風刺、明示的な党派的意見は含まれない。だが、意図の認定は常に恣意を伴う。そこでEUは2025年に入り、「information integrity(情報インテグリティ)」というより広い概念を導入した。焦点は個々の発言の真偽ではなく、民主主義を支える制度的条件の健全性である。
ガイドは、自由な討議・公正な選挙・多元的報道という三層構造を、情報環境の基本条件として定義する。偽情報はそのどこかを劣化させる仕組みとして現れる。対策は誤りを消すことではなく、公共討議が壊れない仕組みを維持することに置かれる。ここで「規制」とは統制ではなく、自由の前提を守るための技術的介入を意味している。
制度設計の全体像──EDAPの六領域
本書の主題は、European Democracy Action Plan(EDAP)の下で展開される偽情報対策の実装構造にある。各制度はばらばらに見えて、実際には六つの領域で一つの枠組みを構成している。
市民の権利とシビック教育
出発点は市民の権利の確保である。EUは、表現の自由と情報アクセスを基本権として保護しつつ、言論封じ訴訟(SLAPP)に対抗する仕組みを整備した。さらに、JRC(欧州共同研究センター)内に熟議民主主義の研究・実践拠点を設け、市民の政治参加を支える制度的基盤を築いている。報告書は、リテラシー教育を「情報を疑う技術」ではなく「制度を理解して使いこなす力」として描いている。
選挙と政治広告の透明化
政治広告規則は、スポンサー、支出額、ターゲティング理由、配信地域、AI生成素材の有無などの開示を義務化した。選挙関連の広告を誰がどのように操作しているかを市民が確認できるようにするものだ。DSA(Digital Services Act)はこの領域で中核的役割を果たす。プラットフォームは選挙リスクを体系的に評価し、緩和策を取る義務を負う。
ガイドは2024年のルーマニア大統領選挙を事例として挙げる。TikTok上でロシアが支援したとされる協調的キャンペーンが発覚し、憲法裁判所が第一回投票を無効とした。これは、プラットフォームの対応義務が司法的判断と接続した初のケースとされる。選挙の正当性を守るための制度的介入が、理論ではなく現実として作動した例である。
外国による干渉──FIMIへの転換
2014年以降のロシアによる干渉を受け、EEAS(欧州対外行動庁)は偽情報対策をFIMI(Foreign Information Manipulation and Interference)に拡張した。FIMIは「虚偽の内容」ではなく、「行動のパターン」に着目する。協調投稿、ボットネット、偽装メディア、資金経路など、情報操作を支える行動様式そのものを監視対象にする。
RTとSputnikの放送禁止は、この枠組みの延長線上にある。EU一般法院はこれを合法と判断したが、ガイドは同時に、表現の自由を侵害しかねない前例になるとの批判を記す。敵対国を想定した制度は、内部統制の口実に転じ得るという警戒を隠していない。
プラットフォーム規制と透明性
DSAは大規模プラットフォームに透明性報告、広告アーカイブ、リスク評価、外部監査を義務づけた。しかし、根本にあるセーフハーバー原則(編集責任を負わない仕組み)は維持されている。ガイドはここを「制度的限界」と明記する。アルゴリズムが実質的に編集行為を行っている現実と、責任の枠組みが一致していない。
EU対Xの調査はその矛盾を露わにした。欧州委員会は内部資料の提出とアルゴリズムの説明を求め、透明性監督の権限を実際に行使した。MetaやGoogleが署名した「偽情報対策コード」にXのみが署名を拒否したことも、共規制の信頼構造を揺るがしたと記されている。
ジャーナリズムの独立と多元性
EMFA(European Media Freedom Act)は、報道機関の編集独立と資金の透明性を法的に保障する。政府・企業・プラットフォームによる圧力を制度的に抑止する枠組みである。報告書は、報道を「民主主義のインフラ」として位置づけ、ニュースの可視性をアルゴリズムに依存させない制度的整備が不可欠だとする。
科学・知識・ポスト真実
COVID-19期に顕在化した科学的不信を、偽情報の一種ではなく、知識が公共討議に届かなくなる構造の問題と捉える。科学的助言や専門的知見が政治的操作や陰謀論に置き換えられる過程を制度的リスクとして扱い、科学コミュニケーションの枠組みを情報政策に組み込む方向が描かれる。
共規制という制度的ジレンマ
EUの偽情報対策は、国家が直接的に削除や検閲を行うのではなく、企業が自律的に対応し、それを当局が監査・評価する「共規制(co-regulation)」を採る。国家が距離を取ることで表現の自由を守り、同時に透明性と説明責任を確保する構造だ。だが、ガイドはその内在的矛盾を隠さない。削除や可視性制御の判断が企業に委ねられれば、民主主義の監視者が私企業に置き換わる。過剰な自主規制は萎縮を招き、過小な規制は公共圏を崩す。EUの立場はその中間に立つが、制度として常に均衡を取り直さなければならないと記されている。
市民の「操作権」と救済手続
D7.5が最も具体的に描くのは、市民に付与される新しい権限である。利用者は、推薦アルゴリズムを非プロファイリング型(時系列表示など)に切り替える権利を持ち、政治広告についてスポンサーやターゲティング理由を閲覧できる。政治的プロファイリングによるパーソナライズは禁止され、投稿削除やアカウント停止の際には理由開示と異議申立ての手続が保障される。
これらは単なるユーザー保護ではない。情報環境の可視性と制御権を市民に返す仕組みである。「なぜこの投稿が見えるのか」「なぜこの広告が届くのか」を自ら追跡できることが、偽情報対策の実効性そのものと結びつく。EUはこの「操作権(agency)」を、民主主義の技術的基盤として位置づけた。
残された構造的課題
ガイドは最後に、制度の限界を明確に書く。第一に、FIMIがロシア・中国を想定した敵対構造に基づく点。外部脅威を口実に内部統制が強化される危険がある。第二に、セーフハーバーの存続とアルゴリズム責任の不一致。情報流通を実質的に編集しているのが企業である以上、責任の所在が曖昧なままでは透明性は達成できない。EU自身がこの二つの問題を「未解決の構造的課題」として自認しているのは重要である。
まとめ
D7.5は、偽情報を「虚偽のコンテンツ」ではなく「制度の歪み」として扱う転換を明確に示した文書である。法規制、監査、報道保護、市民の操作権、研究者アクセスといった複数のレバーを組み合わせ、民主主義を構造的に守る仕組みを作ろうとしている。その一方で、自由のための介入が自由を脅かす可能性も正面から認める。
このレポートは、偽情報対策を倫理や検証の問題ではなく、制度設計の問題として読み替える試みだ。公共圏の信頼をどう維持するか。その問いを、市民、企業、国家の三者が共有するための枠組みとして、このガイドは書かれている。自由を守るための制度的自制──EUの偽情報政策は、いまその実験段階にある。

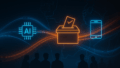
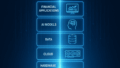
コメント
Die Registrierung bei PSK Casino in Österreich ist ein strukturierter und sicherer Prozess,
der Benutzern Zugang zu vielfältigen Glücksspielen ermöglicht.
Es wurde 2010 gegründet und bietet eine Vielzahl von Spielen, einschließlich Slots,
Tischspiele und Live-Casino-Spielen. Die App bietet ein breites Spektrum an Spielen, einschließlich der beliebtesten Slot-Spiele, Tischspiele und
Teilnahme an regelmäßigen Casino-Turnieren. Die Registrierung bei PSK Casino in Deutschland ist ein strukturierter und sicherer Prozess,
der Benutzern Zugang zu vielfältigen Glücksspielen ermöglicht.
Die PSK Casino App bietet eine umfassende Auswahl an Online-Casino-Spielen, darunter beliebte
Slot- und Tischspiele sowie regelmäßige Casino-Turniere.
Durchsuchen Sie alle von PSK Casino angebotenen Boni, einschließlich jener Bonusangebote, bei
denen Sie keine Einzahlung vornehmen müssen, und durchstöbern Sie auch alle Willkommensboni, die Sie bei Ihrer ersten Einzahlung erhalten werden.
Die Boni an den Spielautomaten in PSK sind großzügig, ich habe 50 Freispiele in dieser casino bekommen! Die Gewinnauszahlungen in PSK
sind schnell und problemlos, was bei einer casino wichtig ist.
Das Blackjack in PSK hat die besten Auszahlungsquoten, die
ich je in casinos gesehen habe. Sie müssen einen kroatischen Ausweis und
ein in Kroatien eröffnetes Bankkonto haben, um hier zu spielen
References:
https://online-spielhallen.de/f1-casino-erfahrungen-ein-umfassender-uberblick-fur-spieler/
Es ist unmöglich, jedes einzelne Spiel von dieser Sammlung zu spielen, aber der Spieler soll
die besten Spiele aussuchen. Um die Qualität
der Dienstleistungen aufrechtzuerhalten, sind hier die Angebote,
die Sie regelmäßig online in diesem Casino finden können. Nutzen Sie
den Bonus, der zu dem Spiel passt, das Sie spielen möchten, um Ihre Gewinnchancen bei den verschiedenen Spielen im MyStake-Online-Casino zu
maximieren. Wie bei den Slots, sind Registrierung und der Einsatz
von Echtgeld nötig, um zu spielen. Zu den Aktionen gehören außerdem das Live Casino Cashback,
wöchentliche Freispiele und der Willkommensbonus für Minispiele.
Im Hilfebereich finden Sie auch schnelle Antworten, beispielsweise wie Sie Anmeldeschleifen,
Aktualisierungsfehler oder nicht angezeigte Benachrichtigungen beheben können. Da Mystake Casino eine
Gerätebindung verwendet, müssen Sie Ihr Profil schnell bestätigen, um es sicher aufzubewahren, wenn
Sie ein neues Telefon erhalten. Wenn Sie Ihren Fortschritt im Casino auf dem besten Niveau halten möchten, wechseln Sie während
des Rollovers nicht von Einzahlungsspielen zu Spielen mit niedrigem Betrag.
Wenn Sie frühzeitige Zugangscodes und saisonale Drops erhalten möchten, die schnell ausverkauft sind, stellen Sie sicher, dass Sie Ihre E-Mail-Adresse hinterlegt haben.
Wenn der Spieler keine nützliche Lösung in MyStake F.A.Q.
finden kann, dann ist es empfehlenswert, Kundendienst per einen eingebauten Chat auf der Webseite zu kontaktieren. Der Spieler kann jeden Geldbetrag auszahlen lassen, den er auf seinem Geldkonto
sehen kann. Mit Hilfe von dieser Promotion kann der Spieler bis 15 % Cashback bekommen, wenn er Live Casino spielt.
There is no atmosphere as that found in land-based casinos.
They also provide attractive bonuses and promotions, as well as flexible
betting limits. Founded in 1999, Playtech is the world’s largest supplier of online gaming and sports
betting software. In 2020, Evolution acquired NetEnt,
making the company one of the largest players in the market.
Some of their most famous games include Starburst, Gonzo’s Quest,
and Mega Fortune.
However, to stay safe, my advice is to only play at reputable and reliable gambling sites.
You can check out all the casinos that failed to
make the grade right here on our list of sites to avoid.
To find even more titles and top slot games, head to our free casino games hub.
The best online casinos don’t skimp on security measures.
At Casinos.com, we only recommend licensed and
regulated online casinos. But of course, not all online
casinos are created equal. These games combine luck, strategy, and show-style energy
to deliver a one-of-a-kind casino experience. Online live casinos operate from studios, broadcasting a live
feed of the games. Bonuses are one of the main attractions of online casinos.
References:
https://blackcoin.co/online-casino-bonus-guide-in-australia/
You’ll see a couple ofdifferent colors. Access Microsoft 365 This link opens in a new window by logging in with your
SNHU email address and password.
We create all our clothes using breathable fabrics. Each outfit is a masterpiece, designed to make you feel fabulous, inside and
out. From XL to XXXL, our collection empowers you to
wear curves with confidence and style. Discover
a dazzling array of stylish threads, crafted for comfort and trendsetting appeal.
Finding the right fit should never be a struggle.
The developer, Google, indicated that the app’s privacy practices may include
handling of data as described below.
References:
https://blackcoin.co/casino-weather-your-comprehensive-guide/
It’s recommended to submit documents early to
avoid delays when withdrawing winnings. KYC approval generally takes between a few hours
and one business day, depending on the volume of requests.
Deposits via Visa and Mastercard remain available,
but approval rates depend on individual banks, a common situation across the Australian market.
Banking at WinSpirit is built around simplicity, although options remain more limited compared with some
larger Australian-facing casinos.
With its elegant interiors, state-of-the-art gaming facilities, and exceptional service, this casino is a
favorite among high rollers. From traditional table games to modern slot machines, this casino caters to
all preferences. With its extensive game selection and regular tournaments, Iveria Casino guarantees an exciting gaming experience.
With an RTP of around 96.0%, it’s a balanced option for players who enjoy steady payouts
and mid-variance gameplay. For Australian players, the
most commonly featured studios include Pragmatic Play, BGaming, Betsoft, Yggdrasil and Novomatic — all well-known for
reliable RTPs and diverse mechanics. Cashback is also frequently provided, giving players
a percentage back on net losses. These offers vary in percentage and maximum value and often come with free spins, especially during themed promotions such as weekend deals or
holiday events. The welcome package is structured to give players extra bankroll during their first
days on the site. WinSpirit is marketed as AU-friendly, offering
AUD as a primary currency, locally supported payment methods, and promotions tailored to the Australian market.
References:
https://blackcoin.co/real-money-casinos-in-australia-2025-play-win-for-real-aud/
Royal Reels Casino is an online gaming platform licensed by the Malta Gaming Authority (MGA),
ensuring a safe and regulated environment for players.
Yes, VIP players enjoy personalized promotions, faster withdrawal processing, exclusive event access,
and a dedicated account manager for enhanced gaming experiences.
Align bonuses with games you excel in, consider timing deposits to coincide with reload bonuses, so maximizing your
return plays become straightforward. As a new player, you’ll benefit from premium bonuses, dedicated customer support,
and innovative game offerings, all tailored to maximize enjoyment and your winning potential.
Besides the FAQ section, players can also contact the Royal Reels Casino customer support team directly
via live chat, email, or phone, providing prompt assistance and solutions to any issues that may arise during
their gaming experience. Royal Reels Casino entices players
with a range of enticing bonuses and promotions, including a
generous welcome bonus for new players and an exclusive VIP program designed to reward high rollers for their loyalty and gameplay.
Royal Reels Casino excels in its focus on pokie games, offering an immersive
and engaging experience with titles from top providers like
Spade Gaming and BetSoft, ensuring that players can enjoy a variety of themes and
gameplay styles. With its sleek interface and user-friendly navigation, Royal Reels Casino provides
a seamless online platform for players to enjoy a wide range of
casino games from the comfort of their own homes. Royal Reels Casino
has emerged as a prominent player in the online gaming industry, offering a diverse and engaging digital casino experience to players.
With over 2000 games to choose from, a focus on pokie games, and live dealer options, this casino is quickly making a name for itself in the Australian online gambling market.
By combining entertainment with stringent security measures, Royal Reels Casino stands out as
a trustworthy destination for online gaming enthusiasts.
Players at Royal Reels Casino can enjoy a seamless gaming experience knowing that their personal and
financial information is protected by top-notch encryption technology.
Players can easily navigate through the carefully curated categories present
in the FAQ section, such as payment methods, bonuses, technical issues, and more.
References:
https://blackcoin.co/roulette-tutorial/
gamble online with paypal
References:
https://rtmsjobs.com/employer/2025-top-paypal-casinos-instant-withdrawals/
paypal casino online
References:
https://job-bee.com/employer/62270/2025s-best-paypal-casinos-expert-verified-sites
online casino australia paypal
References:
https://classifieds.ocala-news.com/author/claudiochap
online blackjack paypal
References:
quicklancer.bylancer.com
paypal casino canada
References:
https://www.workbay.online/profile/florenehawks21
best online casino usa paypal
References:
manpowerassociation.in
online casinos mit paypal
References:
https://thelyvora.com/employer/online-casinos-that-accept-paypal-in-australia-2025
online betting with paypal winnersbet
References:
https://balajee.co.in/employer/new-online-casinos-of-december-2025-latest-nz-sites/
References:
3d roulette
References:
squareblogs.net
References:
Anavar test before after
References:
yogaasanas.science
References:
Anavar female cycle before and after
References:
ai-db.science
I’ll right away grab your rss feed as I can not find your e-mail subscription link or newsletter service. Do you’ve any? Kindly let me know in order that I could subscribe. Thanks.
References:
Aruba casinos
References:
https://historydb.date/
testosterone legal steroids
References:
gpsites.stream
do steroids help you lose weight
References:
sandoval-connor-2.federatedjournals.com
prime labs steroids
References:
socialbookmark.stream
anabolic steroids test
References:
dentepic.toothaidschool.com
what do steroids contain
References:
livebookmark.stream
References:
Anavar in women before and after
References:
coolpot.stream
References:
Test and anavar before and after
References:
scientific-programs.science
are steel supplements steroids
References:
marvelvsdc.faith
References:
Black jack gum
References:
bookmarking.win
References:
Casino sans telechargement
References:
nephila.org
%random_anchor_text%
References:
cameradb.review
where can you get anabolic steroids
References:
graph.org
References:
21 blackjack online
References:
https://escatter11.fullerton.edu
References:
Lucky eagle casino
References:
https://bandori.party/
is dianabol legal
References:
jobs.emiogp.com
how to get legal steroids
References:
obyavlenie.ru
anabolic steroid pills
References:
bookmarkfeeds.stream
top oral steroids
References:
https://pad.karuka.tech
References:
Aria casino
References:
forum.issabel.org
References:
Kahneeta casino
References:
https://peatix.com/
References:
Marksville casino
References:
squareblogs.net
References:
Online video poker
References:
telegra.ph
References:
Play craps online
References:
google.ps
References:
Tulsa casinos
References:
wikimapia.org