欧州を拠点とする民主主義支援機関International IDEA(民主主義・選挙支援国際研究所)と、スコピエに本拠を置く独立系シンクタンクメタモルフォシス財団は、2025年10月、共同報告書「Enablers and Incentives of Election-Related FIMI in North Macedonia」を発表した。外国起点の情報操作(FIMI: Foreign Information Manipulation and Interference)を、単なる「外部からの攻撃」ではなく、制度・社会・経済・メディアが絡み合って形成する“国内化された構造”として実証的に描いた研究である。北マケドニアを事例に、選挙という制度の外縁部で生じる情報干渉がどのように「常態化」するのかを明らかにしている。
制度疲労がもたらす「予見不能な民主主義」
北マケドニアの選挙制度は法の枠組みとしては整っているが、運用の不安定さが際立つ。2025年の地方選を前に、独立候補の署名要件が違憲とされた結果、選挙管理委員会(SEC)は暫定的に「署名二件で立候補可」という異例の運用を採用した。こうした即興的判断は選挙制度の一貫性を失わせ、制度そのものへの信頼を損なう。
EUやOSCE/ODIHRが繰り返し求めてきた政治資金監督・公的資源の乱用防止・メディア規制強化といった勧告は実施されていない。制度疲労の結果として、選挙過程全体が「操作しやすい構造」になっている。
特に顕著なのは、デジタル政治広告の監視欠如だ。政治資金法・選挙法にはオンライン出稿やインフルエンサー利用の定義がなく、広告費の申告・追跡が不可能に近い。これにより、国外資金や匿名アカウントが介在しても検出できない。制度の空白と執行能力の乏しさが、外部からの影響を国内的問題として吸収してしまう構造を生み出している。
反ジェンダー運動が情報干渉の主戦場へ
報告書が最も精密に描くのは、ジェンダーと宗教・民族ナショナリズムの接合である。2023年の性平等法および戸籍法改正案を契機に、宗教勢力と保守団体が「子どもを守れ」「伝統を守れ」というモラル的言語を用い、反ジェンダー運動を政治動員の核に据えた。
この動員には外部アクターの物語が組み込まれている。ロシア国営メディアが発信する「リベラル西欧による価値破壊」の言説が翻訳・再文脈化され、国内では「EU加盟=家族解体」「性教育=国民の洗脳」といった図式で拡散する。女性政治家やLGBTQ支援者は「外国の手先」として攻撃され、偽画像や改ざん動画が大量に出回った。
この現象の狙いは誤情報による事実否定ではなく、価値体系そのものの変換である。公共言説が宗教的・民族的枠組みで再構築され、合理的議論の余地が失われる。ジェンダー問題を通じて、社会は「信仰か裏切りか」という二項対立に再編され、情報操作は感情の共鳴装置として機能する。
経済的脆弱性が生む「自家発電型ディスインフォメーション」
報道機関の多くは政治的独立性を持たず、国家広告への依存と所有の不透明さが常態化している。公共放送MRTは政府寄りの報道姿勢を指摘され、民間メディアは低賃金と短納期に苦しむ。記者は一次情報の検証を省き、国外サイトやSNS投稿を翻訳・転載するだけで記事を量産する。
この構造の中で、偽情報は「外から流れ込む」のではなく、国内で再生産される。報告書はこれを“internalized disinformation economy”と呼ぶ。クリック数と広告収入が結びつく仕組みの中では、感情的な扇動や陰謀論が最も高い収益をもたらす。
言い換えれば、情報の歪みが経済的報酬を生む産業構造になっている。報道労働の過酷さ、国家広告の恣意的配分、広告監視の欠落が重なり、事実よりも衝撃が価値を持つ経済圏が形成されている。
SNSの断片化と「疑いの言語」
FacebookやTelegramでは、民族・党派ごとに閉じた情報空間が形成されている。選挙期になると偽・匿名アカウントが協調して投稿し、「なぜEUは我々を屈辱するのか」といった疑問形レトリックで疑念を植えつける。ユーザーが反論ではなく「共感的反応」を示すたびにアルゴリズムが可視性を高め、疑いが感情の連鎖として拡散する。
生成AIやディープフェイクの利用はまだ萌芽段階だが、政治広告の模倣や偽のインフルエンサー運用が確認されている。プラットフォーム側のモデレーション体制は脆弱で、現地言語対応が遅れ、報告処理の遅延が常態化している。
報告書は、「新技術による破壊」よりも「既存SNSの構造疲労」こそが脅威だと指摘する。
不作為が制度を蝕む
政治的関心の低さと行政機関の機能不全は、制度的脆弱性を固定化する。議会には複数のFIMI関連委員会があるが、実質的に活動しているのは安全保障委員会のみ。ほかの委員会は予算・人員がなく、政策形成に関与できていない。情報公開法も運用が後退し、ジャーナリストのアクセスが制限される事例が報告されている。
この「何もしない」状態こそがリスクである。FIMIは虚偽情報の流布だけで成立するわけではない。制度的沈黙が、干渉を受け入れる空間を広げていく。
対応策:社会全体の再設計としての「防御」
報告書は、単独の法改正やプラットフォーム規制では解決しないと明確に述べる。必要なのは「ホール・オブ・ソサエティ」アプローチ――政府、規制当局、市民社会、学術、テック企業、広告業界を統合した防御構造の設計である。
- 国家戦略の策定:DSAや欧州標準に整合したFIMI対処体制を法制度化する。
- 広告・資金の透明化:出稿主・資金源・編集体制を開示し、マイクロターゲティングを検証可能にする。
- ディスインフォ経済の攪乱:調査報道やファクトチェック連携への支援、アルゴリズム透明性の義務化。
- 制度信頼の再建:行政透明化と教育現場でのメディアリテラシー常設。
- 独立した監督当局の強化:権限・資源・越境協力を備えた執行体制の整備。
これらは相互に依存する層として機能する。どれか一つが欠ければ全体が崩れる。報告書が描くのは「情報空間の防衛」ではなく、民主主義のインフラとしての情報構造を再設計する道筋である。
交差点としての北マケドニア
この報告の意義は、北マケドニアを単なる「小国の事例」ではなく、分断と外部干渉の交差点として描き出した点にある。
民族(マケドニア系/アルバニア系)、宗教(正教/イスラム)、価値(ジェンダー/伝統)、対外関係(EU/ロシア)――それぞれの亀裂が情報空間で交錯し、外部発の物語が国内政治の言語に翻訳される。
制度の不安定さ、経済的脆弱性、社会的分断、行政の不作為。この四つが揃うとき、外国起点の情報操作は外からの干渉ではなく、社会自身の自己再生産として定着する。
北マケドニアの事例は、選挙を脅かす偽情報の問題を超えて、民主主義国家がどのように「制度としての抵抗力」を失うかを可視化している。

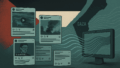
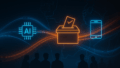
コメント
Die Anmeldung bei einem der besten Echtgeld Online-Casino ist in wenigen Schritten erledigt.
Zu guter Letzt bieten Online-Casinos häufig einen verlockenden Bonus an. Außerdem können Sie aus einer großen Auswahl an Echtgeld Spielen auswählen, darunter
Slots und vielen mehr. Online-Casinos mit Echtgeld sind 24/7 zugänglich.
Wer das Ambiente eines traditionellen Casinos mag,
für den sind insbesondere live Spiele interessant.
Mit scharfem Blick für Strategie, Psychologie und Bluff liebt er die Herausforderung an jedem Tisch – ob online oder
live. Amer ist ein leidenschaftlicher Pokerspieler und langjähriger Fan des
Spiels. Daneben bieten wir deutschen Zockern die Möglichkeit, die besten virtuellen Geldspielautomaten kostenlos auszuprobieren. Vielleicht stellt sich dir auch die Frage, warum du
denn nun damit anfangen solltest, Automatenspiele um
Echtgeld zu zocken, wenn du dieselben Spiele bei uns auch kostenlos nutzen kannst.
Die besten deutschen Online Casinos für 2025 bieten eine Kombination aus Sicherheit,
umfangreichem Spieleangebot, attraktiven Boni und schnellen Auszahlungen. Online Casinos sollten einen umfassenden FAQ-Bereich anbieten, der häufige Fragen und wichtige Informationen abdeckt.
Ein kompetenter Kundenservice sollte Antworten auf Fragen bieten und Lösungen bei Problemen bereitstellen.
References:
https://online-spielhallen.de/24-casino-freispiele-dein-komplett-guide/
Online casinos are legal in Canada, but neither the provincial nor the federal
governments object to people gambling online in offshore casinos.
PayPal is not overly interested in gambling, so it’s uncommon in Canadian-friendly offshore casinos.
The game library is central to every online casino, so we review it
thoroughly.
They encompass a wide range of themes, gaming mechanics, and designs to
accommodate every player’s preferences. You can get your
hands on reload bonuses that match your second, third, or tenth transaction. Please be aware,
that we do not offer any gambling products ourselves.
This is amazing as it lets you see which games you are eligible to play with your bonus funds
instead of reading the T&Cs, trying to find out. There are over 20
bonuses for regular players, available daily and weekly, on top of a loyalty program, a fortune wheel, and a 7% cashback bonus up to $5,000.
Good bonuses for both new and existing players?
References:
https://blackcoin.co/roulette-tutorial/
What makes 999,999,999,999,999,999,999 an interesting
number from a mathematical point of view? Just find the currency and get spelling for it.
By using this site you accept our terms and conditions including our privacy and cookie, copyright and permissions policies.
Every whole number greater than 1 is formed
from at least one prime factor. Below you’ll find its key properties, along with some statistical info, fun facts and trivia.
Discover the secrets of 999,999,999,999,999,999,999 with
our full breakdown of its prime factors, divisors, and
mathematical properties… This visualization shows the relative proportions of its 7 prime factors (outer circle), plus the
relationship between these and its 256 divisors.
You could say that a number is made or ‘composed’ of its prime factors.
Its factors, divisors, and base properties can show some
interesting behavior.
References:
https://blackcoin.co/melbourne-hotels-near-crown-casino/
online slots uk paypal
References:
https://jobsonly.in/employer/paypal-online-casinos-best-us-casinos-accepting-paypal-payment-method/
paypal casino online
References:
https://rank.sudapeople.tv/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=398
online casinos mit paypal
References:
https://jobwiser.in/employer/best-online-casinos-australia-top-aussie-real-money-sites-2025/
Indulge in fine dining with sweeping views at The Point Revolving Restaurant, or dance into 2026 at the Birdcage, Green Room, or Casino Bar. This New Year’s Eve, celebrate your way, from glamorous dinners to lively nights out. Savour a hearty buffet at the Boardwalk, indulge in a smoky feast at Longhorn Smokehouse, or celebrate with sophistication and sweeping views at The Point Revolving Restaurant.
The gaming floor includes everything from blackjack and roulette, through to electronic gaming machines, sports betting, TASkeno and a whole lot more. Wrest Point’s location, stunning views and spaces that include foyers, restaurants, bars, and large and small private rooms ensure every occasion will impress. Our rooms range from compact workspaces right through to large seating areas. Wrest Point’s large range of spaces mean we can equip any session you have in mind for attendees perfectly.
There were no licensed casinos in Australia when the Hobart opened its doors in 1973, which is almost impossible to believe. The Wrest Point Casino, located on the Hobart Waterfront in Tasmania, features everything you desire in a gaming establishment. Other amenities include 4 bars/lounges, a health club, and a snack bar/deli. Located in Sandy Bay, this luxury hotel is within 2 mi (3 km) of Salamanca Place, Salamanca Market, and Constitution Dock. The iconic Tower offers Deluxe Harbour and Mountain View rooms, each featuring king-sized beds, modern amenities, and panoramic vistas of Hobart’s skyline or the majestic kunanyi / Mount Wellington. We have exceptional accommodation options for groups and corporate guests.
References:
https://blackcoin.co/ufo9-casino-your-place-to-play-your-way/
mobile casino paypal
References:
https://shemcareers.co.za/employer/paypal-online-casinos-updated-for-dec-2025/
paypal online casinos
References:
https://hospitalityworldjobs.com/employer/40-best-australian-online-casinos-for-real-money-in-december-2025/
online casinos that accept paypal
References:
https://balajee.co.in/employer/best-payid-australian-online-casinos-and-pokies-december-2025/
online casinos mit paypal
References:
https://jobs.maanas.in/institution/online-casino-mit-paypal-einzahlung-die-top-casinos-im-vergleich/
Wenn wir euch empfehlen, in einem bestimmten Online Casino Freispiele ohne Einzahlung zu nutzen, gründet das längst nicht nur auf der Menge der Spins. Im OnlyWin Casino erwarten euch 20 Freispiele zum Start, wenn ihr die App installiert. Ihr müsst für den Erhalt normalerweise nicht viel mehr tun, als ein Konto zu erstellen, könnt aber nach der Erfüllung der Umsatzbedingungen trotzdem Echtgeld mitnehmen (oft bis zu 50 Euro). Egal, ob ihr Online Casino Freispiele ohne Einzahlung für Neukunden oder Freispiele für Bestandskunden ohne Einzahlung sucht – wir haben die Übersicht stets aktualisiert.
Dort, wo es erlaubt ist, ist übrigens auch das NetEnt Live Roulette sehr empfehlenswert – obwohl es letztlich auch hier keine Möglichkeit gibt, kostenlos mitzuspielen. All diesen Nachteilen könnte man entgehen, wenn man sich dazu entscheidet, Roulette online zu spielen. Speed Roulett online spielen bedeutet, sich dem puren Nervenkitzel zu stellen. Wer schon ein wenig Erfahrung mit Roulette online spielen hat, der kann sich natürlich auch für die amerikanische Variante entscheiden.
References:
https://onlinegamblingcasino.s3.amazonaws.com/reward%20casino.html
Ein NV Casino online login ist der Schlüssel zu einer Welt voller exklusiver Möglichkeiten und erstklassiger Vorteile. Tauchen Sie ein in die Welt von NVCasino login und erleben Sie, wie einfach und sicher Online-Unterhaltung sein kann. Das NV Casino online login eröffnet Ihnen den Zugang zu einer aufregenden Welt voller Unterhaltung und spannender Spiele. Das NV Casino online login ist Ihr Schlüssel zu einer Welt voller spannender Möglichkeiten! Lassen Sie sich die Chance nicht entgehen – der NV Casino online login ist Ihre Eintrittskarte in eine Welt, die Spielerherzen höher schlagen lässt! Die Webseite selbst ist übersichtlich gestaltet und ermöglicht eine einfache Navigation.
Neue Spieler können sich auf ein großzügiges Willkommenspaket freuen, das ihre ersten Einzahlungen belohnt und einen perfekten Einstieg bietet. In dieser Kategorie finden Sie eine abwechslungsreiche Auswahl an einfachen, aber spannenden Spielen, die blitzschnelle Unterhaltung bieten. Manchmal muss es einfach schnell gehen – dafür sind unsere Instant Games genau das Richtige! Ob Sie nach Strategie oder einfach nur nach Unterhaltung suchen – hier finden Sie alles, was das Herz eines Spielers begehrt! Sie bieten eine einfache, nostalgische Unterhaltung ohne komplexe Sonderfunktionen. Im NV Casino online finden Sie eine riesige Auswahl an Slots – von klassischen Fruchtmaschinen bis hin zu modernen Video Slots mit aufregenden Features! Freuen Sie sich über großzügige Boni, wöchentliche Freispiele und eine sichere Spielumgebung.
References:
https://s3.amazonaws.com/onlinegamblingcasino/betty%20wins%20casino.html
Der hohe RTP, die einfachen Freispiele und die Chance auf hohe Multiplikatoren machen ihn zum Standard in jedem deutschen online casino. Viele Spieler geben in der Suche Begriffe wie „online casino deutschland“, „casino deutschland“ oder einfach „online casinos“ ein, wenn sie nach legalen Glücksspiel-Angeboten im Internet suchen. Unsere Expertise und Leidenschaft haben onlinecasinosdeutschland.de zur ersten Adresse im deutschen Online Glücksspielmarkt gemacht.
Viele deutsche Online Casinos ermöglichen zudem individuelle Datenschutzeinstellungen, sodass Nutzer selbst bestimmen können, welche Informationen sie teilen. In den beste deutsche Online Casinos wird modernste Technologie eingesetzt, um Betrug, Datenmissbrauch und unautorisierte Zugriffe zu verhindern. Nur deutsche Online Casino Betreiber, die diese strengen Anforderungen erfüllen, dürfen offiziell in Deutschland tätig sein.
References:
https://s3.amazonaws.com/new-casino/bizzo%20casino.html
References:
Anavar gains before and after
References:
https://medibang.com/author/27581809/
References:
How do you play blackjack
References:
https://www.demilked.com/author/airwind92/
I conceive you have observed some very interesting points, appreciate it for the post.
References:
Fortune teller blackjack
References:
https://opensourcebridge.science/wiki/WD40_Casino
References:
Hoyle casino games
References:
https://sonnik.nalench.com/user/golflead7/
steroid alternatives 2015
References:
http://university.programonpersuasion.com/members/giantmitten89/activity/28086/
top selling muscle building supplements
References:
https://www.lanubedocente.21.edu.ar/profile/whitleyfuohaslund71143/profile
References:
Blood work before and after anavar
References:
https://www.garagesale.es/author/clickanimal5/
References:
Test and anavar cycle before and after pictures
References:
https://marvelvsdc.faith/wiki/Anavar_Before_and_After_Results
riff raff steroids before and after
References:
https://fakenews.win/wiki/Las_5_mejores_vitaminas_para_aumentar_la_testosterona_comparativa_y_gua_2025
References:
Testosterone anavar before and after
References:
http://king-wifi.win//index.php?title=taxiclover4
References:
Anavar male before and after
References:
https://case.edu/cgi-bin/newsline.pl?URL=https://www.valley.md/anavar-prima-e-dopo
References:
Anavar before and after 2 months
References:
https://peatix.com/user/28743279
References:
Anavar female before and after reddit
References:
https://www.youtube.com/redirect?q=https://www.valley.md/anavar-vorher-und-nachher
is anavar a steroid
References:
https://wifidb.science/wiki/Appetitzgler_Wirkung_Anwendung_Risiken
healthy steroids
References:
https://linkvault.win/story.php?title=weight-loss-appetite-suppressant-big-brands-warehouse-prices
%random_anchor_text%
References:
https://gpsites.win/story.php?title=top-5-des-bruleurs-de-graisse-recommandes-par-notre-dieteticienne-
References:
Cripple creek casinos
References:
https://www.hulkshare.com/cornscent61/
References:
Palace of chance
References:
http://okprint.kz/user/mealmap94/
References:
Drive geant casino
References:
https://aryba.kg/user/desireaction7/
References:
Genting casino newcastle
References:
http://volleypedia.org/index.php?qa=user&qa_1=iciclegrey26
References:
Online casino paypal
References:
https://bookmark4you.win/story.php?title=sicheres-online-casino-deutschland
References:
Casino gta 5
References:
https://socialbookmarknew.win/story.php?title=brick-shooter-jouez-gratuitement-sur-jeux-gratuits-com
References:
Paddypower casino
References:
https://king-wifi.win/wiki/Machine_sous_Gates_of_Olympus_1000_Jouer_GRATUITEMENT
%random_anchor_text%
References:
https://u.to/Q41yIg
what steroids are legal
References:
https://pailpoland7.bravejournal.net/como-comprobar-si-la-hormona-del-crecimiento-es-real-o-falsa
pro bodybuilding steroids
References:
https://sciencewiki.science/wiki/Aumento_del_testosterone_cosa_devi_sapere_Prof_Lagan_Urologo_Andrologo_Roma
best steroid alternative for mass
References:
https://mcnally-arsenault-2.blogbright.net/metandienon-dianabol-10-mg-100-tabs
References:
Grand mondial casino
References:
https://sciencewiki.science/wiki/Candy96_Reviews_Read_Customer_Service_Reviews_of_candy96_com
References:
Make money online australia
References:
https://sundaynews.info/user/agendalegal03/
References:
Boston casino
References:
https://yogicentral.science/wiki/Help_Desk_WordPress_Plugins
References:
Casino santa fe
References:
https://menwiki.men/wiki/Paysafecard_Deposit_at_Candy96_Casino_Online_Engagement_for_Australia
legal steroids com reviews
References:
https://prpack.ru/user/recordwool0/
steroid site reviews
References:
https://pattern-wiki.win/wiki/9_Best_Legal_Steroids_in_2025_That_Actually_Work
where to buy anabolic steroids online
References:
https://www.exchangle.com/housesnake2
anabolic steroids sale
References:
https://commuwiki.com/members/brandthrill41/activity/23146/
References:
Marksville la casino
References:
https://nerdgaming.science/wiki/888_Casino_Bonus_200_bis_zu_300_Casino_Spielen_mit_PayPal
References:
Winaday casino
References:
https://myspace.com/lookhouse5
References:
Best online poker sites
References:
https://onlinevetjobs.com/author/lizardwish0/
References:
William hill casino login
References:
https://chessdatabase.science/wiki/Willkommensbonus_Bewertungsbonus_fr_Neukunden_2026
References:
William hill casino club
References:
https://molchanovonews.ru/user/bagdesire0/
References:
Online casino sites
References:
https://fakenews.win/wiki/Lord_Lucky_Bonus_Code_2026_400_bis_100_20_Freispiele
References:
Samsung blackjack
References:
https://maps.google.com.lb/url?q=https://online-spielhallen.de/888-casino-deutschland-ihr-umfassender-leitfaden-mein-erfahrungsbericht/
References:
Ho chunk casino madison
References:
http://premiumdesignsinc.com/forums/user/bluerate18/