インターネットが進化するにつれて、私たちの行動や選択が経済に与える影響についての議論が深まっています。2006年にDoc Searlsが提唱し、2012年に出版された著書『The Intention Economy: When Customers Take Charge』で詳細に述べられた「意図経済」は、消費者が自身の意図を主体的に表明し、それに企業が応答する新しい経済モデルとして注目されました。
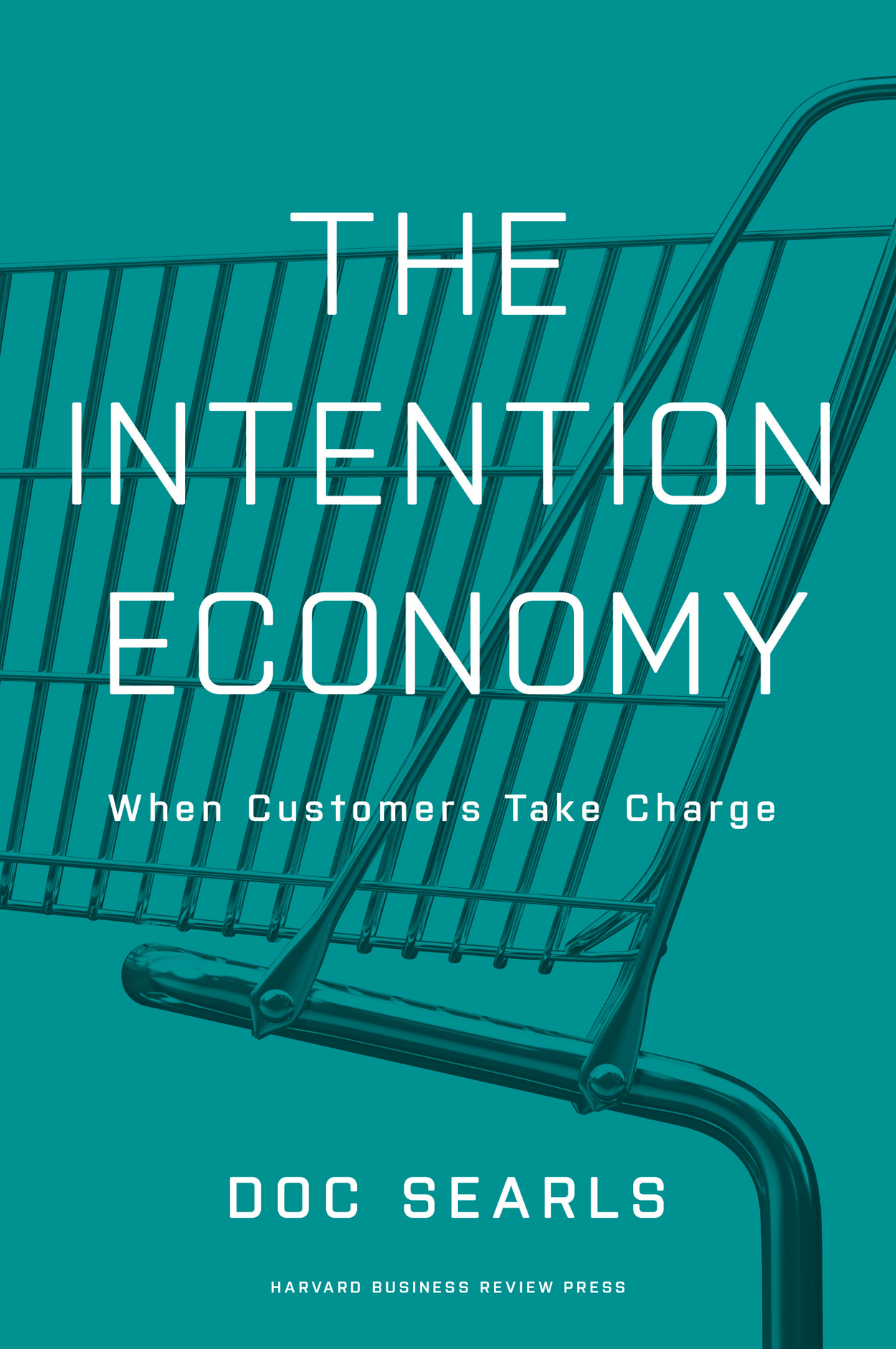
しかし、2020年代の生成AIや大規模言語モデル(LLM)の急速な進化によって、「意図経済」は新たな段階に突入しています。このブログでは、ハーバードデータサイエンスレビューに掲載された「Beware the Intention Economy: Collection and Commodification of Intent via Large Language Models」(公開日:2024年12月31日)という論文を紹介し、Searlsのビジョンとの違いを探ります。
Searlsの「意図経済」とは
Doc Searlsが提唱した「意図経済」は、消費者が自身のニーズや目的(意図)を積極的に表明し、それに応じて企業が適切な提案を行うという仕組みです。このモデルでは、消費者が主導権を握り、選択の自由と市場の透明性が強調されます。たとえば、旅行者が「次のバカンスのアイデアを探している」と意図を表明すれば、それに基づいて宿泊施設やフライト情報が提示されるというものです。
このアプローチは、消費者と企業の関係を対等にし、双方にとって利益のある市場形成を目指すものでした。
論文が描く「意図経済」の新たな形
今回の論文では、生成AIやLLMが中心となり、新しい「意図経済」が形成されつつあると議論されています。この「意図経済」は、従来の消費者主導のモデルとは異なり、企業主導で意図が収集・商品化されることを特徴としています。
1. 意図の収集と商品化
生成AIは、ユーザーの行動や会話から意図に関連するデータを効率的に収集し、商品化する能力を持っています。
- 明示的な意図と暗黙的な意図:
明示的な意図とは、例えば「特定の商品を買いたい」という具体的なニーズです。一方、暗黙的な意図は、ユーザーの言葉遣いや対話の文脈から推測される潜在的なニーズや動機です。 - 技術の進展:
生成AIは、大量の対話データを分析することで、個々のユーザーの好みや行動パターンを深く理解できます。例えば、OpenAIのカスタムGPTは、特定の業界や分野に特化したモデルを提供することで、ユーザーの意図データを細分化して収集します。 - 具体例:
Metaが開発したAIエージェント「CICERO」は、ゲーム「Diplomacy」で人間プレイヤーの意図を推測し、戦略的な交渉を行う能力を示しました。これにより、AIがユーザーの意図をどれほど精密に理解できるかが実証されています。
2. 意図の操作
生成AIが単に意図を収集するだけでなく、それを「操作」する能力を持つ点が強調されています。
- ユーザーの行動誘導:
AIがユーザーに提供する選択肢や情報の提示方法によって、意図を自然に誘導することが可能です。例えば、旅行の計画中に特定のホテルを目立つ形で提示することで、ユーザーの選択を影響下に置くことができます。 - 商業的応用:
NVIDIAが開発したリアルタイム広告システムでは、生成AIがユーザーの対話やクリックデータを分析し、瞬時に最適な広告を生成します。これにより、ユーザーの購買意図を操作する新たな形の広告技術が実現されています。
3. 社会的リスク
こうした技術の進化が社会に及ぼすリスクについても警鐘を鳴らしています。
- 選挙や世論操作:
AIが意図データを利用して特定の政治的メッセージを拡散することで、選挙干渉や世論操作が行われる可能性があります。これは民主主義の根幹を揺るがすリスクを孕んでいます。 - プライバシー侵害:
AIが個々のユーザーの意図データを詳細に把握し、それを商業目的で活用するプロセスは、プライバシーを侵害する可能性があります。これに対しては、規制や倫理的監視の必要性が指摘されています。
「意図経済」の構造の変化
この新たな意図経済では、従来の「消費者が意図を表明し、企業が応答する」という双方向モデルが崩れ、「企業が消費者の意図を推測し、操作する」という一方向的な構造にシフトしています。特に生成AIがその推進力として機能しており、消費者の選択の自由や意思決定に対する影響が懸念されています。
Searlsの反論:真の意図経済とは
Doc Searlsは2024年12月30日、自身のブログ「Doc Searls Weblog」で「The Real Intention Economy」という記事を公開し、生成AIを中心とした新たな「意図経済」の定義に反論しました。
彼は、生成AIを活用した「意図経済」が、彼の提唱する「消費者主導」のモデルとは根本的に異なることを強調しています。Searlsの「意図経済」では、消費者が自由意思を持って意図を表明し、それに企業が応答する双方向的で公平な市場が描かれていました。しかし、論文が描く意図経済は、消費者の意図を商品化し、企業が操作するリスクを含んでいます。
Searlsは、論文の著者たちに対し、自身の提唱した概念を誤用しないよう、新たな名称を用いることを求めるとともに、消費者の自由とプライバシーを守るための倫理的議論を呼びかけています。
結論
Searlsが描いた「意図経済」は、消費者が主導権を持つ経済モデルとして期待されましたが、生成AI時代における意図経済は、企業主導で進化しつつあります。論文が指摘するリスクは、消費者の自由や社会的公平性に深刻な影響を与える可能性を孕んでいます。
この変化にどう向き合うべきか、私たちは今一度、技術の倫理的利用について考える必要があります。生成AIの進化がもたらす意図経済の未来は、Searlsのビジョンに近づくのか、それとも異なる方向へ進むのか、これからの議論が鍵を握るでしょう。



コメント
I’ve been searching for information on this topic for ages, thanks.
Your dedication and enthusiasm resonate in every section you pen. It’s absolutely commendable.
Your approach is welcomed and unique.
Can I simply say what a aid to find someone who truly is aware of what theyre speaking about on the internet. You definitely know easy methods to bring a difficulty to gentle and make it important. More folks have to learn this and perceive this aspect of the story. I cant believe youre not more well-liked because you undoubtedly have the gift.
Its great as your other blog posts : D, thanks for putting up.
You have brought up a very superb points, thanks for the post.
Hiya, I am really glad I’ve found this information. Today bloggers publish only about gossips and net and this is actually frustrating. A good site with exciting content, that is what I need. Thank you for keeping this web site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.
Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I’ll be sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I will certainly return.
I am often to blogging and i really appreciate your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for new information.
You are my inspiration, I have few blogs and sometimes run out from post :). “The soul that is within me no man can degrade.” by Frederick Douglas.
I like this website very much, Its a really nice spot to read and obtain information. “If at first you don’t succeed, you’re running about average.” by M. H. Alderson.
Some really select articles on this internet site, saved to bookmarks.
Hier erhalten Sie ein festes Bonusguthaben (z. B. 10 €), das Sie für
bestimmte Spiele verwenden dürfen. Das beschleunigt den Ablauf und Sie erhalten Ihre Gewinne oft schon in wenigen Minuten oder
Stunden. Die besten Chancen, solche Umsatzbedingungen zu vermeiden, haben Sie, wenn Sie Freispiele ohne Einzahlung nutzen.
Dann solltet ihr einen Blick auf die zahlreichen weiteren Wettanbieter Boni werfen,
die euch die Buchmacher zur Verfügung stellen. Daher empfehlen wir euch regelmäßig bei unserem Wettanbieter
Vergleich vorbeizuschauen. Auf MyWettanbieter.de haben wir uns dennoch auf die Suche begeben und zumindest eine kleine Auswahl für
euch zusammenstellen können. Denn die beliebte Bonusart wird nur von den wenigsten Wettanbietern bereitgestellt.
Damit sichert sich der Wettanbieter gegen zu hohe Verluste ab,
während in der Regel dennoch die Chance auf lukrative Gewinne habt.
Nur in Ausnahmefällen können sich Bestandskunden ebenfalls
einen No Deposit Bonus sichern – auf MyWettanbieter.de halten wir
euch auf dem Laufenden.
Der Einzahlungsbonus ist die bekannteste Form des Wettanbieters
Bonus. Die Wettanbieter bieten beinahe täglich neue Bonusangebote –
dazu gehört auch der Sportwetten Bonus ohne Einzahlung.
Dieses erhaltet ihr meist direkt nach der Registrierung bei einem Wettanbieter als
Teil des Willkommensbonus.
References:
https://online-spielhallen.de/bing-bong-casino-freispiele-ihr-weg-zu-kostenlosem-spielspas/
Die feine Terrasse des Inselhotel Lindau bietet einen Blick
auf den See und verspricht eine malerische Umgebung.
Jede Boutique-Unterkunft bietet einzigartige Rückzugsorte am See, die Ihren Besuch bereichern. Die Erkundung
der nahegelegenen Boutique-Hoteloptionen rund
um die Spielbank Lindau bietet eine Vielzahl von exquisiten Speiseerlebnissen am See, die
unterschiedlichen kulinarischen Vorlieben gerecht werden.
Die Spielbank Lindau bietet eine vielfältige Auswahl
an Spielen, darunter Top-Titel wie Book of Ra Deluxe, Starburst, Roulette
Pro, Power Blackjack und Mega Moolah. Unsere mobile Plattform bietet nahtlose Navigation und blitzschnelle Ladezeiten,
sodass Sie keinen Spin oder Einsatz verpassen. Unsere Seite bietet eine
nahtlose Benutzeroberfläche, blitzschnelle Auszahlungen über
Krypto und eine starke deutsche Lizenzierung, die Fairness und Sicherheit gewährleistet.
Die Spielbank Lindau legt großen Wert auf Barrierefreiheit und
bietet umfassende Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen. Beide Optionen sind nur
wenige Gehminuten von der Spielbank entfernt und bieten ausreichend Parkmöglichkeiten.
Auf 1.750 Quadratmetern, verteilt auf zwei Ebenen, finden die Gäste hier ein erstklassiges Angebot an Tisch- und Automatenspielen vor.
In 2024 konnte insgesamt ein Bruttospielertrag von rund 129,6 Millionen Euro in allen neuen Spielbanken erzielt werden. In jedem dieser Häuser erwarten die Gäste
neben Glücksspielen und ausgewählter Gastronomie auch exklusive Events
und Veranstaltungen, die einen Besuch zum unvergesslichen Erlebnis machen. Das Spielcasino Lindau überzeugt mit einem erstklassigen Glücksspielangebot und einem gelungenen Unterhaltungsprogramm.
Automatenspieler kommen hier ebenso auf ihre Kosten wie Fans von Roulette, Blackjack und Poker.
References:
https://online-spielhallen.de/casino-venlo-aktionscode-maximieren-sie-ihre-spielerfahrung/
Star casino Brisbane promises to become not just a place for gambling but a hub of cultural and entertainment events, attracting both
locals and guests from around the world. The opening of the renovated Star casino
Brisbane will not only mark the completion of a major project but also open new opportunities for the city’s development.
The opening of the renovated Star casino Brisbane is anticipated with great interest not only by gamblers and entertainment enthusiasts but also by the business community.
Springfield Central Fireworks, 9pmThe best viewing sites are Ovals C,
D, E, F, G and H.Springfield Central Sports Complex, Sportstar Drive, Springfield Central, 9pm.
Providence Twilight Picnic in the Park, South Ripley, 9pmProvidence has a DJ,
food trucks, face painting and inflatable fun as well as a view of the
9pm Ripley fireworks display.22 Harmony Crescent, South Ripley, 6-9.15pm.
Miami Twilight NYE, 8pmThorn Park will have market stalls, trackless
train, DJs, bubble zone, craft, face painting and food
trucks, with fireworks at 8pm.Thorn Park,
Marine Parade, Miami, 4-8.15pm. New Year’s Eve in Coomera, 8pmCoomera Sports Park hosts a celebration with DJ, food trucks,
kids’ activities and 8pm fireworks.35 Beatie Road, Coomera, 6-8.15pm.
Broadbeach, 8pm & 12amHave dinner at one of Broadbeach’s top-notch restaurants near
Kurrawa Pratten Park, then watch the fireworks.Pratten Park, Broadbeach, 8pm-12.15am.
Mooloolaba Esplanade, Mooloolaba, 8.30pm & 12amBecause of
the construction works along Mooloolaba Esplanade the fireworks will be fired from an offshore barge in front of the HMAS Brisbane
Lookout.
Queen’s Wharf BrisbaneEntry is on a first-come basis and the recommended viewing spot is The Landing, with
5000 people expected. The year may have ended on a sombre note in parts
of the country, but fireworks will ring out in hope of a happier 2026
across Brisbane and south-east Queensland on Wednesday, December 31.
To access exclusive rates on hotel stays and benefits during your stay, download the Friends of Calile app.
Designed for people who know what they want – people who’ve seen average,
but don’t plan to settle for it.
References:
https://blackcoin.co/bars-the-classic-slot-machine-theme/
The three things these games have in common are that their RTP is very high (usually 98%+),
the gameplay is quick, and they all offer a different type of
gameplay. This adds yet another element to playing casino games,
and I’m all in for this one. This really feels like you’re not just gambling – but you’re playing a
game and completing missions that get harder and harder as
you progress, while the rewards get bigger and bigger.
Many of the top gambling sites in Australia now have
a fully gamified system with challenges and quests that you can complete to
earn real money prizes. Okay, yes, it’s good that all players are eligible for cashback (starting at 5% and going up depending on losses), but we need to be
real that very, very few can actually benefit from this offer.
Experience classic European, French, and American Roulette games on your
PC or mobile device, or explore modern variations like Double Ball
Roulette at new casinos. In games like Infinity Blackjack, you can challenge the dealer while competing against fellow players.
Enjoy an amazing selection of 1000+ games with
RTPs up to 99%, attractive bonuses, and instant cashouts.
As a top online casino in Australia, Casino Bros is giving you
hard stop-limits, cooling-off periods, reality checks and one-click self-exclusion, all visible in your account hub.
When you type “online casino in Australia”, you’re really asking for safety, smooth UX, and promos
written in English, not legalese. Still hunting for the best
online casino in Australia instead of actually playing?
References:
https://blackcoin.co/casino-bonus-ohne-einzahlung/
online roulette paypal
References:
careerjungle.viakasi.co.za
paypal casinos for usa players
References:
https://imgo.cc
I am impressed with this internet site, real I am a fan.
online australian casino paypal
References:
https://www.jobv3.com/companies/best-online-casino-payouts-in-2025-highest-paying-sites-98/
online casino that accepts paypal
References:
https://jobsahi.com/employer/best-online-casinos-in-australia-2025-bnc-au
And if you’re playing with crypto, even better — that adds another layer of protection most Aussie sites don’t offer.
When it comes to safety, Rocketplay doesn’t
cut corners. You won’t find any dodgy game results here everything’s
tested by third-party labs like iTech Labs or GLI to keep the
pokies honest. From the get-go, Rocketplay feels like
it’s been built by people who actually play.
It ensures fair play with licensed software providers and RNG-based games.
The website provides a user-friendly experience with
smooth navigation and fast gameplay. Sign up today and
experience the best online gaming in Australia with RocketPlay.
Some bonuses are automatically credited when you make a qualifying deposit,
while others may require a bonus code. We also offer a dedicated
mobile app for an enhanced gaming experience. Don’t
just take our word for it – hear from some of our satisfied
Australian players.
Downloading the latest version of the RocketPlay bonus apk is a simple
process with no complex steps and is completely free.
Rocket Play Casino has a gambling license from the government of Curacao.
Rocket Play Casino is part of the casino group operated by Direx NV.
Video poker sites often have dozens of different variations of the game.
Video poker machines can be found in gaming venues and even in occasional shops around the world.
The game thus exists in many variations and can benefit one side or the other.
References:
ufo9
online betting with paypal winnersbet
References:
http://www.129koreaems.com
I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great. I do not know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!
online roulette paypal
References:
https://empleoo.net/companies/best-online-casinos-that-accept-paypal-play-for-real-money-in-2025/
online betting with paypal winnersbet
References:
https://clicknaukari.com/employer/best-online-casino-australia-2025-top-australian-online-casinos/
online american casinos that accept paypal
References:
https://udyogseba.com/employer/new-online-casinos-of-december-2025-latest-nz-sites/
References:
When should i take anavar before or after workout
References:
https://md.swk-web.com/s/dTmW3vKGX
References:
Migliori casino online
References:
https://bookmarkstore.download/story.php?title=casino-withdrawal-process-what-happens-after-you-cash-out
References:
Resto a paris
References:
https://atavi.com/share/xnibgwz9yyav
pro hormones steroids
References:
https://writeablog.net/diggerfang6/dianabol-tablets-complete-guide-for-bodybuilders-on-price
anabolic steroids chemical structure
References:
https://browning-eliasen.federatedjournals.com/dhea-50-mg-150-lhormone-anti-age
This is a topic close to my heart cheers, where are your contact details though?
References:
Before and after anavar cycle pics
References:
https://forum.dsapinstitute.org/forums/users/weekfly06/
famous baseball players who used steroids
References:
https://king-wifi.win/wiki/Les_5_Meilleurs_Brleurs_de_Graisse_en_2026
craze pre workout banned
References:
http://millippies.com/members/okraleek8/activity/66044/
man loses additional bit of hope
References:
https://bookmarking.stream/story.php?title=dispensazione-senza-ricetta-quando-si-puo-e-come-si-fa
References:
Casino cherokee nc
References:
https://bookmarkstore.download/story.php?title=all-road-96-codes-and-phone-numbers
References:
Manoir de benerville
References:
http://hikvisiondb.webcam/index.php?title=quiltlamb96
%random_anchor_text%
References:
https://king-bookmark.stream/story.php?title=trenbolon-acetat-kaufen-trenbol-100-trenbolon-acetat-injizierbare-1000-mg-10-ml-genesis
most effective steroid for muscle gain
References:
https://yogaasanas.science/wiki/Trembolona_Acetato_Comprar_al_Mejor_Precio_en_Espaa
References:
Club player casino
References:
https://botdb.win/wiki/Candy96_Casino_Australia_Sweet_Bonuses_Secure_Pokies_in_2025
References:
Casino cairns
References:
https://to-portal.com/clotheggnog3
other names for testosterone
References:
http://dubizzle.ca/index.php?page=user&action=pub_profile&id=121397
how much steroids to take
References:
https://mapleprimes.com/users/oliveend2
where to get steroids bodybuilding
References:
https://justpin.date/story.php?title=anavar-zyklus-oxandrolon-fuer-bodybuilding
fast acting muscle building supplements
References:
https://gpsites.stream/story.php?title=buying-genotropin-legally-and-safely-in-uk
References:
Play online roulette
References:
https://drejer-corneliussen-2.technetbloggers.de/casino-freispiele-ohne-einzahlung-2026-sofort-free-spins
References:
Captain cook casino
References:
https://www.giveawayoftheday.com/forums/profile/1605967
References:
Blackjack guide
References:
https://sciencewiki.science/wiki/Willkommensbonus_Bewertungsbonus_fr_Neukunden_2026
References:
Casino slots online
References:
https://www.giveawayoftheday.com/forums/profile/1607928
References:
Kings casino
References:
http://stroyrem-master.ru/user/lambeffect1/
References:
Great american casino
References:
https://nerdgaming.science/wiki/PayID_Casino_Best_Australian_Online_Casinos
References:
Mgm casino las vegas
References:
https://www.pathofthesage.com/members/ocelotsarah28/activity/764174/
References:
Stargames casino
References:
https://images.google.co.il/url?q=https://blackcoin.co/best-payid-casinos-in-australia-15-sites-that-accept-payid/
anabolic supplement side effects
References:
https://p.mobile9.com/dirtsister61/
different kinds of steroids
References:
http://ezproxy.cityu.edu.hk/login?url=https://cerraelx.es/wp-content/pgs/?pastillas_para_adelgazar_1.html
best non hormonal muscle builder
References:
https://fkwiki.win/wiki/Post:Winstrol_Stanozolol_Kur_Dosierung_Und_Kombinationen
where can i buy winstrol
References:
https://p.mobile9.com/cubshade28/
References:
Crown casino sydney
References:
https://egamersbox.com/cool/index.php?page=user&action=pub_profile&id=272744
References:
Batavia downs casino
References:
https://atavi.com/share/xogxs1zqhqd8
methastadrol for sale
References:
https://lovewiki.faith/wiki/Trusted_Pharmacy_to_Buy_Vicodin_Get_Without_Prescription_www_twelveoaksbrownsvillecom
steroids article
References:
http://pattern-wiki.win/index.php?title=dalrymplesummers7502
steroid for bodybuilding
References:
https://securityholes.science/wiki/Ist_CBD_legal_in_Deutschland_Aktuelle_Rechtslage_01_2026
where can i buy steroids to build muscle
References:
https://lovebookmark.win/story.php?title=amazon-com-nugenix-t-booster-free-testosterone-booster-supplement-for-men-90-count-health-household
taking creatine while on testosterone
References:
https://sonnik.nalench.com/user/femalespring1/
long term steroid use side effects
References:
https://asmussen-lange.mdwrite.net/acetate-de-trenbolone-le-guide-ultime-de-la-tren-wikistero-la-bible-des-steroides-anabolisants
steroids for sale in canada
References:
http://king-wifi.win//index.php?title=hausercase0208
frank zane steroids
References:
https://molchanovonews.ru/user/shelfparcel5/