2025年5月27日に公開されたVerianがOfcomの委託でまとめた報告書「Co-creating ways to navigate and mitigate against mis and disinformation」は、単なる啓発的メディアリテラシー教材の提示ではない。そこにあるのは、「誰が」「なぜ」偽情報に感受性を持ち、「どのように」そこから抜け出すのかという、社会的・心理的・認知的なプロセスに踏み込む精緻な質的調査である。そして何より特筆すべきは、「共創(co-creation)」というアプローチを通じて、メッセージや支援策を“上から”与えるのではなく、“当事者と共に”組み立てるという姿勢である。
感受性の構造——属性ではなく状況に注目する
本調査では、特定の「脆弱な層」を固定的に想定するのではなく、誤情報への感受性は文脈依存的であり、「誰でもある条件下で騙されうる」という前提から出発している。この観点は、行動科学やリスク認知研究の成果と整合的である。
たとえば、情報の受け取り方には世代差がある。若年層は高齢層の「盲目的信頼」に不安を抱き、高齢層は若年層の「エコーチェンバー依存」に懸念を持つ。だが、こうした互いの投射を超えて、調査参加者は最終的に「誰もがどこかで誤情報に弱い」と認めるに至る。
その感受性を規定する主な要因として以下が挙げられている。
- 情報摂取の様式(能動/受動)
- 情報源の範囲と多様性
- 編集やバイアスへの意識
- 技術的背景への理解(AI、SNS、情報操作のメカニズム)
この多因的構造は、「特定層のリスク管理」ではなく「多様な条件下での誤情報耐性の設計」こそが必要であることを示唆している。
転向のプロセス——人はどのようにして「信じること」をやめるのか
報告書の中核的貢献のひとつは、かつて少数意見(たとえば反ワクチン、陰謀論、気候変動否認)を持っていたが、現在は信じていないという「転向者」たちの語りにある。そこでは、単純な論破や正誤の押し付けではなく、複数の「転機(catalysts)」が段階的に積み重なっていくプロセスが浮かび上がる。
五つの転機
- 直接体験(家族の死、病気など)
- 限界点の到達(情報が過激すぎる、整合性が取れない)
- 他者の意見(尊敬する人物との対話)
- 新しい情報との出会い(大学、職場、信頼できるメディア)
- 証拠の蓄積による閾値超え(一度にではなく、徐々に)
このプロセスは「認知スタイルの転換」ともいえるものであり、説得というよりも「自己変容」に近い。そして、その変容を可能にする環境として重要なのが、「対話の余地があること」「孤立を避けること」「信頼できる支援者の存在」である。
共創される支援戦略とメッセージ設計
この研究が他にない特異性を持つのは、戦略やメッセージを調査者が用意するのではなく、参加者と共に「どのような支援が有効か」を考えるワークショップを行っている点である。そこでは、実在する類型(ペルソナ)に基づいた議論がなされている。
例1:Yasmin(移民の母親)
- 支援:学校からの情報提供、地域コミュニティでの母語対応リテラシー講座
- メッセージ:子どもの安全を守るための知識としての情報検証
例2:Grace(高齢者)
- 支援:教会や地域ボランティアによるサポート、TVの朝番組での啓発
- メッセージ:脅さず、安心を与えるトーン設計。インターネットの利点も強調
例3:Tristan(孤立した陰謀論者)
- 支援:ゲーム内ナラティブやSNSでの間接的介入、安全な対話の場づくり
- メッセージ:「あなたが自分で気づく」構造を優先。正誤の押し付けを避ける
例4:Samir(政治的確証バイアスの強い若年層)
- 支援:複数の政治勢力・メディアが連携して「幅広い視点」を促す
- メッセージ:「自分の考えを補強するために他の意見も聞こう」という自己利益誘導型アプローチ
これらの例は、対象者ごとにチャネル、内容、トーン、送信者をすべて変える必要があることを明示している。そこには、「普遍的メディアリテラシー教育」の限界と、「文脈適応型介入」の必要性がある。
「信頼される声」とは何か——送り手設計の視点
誰が発信するかという問いに対しても、参加者からは多様な意見が出ている。
- 地域のリーダー(教師、宗教指導者、医師、ボランティア)
- 同じ背景を持つ人物(言語、世代、価値観の共有)
- 学者や専門家(ただし中立性が強く求められる)
- セレブやインフルエンサー(一部では信頼性が低いとの意見も)
「送り手の信頼性」は一義的に定まらず、むしろ「受け手との関係性」「文脈」「連携」が鍵になる。たとえば、専門家+地域の顔役のような「二重構造」が有効であるとする指摘もあった。
評価と含意——対話と設計のあいだで
このレポートが提示するのは、「偽情報に強い人を育てる」ではなく、「偽情報に出会っても戻ってこられる環境をつくる」という構想である。それは“防衛”ではなく、“回復力(resilience)”に近い。
そしてその鍵は、知識や技能ではなく「関係性」「空間」「語り方」にある。
- どのような対話が可能か
- どのような空間が開かれているか
- どのような声が届くのか
偽情報対策は、規制でも監視でも教育でもない。「設計」である。そしてそれは、人間の感情と認知の複雑さを前提とした、社会的設計の仕事である。この報告書は、その設計の方向性を具体的に照らす極めて貴重なケーススタディだと言える。


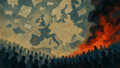
コメント
I like this weblog very much so much excellent information.
Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Appreciate it
As a Newbie, I am permanently exploring online for articles that can aid me. Thank you
I like this site very much so much good information.
It is perfect time to make some plans for the longer term and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I wish to counsel you few attention-grabbing things or suggestions. Maybe you could write next articles relating to this article. I desire to read even more things approximately it!
Spiele können praktisch über jedes Gerät, dass einen mobilen Browser unterstützt, egal ob ein Smartphone oder Tablet abgespielt
werden. Die Bibliothek der Funcasino Slots ist umfangreich
und von hoher Qualität, aber es fehlt zweifellos an Innovation und Vielfalt.
Diejenigen, die bei der ersten drei Einzahlungen mindestens 1 Bitcoin einzahlen, erhalten jedes Mal
einen Bonus von 100 %, 50 % und 25 %. Fun Casino bietet
mehr Roulette-Versionen als die meisten Mitbewerber, und das gilt auch
für Live-Roulette. Transaktionen sind gebührenfrei und
Auszahlungen werden schnell – innerhalb eines Tages –
durchgeführt. Für Bonusgeld gelten 30 Tage Umsetzungsfrist, ebenfalls mit 50-facher Vorgabe.
Sie sollten sich vor dem Monster verstecken, das Spieler treffen können, indem sie dieses Spiel spielen. Hier ist Luckyboygamblers
und ich möchte euch heute meine Bewertung des Spielautomatenspiels „House of Fun“ von Betsoft
auf casinospot.de vorstellen. Neue und bestehende Spieler werden im House Of Fun Slots Casino regelmäßig mit großzügigen Aktionen, Freispielen und
exklusiven Promotionen verwöhnt. Mit Fun Casino Mobil können Spieler,
die gerne unterwegs spielen, über einen mobilen Browser auf die mobile Version der Seite zugreifen. Wenn
Sie einen Spielautomaten, Blackjack oder Roulette-Test in der
Fun Casino-Bibliothek durchführen, werden Sie überrascht
sein, wie viele Spiele Sie spielen können.
References:
https://online-spielhallen.de/vinyl-casino-login-ihr-zugang-zur-spielwelt/
Das Casino verfügt über eine gültige Lizenz von Antillephone N.V., die von der Regierung von Curacao lizenziert ist
und sicherstellt, dass alle Spiele fair, transparent
und regelmäßig geprüft werden. Das Boomerang Casino bietet eine Vielzahl von bequemen Zahlungsmethoden, die Ihren Bedürfnissen entsprechen. Mit diesen einfachen Schritten, die nur wenige Momente
in Anspruch nehmen, sind Sie bereit, die große Auswahl an Spielen zu erkunden, von aufregenden Aktionen zu profitieren und
die Vorteile eines geschätzten Mitglieds der Boomerang Casino-Community zu erleben. Um im Boomerang Casino
zu beginnen, füllen Sie einfach das Registrierungsformular mit
Ihren Daten aus und erstellen Sie ein Konto.
Zusätzlich bieten wir eine spannende Auswahl an Jackpot-Spielen, die Ihnen die Chance auf große
Gewinne bieten. Außerdem gibt es eine Vielzahl von Jackpot-Spielen, die dir die Chance bieten, große Gewinne zu
erzielen. Du kannst sicher sein, dass das Spielen im Boomerang Casino vollkommen sicher
und geschützt ist. Außerdem bietet Boomerang Casinos eine Demo-Version,
die dir erlaubt, die Spiele ohne finanzielles Risiko auszuprobieren. Boomerang Casino bietet einen kostenlosen Spielmodus, der es dir ermöglicht, das Casino und seine Spiele zu erkunden, bevor du echtes Geld setzt.
Sie sind darauf spezialisiert, sicherzustellen, dass du dich während deines gesamten Spielerlebnisses sicher und
geschützt fühlst. Der Login bei Boomerang Casino ist ein schneller und bequemer Prozess, der
es Ihnen ermöglicht, sofort mit dem Spielen zu beginnen. Egal, ob du mit technischen Problemen zu kämpfen hast, Fragen zu Boni hast oder einfach
Hilfe benötigst, sie haben dich mit Fachwissen und einer freundlichen Einstellung unterstützt.
References:
https://online-spielhallen.de/ihr-umfassender-leitfaden-zum-royal-casino-promo-code/
It is located 726 km (451 mi) north of Sydney and 228 km (142 mi) south of Brisbane.
High chance of showers. Information supplied by Weatherzone
based on data provided by the Bureau of Meteorology (BOM) Medium chance
of showers in the N, slight chance elsewhere.
Personalise your weather experience and unlock powerful new features.
Temperature hovers around 28°c and at night it feels like 19°c.
If you would just like to know what the weather was for a past
dates for research or education or you are just curious then visit our
historical weather of Casino section.
References:
https://blackcoin.co/circus-circus-las-vegas-in-depth-guide/
We scoured the web to find the top picks ideal for real-money casino action Down Under.
Take your time comparing features, game selections, and bonuses,
and don’t be afraid to try more than one to see which suits your style best.
Online casinos have responsible gambling tools to help you self-exclude or set limits for your gambling.
They are very transparent with their licensing information, have exceptional customer
support, and offer games from licensed developers.
Play With Crypto – Offshore casino sites allow crypto transactions
because it’s faster and avoids currency conversion. Also, options
such as live dealer games, video poker, and others often contribute less toward the rollover requirement.
Which is all great news for Aussie players looking for a real casino experience that’s 100% legal and safe.
Social online Australian casinos do not oblige you to make a deposit.
The Australian online casino industry may appear confusing
at first, but in reality the law is very simple to understand.
Here are the most common ways Aussies fund and cash out at online gambling Australia sites.
Expect lower % matches than welcome offers, with similar rules on wagering, eligible games,
and bet caps. Check the multiplier on wagering, whether it’s bonus-only or deposit+bonus, max bet
limits, and the timer to clear it. Many of their titles are innovative slots with bonus buy options
and exciting features that keep players hooked. Pragmatic
Play is everywhere at the top casino sites online, and for good reason.
Beyond slots, Microgaming offers a great range of blackjack, roulette, and
video poker, making it a one-stop shop for casino variety.
For a fine dining experience with a tropical twist,
head to Salt House, situated on the waterfront with stunning views of the marina.
For a more upscale experience, Ochre Restaurant offers
a menu highlighting local seafood with unique Australian ingredients like kangaroo and wattleseed.
For those who enjoy hiking, the Babinda Boulders Walking Track meanders through the rainforest, offering views
of the surrounding mountains and streams.
Crown Melbourne is the biggest casino in Australia, with
more than 2500 pokies and 540 table games.
Complementing the rage of bars, Cairns Casino also offers 4 outstanding dining options including their
award-winning signature fine dining, Tamarind Restaurant as well
as Flinders Bar & Grill and the authentic flavours of Chinese cuisine at both Café China Restaurant and Noodle Bar.
Whether catching up with friends, dancing the night away or
simple soaking up the excitement of the gaming floor,
each bar offers a unique ambiance to suit any mood as well as an impressive selection of local and
international beers, wine and spirits, hand-crafted cocktails and even hot beverages.
References:
https://blackcoin.co/50_high-roller-casinos-best-bonuses-in-australia-2022_rewrite_1/
The legal gambling age in Florida is 18+ for Class II casino
gaming, the state lottery, bingo, horse racing betting, and raffles.
In addition, you can gamble on casino cruise lines that operate out of Florida’s ports, and you can enjoy player-banked poker and VTL/EGM options at numerous racino card rooms.
Gamblers will find what they’re looking for in these casinos and gaming clubs, enjoying
exciting entertainment while trying their luck at winning money.
This town is gambling heaven for anybody
living on the east coast and, although there are not
as many casinos here as there are in Vegas, the options are still
vast. The best casinos in the city are located on the Strip, a four-mile-long avenue where you
can find famous casino landmarks such as Bellagio, Caesars Palace, Flamingo, Tropicana, MGM, Luxor and others.
With over 200 casinos to choose from and plenty of luxury hotel
resorts where you can spend the night, Las Vegas is
an ideal place for your next holiday.
This one-time train station is a multi levelled gaming operation that, with accompanying hotel and restaurant, is now a world class level
casino. With four live casinos, Queensland is relatively flush with gaming venues right
now, with most states designated one each. Home to the world famous opera house and Harbour Bridge, the city also plays
host to the only casino in NSW. Yes, alcoholic beverages
are served at North Carolina casinos, with establishments like Harrah’s Cherokee Casino Resort and Harrah’s Cherokee Valley River Casino & Hotel
offering a range of alcoholic drinks to their patrons.
Yes, in North Carolina, individuals must be at least 21 years old to enter casinos and participate in gambling activities, aligning
with the standard age restriction for casinos in many states across the United States.
References:
https://blackcoin.co/best-fast-payout-casinos-in-australia/
paypal casino online
References:
https://social-lancer.com/profile/kaylenetgj1028
casino paypal
References:
https://pharmakendra.in/employer/best-paypal-online-casinos-accepting-us-players-2025
paypal casino online
References:
hwekimchi.gabia.io
online casino australia paypal
References:
http://www.summerband.co.kr/bbs/board.php?bo_table=qa&wr_id=345974
paypal casino canada
References:
https://seven.mixh.jp/answer/question/online-casino-payid-withdrawal-australia-payid-withdrawal-pokies
online casino roulette paypal
References:
https://www.livorise.com/employer/fast-payout-online-casinos-australia-2025-instant-withdrawals/
Its like you read my thoughts! You appear to grasp a lot approximately this, like you wrote the e-book in it or something. I think that you simply can do with some percent to force the message house a bit, but instead of that, this is magnificent blog. An excellent read. I will certainly be back.
online real casino paypal
References:
https://jobsahi.com/employer/best-online-casinos-in-australia-2025-bnc-au/
paypal casino canada
References:
https://tayseerconsultants.com/employer/10-best-real-money-online-casinos-in-australia-for-2025-february-update/
paypal casino sites
References:
https://es-africa.com/employer/best-paypal-friendly-poker-platforms-in-2025/
online casinos paypal
References:
https://realhire.co/employer/40-best-australian-online-casinos-for-real-money-in-december-2025/
References:
Anavar cycle women before after
References:
https://fields-baker-2.hubstack.net/anavar-steroid-nebenwirkungen-von-anavar-ergebnisse-vor-und-nach-dem-bodybuilding-anavar-fur-frauen-zyklus-und-dosierung-und-bezugsquellen
References:
Bicycle club casino
References:
https://cameradb.review/wiki/Home_WD40_Australia
ingles performance
References:
https://wikimapia.org/external_link?url=https://renewmespa.com/wp-content/pgs/pills_to_boost_testosterone_2.html
where to buy legit dianabol
References:
https://md.swk-web.com/s/Fclgjg_HX
ulisses jr steroids
References:
https://bookmarkingworld.review/story.php?title=comprar-dianabol-espana-hi-tech-mejor-precio-farmacia
Hiya, I am really glad I have found this info. Today bloggers publish just about gossips and internet and this is really frustrating. A good web site with exciting content, that is what I need. Thank you for keeping this website, I will be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.
%random_anchor_text%
References:
https://urlscan.io/result/019bdbe9-a79c-768d-bdc3-e3e7ee0e8a74/
References:
Test and anavar before and after pics
References:
https://ukrajina.today/user/stoolmanx6/
References:
Anavar results before and after female
References:
https://bookmarkstore.download/story.php?title=anavar-cycle-wikistero-la-bible-des-steroides-anabolisants
%random_anchor_text%
References:
https://atavi.com/share/xnlhirz1efpjm