栄養に関する誤情報は、もはや「誤解」や「知識の不足」では済まされない。とりわけソーシャルメディア上では、極端な食事法が「医師」や「専門家」を名乗るインフルエンサーによって、感情的共鳴とともに広く拡散されている。Rooted Research Collectiveが2025年5月22日に公開した報告書『Nutrition Misinformation in the Digital Age』(2024–2025)は、この拡散の構造と感情戦略に焦点を当てた。
「ドクター」「反逆者」「起業家」という三類型
報告書が特定したのは、Instagram上で特に高いエンゲージメント率(6%以上)を示した53のアカウント。これらは総計で2,480万人以上のフォロワーを抱え、拡散力において突出している。調査チームはこれらのアカウントを分析し、以下の三つの類型に分類した。
- The Doc:医師資格の有無にかかわらず「Dr」の肩書を使用し、医学的権威を装う。多くは恐怖や制度不信を煽る言説を展開。
- The Rebel:反体制・反科学的な言説をアイデンティティとし、陰謀論と自己啓発を融合させる。
- The Hustler:商品販売や自己ブランド構築を目的とし、成功談とポジティブな情動に訴える「ライフスタイル型」偽情報拡散者。
注目すべきは、医療関連資格の実態と表示との乖離である。分析対象のうち59%がそもそも正式な医療・栄養資格を持たず、それでも「Dr」などの表記を用いていた。また、MD(医学博士)を名乗るアカウントであっても、その専門が精神科や整形外科であり、栄養やNCD(非感染性疾患)に直接関係のないケースが多かった。
感情が駆動する栄養言説
偽情報拡散の中核にあるのは「感情」だ。調査では、53のスーパー・スプレッダーすべてが、以下いずれかの感情的拡散戦略に該当していた。
- Fear-mongering(恐怖):公的機関への不信、食品の「毒性」強調、伝統的食文化との対比などによって不安を喚起。
- Joy-mongering(喜び):個人の「劇的改善」ストーリー、レシピ、活力の回復など、自己実現を強調したポジティブなナラティブ。
- Sprinkling(混入):主にフィットネスや美容、ライフスタイル投稿のなかに偽情報を散りばめ、見落とされやすくする。
このような言説では、種子油や植物性食品が「毒」とされる一方で、赤身肉・レバー・脂肪分が「スーパーフード」として讃えられる。とくに「原始人食」「男性ホルモンの回復」「自由と反抗」といった価値観と結びつけられることで、食習慣は一種の信念体系となっている。
エビデンスとの乖離と、制度的応答の課題
報告書は、WHOやEAT-Lancet、各国の栄養ガイドラインをもとにした「栄養的ベースライン」との整合性も評価している。その結果、スーパー・スプレッダーによる主張の多くが以下の点で逸脱していた:
- 植物性食品の摂取量が極端に少ない
- 飽和脂肪の過剰摂取を奨励
- 栄養的多様性とバランスを否定
特に、こうした情報が医師や「専門家」の語り口で語られることにより、公共の栄養指針が「信頼できない」「裏がある」といった認識が強化されている。報告書は、教育カリキュラムへの批判的思考導入や、医療・栄養専門家によるSNS上での発信強化を提案している。
まとめ
このレポートは、栄養偽情報の拡散が単なる情報精度の問題ではなく、信頼・感情・アイデンティティに根ざした構造的現象であることを明確に示している。そのため、単に「科学的事実を正しく伝える」だけでは対抗できず、エモーショナルな接続、物語性、そしてSNS上の可視性が対抗策として求められる。

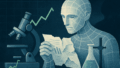

コメント
changan cs55 plus https://changan-v-spb.ru
Howdy! This post could not be written any better! Reading through this post reminds me of my old room mate! He always kept talking about this. I will forward this write-up to him. Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing!
Magnificent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just extremely great. I really like what you’ve acquired here, really like what you are saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it sensible. I cant wait to read far more from you. This is really a wonderful web site.
I like what you guys are up too. Such smart work and reporting! Keep up the superb works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my web site :).
I appreciate, result in I discovered exactly what I was looking for. You have ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye
Ein attraktiver Casino-Bonus kann ein wichtiger Faktor bei der Wahl eines Online-Casinos
mit deutscher Lizenz sein. Der Casino-Bonus ist ein wichtiger Aspekt bei der Bewertung eines Online-Casinos mit deutscher Lizenz.
Diese verschiedenen Möglichkeiten bieten den Spielern eine breite Palette an Optionen und Spielstilen, um ihre
individuellen Vorlieben und Gewinnziele zu erfüllen. Casino-Rubbellose bieten eine schnelle
und einfache Spieloption mit sofortigen Gewinnmöglichkeiten.
Solange alle auf dieser Seite aufgeführten Kriterien für seriöse Online Casinos erfüllt sind, spielt ihr sicher um Echtgeld.
Wenn ein Betreiber lizenziert ist, könnt ihr sicher sein, dass das Online Casino zuverlässig ist.
Wenn ihr in einem Online Casino mit echten Einsätzen spielen möchtet, ist das sorgfältige Lesen des Kleingedruckten ein Muss.
References:
https://online-spielhallen.de/n1-casino-auszahlung-im-detail-ihr-ultimativer-leitfaden/
Hello, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam comments? If so how do you reduce it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me mad so any help is very much appreciated.
Currently, Lucky ones does not offer a no deposit bonus.
New members enjoy access to guidance, demo sessions, and a generous welcome package.
Enjoy enticing welcome bonuses, cashback deals, and exclusive free spins.
This design is not just mobile-friendly, it is sensory-tuned to how players actually hold, swipe, and tap
through their sessions. This ensures players trust what they are playing
and know what to expect with every spin, hand or bet.
Players can review game-specific Return to Player (RTP) percentages to
make informed choices, all figures are based on real statistical outcomes, not promises.
Every win at Lucky Ones Casino is backed by transparent mechanics and real-time data, verified through independently
audited RNG systems. All our games utilize RNG systems tested by
certified third-party labs, ensuring unbiased outcomes.
Each of these methods offers unique advantages depending on your play style and bankroll goals.
Are you ready to take a spot at our tables? Command the
games where legends are made. Smooth withdrawals and an engaging gaming experience?
From high-stakes tables to bespoke VIP rewards, this is where champions carve their legacies.
Not all online casinos are created equal. Whether you value
speed, security or anonymity, our robust payment options ensure a
hassle-free experience.
References:
https://blackcoin.co/sign-in-your-gateway-to-online-casino-action/
Our Level Up Casino login system implements robust verification procedures to
ensure player security and regulatory compliance. We comply with international gaming
standards that align with Australian consumer protection principles.
These assessments cover financial stability, technical systems integrity,
and player protection measures. We undergo periodic
regulatory reviews to maintain our gaming authority approvals.
Serves as our direct licensing authority, conducting regular compliance assessments and monitoring our adherence to
gaming regulations.
Remember to double-check the accuracy of all the information you enter to prevent
any issues, particularly when it comes time to process withdrawals.
This time-saving feature makes the whole experience even more convenient, letting you jump straight into the fun. Players who
already know their favourite title can use the handy search bar — just type in the game
or provider’s name, and results appear instantly.
References:
https://blackcoin.co/40_best-vip-online-casinos-for-high-rollers-in-2022_rewrite_1/
casino online paypal
References:
https://www.referall.us/
casino online paypal
References:
http://jinbang.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=167
I discovered your blog site on google and check a few of your early posts. Continue to keep up the very good operate. I just additional up your RSS feed to my MSN News Reader. Seeking forward to reading more from you later on!…
online casinos mit paypal
References:
https://www.recruit-vet.co.uk/employer/online-casinos-that-accept-paypal/
gamble online with paypal
References:
https://i-medconsults.com/companies/best-payout-online-casinos-australia-2025-97-rtp-big-bonuses/
Das HitnSpin Casino bietet gute Quoten, besonders bei Top-Ligen im Fußball. Zudem gibt es ab der Stufe Krieger einen Geburtstagsbonus. Je mehr Punkte du sammelst, desto höher steigst du im Level – und sicherst dir Cashback, Freispiele und wöchentliche Bonusangebote. Die genauen EUR Beträge und Freispiele variieren je nach Einzahlung und VIP-Level und können einmal pro Woche beansprucht werden. Aktive Spieler erhalten regelmäßig Reload-Boni.
Die Hitnspin Boni reichen von Willkommensboni, die Ihre Reise mit einem Schub beginnen, bis hin zu laufenden Aktionen, die die Spannung aufrecht erhalten, glauben wir daran, unseren Spielern jeden Grund zu geben, ihre Gewinne zu feiern. Sie müssen also auch von unterwegs keine Kompromisse eingehen und können jeden gewünschten Titel von jedem Ort und zu jeder beliebigen Zeit spielen. Darüber hinaus haben wir einen Überblick über die verschiedenen mobilen Casino Spiele und die Möglichkeit, um echtes Geld zu spielen. Wir haben herausgefunden, dass Hit’n’Spin ein führendes Online-Casino ist, das Spielern ermöglicht, alle Casinospiele auf ihren Mobiltelefonen zu spielen. Außerdem können Sie Ihren Fortschritt und Ihre Gewinne verfolgen, egal ob Sie auf dem Mobilgerät oder dem Desktop spielen.
References:
https://onlinegamblingcasino.s3.amazonaws.com/crypto%20casino%20no%20deposit%20bonus.html
References:
Sycuan casino
References:
https://clashofcryptos.trade/wiki/Winz_io
References:
Anavar before and after photos
References:
https://hedgedoc.eclair.ec-lyon.fr/s/e_pWORk7w
References:
Anavar and test before and after
References:
http://pandora.nla.gov.au/external.html?link=https://www.valley.md/anavar-results-after-2-weeks-ca
References:
Casino sanremo
References:
https://socialbookmarknew.win/story.php?title=contact-wd-40-find-wd-40-distributors
References:
Hard rock casino las vegas
References:
https://www.youtube.com/redirect?q=https://wd40casino.blackcoin.co
1 year steroid transformation
References:
http://celebratebro.in/birthdays-in-bangalore/index.php?qa=user&qa_1=toadbun26
anabolic steroids physical effects
References:
https://bookmarks4.men/story.php?title=clenbuterol-dosierung-wie-viel-ist-richtig
is trt steroids
References:
https://md.ctdo.de/s/Fgh5H6sjQx
References:
Test tren anavar before and after
References:
https://hikvisiondb.webcam/wiki/Winstrol_and_Anavar_cycle_Dosage_and_Result
steroids stack for mass
References:
https://instapages.stream/story.php?title=comprar-anavar-esteroides-anabolicos-espana-farmacia-en-linea
Hey! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to no back up. Do you have any methods to stop hackers?
weightlifting steroids for sale
References:
https://chase-chase.technetbloggers.de/trembolona-comprar-esteroides-venta
References:
Anavar before after meal
References:
https://a-taxi.com.ua/user/woodsalad33/
anabolic steroid online
References:
https://linkagogo.trade/story.php?title=quels-sont-les-medicaments-pour-maigrir-autorises-