欧州連合(EU)において2024年2月から全面適用となった「デジタルサービス法(Digital Services Act, DSA)」は、オンラインプラットフォームに対する新たな責任の枠組みとして大きな注目を集めている。中でも、偽情報(disinformation)への対応において、DSAが主要な法的基盤となりつつある現状には、立法的にも実務的にも多くの含意がある。
本稿で紹介するのは、アムステルダム大学情報法研究所(IViR)所属の法学者らによる論文「The Regulation of Disinformation Under the Digital Services Act」(Media and Communication, 2025年5月)である。DSAがどのように偽情報の規制に関与しているのか、そしてそれがEUの基本権(特に表現の自由)といかに緊張関係にあるのかを精緻に分析した内容となっている。
明示されない「偽情報」:DSAの構造的な曖昧さ
まず最初に指摘されるのは、DSAの条文中に「disinformation」という用語が一度も登場しないという事実である。偽情報はあくまで「Recital(前文)」において言及されるにとどまり、法的拘束力を持つ本文中には明記されていない。
にもかかわらず、欧州委員会はDSAを「偽情報から欧州市民を守るための主要なEU法」と位置づけ、実際にXやMeta、TikTokなどに対して、偽情報対策の不備を理由とした情報提供要求や正式調査を行っている。このギャップは、法的確実性と表現の自由の保護の観点から重大な意味を持つ。
加盟国法との連動:違法コンテンツとしての偽情報
DSAは「違法コンテンツ」を広く定義しており、EUまたは加盟国の法令に違反するすべての情報が対象となる。その結果、たとえばマルタやキプロスなどで施行されている「虚偽情報の拡散」を刑事罰とする国内法が適用される場合、当該情報はDSA上の「違法コンテンツ」として削除の対象となる。
このような加盟国ごとの定義のばらつきは、プラットフォームにとって極めて対応の難しい環境を作り出す一方で、EU域内の表現の自由の水準が一様でなくなるという問題をもたらしている。
DSAの二面性:削除と保護の両立
DSAは、偽情報の削除を可能にする規定を備えつつ、その削除が恣意的に行われないよう、ユーザー保護のための制度も同時に整備している。
具体的には、プラットフォームが自身の利用規約に基づいてコンテンツを制限する際には、EU基本権憲章の表現の自由(第11条)に「十分配慮」しなければならない(第14条)。また、削除時の理由説明の義務(第17条)や、内部苦情処理制度・裁判外紛争処理制度(第20〜21条)なども明記されている。
これらの条項は、偽情報とされたコンテンツが実際には合法な情報であった場合のユーザー保護を担保するための手段とされているが、実務面では自動化された短文による通知が多く、透明性の確保には課題が残るとされる。
VLOPsとリスク評価:制度的中核としての「システミックリスク」枠組み
DSAの特徴的な枠組みとして、ユーザー数が月間4500万人を超える「非常に大規模なオンラインプラットフォーム(VLOPs)」に対しては、「システミックリスクの評価と緩和」(第34〜35条)が義務づけられている。
ここで注目すべきは、偽情報がリスク要素として明記されていないにもかかわらず、前文において「公衆衛生」「選挙プロセス」「市民的対話」への悪影響の原因として偽情報が例示されており、事実上はリスク評価の対象とされている点である。
2024年の欧州議会選挙を前に、欧州委員会は選挙関連のリスク緩和に関するガイドラインを発表し、ファクトチェック表示、アルゴリズムによる表示抑制、広告利用の制限などを「ベストプラクティス」として推奨。これらは形式上は勧告にとどまるが、VLOPsが従わない場合には「同等の効果を立証せよ」という圧力がかけられる。
実質的な削除の場となる「2022行動規範」
DSA本文には偽情報削除の義務規定はないにもかかわらず、実際の削除措置の多くは2022年改定の「偽情報に関する行動規範(Code of Practice)」に基づいて行われている。
この規範は2025年7月からDSAに正式に組み込まれ、VLOPsの「リスク緩和策」の一環として位置づけられる。報告された事例では、TikTokがEU選挙前に25万件以上の動画を削除、YouTubeも1.9万件超の削除を行っており、実質的にはこの規範が偽情報規制の中核となっている。
このような「自発的措置」がDSAの執行の一部として制度化される構造は、規制の透明性や説明責任に対して懸念を残す。
表現の自由と規制権限:CSOからの批判とECHRとの整合性
欧州委員会が偽情報対策を理由にプラットフォームへ警告文や調査開始を行っていることについて、市民社会団体からは強い懸念が表明されている。具体的には:
- 「削除の迅速化を事実上強制している」
- 「DSAの文言以上の権限行使」
- 「政治的にセンシティブな時期に圧力をかけている」
といった批判が相次いでおり、DSAの運用が欧州人権条約(ECHR)第10条が保障する表現の自由に違反しうるという指摘もなされている。
特に、行政機関からの警告や情報要求が、内容規制の「圧力」として機能し、実質的な言論萎縮を引き起こす可能性について、欧州人権裁判所の判例(Karastelev v. Russia, 2020など)と照らしあわせて検討されている。
まとめ:偽情報対策の名の下に、何が行われているのか
この論文は、DSAが偽情報に関してどのような実効性を持ちうるのかを評価するだけでなく、形式的には明示されていない規制が実質的には行われている現状、そしてそれが法的・民主的にどれほど問題含みであるかを浮かび上がらせている。
特に、削除と自由の「両立」を謳いながらも、削除措置の実態がガイドラインや規範に依存しており、明確な法的制約がない中で行政当局の裁量が広がっているという現状は、今後の制度運用にとって大きな論点となるだろう。
偽情報規制と表現の自由の交差点に立つDSAの構造を理解するうえで、本論文はきわめて重要な出発点を提供している。

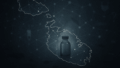

コメント
Hello everyone, it’s my first pay a visit at this website, and paragraph is truly fruitful
in support of me, keep up posting such articles or reviews.
It is perfect time to make some plans for the future and it is time to
be happy. I have read this put up and if I may
just I wish to counsel you some attention-grabbing things or tips.
Maybe you can write subsequent articles referring to this article.
I wish to read even more things about it!
Mit super Grafiken, schnellen Ladezeiten, tollen Animationen, lustigen Animationen und tollen Soundeffekten bietet ZetCasino für jeden etwas.
ZetCasino bietet eine Fülle von Spielautomaten, darunter eine Reihe von Megaways-Spielen wie The
Dog House Megaways von Pragmatic Play. Mit einer umfangreichen Bibliothek von über 3.000 Spielen gibt es Spielautomaten, Video-Slots,
Tischspiele, Kartenspiele, Video-Poker, Live-Dealer-Spiele – in einer kompletten Palette von Themen. ZetCasino
bietet die gesamte Bandbreite an Spielen für jeden Spieler.
Für ein neueres Online-Casino scheint ZetCasino alles für die eifrigen kanadischen Sport-
und iGaming-Fans zu bieten, alles verpackt in einer intuitiv
gestalteten Website mit einfacher Registrierung.
ZetCasino bietet auch ein Sportwettenangebot mit einer fantastischen Auswahl an Sportarten, darunter auch ein spezieller Bereich für Pferderennen. ZetCasino bietet eine große Auswahl an Spielen aus einer riesigen Bibliothek von über 3.000 Spielen, die von über 40 Designern ausgewählt wurden, darunter
die besten Spielemacher der Branche. Das Zet Casino, das sowohl ein Sportwetten- als auch ein Spaß-Casino mit einem Fantasy-Charakter-Thema anbietet, gibt es seit
seinem Start im Jahr 2018. Um auf alle Funktionen der Website zuzugreifen, genügt
es, eine einfache Registrierung durchzuführen. Darüber hinaus finden Spieler
hier ein ausgezeichnetes Bonusprogramm, nicht nur für Casinospiele, sondern auch für Sportwetten. ZetCasino ist
ein zuverlässiges Online-Casino für Spieler aus Deutschland, das über eine Lizenz
verfügt und bequeme Zahlungsmethoden, einschließlich Kryptowährungstoken, anbietet.
Um das Angebot zu aktivieren, ist eine Mindesteinzahlung von 20 € erforderlich.
Das ZetCasino Willkommenspaket umfasst einen 100 % Bonus bis zu 500 € sowie 200 Freispiele.
Für alle Sportfans bietet ZetCasino neben dem klassischen Casino-Angebot auch ein spezielles Sportwetten-Bonuspaket.
References:
https://online-spielhallen.de/jackpot-de-slots-casino-deutschland-dein-ultimativer-guide-fur-kostenlosen-spielspas/
TubiTV is accessible on a wide range of devices, making it easy to watch your favorite content anywhere, anytime.
With over 100 original titles and more on the way, TubiTV is building a unique library that sets it apart from other free streaming services.
TubiTV has invested in original content, producing exclusive movies and
series available only on the platform. Users can filter content by genre, IMDb rating, and more to
find exactly what they want to watch. TubiTV operates on an ad-supported
model, meaning that users can access all content for free
in exchange for watching commercials.
Embattled casino operator Star Entertainment confirmed its partners
in the Queen’s Wharf facility — Chow Tai Fook Enterprises (CTF) and Far East Consortium (FEC) — have offered to
buy out its share. Shares in struggling casino giant Star Entertainment have plummeted on Friday after a brief
trading halt was lifted, as the company searches for
a financial lifeline to avoid collapsing. A Tax Calculator is provided below to assist shareholders in calculating the Australian capital gains tax
cost base allocation for Tabcorp shares and The Star Entertainment Group shares.
On 5 April 2016, eligible shareholders were sent a letter together
with a Share Retention Form (for the Small Holding Sale Facility) or a Sale Instruction Form (for the Voluntary Share Sale Facility), and Terms and Conditions for the relevant share sale facility.
There is no monthly subscription fee and you can begin to watch TV shows and movies for free right now by downloading the Tubi app.
Tubi is always adding great new content, so stay tuned
to find out what you can watch completely for free right now on Tubi.
Follow the topics, people and companies that matter to you.
References:
https://blackcoin.co/sweeps-oasis-casino/
Players should monitor their behavior and use the casino’s tools
to stay in control. However, wagering requirements apply so winnings must
be played through before withdrawal. Claiming bonuses and
promotions at King Billy Casino is easy, rewards are available immediately after you log in. For persistent issues King Billy Casino’s 24/7 support team is
available via live chat and email. Whatever device you use, desktop, smartphone or tablet, the login process is the same.
Do not gamble with funds you cannot afford to lose.Please play responsibly
and seek help if gambling becomes a problem.
King Billy Casino supports fast and secure transactions for Aussies with
multiple deposit and withdrawal options, including cryptocurrency
and Neosurf. New players at King Billy Casino Australia are greeted with
a royal welcome package offering up to A$2,500 in bonus funds and
250 free spins across the first four deposits.
Australian players can use various payment methods
including Visa/Mastercard, Neosurf, and cryptocurrencies like Bitcoin, Ethereum,
Litecoin, and Tether. Manage gaming time with customizable
session limits and reality checks that remind you how long you’ve been playing.
References:
https://blackcoin.co/ripper-casino-login-australia-complete-guide/
casinos online paypal
References:
aviempnet.com
us online casinos paypal
References:
koftc.com
online poker real money paypal
References:
https://volunteeri.com/companies/find-the-top-online-casinos-in-australia-aus-casinos/
paypal casino online
References:
https://itheadhunter.vn/jobs/companies/best-paypal-casinos-2025-100+-real-money-paypal-sites-%EF%B8%8F/
References:
Mirror ball slots
References:
http://lideritv.ge/user/spainkarate0/
References:
Leelanau sands casino
References:
https://case.edu/cgi-bin/newsline.pl?URL=https://wd40casino.blackcoin.co
is strong supplement shop legit
References:
http://premiumdesignsinc.com/forums/user/heronnoise4/
monster massive protein review
References:
https://notes.io/euaZs
References:
Anavar alone before and after
References:
https://doodleordie.com/profile/powderappeal3
how many types of steroids are there
References:
https://intensedebate.com/people/foxarm12
steroid stacks for mass
References:
https://mensvault.men/story.php?title=exploring-winstrol-in-the-uk-benefits-risks-and-legal-status
can steroids cause kidney failure
References:
https://imoodle.win/wiki/7_Lebensmittel_die_das_Testosteron_auf_natrliche_Weise_steigern_knnen
References:
Anavar female before and after
References:
https://linkagogo.trade/story.php?title=anavar-le-guide-complet-sur-ce-steroide-et-ses-effets
%random_anchor_text%
References:
https://urlscan.io/result/019bd099-c984-77b4-ab4b-8f00dec2046c/