2025年6月に発表された報告書『Global Trends in Climate Change Litigation: 2025 Snapshot』(ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス、Grantham Research Institute)は、世界中で急増する気候変動関連訴訟の最新状況を網羅的に示している。本稿ではこの報告の中でも、企業や制度が気候に関して「誤った情報」「誤解を招く主張」「隠蔽」をどのように行い、それがどのように訴訟で争点化されているかに焦点を当てる。
報告書そのものは「disinformation」という語を用いていない。しかし、分析対象となった多くの訴訟には、事実の歪曲・誇張・不開示といった偽情報的要素が明確に存在する。それらは「climate-washing(気候ウォッシング)」「misleading claims(誤認誘導的主張)」「facilitated emissions(助長排出)」といった術語で表現されており、偽情報研究の射程に入る。
気候ウォッシング訴訟:企業広報の“法廷化”
2020年以降に160件以上が提起されたとされる「climate-washing」訴訟は、気候訴訟における偽情報的構造を最も端的に示している。
たとえば2024年、ニューヨーク州司法長官はJBS USA Food Coに対して消費者保護法違反で提訴した。JBSは「2040年までにネットゼロ」を掲げていたが、その公約には間接排出(Scope 3)が含まれていなかった。原告はこれを誤認を招く表現によって消費者を欺いたとして訴えている。
同年、オーストラリア連邦裁判所もMercer Superannuationに対し、実際には石炭・ギャンブル関連企業への投資を含んでいた「サステナブル投資商品」の虚偽表示に対して1,130万豪ドルの罰金を科した。いずれも「広告の誇張」ではなく気候影響に関する虚偽表現が法的責任を生じうると認定された点で重要である。
誤情報の“媒介者”を問う訴訟群
2025年に入り、「誤情報を直接発信した企業」だけでなく、その伝達・支援を行った助言機関・法律事務所・広告代理店が訴訟対象となる例が明確になってきた。
米オレゴン州マルトノマ郡は、コンサル大手マッキンゼー社を含む複数企業を相手取って提訴し、同社が数十年間にわたり主要排出企業に対し気候リスクを軽視・隠蔽する戦略を助言してきたと主張した。
また、グリーンピースはオランダの法律事務所Loyens & Loeffに対し、温室効果ガス排出企業JBSの企業再編支援が「facilitated emissions(助長排出)」に該当するとして法的警告を発している。英国では広告代理店WPPが、複数のNGOからOECDのナショナル・コンタクト・ポイントに対して正式に苦情を申し立てられている。
これらはいずれも、「誤情報の構造的流通」に関与した専門職が、直接的な法的アカウンタビリティの射程に入ってきていることを示している。
ポリューター・ペイズと歴史的偽情報
近年の「polluter pays(汚染者負担)」型訴訟では、単なる温室効果ガス排出だけでなく、過去に行われた気候影響の矮小化や科学の否定的キャンペーンが、損害賠償請求の論拠として組み込まれる傾向が強まっている。
ハワイ州ホノルル市によるHonolulu v. Shellでは、石油企業らが何十年にもわたり自社製品が地球温暖化に与える影響を意図的に過小評価・隠蔽したとされ、訴訟は州最高裁で審理に進むことが決まっている。
このように、誤情報によって形成された「知の空白」が、その後の被害を導いた構造を、法廷上で可視化し、責任を問う流れが鮮明になっている。
偽情報の“制度的支援”としての反ESG訴訟
一方で、米国では政権交代によって新たなタイプの「制度的偽情報」支援構造が立ち上がりつつある。
2025年1月に発令された「Protecting American Energy from State Overreach」という大統領令は、州や自治体による気候訴訟を「越権行為」とみなし、司法長官に対し阻止訴訟を命じるものである。実際にバーモント州やニューヨーク州の「気候スーパーファンド法」は、連邦政府自身により提訴される事態となっている。
ここでは、偽情報的な主張(気候対策は無意味・有害)を根拠に正規の制度的対応を妨げるという構図が見て取れる。
法廷は偽情報研究の新たな前線になるか
気候訴訟の近年の展開は、従来「社会心理的」「情報論的」に扱われてきた偽情報問題が、明確に制度責任・法的因果関係の論拠となりうることを示している。
- 誤った主張が「売上」や「評判」だけでなく、「環境破壊」「人命損失」「経済的損害」に直結する場合、それは単なるミスリードではなく、損害因子として構成されうる。
- 偽情報の流通経路にいる者(広告代理店、法律事務所、金融機関)が、助言者責任・媒介者責任として裁かれる余地が生まれている。
- 訴訟を通じて、誤情報の構造そのものが検証対象となる段階に来ている。
このように、気候訴訟の実態は、偽情報研究にとっても制度論・責任論・インフラ論の実証的素材を与える。『2025 Snapshot』は、訴訟という形式のなかで、誤情報の影響と可視化、そして是正の可能性がいかに組み込まれているかを理解する上で、貴重な手がかりとなるだろう。

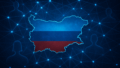

コメント
Roulette ist wohl eines der berühmtesten Casinospiele überhaupt und untrennbar
mit der Identität von Casinos verbunden. So kann man den Tisch finden, der die passenden Setzbedingungen und Regeln für die eigenen Vorstellungen hat.
Da man die meisten dieser Tischspiele als Demoversion testen kann, besteht die Möglichkeit viele Casino Spiele kostenlos auszuprobieren. Tischspiele waren lange Zeit das Herz von Casinos und auch
heutzutage kann man sich viele dieser klassischen Casinospiele nicht aus einer Spielhalle wegdenken. Casino Spiele kostenlos auszuprobieren ist eine hervorragende Methode, um sich an Glücksspiele heranzutasten.
Unser Team hat festgestellt, dass dieses Casino eine Reihe von Bonusanreizen anbietet, die sich sowohl an Neueinsteiger als auch an erfahrene Spieler richten. In der Fußzeile der Seite finden Sie wichtige Informationen über Hit’N Spin.
Oben rechts befinden sich die Schaltflächen für die Anmeldung und
die Registrierung sowie eine Option zum Umschalten der Sprache der Website.
Das benutzerfreundliche Layout sorgt dafür, dass sich auch Erstbesucher leicht zurechtfinden. Zusammenfassend lässt sich sagen,
dass Hit’N Spin für Liebhaber des online-Glücksspiels eine zuverlässige Option für ein ganzheitliches
Casino-Erlebnis darstellt. Das Casino bietet ein breites Spektrum an Spielen von führenden Softwareanbietern, die ein vielfältiges und ansprechendes Sortiment
für seine Kunden gewährleisten.
Auszahlungen werden reibungslos abgewickelt, mit einem Mindestauszahlungsbetrag von 20 CHF und keinen spezifischen Höchstbeträgen. Sie finden eine umfassende Auswahl an Spielautomaten, darunter klassische Slots,
Video-Slots und innovative Megaways-Slots mit dynamischen Walzenkonfigurationen. Das Casino bietet eine riesige
Spielwelt, die den unterschiedlichsten Vorlieben gerecht wird.
Die Plattform hat einen Mindestauszahlungsbetrag von 20 CHF festgelegt,
wobei es keine bestimmten Höchstbeträge gibt.
References:
https://online-spielhallen.de/monro-casino-test-erfahrungen-fur-deutsche-spieler/
The most legitimate online gambling sites include Ignition Casino,
Cafe Casino, Bovada Casino, Slots LV, DuckyLuck Casino,
SlotsandCasino, and Las Atlantis Casino. Responsible gambling practices help prevent addiction and ensure a safer gaming
experience. Progressive jackpot slots like Major
Millions, Leprechaun Goes to Hell, and Gunslinger Reloaded offer
players a chance to win life-changing amounts.
Understanding the house edge is vital when it comes to playing
real-money casino games. One of the safest moves as a player to get your
credit converted into real money, is to play live casino.
Real-money online casino sites are legal in seven US states — New Jersey, West Virginia, Michigan, Pennsylvania, Connecticut, Delaware, and Rhode Island.
After evaluating numerous real-money casinos, these
selections offer superior payouts, enabling you to play while effectively managing your
bankroll. By setting gaming limits and accessing resources like GAMBLER, players
can enjoy a safe and rewarding online gambling experience.
References:
https://blackcoin.co/complete-list-of-las-vegas-casinos/
That’s why more Aussies are turning to online casinos instead.
Once you’ve picked up a bonus or two, the real fun starts with the huge range of games on offer.
You’ll notice straight away how much more offshore Australian casino
sites offer when it comes to games. The table below lets you quickly compare
the top 10 Australian online casinos and their key
features. Keep in mind you will need to use these casino bonus funds on eligible games in order to cash out any bonus winnings.
Keep in mind that there may be a minimum deposit amount and that games contribute different
percentages depending on the bonus and site.
Additional offers like 20% daily cashback and 100 free spins on Wednesdays make Neospin a rewarding choice for users.
The platform features a wide selection of pokies with diverse themes and engaging mechanics, alongside classic table games like blackjack and roulette.
Our top picks for 2025 offer a unique blend of gaming options and user-centric
features that cater to diverse preferences.
Please note that third parties may change or withdraw bonuses and promotions
on short notice. Our goal is to help you make the best choices to
enhance your gaming experience while ensuring transparency and quality in all our
recommendations.
References:
https://blackcoin.co/a-guide-to-casino-comp-points-vip-programs/
casino online uk paypal
References:
https://www.kondograpla.site/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=206
online american casinos that accept paypal
References:
https://almeslek.com/employer/paypal-casinos-2025-paypal-casino/
Remember though, the bonus money comes with wagering requirements before cashing out any winnings. The cash and spins land instantly after deposit confirmation. New members start with welcome packages consisting of deposit matches and free spins across initial deposits. The competitive atmosphere transforms standard gaming sessions into adrenaline-fueled contests where strategy matters just as much as luck.
Fast navigation, clean promos, and reliable gameplay sessions. Skycrowncasino has quick load times for live blackjack. Support was reliable through live chat and email, though the absence of phone support and a shallow FAQ are drawbacks. Mobile play was smooth across browsers and via the APK app.
Its extensive selection of pokies and well-designed bonus system are definite highlights. However, the 24/7 live chat feature is only accessible to registered users—a limitation that we see as a drawback. Achieving VIP status unlocks exclusive benefits such as a personal manager, priority withdrawals, and tailored bonuses. It’s important to note that only one welcome bonus can be activated per account, so choose wisely! Get 10% cashback on all Skycrown games, up to 300 AUD, every Friday. Enjoy a 75% bonus on your 2nd deposit, up to 500 AUD, plus an additional 75 free spins on Sun of Egypt 3 by Booongo.
References:
https://blackcoin.co/ufo9-casino-your-place-to-play-your-way/
online casino uk paypal
References:
https://www.dynamicviewpoint.co.uk/employer/online-casino-mit-paypal-einzahlung-die-top-casinos-im-vergleich/
paypal casinos online that accept
References:
https://www.madhurta.in/employer/best-online-casinos-australia-in-2025-real-money-pokies/
online slots paypal
References:
https://jobcop.ca/employer/online-casino-mit-paypal-einzahlung-die-top-casinos-im-vergleich/
online poker real money paypal
References:
https://thesecurityexchange.com/employer/best-online-casinos-in-australia-top-casino-sites-for-2025/
paypal casino usa
References:
https://hitechjobs.me/companies/best-online-casinos-australia-2025-find-top-aussie-casino/
best online casino usa paypal
References:
https://www.govconnectjobs.com/employer/payid-casinos-in-australia-best-casino-sites-accepting-payid-withdrawal/
casino mit paypal
References:
https://realestate.kctech.com.np/profile/ellioty5349790
online casinos that accept paypal
References:
https://jobteck.com/companies/us-online-casinos-that-accept-paypal-2025/
Danach steht das daraus resultierende Echtgeld zur Auszahlung bereit. Je nach Anbieter werden die Gewinne vom No Deposit Casino Bonus sofort als Echtgeld gezählt oder das Casino zählt den Betrag zum Bonusguthaben. Der Echtgeld Bonus ohne Einzahlung wird auch als „No Deposit Bonus“ bezeichnet. Zögert nicht länger und gewinnt kostenloses Spielguthaben mit Top Echtgeld Boni ohne Einzahlung!
Aus diesem Grund stellen wir dir alle verfügbaren Echtgeldspiele im Detail vor. ZahlungenWelchen Zahlungsanbieter nutzt du am liebsten und am häufigsten? Damit ist gemeint, ob auch genau die Automaten angeboten werden, die du spielen willst. Dann bekommst du sozusagen vor dem Einzahlungsbonus, den du über die Einzahlung aktivierst, einen No Deposit Bonus in Form von Guthaben oder Freispielen. Regelmäßige Stammspieler oder aktive Kunden erhalten dabei über ein entsprechendes Feature monatlich oder wöchentlich prozentuale Teilrückzahlungen verlorener Einsätze. Und wenn dir das Casino nach den 50 Freispielen immer noch gefällt, kannst du den attraktiven Neukundenbonus mit Extra Freispielen aktivieren. Und du kannst somit auch mehr Spielrunden an den Echtgeldspielen in einer Online Spielothek absolvieren.
References:
https://s3.amazonaws.com/new-casino/lex%20casino.html
Du kannst darauf vertrauen, dass eine derartige Glücksspiellizenz zugleich auch ein Schutz gegen Abzocke ist. Es gibt genau festgelegte Regelungen zum Datenschutz, dem Umgang mit dem Geld der Spieler oder etwa der Fairness der Casinospiele. Damit ein Casino eine staatliche Glücksspiellizenz bekommt, muss es strenge Auflagen erfüllen. Je exakter du diese benennen kannst, desto einfacher wird es, den geeignetsten Anbieter zu finden – nämlich einen, der perfekt zu deinen Bedürfnissen passt. Unser umfangreicher Test hat diejenigen Casinos identifiziert, die dies erfolgreich umsetzen und somit ein herausragendes Spielerlebnis bieten. Unser umfassender Test der Online Casinos hat gezeigt, dass die Einführung einer offiziellen Lizenz in Deutschland ein positiver Schritt für die Branche ist. Das haben die meisten Online Casino-Betreiber erkannt und bieten inzwischen auch Casino Apps oder zumindest eine mobile Version ihres Casinos an.
Beachte, Demo Versionen sind in deutschen Casinos lediglich im eingeloggten Zustand möglich. Ideal für Neulinge, um Erfahrungen zu sammeln, und für erfahrene Spieler, um verschiedene Taktiken risikofrei zu testen. Tischspiele wie Roulette und Co. sowohl als auch Jackpots und Live Dealer Spiele werden momentan nicht angeboten. Die besten Online Casinos in Deutschland bieten neben einer großen Auswahl an beliebten Spielen auch hohe Gewinnchancen an. Denn seien wir ehrlich, wer mag kein extra Geld oder kostenlose Freispiele? Sobald das Guthaben gutgeschrieben ist, kannst du deine Lieblingsspiele starten und erste Gewinne erzielen.
References:
https://s3.amazonaws.com/new-casino/verde%20casino%20deutschland.html
References:
Test and anavar cycle before and after
References:
https://mel-assessment.com/members/skinsnail0/activity/1880677/
References:
Should you take anavar before or after workout
References:
https://md.un-hack-bar.de/s/Qfk6Wvfq-O
References:
Best online game sites
References:
https://ennis-floyd.thoughtlanes.net/top-vip-casino-programs-for-2026-exclusive-rewards
References:
Schecter blackjack sls c 1
References:
https://bookmarking.win/story.php?title=40-best-real-money-australian-online-casinos-for-january-2026
References:
Choctaw casino pocola ok
References:
https://pads.jeito.nl/s/7wZEE_1aZq
References:
Play online poker
References:
https://www.generation-n.at/forums/users/ashnut7/
steroids abs
References:
https://bonsaiyak30.bravejournal.net/dianabol-buying-guide-tips-dosage-where-to-buy
anabolic steroid in sports
References:
https://hedgedoc.eclair.ec-lyon.fr/s/_qxDss-Hl
steriods workout
References:
http://techou.jp/index.php?operawriter81
anabolic fast
References:
https://pattern-wiki.win/wiki/Dianabol_Tablets_Complete_Guide_For_Bodybuilders_On_Price
References:
Test e and anavar cycle before and after
References:
https://yogicentral.science/wiki/28_Giorni_dopo_Il_Tempio_delle_Ossa_prima_Londra_Video
drugs like steroids
References:
https://bom.so/zHIAFf
brad castleberry steroids
References:
https://dokuwiki.stream/wiki/ANAVAR_Oxandrolona_100_Cpsulas_MDH_LABORATORIES
References:
Anavar reviews before and after
References:
https://www.24propertyinspain.com/user/profile/1358575
References:
Anavar female before and after
References:
https://prpack.ru/user/pigeondrama2/
References:
60 days anavar before and after
References:
https://funsilo.date/wiki/Lifters_Lounge_Anmelden
gnc muscle building products
References:
https://md.un-hack-bar.de/s/JfCGvIYPV7
%random_anchor_text%
References:
https://coolpot.stream/story.php?title=heisshunger-die-besten-tricks-gegen-appetit-attacken