キャンベラ大学News & Media Research Centre(NMRC)が発表した『Unpacking Election Misinformation』は、2025年のオーストラリア連邦選挙を対象に、偽情報の発生・拡散・知覚・規制意識を総合的に測定した報告書である。YouGovが実施した全国オンライン調査(2025年5月12日〜6月2日、回答2,003件)と、接戦4選挙区(Deakin, Dickson, Gilmore, Werriwa)での半構造化インタビュー35件を組み合わせ、個人の情報行動と心理的変数を結びつけて分析した。測定項目には政治的効力感(内的/外的)、メディア・リテラシー経験、情報源別信頼度、偽情報識別課題、そして規制への態度が含まれ、全体を「アクセス」「識別」「反応」「制度意識」の四層構造で整理している。
情報アクセス:主流報道が残る一方、SNSが世代を分断する
主情報源として「主流ニュースブランド(TV・新聞・ニュースサイト)」を挙げた人は全体の52%。しかし18〜24歳では57%、25〜34歳では52%がSNSを選び、35歳未満ではSNSが主流メディアを逆転した。報告書はこの分岐を“split-source structure”と呼び、同一の政治空間が異なる情報経路で再構成されていることを指摘する。
SNSの中でも構成は異なる。18〜24歳ではTikTok(43%)、Instagram(39%)、YouTube(38%)が主要三位。25〜34歳ではYouTube(41%)が最上位で、特に男性では42%が「YouTubeを選挙情報の主経路」と答えた。動画解説型チャンネルや“オルタナ声”への関心が高く、報告書は「映像言説が若年男性の政治的認知を形成する主要な層をなしている」と分析する。
SNSで注目した発信者を問う設問では、「ニュースブランド」47%、「政党・政治家」44%、「一般ユーザー」37%。18〜24歳に限ると「インフルエンサー」が38%に上り、政治情報の可視化が報道からエンタメ領域へと拡張している。
信頼構造は逆である。最も信頼されたのは選挙管理委員会(AEC, 63%)、次いで公共放送ABC/SBS(54%)。SNSは70%が不信、生成AIチャットボットは信頼9%、不信73%。情報を得る場所と信頼を置く場所が乖離しており、報告書はこの二重構造を「民主的信頼の分断」として描く。
偽情報の出所:発信源としての政治家・政党
「偽情報を見聞きした」と答えた人は全体の60%。しかし、その発信源として最も多く挙げられたのは「政治家・政党」(66%)で、「ニュースメディア・記者」(41%)、「アクティビスト」(39%)を上回った。家族や友人を挙げた人は17%にすぎない。SNSを利用していない層でもこの傾向は変わらず、偽情報の知覚はプラットフォームではなく発話主体への不信として現れている。
主題別では「生活費(53%)」「原子力(51%)」「気候変動(47%)」「移民(44%)」が上位。CALD層(文化・言語的多様性層)では移民・外国影響関連が30%で他層より高く、報告書はこれを「アイデンティティを軸とした偽情報(identity-based misinformation)」と定義する。
この章の特徴は、偽情報を「SNS上の誤った投稿」として扱うのではなく、政治的メッセージ全体の中でどの発話が誤導的と受け止められるかを調べている点にある。
ディープフェイク遭遇:実体よりも“不確実性”
「選挙関連のディープフェイクを見た」と答えた人は12%。しかし「覚えていない/不明」が36%にのぼる。この“見たかどうか分からない”という不確実性そのものが、報告書の着眼点である。若年層、男性、高所得者、CALD層、メディア・リテラシー経験者で遭遇率が高く、形式別では「政治家のなりすまし画像」(44%)、「動画」(37%)、「音声」(20%)。報告書は「ディープフェイクは誤情報の一形態ではなく、知覚の曖昧化を拡大する装置」と位置づけている。
偽情報識別課題:党派的整合性が判断を支配する
専門ファクトチェッカーが抽出・検証した5件の事例(与党系2件、野党系2件、非党派1件)を提示し、真偽を判定させる識別タスクの結果は、正答率43〜58%。非党派例で最も低く、政治的対立に直接関わらない情報ほど判断が困難だった。右派は反野党的情報、左派は反政府的情報を「真実」と判断する傾向があり、信念の整合性が認知精度を上書きする。
識別能力を高める要因としては、ニュース消費量と内的効力感が有意に作用したが、メディア・リテラシー教育単独の効果は限定的。報告書はこの現象を“selective discernment bias”として理論化し、「確信を持って誤る」層の存在が政治的分極を強化すると述べる。
行動反応:無視か介入か
偽情報に直面した際の行動で最も多かったのは「無視する」(44%)。次いで「信頼できる人と議論」(25%)、「他メディア照合」(25%)、「検索」(20%)、「ファクトチェックサイト利用」(15%)。能動的な反応は少数派にとどまる。
年齢が若いほど「無視」は減り、照合・検索・警告・苦情といった介入行動が増える。リテラシー教育経験者では「照合」29%、「検索」23%、「FCサイト」20%、「警告」9%、「苦情」7%と、全項目で非経験者を上回った。行動差を説明する主因は内的政治効力感の高さであり、自分の理解と行動が政治に影響し得るという感覚が、検証行動を誘発している。外的効力感(制度が正すという信頼)は逆に無視行動と結びつく。報告書は「制度への依存が個人の検証を抑制する」という逆相関を指摘している。
インタビューの証言:嫌悪と疲労のなかで
35件のインタビュー記録は、数値の背後にある心理的反応を照らしている。多くの回答者は「誇張された広告」「攻撃的メッセージ」を“偽情報”と同義に語り、事実誤認よりも操作的言説を問題視した。SMSや自動音声メッセージの氾濫は「侵襲的」と受け取られ、政治広告の過激化が「真実性」そのものを損ねると感じる人が多い。
「情報が多すぎて判断できない」「誰も本当のことを言っていない」といった諦観も頻出する。報告書はこの状態を「疲労による脱関与(disengagement through fatigue)」と定義し、偽情報の影響は誤信よりも“判断放棄”を通じて現れると論じる。
規制態度:真実広告法への圧倒的支持
偽情報拡散に懸念を抱く人は75%。政府による制限支持70%、プラットフォームによる制限支持75%、成人向けリテラシー教育導入支持69%。最も顕著なのは「政治広告の真実性法制(truth in political advertising law)」導入支持83%である。
政治的立場による対照も興味深い。右派は偽情報への懸念が最も強いが、規制・教育への支持は最も弱い。左派は懸念がやや低いが介入支持は高い。報告書はこの非対称性を「表現の自由の価値付けの違い」と整理し、国家規制だけでなく広告の出所表示やメタデータ保全、アーカイブ制度といった透明化措置を提案する。
まとめ:アクセスと能力の二重インフラ
最終章は、偽情報対策を「アクセス」と「能力」の二重の基盤として整理する。第一に、公共放送や選挙管理機関のような信頼源へのアクセス保証。第二に、個人が情報を検証できる能力。両者が揃って初めて耐性が形成される。
報告書が強調するのは、偽情報の主要源がSNSではなく政治家・政党であるという点だ。この構造を前提に、対策はプラットフォームの削除やラベリングだけではなく、政治広告の透明化・証跡表示・広告アーカイブ制度へと拡張されるべきだとする。
選 挙期に見えたのは、誤情報そのものよりも、信頼の空洞である。情報を受け取る経路と信頼の拠り所がずれ、制度的発話も信用を失う。その結果、人々は「検証」より「無視」を選ぶ。NMRCの調査は、この退行を数値と語りの両面で描き出し、民主主義の疲弊を実証的に記録した。

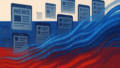

コメント
does testosterone increase hgh
References:
how much is a cycle of hgh – https://www.instapaper.com/p/17114945 –
cycle hgh
References:
hgh for bodybuilding Dosage (posteezy.com)
hgh how many iu’s per day
References:
Hgh long Term effects (http://pattern-wiki.win/)
how long to take hgh for bodybuilding
References:
hgh cycle for Bodybuilding (https://harrison-bossen-2.Thoughtlanes.net/)
hgh cycle for muscle gain
References:
hgh voor Vrouwen – https://md.ctdo.de/7foMn5DlQTGmIC-sytutOw/ –
long term side effects of hgh
References:
elearnportal.science
ciclo hgh
References:
synergycommons.net
hgh female dosage
References:
mogensen-norwood.technetbloggers.de
Real instructive and wonderful structure of content material, now that’s user pleasant (:.
I have recently started a site, the info you provide on this website has helped me tremendously. Thanks for all of your time & work.
That is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your rss feed and look ahead to in search of extra of your great post. Also, I have shared your site in my social networks!
There is noticeably a bundle to know about this. I assume you made certain nice points in features also.
I don’t normally comment but I gotta state thanks for the post on this one : D.
Great web site. Lots of useful info here. I’m sending it to a few friends ans also sharing in delicious. And naturally, thanks for your sweat!
Good web site! I truly love how it is easy on my eyes and the data are well written. I am wondering how I could be notified whenever a new post has been made. I have subscribed to your RSS which must do the trick! Have a great day!
Mit der Sicherheit und Anpassungsfähigkeit eines regulierten Casinos bietet Mr. O Casino eine erstklassige Spielerfahrung. Erhalten Sie bis zu 500 Freispiele bei Ihrer ersten Einzahlung und sammeln Sie Treuepunkte für exklusive Prämien bei Mr. O Casino!
Neue Spieler im Mro Casino können sich über einen attraktiven Willkommensbonus freuen, der sowohl Bonusgeld als auch Freispiele umfasst. Das Casino bietet eine breite Palette an Spielen, von klassischen Slots bis hin zu Live-Casinospielen, die von führenden Softwareanbietern der Branche bereitgestellt werden. Dank der gültigen Lizenz und der hohen Sicherheitsstandards können Spieler hier bedenkenlos spielen. Das Mro Casino bietet eine moderne und benutzerfreundliche Plattform, die sowohl auf dem Desktop als auch auf mobilen Geräten überzeugt.
References:
https://online-spielhallen.de/greatwin-casino-mobile-app-dein-umfassender-guide-fur-unterwegs/
Unbenutzte Freispiele verfallen nach Ablauf der Frist, ebenso wie Gewinne,
die ihr nicht rechtzeitig umgesetzt habt. In den meisten Fällen müsst ihr
die Freispiele innerhalb von 7 bis 30 Tagen nach Erhalt nutzen. Ja, Freispiele haben oft ein festgelegtes Ablaufdatum, das in den Bonusbedingungen angegeben ist.
Einige Casinos bieten sogar Freispiele ohne Umsatzbedingungen an, wodurch Gewinne direkt
ausgezahlt werden können. Meist werden diese Freispiele direkt
bei der Registrierung oder als Teil von Aktionen gutgeschrieben.
Denn Einzahlungsboni wie beim Instant Casino bieten oft deutlich
bessere Vorteile – höhere Bonusbeträge, Cashback und
mehr Freispiele. Beachten Sie, dass manche Boni Einschränkungen bei
Tischspielen haben, deshalb ist ein Blick in die
Bonusbedingungen wichtig. Manche Echtgeld Boni ohne Einzahlung
kann man auch für Tischspiele einsetzen.
Der übliche Höchstgewinn liegt zwischen 25 und 50 €,
wie viel du genau bekommst, hängt aber davon ab, wie viel du während der Freispiele gewinnst.
Die Experten von Automatenspielex empfehlen diese
Alternativen zu 50 Free Spins ohne Einzahlung,
um Spielern noch mehr Chancen auf kostenlose Gewinne zu bieten.
Wie gut ein Bonus ist, hängt nicht nur von der Höhe der Freispiele ab, sondern auch von anderen Faktoren. Auch wenn 50 Freispiele, die sofort erhältlich sind, verlockend
klingen, solltest du bei der Auswahl genau hinschauen.
References:
https://online-spielhallen.de/nomini-casino-aktionscode-dein-schlussel-zu-besseren-pramien/
AllySpin Casino überzeugt mit einer breiten Spielauswahl, attraktiven Boni und modernen Zahlungsmethoden, einschließlich Kryptowährungen.
AllySpin Casino bietet keine spezielle mobile App, jedoch ist die Website vollständig für Mobilgeräte optimiert.
Neue Spieler erhalten einen 200 % Willkommensbonus bis zu 500 € – ohne Wettanforderungen.
Das Casino bietet eine breite Auswahl an Slots, Roulette, Baccarat und Tischspielen und deckt damit alle Spielstile ab.
Mit einer Mindesteinzahlung von nur 10 € können Sie sofort Geld auf Ihr Konto einzahlen und mit Ihren Lieblingsspielen beginnen. Durch die Zusammenarbeit mit erstklassigen Anbietern können wir
eine vielfältige Auswahl an Slots, Tischspielen, Live-Dealer-Erlebnissen und Jackpots
anbieten, die alle Spielerwünsche abdecken. Neben Casinospielen bietet Ally Spin Casino ein umfangreiches Sportwettenangebot, das Fußball, Basketball, Tennis, Eishockey und vieles
mehr umfasst. Wir bieten auch eine Reihe von Sofortgewinnspielen an, bei denen schnelles
Gameplay schnellere Ergebnisse und Non-Stop-Action bedeutet.
Bei den Limits für Ein- und Auszahlungen zeigt Ally Spin Casino
Österreich eine ausgewogene Struktur, die sowohl Gelegenheitsspieler als auch ambitionierte Highroller anspricht.
Viele Angebote sind in mehreren Stufen erhältlich, sodass sowohl Gelegenheitsspieler als auch Highroller
passende Limits finden. Die klare Gliederung der Lobby nach Slots,
Live-Casino, Crash-Games und Sportwetten sorgt dafür, dass sich selbst neue Nutzer schnell zurechtfinden und gezielt nach ihren Lieblingsspielen suchen können.
References:
https://online-spielhallen.de/buran-casino-bewertung-ein-detaillierter-blick-auf-ein-serioses-online-casino/
There are many Crown Coins Casino bonus offers for regular players as well.
Instead, you’re rewarded instantly upon registration allowing you to explore and enjoy
real casino-style gameplay right away. Whether you’re here for fun or aiming to
redeem real cash prizes, Crown Coins offers a smooth and secure entry into social casino gaming.
Each completed challenge gives you more than just bragging rights — earn bonus spins, mystery boxes, and ticket entries to major prize draws.
The Crown Rewards program is the cornerstone of our appreciation for player loyalty.
All offers are easy to claim and clearly explained, so you know exactly how to make the most of
them. Our digital platform is packed with engaging promotions available around the clock.
There’s no need to spend money to gain a generous bonus when signing up for
a new account. Users can use these offers to get more coins, enter more prize draws
and stay active every day. This company knows that player incentives play a key role
in attracting and keeping users in the ever-competitive social
casino world.
References:
https://blackcoin.co/betcity/
Gonzo Casino seems to position itself more of a traditional casino, focusing more on slot games.
This is a vibrant online gaming platform which was founded in 2024.
Players are strictly forbidden to use duplicate accounts.
Our Safety Index rating is designed to showcase the safety and fairness of online casinos.
There aren’t any real game-changer features or tremendous bonuses that will bless you with super winnings.
Gonzo Casino offers a No Deposit Bonus for players who sign up
and create a new account. Other than that, expect most of the games to have a free
demo version, but to use it, you have to create a casino account.
Welcome Bonus can be claimed by newly registered
players only and requires a minimum deposit. Free professional educational courses for online casino employees aimed
at industry best practices, improving player experience, and fair approach to gambling.
You can click these links to clear your history or disable it.
This menu’s updates are based on your activity.
References:
https://blackcoin.co/popular-variations-of-casino-slots-game-rules-and-descriptions/
This project is based on one of my other repositories,
josStorer/chatGPT-search-engine-extension 该API Key用于转发API,需要将Host改为api.chatanywhere.tech(国内首选)或者api.chatanywhere.org(国外使用)。 Your support is
greatly appreciated!
When we try to use the Sky go app on the computer it does not work properly.
Anybody with individual sports packs will need to upgrade.
Only customers with the complete Sky Sports pack will get
access to Sky Sports+ at no extra cost. As part of
the Sky Sports+ launch, NOW members will also be able to pause and
rewind live sports content for the first time.
Integrated into Sky TV, streaming service NOW, and a revamped
Sky Sports mobile app, Sky Sports+ will make it easier for fans to browse, discover and watch the sport
they love. Launching this August, Sky Sports+ is transforming the amount of choice sports fans have, all at no extra cost
References:
https://blackcoin.co/lucky-hunter-casino-a-comprehensive-review/
Because the Star is located geographically in Sydney’s premium entertainment area, it’s able to provide accommodations that are uniquely luxurious.
Rocking live bands, hilarious comedians, and engagingly unique musical acts are also on-hand.
The one thing that is missing from the facility is the chance to
enjoy electronic gaming. Whether you are a low stakes player or a high roller, you’ll find the table that’s just right for
you at this casino.
As part of the Demerger, Tabcorp sought a ruling from the
Australian Taxation Office on the taxation implications for shareholders.
Eligible shareholders who wished to sell their shares under the Voluntary
Share Sale Facility were required to return a Sale Instruction Form
by the Closing Date. Based on a share price of $5.68, being the closing price of The Star Entertainment Group (SGR) shares on the Australian Securities Exchange on the Record Date, an Unmarketable Parcel was any holding of 88 shares or less.
Payment of the sale proceeds were made to participating shareholders
on 27 May 2016 in accordance with their payment instructions as recorded on the share register.
Alarming laws and legislation have been passed in other countries that
can significantly impact people’s lives. Though a
few movies without the most sterling scores sometimes slip through, this section is a
splendid resource on Certified Fresh movies currently streaming on Tubi.
“I’m pretty sure there’s plenty of deals around that can be done to stop it from doing that,” he said.
“To me, it has been a disaster dealing with the management of Star and I think … there is no doubt the board should be blamed for how bad it is,” he told ABC Radio
Brisbane. He said poor management has been the company’s main issue.
Now the chances of losing it all have been turned back onto one of Australia’s biggest casino operators.
At casinos, the odds are never in a punter’s favour. “Traditionally, probity checks have taken many months for new operators in casinos across the different state jurisdictions,”
Mr Jones said.
References:
https://blackcoin.co/spinstralia-casino-a-comprehensive-review/
You have observed very interesting details! ps decent web site.
casino mit paypal
References:
https://jobs.ethio-academy.com/employer/trusted-bitcoin-casinos-accepting-paypal-deposits/
australian online casinos that accept paypal
References:
https://futuremanager.nl/employer/paypal-casinos-best-online-casinos-that-accept-paypal-deposits/
best online casino usa paypal
References:
https://icqpro.com.br/employer/paypal-casinos-in-australia-2025-top-online-casinos-accepting-paypal-onlinecasinopulse/
online slots paypal
References:
https://muwafag.com/compani/top-online-us-casinos-that-accept-paypal-in-dec-2025/
online slots uk paypal
References:
https://skillproper.com/employer/best-online-casinos-australia-top-aussie-real-money-sites-2025/
casino online uk paypal
References:
razib.cretechbd.com
paypal casino canada
References:
https://www.lookingforfresher.com/profile/jani2563499756
online slot machines paypal
References:
https://career.cihpng.org/companies/best-10-real-money-online-casinos-gambling-sites-usa-2025/
online casino paypal einzahlung
References:
http://www.advertiseajob.co.uk
References:
Should you take anavar before or after lifti
References:
kilic-rosenkilde-3.thoughtlanes.net
References:
Play slot machines
References:
https://pad.karuka.tech/s/52RN67Zh0
References:
Female anavar before and after pics reddit
References:
ondashboard.win
References:
Casino slot machine
References:
prpack.ru
body building drug
References:
downarchive.org
negative side effects of sam-e
References:
bookmark4you.win
anabolic precursor
References:
https://bookmarkspot.win/story.php?title=suplemento-testosterona-las-mejores-opciones-en-comparacion
steroid addiction symptoms
References:
bookmarkstore.download
Wow! Thank you! I constantly wanted to write on my website something like that. Can I include a part of your post to my blog?
References:
Anavar results before and after female pictures
References:
livebookmark.stream
References:
Female anavar before and after pics reddit
References:
kanban.xsitepool.tu-freiberg.de
legal supplements that act like steroids
References:
freebookmarkstore.win
References:
Yukon gold casino
References:
stackoverflow.qastan.be
References:
Kelowna casino
References:
buyandsellhair.com
References:
Grand casino
References:
morphomics.science
%random_anchor_text%
References:
https://adsintro.com/
best supplements for muscle definition
References:
bookmarkfeeds.stream
References:
Treasure island jackpots
References:
trade-britanica.trade
References:
Gran casino barcelona
References:
https://clashofcryptos.trade
workout steroids for sale
References:
community.srhtech.net
steroid bulk cycle
References:
fakenews.win
best muscle gain products
References:
nerdgaming.science
common anabolic steroids
References:
may22.ru
References:
Lucky eagle casino
References:
onlinevetjobs.com
References:
Winning at slots
References:
graves-mackenzie-3.hubstack.net
References:
Slots online
References:
pads.zapf.in
References:
Roulette strategy
References:
https://images.google.cg
References:
Manistee casino
References:
maps.google.gg
References:
Atlantic club casino
References:
maps.google.gg
References:
Gulfport casinos
References:
https://oren-expo.ru/
References:
Regles blackjack
References:
md.un-hack-bar.de
References:
No deposit roulette
References:
http://www.aaisalearns.ca/
References:
Treasure island casino
References:
chessdatabase.science
References:
William hill slots
References:
https://king-wifi.win/
best steroid for lean muscle
References:
https://classifieds.ocala-news.com/