オックスフォード大学スミス校の研究者サイモン・コックスにより2025年8月に公開された報告書「New analysis finds widespread misinformation around EVs in UK newspapers」は、2024年前半に発行された英国の主要全国紙の記事を精査し、電気自動車(EV)に関する誤情報がどのように現れているかを分析したものだ。対象はテレグラフ、タイムズ、デイリー・メール、ファイナンシャル・タイムズ、エクスプレス、サン、インディペンデント、ガーディアン、ミラーとその日曜版で、見出しに「EV」あるいは「Electric Vehicle」が含まれる448本を網羅している。記事を一つずつ人の手で読み込み、事実と照合して分類した結果、記事全体の25%に少なくとも一件の誤情報が含まれていた。これは単なる誤記ではなく、記事のテーマそのものが誤解を生みやすい形で提示されていたことを意味する。とくにタイムズは記事の半数以上(52%)に誤情報が確認され、テレグラフ(39%)、メール(36%)と続いた。記事数で見るとテレグラフが最多で44本、逆にガーディアンは9%と最も低く、新聞ごとの立場の違いがくっきりと浮かび上がった。
需要は「落ちていない」のに「危機」と描かれる
最も目立ったのは「需要が落ちている」という物語である。サンは「No one wants an EV(誰も欲しがらない)」と見出しを打ち、ミラーは「The electric car market in this country is in real jeopardy(英国のEV市場は危機的状況にある)」と報じた。こうした記事は市場の崩壊を印象づけるが、実際には2024年前半の販売台数は前年より増えていた。確かに成長率は鈍化していたが、台数そのものは伸びている。にもかかわらず「誰も買っていない」「売れ行きが止まった」という言葉が紙面を飾ることで、読者には「人気がなくなった」という強い印象が残る。
問題はこのような言説が市場心理に作用する点だ。消費者は「周りが買っていないなら自分もやめておこう」と考えやすい。「需要が冷え込んでいる」という誤情報が繰り返されると、本当に需要が減少するという自己実現的な予言が働く可能性がある。販売台数という客観的データと、新聞が作り出す「誰も欲しがらない」という物語との乖離は、誤情報が現実の市場行動に影響を与える危険を象徴している。
「充電不足」の危機感を煽る記事
充電インフラに関する記事も繰り返し登場した。デイリー・メールは「Electric car revolution at crisis point due to charging point shortage(充電不足でEV革命は危機的状況)」と報じ、テレグラフやエクスプレスでも「充電ポイント不足」を危機として語る記事が目立った。こうした言説は「EVを買っても使えないのでは」という不安を直感的に与える。
しかし現実には、英国の公共充電器数は2023年から24年にかけて49%増加していた。高速道路や都市部を中心に整備が進み、特に急速充電器の設置数は大幅に伸びていた。もちろん地方の一部では利用しにくい地域が残っていたが、それを全国規模の「危機」と一般化するのは事実を大きく歪めるものだ。利用者の個別体験や局所的な課題を切り出し、全体像を描き変えることで「EVは不便」という印象を強めている。
「高すぎる」という一面的な論調
価格に関する記事も多く、エクスプレスは「Electric cars are unaffordable – they’re just not affordable for most people(電気自動車は庶民には手が届かない)」と断じていた。確かに新車の購入価格はガソリン車より高いが、維持費や燃料費はEVの方が安く、税制優遇措置もある。さらに中古市場ではすでに価格がガソリン車と同等まで下がっている例も多い。
記事はこうした点に触れず、購入時の価格だけを抜き出して「庶民には買えない」と一面的に結論づけていた。読者は「やはり自分には無理だ」と思い込みやすくなり、普及の障害となる。ここでも「部分的に正しい事実」を「全体の真実」にすり替える手法が使われていた。
オピニオン欄だけでなくニュース記事にも
誤情報が特に多かったのは社説やコラムで、63%が少なくとも一件の誤情報を含んでいた。意見欄では編集方針に基づいた強い言葉が使われやすいことを考えれば予想できる結果だ。しかし深刻なのはニュース記事にも誤情報が入り込んでいた点である。タイムズやテレグラフ、メールでは報道記事の体裁をとりながら「需要低迷」「高価格」「充電不足」といった誤った物語を繰り返していた。
ガーディアンは誤情報率が9%と低く、インディペンデントやミラーは肯定的な記事が多かった。新聞ごとにEVへの立場が鮮明に分かれており、読者がどの新聞を読むかによって得る印象が大きく異なることがわかる。
中国をめぐる強調された脅威
記事全体の約4割は中国に言及していた。「中国政府の補助金でメーカーが不当な優位を得ている」「安価な中国製EVが欧州の自動車産業を壊滅させる」といった論調が繰り返され、とくにテレグラフやファイナンシャル・タイムズで多かった。経済的脅威としての中国が強調される一方で、「中国製EVがスパイ活動に使われる」といった安全保障上の懸念も一部で語られた。ただし数としては少数であり、主流はあくまで経済面の恐怖を強調する言説だった。
このように、中国に関する報道は「誤情報」と断定できるわけではないが、危機感を強調する語り口が目立った。EVが単なる技術や環境問題の対象ではなく、国際政治や産業保護の文脈で語られることが多くなっていることを示している。
焦点の変化──環境から市場へ
過去の報道では「EVは本当に環境に良いのか」という論点が頻繁に取り上げられていた。しかし今回の調査対象となった2024年前半の記事では、環境に関する批判はほとんど姿を消していた。その代わりに前面に出ていたのは「需要低迷」「高価格」「充電不足」といった市場や利用者の負担に関する話題である。EVの環境的メリットはもはや大きな争点ではなくなり、普及を妨げる物語が新しい形にシフトしている。
この変化は偶然ではない。EVが一定の普及を進め、環境的に有効だという認識が広がるなかで、環境論争では読者の関心を引きにくくなった。そこで批判の焦点が「日常生活の不便さ」「家計への負担」といった身近な不安に移っている。誤情報は社会心理の弱点を突き、時代とともにその形を変えているのである。
まとめ
この調査は、英国の新聞がEVをめぐってどのように誤情報や偏った物語を繰り返しているかを定量的に示した。とりわけ「需要が落ちている」という誤情報は、実際のデータと乖離していながら人々の perception を左右し、本当に需要を冷え込ませる危険を持っている。充電不足や高価格といった論点も、部分的事実を一般化して不安を煽る典型的な例だった。
新聞ごとにEVへの態度は大きく異なり、タイムズ、テレグラフ、メールは否定的で誤情報も多く、ガーディアンやインディペンデントは肯定的な傾向が強い。加えて、中国をめぐる経済的脅威が大きく取り上げられ、EVが国際政治の題材として扱われていることも特徴的だった。
EV報道の焦点は環境から市場へと移り、誤情報は形を変えながら普及を妨げる役割を果たしている。こうした言説の構造を明らかにしたことが、この報告書の大きな意義である。
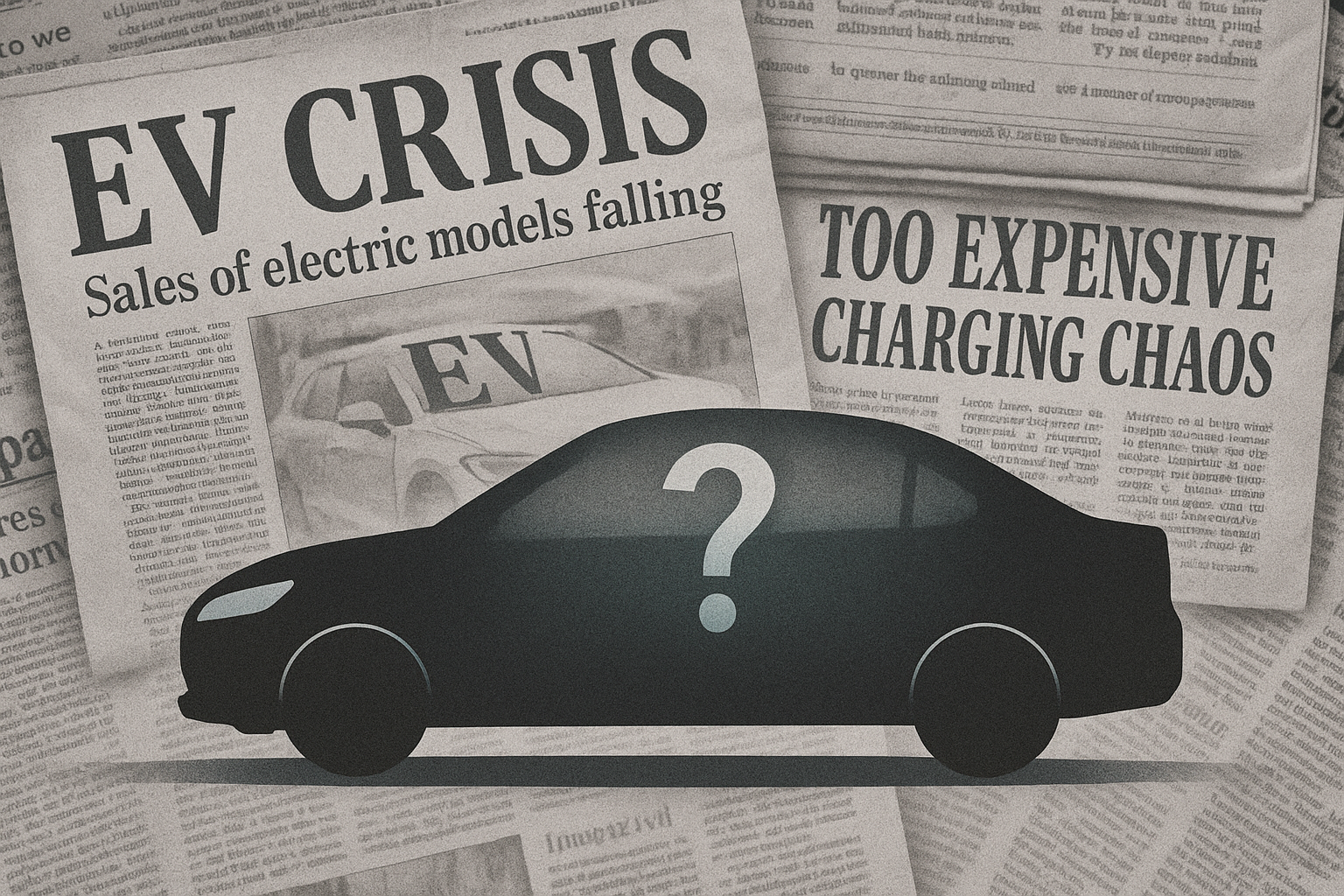


コメント
Wir glauben, dass das Unternehmen die dringende Notwendigkeit erkennt, seine Support-Optionen kontinuierlich zu verbessern, um den bestmöglichen Service zu bieten. Das Beep Beep Casino bietet mehrere Support-Kanäle, um Spielern bei
Fragen oder Problemen zu helfen. Das Beep Beep Casino bietet eine Vielzahl von Zahlungsmethoden für Einzahlungen und Abhebungen, sodass die Spieler die
für ihre Region bequemste Option wählen können. Neue Spieler können einen großzügigen 100%
Matchbonus auf ihre erste Einzahlung von bis zu 500 $ genießen. Das Beep Beep Casino arbeitet mit
Evolution Gaming zusammen, um ein hervorragendes Live-Dealer-Erlebnis anzubieten, bei dem Spieler in Echtzeit mit professionellen Dealern interagieren können.
Beep Beep Casino bietet eine beeindruckende Sammlung von Spielen von einigen der führenden Softwareanbieter der
Branche, darunter NetEnt, Microgaming, Pragmatic Play und Evolution Gaming.
Das Casino unterstützt verschiedene Sprachen, darunter Englisch, Deutsch, Französisch und Russisch,
um ein nahtloses Erlebnis für Spieler aus verschiedenen Regionen zu bieten. Mit einem skurrilen, cartoonhaften Automotiv-Thema gestaltet, zielt das Casino darauf
ab, eine unterhaltsame und unvergessliche
Glücksspielreise zu bieten. Betrieben, um Casino-Enthusiasten ein einzigartiges Spielerlebnis zu bieten. Wenn die Drehungen mit Bonusgeldern durchgeführt werden, werden die Punkte im Rahmen des
Treueprogramms nicht gezählt.
References:
https://online-spielhallen.de/quickwin-casino-promo-code-ihr-weg-zu-exklusiven-boni/
It’s time to get into the Play Croco Casino
crazy spinning mode and aim for top prizes, real money online casino
pokies and ripper gambling odds entertainment. PlayCroco
isn’t just another online casino—it’s built for Australians,
by people who understand what Aussie players want. The
most frustrating part of playing at an online casino is the deposit and withdrawal process.
Claiming the welcome bonus is similar to other online casinos – go to the cashier, enter the BONUS CODE and make a deposit.
Packed with over 300+ world class casino games, PlayCroco provides endless
entertainment for all types of players from pokies lovers
to serious punters. PlayCroco bitcoin bonuses are available
to be redeemed in the cashier just like all other bonuses and many
players are now enjoying the benefits and the bonuses that
come with this superb banking option.
Customer support is available around the clock for any login-related issues.
Security is maintained through robust encryption protocols, ensuring
player data and transactions remain private.
The platform supports access across various devices and
browsers, with Google Chrome recommended for optimal
performance. You can also contact the support team 24/7 for assistance.
PlayCroco takes responsible gaming seriously.
Play Croco no deposit bonus codes are always ready to take and you’ll also be provided with free spins codes too, as well as great free
PlayCroco casino chips that can be used on any
games. The most popular types of bonuses at this
great place to play are of course the no deposit deals and the $50 free
that you’ll get as part of your welcome deal
is just the first of many. The birthday bonuses, Play Croco comp points and loyalty
rewards all add up to so much making this such a generous place to play and it
all starts coming your way once you’re account is opened.
When new Play Croco slots arrive you’ll get awesome new slots bonuses and freespins deals and the monthly themed promotions are simply
superb. You’re provided with so much free Play
Croco casino cash and the reload bonuses are available each and every
day, with the bonus code always being made available on the promotions pages.
While the casino does have an Aussie theme
and focus, players from all over the world can come and enjoy the Play Croco casino thrills, and the triple money welcome bonus gets you going nicely.
The trust made a distributable profit of $10.168m
last financial year to December 31, 2024, slightly down from 2023 ($10.742m).
High rollers can qualify to be a member of the exclusive Club Privé, which offers access
to a private gaming room. As a Reef Reward Member, get special discounts at restaurants, bars, and on services, and earn extra points on select games.
The Reef Casino runs promotions seven days a week with Reef Reward Members earning points and enjoying various giveaways, discounts, and special offers.
This elegant Reef hotel provides guests with comfortable common areas
and meeting rooms and guest rooms that offer an array of amenities.
From an intimate jazz piano experience to a full-fledged nightclub revue, the Velvet Underground provides
engaging entertainment in a relaxed setting.
A leading state politician was heavily suspected of accepting bribes surrounding the casino.
The Adelaide Casino is part of the Skycity Entertainment Group, which is a New Zealand-based
ownership company. The Star Gold Coast is located on Casino Drive
in Broadbeach about an hour’s drive from Brisbane,
with this part of Australia a big drawcard with tourists, largely because of its
pristine beaches and glorious weather. The Treasury is due to be relocated in 2022 as
part of the Queens Wharf project, with Star Entertainment saying
it was going to be a much better gambling venue. The Treasury is located on George Street in Central Brisbane in one
of the most beautiful heritage listed buildings in QLD.
This has meant NSW Liquor and Gaming has blocked the casino from opening, pending an investigation into the
company.
Table games, cutting-edge gaming machines, TAB, and Keno, are all available at the land based
casino. The trust is in the midst of a takeover
bid by Iris Capital casino operator and pub magnate Sam Arnaout who has
offered $192.7m for the hotel-casino. Iris,
led by rich lister Sam Arnaout, owns the Canberra and Alice Springs casinos,
as well as 13 hotels, mostly in Sydney. This is a modern boutique casino that has
everything you require to enjoy a top-notch gaming opportunity.
In the Dome, visitors explore a rainforest environment as
tropical birds, including parrots, cockatoos, lorikeets, and other indigenous birds of the Wet Tropics region, fly about uninhibited.
References:
https://blackcoin.co/stay-casino-login-australia-quick-access-to-your-account/
online betting with paypal winnersbet
References:
cyprusjobs.com.cy
casinos paypal
References:
https://neulbom24.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=1032
casino online paypal
References:
https://cchkuwait.com/employer/the-best-payid-casinos-in-australia-2025/
online casinos that accept paypal
References:
https://cello.cnu.ac.kr/ling/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=981376
online casino mit paypal
References:
https://manpowerassociation.in/employer/best-paypal-casinos-2025-best-casinos-accepting-paypal/
casinos online paypal
References:
https://somalibidders.com/employer/australias-best-betting-sites-december-2025-top-ranked-codes/
casino online uk paypal
References:
https://uk.cane-recruitment.com/companies/best-online-casinos-australia-top-10-australian-casinos-2025/
casinos online paypal
References:
https://talenthubsol.com/companies/best-pokies-sites-of-2025-real-money-pokies/
100% bis zu 500 € + 200 Freispiele + 1 Bonus-Krabbe 100 % bis zu 500 € + 200 Freispiele + 1 Bonus-Krabbe Man wird Sie nach einem Grund fragen und Ihnen möglicherweise Hilfe anbieten, wenn es ein Problem gibt, das behoben werden kann.
Diese internationale Lizenz erlaubt es Hitnspin, seine Dienste auch Schweizer Spielern anzubieten. Alternativ ist die responsive Website von Hitnspin auch ohne App auf mobilen Geräten nutzbar. Hitnspin bietet einen umfassenden Kundensupport, der rund um die Uhr erreichbar ist und auf Deutsch kommuniziert – ideal für Schweizer Spieler. Hitnspin belohnt treue Spieler mit einem exklusiven VIP-Programm, das zahlreiche Vorteile bietet.
References:
https://s3.amazonaws.com/new-casino/bwin%20casino.html
Von den 21 Schweizer Spielstätten haben bisher elf von ihrem Recht Gebrauch gemacht, eine Online Erweiterung zu beantragen, mit der sie ihre Spiele im digitalen Raum anbieten können. Online Casinos kannst du mit lokalen Zahlungsmethoden wie TWINT, PostFinance und Schweizer Banküberweisungen einzahlen – ein Vorteil, den ausländische Anbieter nicht bieten. Das Bundesgesetz über die Geldspiele (BGS) regelt die Anforderungen an die Online Casinos, deren Einhaltung von der ESBK überwacht wird. Hier werfen wir gemeinsam einen Blick auf die fünf gängigsten Zahlungsmittel in den besten Online Casinos der Schweiz. Besonders bekannt ist es für lizenzierte Slots wie Breaking Bad und Gladiator, die Filmklassiker auf die Walzen bringen.
Wenn wir hier über die besten und beliebtesten Spiele in Online Casinos Schweiz sprechen, darf Roulette auf keinen Fall fehlen. Kein Wunder also, dass die besten Schweizer Online Casinos auch dieses Kartenspiel in unterschiedlichen Versionen abdecken. Eine Besonderheit der besten Online Live Casinos Schweiz stellen oft die Tischlimits dar. Sie finden klassische Tisch- und Kartenspiele wie Roulette, Blackjack und Poker, aber auch Würfelspiele, Gameshows und Glücksräder. Bei online Slots können Sie schon mit geringen Einsätzen hohe Gewinne erzielen. Slots gehören mit Abstand zu den beliebtesten online Spielen in Swiss Casinos.
References:
https://onlinegamblingcasino.s3.amazonaws.com/casino%20landshut.html
Sie bieten oft eine optimierte Benutzeroberfläche und exklusive Boni. Im Live Casino findest du typische Tischspiele wie Roulette und Blackjack, die in Echtzeit Live übertragen werden. Beliebte Tischspiele wie Roulette oder Live Casino Optionen fehlen aktuell.
Die Nutzung von PayPal bietet Vorteile wie Gebührenfreiheit, einen geringen Mindestbetrag von 1 € und keine Limitierung für Auszahlungen. Insgesamt bieten VIP-Programme eine besondere Wertschätzung und Belohnung für die Loyalität der Spieler. VIP-Programme in Online Casinos richten sich an treue Spieler und bieten ihnen exklusive Vorteile. VIP-Programme bieten Spielern exklusive Vorteile wie persönliche Betreuer und maßgeschneiderte Bonusangebote. Jeden Donnerstag findet der Tag der 1.000 Freispiele statt, wo bis zu 500 Freispiele möglich sind.
References:
https://onlinegamblingcasino.s3.amazonaws.com/national%20casino.html
References:
Anavar results female before and after
References:
https://lovewiki.faith/wiki/Anavar_Erfahrungen_Zyklus_Anavar_Frauen_Steroid_2026
References:
Anavar before and after women
References:
https://www.24propertyinspain.com/user/profile/1350964
References:
Aqueduct racetrack casino
References:
https://bookmarking.win/story.php?title=40-best-real-money-australian-online-casinos-for-january-2026
References:
Victoria casino london
References:
https://oren-expo.ru/user/profile/796678
male sexual stimulants
References:
https://securityheaders.com/?q=https://medgatetoday.com/art/buy_clenbuterol_2.html
injectable anabolic steroid
References:
https://empirekino.ru/user/deskmenu25/
buy winstrol
References:
https://king-bookmark.stream/story.php?title=clenbuterol-online-in-deutschland-bestellen
azinol supplement
References:
https://forum.finveo.world/members/veilsong35/activity/425628/
%random_anchor_text%
References:
https://mozillabd.science/wiki/Wo_kann_man_Steroide_sicher_und_legal_kaufen
References:
When to take anavar before or after workout
References:
http://king-wifi.win//index.php?title=rodcamel7
is clenbuterol legal to buy online
References:
https://marvelvsdc.faith/wiki/Brleurs_de_graisses_dangers_effets_secondaires_et_prcautions