2024年12月に実施されたガーナ大統領選挙は、民主的な権力移行の文脈においては一見平穏に見えるが、その裏側では複雑な情報戦が繰り広げられていた。偽情報の拡散、プラットフォームの無対応、政治と報道の癒着、AI生成コンテンツの台頭など、現代選挙を取り巻く典型的なリスクがすべて揃っていたといってよい。
本稿では、Research ICT Africaが公表した詳細な調査報告書『Exploring the Role of Multistakeholder Coalitions in Mitigating the Threats to Information Integrity during Ghana’s 2024 Elections』(2025年5月)を基に、コアリションによる偽情報対策の実践とその成果、そして課題について紹介する。
偽情報は抑え込まれたのか?
結論から言えば、偽情報は選挙プロセスにおいて多数流布されたが、それが結果を決定的に揺るがす事態には至らなかった。これは特筆すべき点である。報告書によれば、この安定の背後にはいくつかの要因がある。とりわけ興味深いのは、二大政党である与党NPP(New Patriotic Party)と野党NDC(National Democratic Congress)がお互いの主張をファクトチェックしあうという、ある種の「相互監視」構造である。これは歪んだ形ながらも、均衡装置として機能した。
また、ガーナの市民社会は非常に活発であり、報道機関、NGO、研究者が複数のメカニズムを通じて誤情報の検出と修正に努めた。Electoral Commission(選挙管理委員会)やCoalition of Domestic Election Observers(CODEO)といった機関も情報の透明性に一定の努力を見せた。
直前に立ち上がった「多主体コアリション」
選挙の約1か月前、ガーナでは市民社会主導による「選挙偽情報対策コアリション」が急ごしらえで組織された。Penplusbytes、Dubawa、GhanaFactなど既存のファクトチェック団体を中核に、メディア関係者、研究者、選挙管理機関が参加し、WhatsAppとメールによる情報共有、選挙当日の状況室設置などを通じて、即応的な対応体制を構築した。
同コアリションは、南アフリカで開発されたSANEF(South African National Editors’ Forum)のリスク評価ツールを改変し、攻撃対象、頻度、影響度に基づいて偽情報リスクを評価・優先順位化した。特に注目されたのは以下の3項目である。
- Electoral Commissionと関連ページのハッキング
- AIによる合成コンテンツ(ディープフェイク等)
- 本物の情報へのアクセスを歪める偽情報
実際、これらの項目は選挙期間中に相応の脅威を示したが、最も広範に流布したのは「選挙日の誤情報」「選挙結果に関する虚偽投稿」「暴力事件に関する古い映像の再利用」などであった。
AIによる介入とその追跡
注目すべきは、NewsGuardが報告した「171件のAI生成アカウント」による政治的介入である。X(旧Twitter)上で、Bawumia(与党NPP候補)を賛美し、Mahama(野党NDC候補)を攻撃する投稿が自動的に行われ、これらはすべてAI生成と疑われるプロファイルで構成されていた。
他方で、対抗手段としてもAIは利用された。Full Fact AI、Media Watch App、PenplusbytesのDisinformation Detection Platform(DDP)などが導入され、数千件に及ぶ投稿の自動分析とファクトチェックが試みられた。だが、これらのツールの適用範囲は限定的で、特にWhatsAppやTelegramなどのクローズド環境には対応できなかった。
メディアは機能したのか?
一定の役割は果たしたが、深刻な構造的問題も浮き彫りになった。最も象徴的な例は、与党NPPの地域幹部が所有するWontumi FMが誤情報を放送し、司会者が拘束されたものの、局には一切の制裁がなかった件である。選挙管理機関や報道規制機関が政治的に中立に機能していない状況が明確となった。
また、多くの地方メディアは情報検証の訓練や人材を欠いており、SNSで拡散された誤情報をそのまま伝える例が多かった。報道現場の制度疲労は、偽情報対策にとって深刻なボトルネックである。
誤情報の具体例:選挙当日に起きた事象から
報告書に挙げられた偽情報の事例から、特に象徴的なものを以下に挙げる。
- 選挙日が変更されたとする誤情報
- 投票所で候補者が食べ物を提供して買収しているという虚偽動画
- BawumiaがMahamaに票を入れたという合成動画
- NDCが手動カウンターを使って生体認証をハッキングしているという陰謀論
- MahamaがLGBTを推進しているという偽キャンペーン
- Bawumiaが「24時間経済では幼稚園児が深夜に登校する」と語ったという誤引用
これらの事例は、AIや画像加工、文脈の切り取りによって生成され、SNSを通じて急速に拡散した。
コアリションの限界と残された課題
コアリションの活動は評価されるべき点も多いが、いくつかの本質的な課題も明らかになった。
- ファクトチェックの拡散力の弱さ:誤情報に比べて修正情報の到達範囲が圧倒的に狭い。
- 公式機関の反応の遅さ:Electoral Commissionなどが迅速に対応しないことで、誤情報が拡散しやすくなる。
- 地方言語・非都市部への伝達困難:英語中心の情報発信では、地方コミュニティに届かない。
- ビッグテックとの非協力:FacebookやXとの連携が制度化されておらず、アカウント停止や情報提供が一方的。
- 構造的持続性の欠如:多くの活動が選挙期間限定で、平時に備える恒常的な体制がない。
今後に向けた論点
報告書は、単なる「ファクトチェック」から一歩進んで、予防的・構造的対応を求めている。具体的には、以下のような提案がなされている。
- 「情報への免疫」を育てるアプローチ:事前に典型的な偽情報に触れさせることで、耐性を高める(inoculation approach)。
- ビッグテックとの制度的協定構築:コンテンツ監視の透明性確保と共同モデレーション体制の必要性。
- 情報アクセスの多言語対応と地域化:地方言語によるファクトチェック拡充とラジオなど地域媒体との連携。
2024年のガーナ選挙は、偽情報という現代民主主義に共通する脅威に対し、限定的ながらも注目すべき実践を示した。多主体連携、AI活用、状況室設置といった対策は、日本を含む他国の取り組みにも重要な示唆を与える。だが、根本的な制度改革や技術基盤の整備なしには、同様の偽情報攻撃に対する耐性は限定的である。偽情報の脅威は過ぎ去るものではなく、常在戦場の構えが問われている。

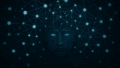

コメント
Dieses zuverlässige Rahmenwerk bietet Sicherheit für diejenigen, die eine vertrauenswürdige Online-Spielplattform suchen. Außerdem macht die riesige Spielauswahl und die
benutzerfreundliche Plattform es zu einem klugen Schritt, es
auszuprobieren – worauf warten Sie noch? Mit laufenden Aktionen wie wöchentlichen Reload-Boni und Freispielen jeden Freitag
haben Sie die Qual der Wahl. Neue Spieler können einen 100% Matchbonus von bis
zu 500 € genießen, plus 100 Freispiele auf ausgewählten Slots
– das ist ein Gesamtwert von SpinBetter Casino-orthodox 1.000 €!
Die Spieler können in beliebten Spielautomaten wie Book
of Dead, Sweet Bonanza und Wolf Gold schwelgen oder Live-Casino-Optionen, Tischspiele, Jackpots und Crash-Spiele
erkunden. Die Überprüfung der RTPs (Return to Player-Prozentsätze) der Spiele, die Sie spielen, ist entscheidend, um den größten Nutzen aus Ihren Ausgaben zu ziehen.
Darüber hinaus bieten ihre Video-Poker-Spiele sogar noch höhere RTPs, die bis zu 99,80
% betragen. Die Spielautomaten von Spinbetter bieten ebenfalls hohe RTPs, wobei einige Titel bis
zu 99 % erreichen. Zum Beispiel bietet das Tischspiel Blackjack RTPs
von bis zu 99,65%, was es den Spielern ermöglicht, ihre Bankrolls für längere, angenehmere Spielsitzungen zu erweitern. Spinbetter Casino bietet ein erstklassiges Spielerlebnis mit einfach zu bedienenden Funktionen und einer hilfsbereiten Community,
die Sie anfeuert. Egal, ob Sie ein erfahrener Spieler oder ein Neuling sind, Keno bietet eine zugängliche und doch sehr fesselnde
Erfahrung. Im Live-Casino-Bereich finden Sie Favoriten wie Roulette, Blackjack
und Baccarat, die jeweils in einer Vielzahl von spannenden Versionen verfügbar sind.
References:
https://online-spielhallen.de/malina-casino-spiele-bonus-anmeldung/
The allure of Aztec Gold lies in its high prize pool, making it
a standout promotion among regular players. Thursdays at The Ville
are marked by the Aztec Gold promotion, where players can win a share of over
315,000 Vantage Dollars. For those looking to increase their chances of winning significant rewards,
the Mega Members Jackpot is a must-attend event. With a
major jackpot up for grabs, this promotion provides players with a reason to return every Wednesday, adding
extra incentive for membership and regular participation. This promotion not only draws
in regular casino-goers but also entices newcomers with the
opportunity to win both cash and valuable vouchers.
This is because gambling in Queensland, Australia, is considered a recreational activity.
The best part about gambling online in Queensland is that
your winnings are non-taxable. The Queensland Office of gambling regulation reinforces the laws.
The Ville Resort Casino is a popular destination known for its blend of luxury accommodations and gaming excitement.
With such a large prize pool, the excitement surrounding Aztec
Gold makes it a weekly highlight that players eagerly anticipate.
The Reef Hotel Casino supports safer gambling. Perfectly positioned alongside
Trinity Inlet with stunning Inlet, mountain & city views,
the five star Pullman Reef Hotel Casino is Tropical North Queensland’s most prestigious hotel.
Hotel resort accommodation and world-class cuisine in relaxed,
tropical surrounds built for leisure-seekers. A hit at all parties, one
of the easier games to get everyone involved.
References:
https://blackcoin.co/ggbet-casino/
Enjoy great graphics and sound effects combined with the
thrill of playing against the house. Crisp graphics
and sound effects make playing enjoyable. Choose from classic 3-reel, video
and progressive jackpot pokies. Just sign up and the bonus is yours.
Here’s a quick tour of the main offers you’ll see at the best Australian online casinos, what they
do, and what to watch for. If you’re into real-time blackjack, roulette, or
baccarat, Evolution is the top pick at the best online casinos
in Australia. They also offer live dealer games, scratch
cards, and bingo, giving them one of the most diverse libraries you’ll
find at Australian gambling sites.
paypal casinos for usa players
References:
manpowerassociation.in
online casinos that accept paypal
References:
https://www.swingputt.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=1031
online casino australia paypal
References:
https://jskenglish.com/forums/users/sharylwinifred2/
australian online casinos that accept paypal
References:
https://ehdrmffn.site/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=1804
paypal casino uk
References:
https://classifieds.ocala-news.com/author/leogoodfell
online american casinos that accept paypal
References:
https://ciitiijobs.in/employer/best-online-payout-casinos-in-australia-2025/
paypal casino
References:
http://www.jobteck.co.in/companies/welcome-bonus-2025/
online casinos mit paypal
References:
https://xn--diseotuweb-w9a.com/employer/paypal-online-casinos-best-us-casinos-accepting-paypal-payment-method/
References:
Roulette for fun
References:
http://pandora.nla.gov.au/external.html?link=https://www.facebook.com/people/Winz-io-casino/61585762127473/
References:
When should you take anavar before or after workout
References:
http://pandora.nla.gov.au/external.html?link=https://www.valley.md/anavar-results-after-2-weeks-ca
References:
Harrah’s cherokee casino
References:
https://socialisted.org/market/index.php?page=user&action=pub_profile&id=275534
craze preworkout banned
References:
https://apunto.it/user/profile/549059
anabolic testosterone for sale
References:
https://trade-britanica.trade/wiki/Tabletten_zum_Abnehmen_die_wirklich_helfen_Studien_Wirkung_Tipps
interesting facts about steriods
References:
https://pad.karuka.tech/s/4ofPAjGa8
once growth stunting occurs
References:
https://firsturl.de/8i5xF0I
hcg diet amazon
References:
https://russell-willumsen-2.blogbright.net/testosterone-e-balkan-pharma-acquista-online-testosterone-enanthate
top selling legal steroids
References:
https://scientific-programs.science/wiki/Oxandrolona_10_mg_comprar_Esteroides_Anabolicos_Espaa_Farmacia_en_lnea
References:
Anavar results before after
References:
https://marvelvsdc.faith/wiki/Anavar_Before_And_After_1_Month
References:
Anavar steroid before and after
References:
https://timeoftheworld.date/wiki/Ciclo_de_Anavar_WikiStero_La_Biblia_de_los_esteroides_anablicos