2025年7月1日、イスラエル政府の「ディアスポラ問題・反ユダヤ主義対策省(The Ministry for Diaspora Affairs and Combating Antisemitism)」が、X上でのイラン発とされる偽情報活動に関するレポートを公表した。
本記事ではその内容を紹介しつつ、このレポートが持つ政治的性格と、その読み方についても検討する。
イランのSNS活動に関する報告の全体像
レポートは、イラン・イスラエル間の武力衝突が激化する中で、SNS空間においてイランがボットを用いた情報操作を大規模に展開していると主張している。
報告によれば、X上における親イラン的な投稿のうち、ある種のハッシュタグでは全投稿の30〜60%がボットによるものだったとされる。たとえば「#المتحدون_نحن(われら団結せり)」のようなタグでは、60%以上が自動アカウントによって生成されており、イラン国内の世論を「国民全体が体制のもとで団結している」と錯覚させる役割を果たしているという。
投稿内容の中心は以下の3つに分類される:
- 国内向けの士気高揚(カメネイ礼賛、国民的団結の演出)
- イスラエル国民への威嚇(軍事的脅威や報復の示唆)
- アメリカ国内の分断工作(反ユダヤ的陰謀論の拡散、介入反対世論の醸成)
具体例:ボットネットワークの構成と活動
調査では、膨大なアカウント群がネットワーク状に連携して行動している様子が可視化されている。代表的な例では、以下のような特徴が共通する:
- アカウント作成時期が直近18か月以内
- 投稿数が極端に多く、同一内容を繰り返す
- 個人情報や他SNSとのリンクが欠如
- 特定の政治テーマにのみ集中(例:ハメネイ賛美、イスラエルの弱体化など)
たとえば「@s_yas_1」というインフルエンサー風のアカウントは16万フォロワーを持つが、投稿はすべて親体制的で、プロフィール画像は他人からの盗用であると指摘されている。
また、AI生成による偽画像も多く活用されており、過去のデモ画像を「最近の愛国的抗議」として再投稿する手法も確認されている。
対外的な影響操作:アメリカ国内への干渉
レポート後半では、アメリカ世論への干渉工作が焦点となる。具体的には以下のような言説がボットネットによって拡散されているとされる:
- 「イスラエルはテロ国家」「アメリカはイスラエルに操られている」
- 「トランプはネタニヤフの操り人形」
- 「ユダヤロビーが米国政策を支配している」
こうした主張は、アメリカの保守層・リベラル層双方に響くよう設計されており、過去の戦争介入への不信感と結びつけて「イラン攻撃反対」世論を形成しようとする試みだとされる。
報告書は、こうした活動の一部はロシアの影響工作と連携している可能性もあると示唆している。
情報操作か、戦時の広報か
このレポートは、形式上はボットネット分析だが、実際には国家的な認知戦の構図を描き出すものである。
発信者がイスラエル政府である以上、その主張や事例の取り上げ方は当然、イスラエルの安全保障的利益に沿ったものとなる。イラン側の見解や、ボット検出の精度・誤判定の可能性などは一切扱われていない。
また、「脅威の可視化」を通じて、国内外に向けてイスラエルの正統性と正当防衛を印象づける目的も明白である。
戦時の情報空間と、その読み方
重要なのは、このようなレポートを「正しいか間違っているか」で判断するのではなく、どのような文脈で出されたか、どのような目的に沿って構成されたかを読むことである。
情報戦が加熱する現代では、調査レポートそのものが戦略的文書になりうる。そして、その存在自体が、SNSというプラットフォームがいかに戦場になっているかを物語っている。


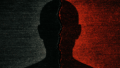
コメント