2025年5月18日に実施されたポルトガルの総選挙は、SNS上での政治情報の流通と偽情報の影響を記録する上で、きわめて重要なケースとなった。MediaLab CIES_Iscteと国家選挙委員会(CNE)による報告書「Portuguese General Elections 2025 – Information and Disinformation on Social Media」は、この選挙戦におけるオンライン言論空間の構造を詳細に分析している。特に注目すべきは、極右政党Chegaとその党首アンドレ・ヴェントゥーラの存在感である。彼らのSNS上での突出したパフォーマンスは、既存メディアや制度的政治と別軸で展開される「もう一つの選挙戦」を可視化した。
フォロワー数と投稿の量──Chegaとヴェントゥーラの支配力
2024年から2025年にかけて、政党アカウントのフォロワー数は20%、候補者アカウントは55%増加した。とりわけTikTokでは政党全体でフォロワー数が3倍に増え、ヴェントゥーラを含む6人の候補がアカウントを開設。こうした背景のもとで、SNS上では候補者が政党そのものよりも広いリーチを持つようになった(総フォロワー数:候補者2.5M、政党2.2M)。
その中でヴェントゥーラは、Facebook、Instagram、TikTokのいずれにおいても候補者全体の6~8割の注目を集めた。投稿ごとの平均インタラクション数は18,500件と、他候補(マリアナ・モルターグアやペドロ・ヌーノ・サントス)の6倍以上。Facebookに限れば1投稿で39,000件の反応を得る例もあり、政党アカウントの平均(6,500件)とも大きく乖離している。
プラットフォーム別の特性と感情反応
投稿数ではX(旧Twitter)が最も多く、全体の72%を占めたが、反応(コメント、共有、リアクション)で最多だったのはFacebookで、全体の46%。InstagramとTikTokは投稿数が少ないものの、1投稿あたりの反応率が極めて高い。とくにTikTokでは1投稿あたりの平均再生数が6万件を超えており、少数の投稿で広範な注意を獲得している。
メディアアカウント(SIC Notícias、CNN Portugalなど)が多くの言及を行うFacebookでは、政治的な事件に対する感情的な反応が集中した。特に注目されたのが、選挙終盤に起きたヴェントゥーラの体調不良に関する投稿である。これはFacebook、Instagram、TikTok、Xのすべてにまたがって大量拡散され、単独で100万再生超を記録した例もある。
論点の変化:汚職から移民へ
過去のポルトガル選挙では「汚職」が中心的なテーマであったが、2025年は明確に「移民」へと関心が移行した。報告書では、2022~2025年の3回の選挙におけるFacebook投稿の傾向を比較しており、表示回数で見ると移民関連投稿は約2100万回、汚職関連は400万回と、およそ5倍の差がついている。
この「移民」テーマの広がりには、特定の誤情報やナラティブが重要な役割を果たしている。たとえば、2025年にAIMA(移民庁)が違法滞在者に対して発した通知に関する投稿群(クラスター1)は、総投稿数はそれほど多くないにもかかわらず、怒りのリアクション(😠)は最大級だった。感情的な分極化を呼び起こすテーマとして「移民」は極めて効果的に機能したといえる。
偽情報を支えるメタナラティブの構造
この選挙戦では、三つの主要なメタナラティブが確認されている。
- 「ポルトガルは侵略されている」
- 虚偽の「移民200万人」説(実際には存在しない数字)がSNS上で拡散
- Chegaの議員ペドロ・フラザンが複数の投稿で強調、総再生数150万超
- Goaの映像を使った「国籍売買」説や、不法占拠に関する誤情報が連動
- 「ポルトガルのイスラム化」
- 風刺として作成された「イスラム政党」ページが、本物と誤解されて拡散
- 若年層に向けた「投票しないとイスラム国家になる」という扇動動画も出現(再生数120万)
- 「50年の腐敗」
- 1974年の民主化以降の政体そのものを否定する語り
- Chegaが「体制内政党はすべて同じ」という反政治的言説を拡散
- 例:「PSやBEは移民と引き換えに票を買っている」とする動画(再生数35万)
これらの語りは互いに補完的であり、共通して「制度への不信」「感情的動員」「敵対的分断」を促進する設計になっている。
ボットなき協調行動──匿名ネットワークの構造
この選挙では、従来のような自動ボットの使用は確認されていない。一方で、Instagram上を中心に、匿名・偽名アカウントによる協調的投稿ネットワークが存在していた。
これらは相互にフォロワーを共有し、同一の投稿をほぼ同時にアップする。プロフィールは抽象的で、政党名を直接出さずに「右派」的イメージだけを醸し出す設計がされている。報告書では、これは「高度に動員された個人による非自動協調行動」とされており、運営の主体はおそらく数名の人間だが、実質的にはプロパガンダ機構として機能している。
「偽アカウント」の錯誤──反偽情報が偽情報になるとき
象徴的な事例として、イスラエル系企業Cyabraが発表した「Chega支持のXアカウントの58%が偽アカウント」という主張がある。このデータはCNN Portugalを含む複数メディアに報道されたが、報告書ではその定義の曖昧さが批判されている。
具体的には、「偽アカウント」の定義が不明瞭で、匿名アカウントや活動的な個人アカウントも一括で分類されていた。この混乱により、「Chegaへの支持は捏造である」というナラティブが拡散され、一部では反発も生んだ。報告書は、こうした「反偽情報の拡散」がむしろ陰謀論的言説に利用され、制度批判を補強するリスクを指摘している。
選挙と情報空間の非対称性
このレポートが描き出すのは、制度的な選挙過程と非制度的なSNS言説空間との間の非対称性である。政党や候補者が公式チャンネルで発信する情報は、個人・匿名・風刺・煽動の混在する非公式言説に比して、拡散効率も感情動員の力も限定的である。特にChegaのようなラディカルな勢力が、制度的不信と情動を結びつけて語るとき、その拡散速度と浸透力は桁違いになる。
本レポートは、そうした動きの統計的・構造的実態を精密に記録した、きわめて貴重な資料である。とくに「ボットではなく、人間が感情的にシェアする偽情報」の存在構造を理解する上で、示唆に富んでいる。ポルトガルの事例は、そのまま他国の未来でもある。

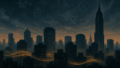
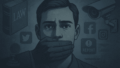
コメント
I am now not positive where you’re getting your info, but great topic. I needs to spend a while learning more or figuring out more. Thank you for excellent info I was searching for this info for my mission.
Good info and right to the point. I don’t know if this is truly the best place to ask but do you guys have any ideea where to employ some professional writers? Thank you 🙂
I’m really enjoying the theme/design of your web site. Do you ever run into any internet browser compatibility issues? A small number of my blog audience have complained about my site not operating correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any advice to help fix this problem?
It¦s truly a nice and helpful piece of info. I am satisfied that you simply shared this useful information with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.
I appreciate, cause I found just what I was looking for. You’ve ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye
Having read this I thought it was very informative. I appreciate you taking the time and effort to put this article together. I once again find myself spending way to much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!
There may be noticeably a bundle to find out about this. I assume you made certain nice factors in features also.
Very good website you have here but I was wanting to know if you knew of any community forums that cover the same topics discussed in this article? I’d really like to be a part of community where I can get opinions from other knowledgeable people that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Appreciate it!
Yay google is my queen helped me to find this great web site! .
Heya this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding know-how so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!
fivt
Its fantastic as your other content : D, thankyou for putting up. “The present is the necessary product of all the past, the necessary cause of all the future.” by Robert Green Ingersoll.
Auch Lotterien des deutschen Lotto-Toto-Blocks oder Casinospiele in Spielbanken. Die Whitelist
führt auch Glücksspielangebote auf, die nicht unter der Aufsicht der GGL, sondern unter der Aufsicht anderer
deutscher Glücksspielaufsichten stehen. Im gleichen Jahr
trat die Technische Richtlinie 5.0 in Kraft, die das Automatenspiel in Spielhallen deutlich restriktiver regulierte und dafür sorgte,
dass vermehrt Spieler die weniger limitierten Automatenspiele in den deutschen Spielbanken nutzen. November 2003, dürfen die EU-Mitgliedstaaten Glücksspiele nur aus Gründen des Allgemeininteresses – wie dem Schutz vor Geldwäsche oder Spielsucht – beschränken.
1638 wurde die venezianische „Ridotto“ erster
ausschließlicher Glücksspielort. Laut historischen Quellen fand
bereits seit 1170 in Venedig das erste Glücksspiel unter freiem Himmel statt, besonders in Zeiten des venezianischen Karnevals.
Eine Institutionalisierung des Glücksspiels gab es seit dem 18.
Gerade für Poker-Fans, aber auch Spielautomaten Freunde lohnt sich zum Beispiel ein Abstecher nach Schenefeld im Westen Hamburgs.
Das Automatencasino, das von der Spielbank Hamburg KG betrieben wird, befindet sich im Erdgeschoss des Hotels Graf Moltke
und verfügt über etwas mehr als 75 Spielautomaten, die auf 370
Quadratmeter verteilt sind. Das aufregend gestaltete Automatencasino gehört zu den modernsten in Deutschland und auch die Automatenauswahl ist auf dem neuesten Stand.
References:
https://online-spielhallen.de/1red-casino-bewertung-meine-10-jahre-erfahrung-auf-den-prufstand-gestellt/
Join our newsletter and get the lowdown on the latest pokies, top bonuses, and new
casinos – no bluffing! Join our newsletter
and get the lowdown on the latest pokies, top
bonuses, and new casinos – no bluffing! Ozwin Casino will be great for some players, but others
may want a more robust table game and live dealer game
selection. One of the perks of playing casino games online
is the opportunity to play exciting specialty games.
The minimum deposit amount depends on the payment method
you choose. Will the credit card statement show
that a transaction was made to/from a casino? Under the “Deposit” tab,
choose your preferred deposit method and follow the steps to deposit.
References:
https://blackcoin.co/casumo-casino-review-rewards-slots-and-payments-how-is-customer-service/
If you love the whole cocktail-sipping, sun-soaking beach
club experience, INFINITY at the Mindil Beach Casino Resort
is the ultimate venue where Darwin’s social scene hits a whole new
level. Situated on the resort’s expansive lagoon, these rooms offer swim out access, private sun lounges plus an outdoor setting on your private balcony.
The spacious one bedroom suites offer guests an elegantly appointed
lounge area, a marble ensuite and luxurious corner spa, and a private balcony with views of the lush tropical gardens,
pool or ocean. The elegantly appointed lounge features
separate living and dining areas which can host up to six people and has two private balconies.Bedrooms offer guests a sanctuary with a marble ensuite
and a balcony with magnificent views. Grand suites offer guests
the space to relax and enjoy the natural beauty of lush tropical gardens.
Relax in one of the 152 stylishly appointed hotel or resort
rooms, swim in our spectacular infinity-edged pool or lagoon pool with a swim-up bar, enjoy the cuisine of our five distinctive dining experiences, indulge
in spa treatments, and relax on our beautiful private beach.
IKOU creates a fusion of wild-harvested indigenous ingredients
combined with global spa traditions for a sensory experience
that not only deeply relaxes, but also connects you with the true heart of this ancient
land. Our private dining room provides an ideal setting for special occasions,
corporate events, or intimate get-togethers.
References:
https://blackcoin.co/crown-casino-sydney-a-comprehensive-guide/
casino sites that accept paypal
References:
https://www.tokai-job.com/employer/best-real-money-poker-sites-for-2025-real-money-online-poker-for-usa/
mobile casino paypal
References:
https://www.munianiagencyltd.co.ke/employer/beste-paypal-online-casinos-2026-im-casino-mit-paypal-bezahlen/
online casino paypal
References:
joblinksolution.org
Glad to be one of several visitors on this awesome site : D.
It’s actually a cool and helpful piece of info. I am glad that you simply shared this helpful info with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.
paypal online casinos
References:
http://hg3b25hm0h.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=1790903
Keep on working, great job!
лицензионные мобильных казино онлайн в россии рейтинг
https://t.me/s/kazIno_S_mInImaLNYM_depOziToM/6
https://1wins34-tos.top
https://t.me/s/minimalnii_deposit/44
Мир онлайн-слотов растёт: новые провайдеры, повышенные RTP и постоянные турниры поддерживают интерес игроков.
Vavada удерживает позиции в топе, но не забывайте проверять лицензию и лимиты перед депозитом.
Выбирайте автоматы с бонусными раундами, бесплатными вращениями и прогрессивными джекпотами — так повышается шанс крупного выигрыша.
Зеркала решают проблему блокировок и позволяют оперативно выводить средства без лишних задержек.
Актуальные возможности доступны здесь: https://temp-tools.kz//vendor/pgs/index.php?nel_kten_vavada_aynasu__azghet_.html.
Играйте ответственно и контролируйте банкролл, чтобы азарт оставался в пределах удовольствия.
https://t.me/s/KAZINO_S_MINIMALNYM_DEPOZITOM
What’s up, I wish for to subscribe for this blog to obtain newest updates, thus where can i do it please help.
https://protein.kiev.ua/bi-led-linzy-vs-halohenky-h7-bii-za-lyumeny.html
Hi there Dear, are you genuinely visiting this web page regularly, if so after that you will definitely get pleasant know-how.
igrice za decake auta
real dianabol steroids for sale
References:
https://justbookmark.win/story.php?title=how-to-buy-testosterone-online
Hello to all, for the reason that I am really eager of reading this web site’s post to be updated daily. It contains fastidious information.
byueuropaviagraonline
Hello my friend! I wish to say that this post is amazing, nice written and include almost all significant infos. I would like to see more posts like this.
https://t.me/s/russiA_caSinO_1WIn