「偽情報」はしばしば国家単位の問題として語られるが、その実、もっとも深刻な影響を受けているのは市民の生活に直接関わる都市の現場である。地方行政が提供するのは、医療、住環境、交通、多様性政策といった「日常」に関わる領域であり、それゆえに偽情報はその機能を直接的に麻痺させる武器として使われる。
メルボルン大学の都市研究チームとドイツ・マーシャル基金が共同でまとめたレポート『Disinformation in the City Brief #2』は、都市が直面する偽情報の実態を、分野別に具体的に描いている。ここではその中から、影響の大きい3領域―ジェンダーと多様性、気候と都市計画、そして医療とワクチン―に焦点を絞って紹介する。
DEIは危険?:「多様性推進」が陰謀にされる構図
2024年3月、米ボルチモアで起きた大規模な橋崩落事故に関し、「DEI(Diversity, Equity, Inclusion)に配慮して無能な人間を雇ったから橋が落ちた」という言説が一部右派系メディアで拡散された。もちろん事実無根である。だがこのような「多様性=能力不足」というナラティブは、近年の偽情報キャンペーンにおいて繰り返し使われている。
さらに悪質なのはAI技術を用いたジェンダー攻撃の事例である。2023年、スペイン・アルメンドラレホでは、10代の女子生徒20人の顔を使ってAI生成されたヌード画像がSNS上に拡散された。これは単なる「いじめ」や「悪ふざけ」ではなく、明確な偽情報による人格攻撃であり、現実の都市社会に深刻な傷痕を残した。
他にも、オーストラリアや米国のいくつかの都市では、LGBTQ+コミュニティ向けのイベント(特に「ドラァグ・ストーリータイム」)が「子どもを狙った性的逸脱行為」といった虚偽の言説により中止に追い込まれている。これらの攻撃は、文化的マイノリティの排除だけでなく、自治体による多様性推進政策そのものを萎縮させる効果を持つ。
「15分都市」は監視体制か? 気候政策への陰謀論的攻撃
都市計画の分野では、「15分都市」構想が激しい偽情報の標的となっている。この構想は、生活に必要な施設をすべて徒歩15分圏内に配置することで、持続可能な都市を目指す政策だ。しかし、SNSでは「気候変動対策を口実に、市民の移動を制限しようとしている」「このままでは都市が“屋外刑務所”になる」といった陰謀論が出回った。
英国では、このような陰謀論が議会にまで影響を及ぼし、歩行者・自転車優先の都市計画が中止・縮小に追い込まれる事態が発生している。都市のサステナビリティを高めるはずの政策が、「自由を奪う装置」として描かれることで、政治的な後退が起きている。
EU DisinfoLabが指摘するように、気候偽情報にはいくつかの典型的なパターンがある。「気候アラーム主義 vs. 現実主義」という二項対立を作り出し、科学者や環境保護活動家を「過剰反応するパニック屋」として揶揄する手法が多く使われる。さらに、気候政策を「グローバルエリートによる技術支配」と結びつける物語も根強く存在している。
ワクチンは危険? 医療と信頼への攻撃
2019年にはウクライナ、サモア、フィリピン、カザフスタン、ジョージアなどで麻疹の大流行があった。共通していたのは、反ワクチン偽情報によって予防接種の率が低下していたことだ。たとえば「ワクチンは自閉症を引き起こす」といった、すでに否定されている説が未だに信じられ、多くの親が子どもへの接種を拒否した。
COVID-19パンデミック時にはさらに激しい情報戦が展開された。「ウイルスはビル・ゲイツが世界人口削減のために開発した」「消毒液を飲めば感染しない」といった明白な虚偽が出回り、実際に米国の毒物センターへの通報件数が急増した。また、感染症専門家や医師が暴力や脅迫の標的になるケースも多数報告されている。
都市の医療行政は、予防接種、医療サービスの提供、福祉政策など、偽情報の影響を受けやすい領域を多数抱えている。そのため、科学的根拠への信頼が崩れると、政策そのものが機能しなくなる。しかも、こうした攻撃は高齢者や移民など、もともと不信感を抱きやすい人々に向けて精密に投下されている。
なぜ都市が狙われるのか
レポートでは、都市が偽情報の主戦場となる理由を以下のように整理している。
- 地方自治体は住民と物理的にも制度的にも近く、「アクセス可能なターゲット」である
- 地元の選挙は国政と比べて中立的な関心層が多く、偽情報による意見操作が効果的
- 高密度で多様な都市社会は、分断や疑念を拡大しやすい構造を持っている
さらに、偽情報はしばしば複数のテーマをまたぐ。たとえば、「DEI政策によって無能な職員が起用された」という偽情報は、人種差別・ジェンダー攻撃・制度不信・インフラ不安という複数のナラティブを束ねている。このように、偽情報は単発の「嘘」ではなく、都市構造そのものに亀裂を入れる構造的攻撃になっている。
終わりに
『Disinformation in the City Brief #2』は、抽象的な「偽情報」論ではなく、都市という具体的な空間と制度における被害を、実例と共に描いている点で重要である。それは単なるメディアリテラシーの話ではない。ジェンダー政策が機能しなくなる、気候対策が頓挫する、医療現場が麻痺する――こうした被害が現に起きている。偽情報の問題を都市政策と切り離して考えることはもはやできない。
次の論点は、「では都市はどう対応すべきか」だろう。だがその前提として、まずは「何が起きているのか」を具体的に知ること。このレポートはその起点として機能する。おすすめである。

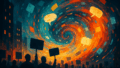
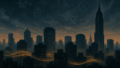
コメント
Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It really helpful & it helped me out a lot. I hope to present one thing back and aid others like you helped me.
This site is my breathing in, rattling superb style and perfect content material.
excellent points altogether, you simply gained a new reader. What would you recommend about your post that you made some days ago? Any positive?
You actually make it seem so easy together with your presentation but I find this matter to be really something that I believe I would by no means understand. It kind of feels too complicated and extremely large for me. I am having a look forward to your next put up, I will try to get the hang of it!
Der Anbieter stellt dir direkt im Zuge der
Registrierung insgesamt fünf Millionen Spiel-Chips zur Verfügung.
In beiden Fällen benötigst du keine Huuuge
Casino Codes, sondern erhältst den virtuellen Münz-Bonus direkt im Anschluss an deine Registrierung.
Mit Hilfe von Ranglistenplätzen kannst du dir zudem Münz-Booster und ähnliche Belohnungen sichern. Innerhalb der Spielrunden werden zum
Beispiel neue Spielstufen oder Einsatzlimits freigespielt.
Aber auch Tischspiele wie Roulette oder Black Jack sind im Angebot vertreten. Zudem kannst du bei Bedarf auch Spielchips kaufen und so mit eigenem Guthaben zuschlagen. Darüber hinaus
sorgen verschiedene Herausforderungen und Missionen dafür, dass sich dein Spielerkonto regelmäßig wieder mit
neuen Spielchips füllt. Teilnahme an Glücksspiel ab 18 Jahren – Glücksspiel kann süchtig machen. Mit PayPal ist zum Beispiel eine der beliebtesten und sichersten Zahlungsmethoden auf dem Markt mit von der Partie.
In Deutschland darf der Anbieter als Social Casino ohne Glücksspiel-Lizenz
agieren, stellt aber dennoch einen verlässlichen Rahmen bereit.
Du kannst also problemlos alle Spiele mit dem Einsatz spielen, den du möchtest.
Es gibt im Huuuge Casino unterschiedliche Möglichkeiten, um neue Spielchips kostenlos
zu erhalten. Du wirst also nicht zu einem Kauf der Chips gedrängt, sondern kannst tatsächlich dauerhaft
gratis spielen.
References:
https://online-spielhallen.de/nomini-casino-app-das-ultimative-mobile-spielerlebnis/
Always aim to provide excellent customer service, manage your listings meticulously, and keep an eye on your shipping
performance for best results. Providing tracking information helps prevent chargebacks and builds trust with buyers.
However, cash payments and third-party processing apps don’t qualify for Facebook’s return policy, so most sales are final.
You want to upload high-quality, crisp, and creative pictures in order to get your items sold.
Some customers would prefer to pay slightly more money to purchase
items but instead, have that item shipped for free.
A mistake that new online sellers make is weighing the item before they’ve packaged it, only
to be on the hook for the extra shipping costs to cover the
additional weight of the box and padding. Five business days after the
tracking information updates to “delivered,” your earnings will be released from Facebook marketplace.
Let’s get into the first few steps of shipping on the Facebook Marketplace… Selling on Marketplace can be a great way to declutter your
home and make some extra cash, so let’s
get started! If so, you might be curious about how does shipping
work on Facebook Marketplace. If you choose to
use Facebook’s prepaid shipping labels, they are available through USPS and
FedEx at discounted rates. This can affect the accuracy of the shipping cost calculation. You can switch between using a Facebook prepaid shipping label and using your
own label, even after a label has been generated.
References:
https://blackcoin.co/amunra-casino-a-complete-review-of-the-egyptian-themed-gaming-platform/
At Lucky ones, players can indulge in a diverse array of games, catering to all tastes and preferences.
Brand Casino, known as Lucky ones, is a renowned online gambling platform offering a wide range
of games including slots, blackjack, roulette, and poker.
Their live dealer options bring the casino vibe right to your
home. Get cashback rewards on your gameplay, allowing you to enjoy
more of your favourite games with reduced risk.
Dive into the world of slots and table games with
exclusive promotions available at Lucky ones! Discover the exciting bonus offers
at Lucky ones online casino, crafted for your delight.
This lets you block yourself from the casino
for a set period or permanently. While Lucky
Ones Casino shines with its game selection, sussing out
the responsible gambling features shows a mixed
bag. Beyond the usual suspects like Bitcoin (BTC) and Ethereum (ETH), you’ll find options like Dogecoin (DOGE), Cardano
(ADA), Ripple (XRP), and Litecoin (LTC).
You’ll see new jackpot entrants, seasonal live tables, and
limited-time exclusives before they hit general release.
Each week, new games are added to keep the experience fresh and rewarding for
every returning player. Step into Lucky Ones Casino, where smart gameplay meets full-time access and real-time
rewards.
References:
https://blackcoin.co/monte-casino-overview/
us poker sites that accept paypal
References:
http://koreapsychiatry.com/main/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=1786
online casino for us players paypal
References:
https://payment.crimmall.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=138548
Great blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers? I’m hoping to start my own site soon but I’m a little lost on everything. Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally confused .. Any ideas? Many thanks!
online casino mit paypal
References:
https://capitalplacementservices.com/employer/best-paypal-casinos-2025-online-casino-sites-that-accept-paypal/
us poker sites that accept paypal
References:
https://jobshop24.com/employer/50-free-chip-no-deposit-sign-up-bonus-australia/
Круиз из Дубая оставил массу положительных эмоций, маршрут интересный, лайнер комфортный, организация четкая https://kruizy-po-persidskomu-zalivu.ru/
Путешествие на лайнере из Китая запомнилось отличной атмосферой, чистотой, сервисом и красивыми морскими пейзажами: https://kruizy-iz-kataya.ru/
Best Gay site porn
References:
Anavar before and after 2 months
References:
https://pikidi.com/seller/profile/sharkankle78
накрутка подписчиков телеграм
Для детской лучше брать безопасные материалы и заранее продумать свет и вентиляцию, выбирайте полотно с фактурой штукатурки, оно выглядит аккуратно даже при сложной геометрии комнаты, проверьте сертификаты на полотно и репутацию монтажной бригады, получится ровно и аккуратно без лишних затрат времени https://natyazhnye-potolki-moskva.ru/
Натяжные потолки дают ровную геометрию и стабильный цвет на годы, парящий контур помогает зонировать пространство светом, и при этом монтаж проходит спокойно; замер занимает около получаса, после чего готовится смета и договор: теневые натяжные потолки москва
https://alstrive.ru/blog/iphone-17-air-balans-stilja-i-proizvoditelnosti/
купить vps
Продвижение сайтов https://team-black-top.ru под ключ: аудит, стратегия, семантика, техоптимизация, контент и ссылки. Улучшаем позиции в Google/Яндекс, увеличиваем трафик и заявки. Прозрачная отчетность, понятные KPI и работа на результат — от старта до стабильного роста.
Тяговые аккумуляторные https://ab-resurs.ru батареи для складской техники: погрузчики, ричтраки, электротележки, штабелеры. Новые АКБ с гарантией, помощь в подборе, совместимость с популярными моделями, доставка и сервисное сопровождение.
Продажа тяговых АКБ https://faamru.com для складской техники любого типа: вилочные погрузчики, ричтраки, электрические тележки и штабелеры. Качественные аккумуляторные батареи, долгий срок службы, гарантия и профессиональный подбор.
Продажа тяговых АКБ https://faamru.com для складской техники любого типа: вилочные погрузчики, ричтраки, электрические тележки и штабелеры. Качественные аккумуляторные батареи, долгий срок службы, гарантия и профессиональный подбор.
хороше кіно онлайн детективні серіали онлайн безкоштовно
дивитися фільми онлайн кінотеатр uakino безкоштовно
sonabet live login
Инженеры компании разрабатывают электронные устройства для промышленных, научных и коммерческих проектов. Создаются схемы и проектируются печатные платы с подбором компонентов. Параллельно создается встроенное и прикладное программное обеспечение для управления устройством и его интеграции с системами. Прототипы собираются и тестируются на функциональность и надежность. После успешного тестирования выполняется сборка и монтаж плат. Предоставляется мелкосерийное и серийное производство изделий. Разрабатываются корпуса с учетом эргономики, защиты компонентов и внешнего вида, проводится промышленный дизайн. При необходимости осуществляется реверс-инжиниринг старых решений для их модернизации. 3D-моделирование и 3D-печать ускоряют процесс создания прототипов. Все изделия сопровождаются документацией и технической поддержкой. Заказчик получает полностью готовое изделие: http://istinastroitelstva.xyz/index.php?subaction=userinfo&user=waryfame7
Инновации, которые делают проекты более предсказуемыми!
Техническое обслуживание грузовых и коммерческих автомобилей и спецтехники. Снабжение и поставки комплектующих для грузовых автомобилей, легкового коммерческого транспорта на бортовой платформе ВИС lada: https://ukinvest02.ru/
sonabet net
гражданство румынии
sona bet app
I simply couldn’t leave your web site before suggesting that I actually enjoyed the usual information an individual supply to your visitors? Is gonna be back ceaselessly in order to check out new posts
Выгодный стор https://buyaccountstore.today приветствует арбитражников в своем каталоге цифровых товаров для FB. Если вам нужно купить аккаунты Facebook, чаще всего важен не «одном логине», а в проходимости чеков: уверенный спенд, зеленые плашки в Ads Manager и правильно созданные ФП. Мы подготовили понятную навигацию, чтобы вы сразу понимали что подойдет под ваши офферы до оплаты.Быстрый ориентир: откройте разделы Автореги, а для масштабирования — идите сразу в профильные позиции: BM 250$. Важно: аккаунт — это инструмент. Дальше решает подход к запуску: какой прокси используется, как вы передаете лички аккуратно, как проходите чеки и как масштабируете адсеты. Гордость данной площадки — заключается в наличие приватной базы знаний по FB, в которой написаны свежие рекомендации по запуску рекламы. Команда сориентируем, каким образом аккуратно привязать карту, чтобы вы спокойно отливали бюджет а также продлили жизнь аккаунтам . Заходите в наше комьюнити, смотрите практичные кейсы по заливу, упрощайте работу с Meta и улучшайте конверт на базе наших расходников прямо сейчас. Дисклеймер: действуйте в рамках закона и всегда в соответствии с правилами Facebook.
Мультимедийный интегратор i-tec интеграция мультимедийных систем под ключ для офисов и объектов. Проектирование, поставка, монтаж и настройка аудио-видео, видеостен, LED, переговорных и конференц-залов. Гарантия и сервис.
References:
Palm casino
References:
https://skitterphoto.com/photographers/2121048/jacobson-hirsch
References:
Casino las vegas
References:
https://latexprice9.werite.net/wd40-casino-2026-1-500-welcome-bonus-7-000-games-and-fast-withdrawals
References:
Ny casino
References:
https://commuwiki.com/members/thrilldead7/activity/13224/
Hello team!
I came across a 152 interesting resource that I think you should dive into.
This platform is packed with a lot of useful information that you might find valuable.
It has everything you could possibly need, so be sure to give it a visit!
[url=https://www.otthonmelege.hu/a-munkahelyi-kieges-uj-dimenzioi]https://www.otthonmelege.hu/a-munkahelyi-kieges-uj-dimenzioi[/url]
Furthermore don’t overlook, guys, that you constantly can within the publication find solutions to address the most the absolute tangled inquiries. We tried — lay out all of the information in the most understandable manner.
https://pamyatniki-granitnye.by/
2024 смотреть онлайн zfilm-hd.net полная версия сайта
сервис e mail рассылок онлайн сервис рассылки email
задвижка 30с41нж ду80 30с41нж задвижка
Hello .!
I came across a 152 useful website that I think you should check out.
This tool is packed with a lot of useful information that you might find insightful.
It has everything you could possibly need, so be sure to give it a visit!
[url=https://www.businessupturn.com/lifestyle/home/diys-christmas-decoration-ideas-to-bring-sparkles-in-your-house/]https://www.businessupturn.com/lifestyle/home/diys-christmas-decoration-ideas-to-bring-sparkles-in-your-house/[/url]
And don’t neglect, guys, — one at all times are able to in this particular publication discover answers for the most most complicated queries. We tried — explain the complete information using the most accessible method.
what do medical steroids do to your body
References:
https://marvelvsdc.faith/wiki/8_Best_Testosterone_Boosters_For_Men_2025_Updated
buy steroids in mexico
References:
https://www.pradaan.org/members/wiresandra98/activity/753940/
Как стать добровольцем и заключить контракт на СВО в России в 2026 году https://vc.ru/1563952
На big-bag-rus.ru вы можете купить биг-бэги и мягкие контейнеры МКР от производителя: мешки биг бэги 1–4 стропы, с верхней сборкой, люками и вкладышем. Изготовление под ваши требования, стабильное качество, выгодный опт и отгрузка по России: https://big-bag-rus.ru/
References:
Anavar before and after 1 month male
References:
https://saveyoursite.date/story.php?title=15-steroide-vor-und-nach-bildern
References:
Before and after anavar women
References:
https://ccsakura.jp:443/index.php?violettyvek5
does ritalin stunt growth
References:
https://peatix.com/user/28723106
injectable steroids names
References:
https://pediascape.science/wiki/La_gua_definitiva_de_los_suplementos_que_mejor_funcionan_para_potenciar_la_testosterona_de_los_hombres_segn_un_experto_doctor
where do pro bodybuilders get steroids
References:
https://www.folkd.com/submit/sebastiano.fr/img/pgs/?acheter_de_la_testosterone_1.html/
https://vc.ru/2216349, Как начать развивать Инстаграм – Мой рейтинг из 20 сервисов для стремительного роста популярности в 2026 году
Hello friends!
I came across a 153 useful resource that I think you should dive into.
This tool is packed with a lot of useful information that you might find valuable.
It has everything you could possibly need, so be sure to give it a visit!
[url=https://www.bazaaretcompagnie.com/15814/faire-paris-sportif-courses-hippiques-methode-pour-gagner/]https://www.bazaaretcompagnie.com/15814/faire-paris-sportif-courses-hippiques-methode-pour-gagner/[/url]
Furthermore do not forget, guys, that a person always are able to inside the piece locate answers for the most the absolute tangled inquiries. Our team tried to present all of the content via the most extremely easy-to-grasp manner.
It’s best to take part in a contest for among the finest blogs on the web. I’ll advocate this website!
Накрутка Телеграм – 25 способов бесплатной накрутки в 2026 году https://vc.ru/1495694
signs a woman is using steroids
References:
https://justbookmark.win/story.php?title=how-to-buy-testosterone-online
References:
Anavar men before and after
References:
https://sciencewiki.science/wiki/Dianabol_Kur_Die_besten_Optionen_fr_Anfnger_und_Fortgeschrittene
References:
Before and after test cyp 500 week and anavar
References:
https://sciencewiki.science/wiki/Oxandrolone_ciclo_bodybuilding_rischi_effetti_collaterali_e_alternativa_legaleTargatocn_it
Накрутка подписчиков в Тик Ток купить – ТОП-27 способов в 2026 году. Наш рейтинг https://vc.ru/1571685
Как получить информацию о раненом в спецоперации – контракт на СВО Россия 2026 https://vc.ru/1559725
Hello .!
I came across a 153 fantastic website that I think you should check out.
This platform is packed with a lot of useful information that you might find interesting.
It has everything you could possibly need, so be sure to give it a visit!
[url=https://businesscutter.com/distance-work-for-better-result/]https://businesscutter.com/distance-work-for-better-result/[/url]
Additionally remember not to neglect, folks, — one at all times are able to within the piece locate solutions for the the absolute complicated questions. Our team tried to present the complete content via the most most accessible way.