2022年2月末、欧州連合(EU)はロシア国営メディアRT(Russia Today)とスプートニクの放送を加盟域内で禁止する異例の措置を取った。表現の自由と報道の自由はEUの根本的価値のはずだが、この決定はそれらと明らかに衝突する。それにもかかわらず、加盟27カ国が短期間で合意に達した背景は何だったのか。
国際政治学者ソフィー・L・ヴェリテールは、2025年8月に公開された「The collective securitization of ‘disinformation’ and the EU’s ban on Russia Today and Sputnik」で、この決定を「集合的セキュリティ化(collective securitization)」理論を使って分析し、EUの安全保障政策の裏側を描き出している。本稿は、その分析のポイントを紹介する。
偽情報はどう「安全保障」になったのか
「偽情報(disinformation)」がEUの安全保障課題として正式に扱われるようになったのは、2014年のウクライナ危機がきっかけだった。ロシアによるクリミア併合やマレーシア航空MH17撃墜事件では、事実と異なる報道が両陣営で飛び交い、EU内部でもロシア発の情報操作が警戒されるようになる。
バルト三国やポーランドは、この脅威を「全EUの問題」として共有させるため、EEAS(欧州対外行動庁)内にEast StratCom Task Force(ESTF)を設置させた。この部局は、対ロシアプロパガンダの監視・反駁を行うEUvsDisinfoサイトで知られるが、設立当初から戦略的広報や独立メディア支援も任務としていた。
当初は外交・安全保障政策(CFSP)の枠内で扱われていたが、やがて欧州委員会のデジタル政策部門や司法部門も加わり、デジタルサービス法(2022年)や欧州メディア自由法(2024年)といった法的枠組みが整えられた。偽情報対策は、外向きの外交ツールからEU内部の情報空間統治へと広がっていった。
2022年2月──通常手続きを飛ばした「コンフェッショナル」
ロシアのウクライナ全面侵攻が始まったのは2022年2月24日。この軍事行動が、RTとスプートニク禁止決定の「引き金」になった。
通常、CFSPの決定は理事会の作業部会や常駐代表委員会(COREPER II)で公式に協議される。しかし今回は、それらを経ずに「コンフェッショナル(confessionals)」と呼ばれる非公式・小規模の会合が使われた。加盟国大使が少人数に分けられ、欧州委員会やEEASの幹部と週末を含めて集まり、非公開で協議する形式だ。
この場で、欧州委員会とEEASが禁止案を提示。バルト三国とポーランドが「初動の押し」をかけていたこともあり、議論は短時間で方向が固まった。
法的根拠は制裁措置として急ぎ整えられ、理事会は書面手続きで採択。加盟国によっては憲法や権限の面で懸念があったが、戦時の緊急性のもとで反対はほぼ不可能だった。
合意を導いた4つの論理
ヴェリテールは、各国の賛同を引き出した背景に4つの「相互作用の論理」があったと指摘する。
- 地政学的懸念
ロシアのプロパガンダはEUの存在そのものや国際的信頼性を損なう──そうした危機感から、禁止は政治的決意の表明とされた。 - 領土保全と独立の脅威
バルト三国やポーランドでは、ロシア語話者が多く、情報操作による国内不安定化への恐れが現実的だった。 - 連帯
直接の影響が小さい国も、「被害が大きい国を見捨てない」という連帯感から賛成に回った。 - 緊急性と政治的圧力
侵攻直後という非常事態で、迅速な一致がEUの結束と外部へのメッセージになると考えられた。
決定への批判と実効性の限界
この禁止措置は採択直後から多方面で批判を受けた。
- 法的権限の疑問:放送規制は本来、独立規制機関の権限であり、理事会が行うのは越権との指摘。
- 表現の自由:欧州人権条約や国際人権規約に抵触する恐れ。
- 実効性不足:禁止後もRTやスプートニクのコンテンツはVPNやSNS経由で閲覧可能。
- 国際的反発:ロシアが西側メディアを締め出す報復措置を取り、対立構造を強化。
ノルウェーやスイスは、憲法や影響の軽微さを理由に追随を拒否した。国連特別報告者も「非常に厳しい措置で、必要不可欠ではない」と批判している。
集合的セキュリティ化モデルの修正
この事例は、EUにおける安全保障化が加盟国からの初動と欧州委員会の推進力の組み合わせで進むことを示した。また、最終的な合意には市民感情や世論の影響も無視できず、従来の「上から下へ」の一方向モデルでは説明しきれない。
ヴェリテールは、複数のアクター(加盟国、EU機関、市民)が長期的に相互作用するモデルに修正すべきだと提案している。
表現の自由と安全保障、そのはざまで
RT・スプートニク禁止は、EUが自らの価値よりも地政学的利害を優先した瞬間だった。緊急時の決定が常態化すれば、透明性や民主的統制はさらに弱まる可能性がある。
偽情報対策は必要だが、それが「情報空間の制限」という形を取るのか、「市民の情報リテラシー向上」という形を取るのかで、社会への影響は大きく異なる。この事例は、その岐路を象徴している。


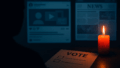
コメント
magnificent post, very informative. I ponder why the other experts of this sector don’t understand this. You should continue your writing. I am sure, you have a huge readers’ base already!
Pinco oyunları ilə böyük qazanc əldə et. Əyləncə və uduş bir arada — bax [url=https://pinkoaz.website.yandexcloud.net/]pinco[/url]. Pinco online kazino etibarlıdır.
Pinco-da slotlar hər zövqə uyğundur.
Thanks for your marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you may be a great author.I will make sure to bookmark your blog and definitely will come back at some point. I want to encourage one to continue your great posts, have a nice morning!
I like what you guys are up too. Such intelligent work and reporting! Carry on the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my web site 🙂
A Casino Royale póker játék minden játékos számára új kihívást jelent. Ha szereted a sportot és a szerencsejátékot, a Casino Royale az ideális hely. Különleges bónuszok várnak a [url=https://casino-hungary.website.yandexcloud.net/]casino royale poker chips set[/url] játékosaira. Keresd meg a nyerő kezet a Casino Royale asztalán.
A mobil app segítségével mindig naprakész lehetsz az új játékokról. A nyerő kombináció mindig a türelmes játékosokat jutalmazza. Nézd meg a Casino Royale streamet, és tanulj új stratégiákat. A Casino Royale mobil verziója könnyen kezelhető. Az apk verzió minden funkciót tartalmaz. A mobil app-ban bármikor elérheted kedvenc játékaidat. A Casino Royale mindig a játékosokért van.
A nine casino kiváló lehetőség a sportfogadás és online kaszinó kedvelőinek. [url=https://nine-casino-slothu.website.yandexcloud.net]No deposit bonus[/url] – próbáld ki kockázat nélkül. A nine casino magyarországi játékosoknak kínál egyedi bónuszokat
A nine casino promo code no deposit használatával kockázat nélkül próbálkozhatsz A nine casino prelievo gyors és megbízható. A nine casino kontakt szám segítségével gyors segítséget kaphatsz. A nine casino játékok tesztelhetők demo módban
A nine casino opinie pozitív visszajelzéseket mutat. A nine casino regisztráció pár perc alatt elvégezhető. A nine casino promo code segítségével extra esélyeket kapsz
I’m really loving the theme/design of your site. Do you ever run into any internet browser compatibility problems? A small number of my blog readers have complained about my blog not working correctly in Explorer but looks great in Safari. Do you have any tips to help fix this issue?
Aki élő sportfogadást keres, annak a Malina sport részlege nagyon erős.
Én leginkább a focis élő fogadást használom a Malina Casinón, elég gyors. Az online casino Malina jó kombináció sport és kaszinó játékokkal.
A Malina Casino app download után minden gyorsabb. Többen dicsérik a gyors kifizetéseket, nézd meg te is → [url=https://malina-casino-hgr.website.yandexcloud.net]malina casino kifizetés[/url]. A Malina Casino reviews nagyon sok pozitív visszajelzést tartalmaz.
A Malina Casino promóciók elég gyakoriak. A Malina Casino app jól működik még gyengébb telefonon is. A Malina Casino ingyen fogadás jó kipróbálásra. A Malina Casino 7-es promó sokak kedvence lett.
Kazino oyunlarını Pinco-da test edib daha sonra real pula oynamaq mümkündür. Futbol bahislərini tez yenilənən əmsallarla etmək istəyənlər Pinco-dan istifadə edir. Slot həvəskarları üçün sürətli giriş imkanı yaradır — [url=https://abillionhectares.com/]abillionhectares online[/url]. Yeni slotlar ilk olaraq Pinko AZ platformasında görünür.
Pinco tətbiqi canlı oyunlarda yüksək stabilik təqdim edir. Mobil Pinko ilə həm aviator, həm də klassik slotları oynaya bilərsən. Pinko-da depozitlər dərhal hesabda görünür.
Pinko mərc kuponları tez təsdiqlənir. Pinco tətbiqi az internetlə də stabil işləyir.
Pinko tətbiqi oyun prosesində donma yaratmır.
Pinco kazino az istifadəçilərə sürətli giriş və geniş oyun seçimi təqdim edir. [url=https://americanrentalcenters.net/]pinco bonus[/url] Aktiv oyunçular üçün gündəlik bonuslar və xüsusi kampaniyalar mövcuddur, qeydiyyat isə cəmi bir neçə saniyə çəkir. Pinco azerbaycan yukle versiyası daha az internet sərf edir.
Pinco dəstəyi 24/7 istifadəçilərə cavab verir. Pinco casino mobil versiyası mərc üçün ideal interfeysə malikdir. Pinco bonus kampaniyaları mütəmadi yenilənir
Pinco kazino oyunçulara pulsuz spin fürsətləri də verir. Pinco kazino apk versiyası köhnə telefonlarda da işləyir. Pinco oyunu açmaq üçün stabil internet kifayətdir. Pinco casino apk indir daha sabit performans verir.
I like what you guys are up too. Such smart work and reporting! Keep up the excellent works guys I?¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my website 🙂
You made some respectable factors there. I regarded on the internet for the problem and located most individuals will associate with along with your website.
It is perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I’ve learn this submit and if I may I want to suggest you some attention-grabbing issues or advice. Maybe you could write subsequent articles relating to this article. I want to learn more things about it!
Wenn wir das Gefühl haben, die Kontrolle zu
verlieren, ermöglicht uns PSK die einfache Aktivierung einer Selbstausschluss-Option, entweder vorübergehend oder dauerhaft.
Deshalb nutzen wir alle verfügbaren Tools, um unsere Spielgewohnheiten zu kontrollieren – wir setzen Limits für
Einzahlungsbeträge, Verluste und die Zeit, die wir im Spiel
verbringen. Wir sind uns bewusst, wie unterhaltsam Glücksspiele sein können, wissen aber auch, dass sie zu Problemen führen können, wenn nicht verantwortungsvoll gespielt wird.
Diese Meilensteine ermöglichten die Erweiterung des Angebots und den Übergang zu
digitalen Kanälen. Im Jahr 2012 wurde die Lizenz für Online-Wetten erworben und 2016 die
Lizenz für Online-Casinospiele. Im Laufe der Jahre expandierte das Geschäft durch den Ausbau des Filialnetzes und die Eröffnung einer Online-Plattform
für Wetten und Casinospiele, entsprechend den wachsenden Marktbedürfnissen.
Der Sicherheitsindex ist die wichtigste Kennzahl, die wir verwenden, um die Vertrauenswürdigkeit,
Fairness und Qualität jedes einzelnen Online Casinos in unserer
Datenbank zu beschreiben. Wenn Sie Schwierigkeiten mit der Auszahlung haben, können Sie sich an die Zahlungsservice-Abteilung von PSK Casino wenden. Wenn Sie Schwierigkeiten mit dem Spiel haben, können Sie sich an die Spiele-Abteilung von PSK Casino wenden. Wenn Sie
Schwierigkeiten mit der Einzahlung haben, können Sie sich an die Zahlungsservice-Abteilung von PSK Casino wenden. Wenn Sie Schwierigkeiten mit der Registrierung haben, können Sie sich an die Kundenservice-Abteilung von PSK Casino wenden.
PSK Casino bietet eine bessere Umsatzrückzahlungsrate und ein flexibles Zahlungssystem als Betway Casino
und 888 Casino.
Es bietet eine Vielzahl von Spielen, ein sicheres Zahlungssystem und eine freundliche Kundenservice-Abteilung.
Die Jackpot-Automaten in PSK von sind spannend, die Casino bietet großartige
Gewinnmöglichkeiten! Roulette ist mein Lieblingscasino, die Grafik in PSK ist erstaunlich und die casino läuft
flüssig.
References:
https://online-spielhallen.de/wazamba-casino-erfahrungen-ein-umfassender-testbericht/
F*ckin¦ tremendous issues here. I am very happy to peer your article. Thanks a lot and i’m having a look ahead to contact you. Will you please drop me a mail?
Ja, Casino Barcelona ist für Spieler aus der Schweiz mit einer internationalen Lizenz von Gibraltar legal
und bietet höchste Sicherheitsstandards durch moderne Verschlüsselungen. Die Spielauswahl,
der schnelle Casino Barcelona Login sowie die attraktiven Boni werden häufig gelobt.
Besonders beliebt sind sowohl klassische Tischspiele als
auch moderne Video-Slots und Live-Spiele.
Das ist die beste Bewertung, die ein Casino von uns erhalten kann.
Ja, die Casino Barcelona App ist sowohl für iOS als auch
für Android kostenlos erhältlich und bietet Zugriff auf das gesamte Angebot,
sichere Ein- und Auszahlungen sowie schnellen Login. Neue Spieler erhalten einen Willkommensbonus von bis zu 500 CHF und 100 Free Spins.
Wer nach einer Rundreise durch Spanien auch das Baskenland
erkunden möchte, findet dort ebenfalls attraktive Spielbanken. Der Flughafen Barcelona-El Prat (BCN)
bietet zahlreiche Direktverbindungen von deutschen Städten wie Frankfurt,
München oder Berlin. Wie in fast allen Casinos in Spanien werden klassische Casinospiele wie Amerikanisches und Französisches Roulette, Blackjack und Baccara angeboten.
References:
https://online-spielhallen.de/lex-casino-promo-code-ihr-schlussel-zu-exklusiven-vorteilen/
Customizing your library or adding lots of content downloads becomes very easy with Plex.
You get live access to over 100 networks, cloud DVR with unlimited
storage, plus national and local channels with the platform.
So if watching your loved teams is what you do on weekends,
it’s probably smart to opt for Fubo. Entertainment and news play a part,
but what it does best is ensure you won’t miss a major sports event.
Because the Star is located geographically in Sydney’s premium entertainment area, it’s able to provide accommodations that are uniquely luxurious.
Rocking live bands, hilarious comedians, and engagingly unique musical acts are also on-hand.
The one thing that is missing from the facility is the
chance to enjoy electronic gaming. Whether you are a low stakes
player or a high roller, you’ll find the table that’s just right for you at this casino.
As part of the Demerger, Tabcorp sought a ruling from the
Australian Taxation Office on the taxation implications
for shareholders. Eligible shareholders who wished to sell
their shares under the Voluntary Share Sale Facility were required to return a Sale Instruction Form by the Closing Date.
Based on a share price of $5.68, being the closing price
of The Star Entertainment Group (SGR) shares on the Australian Securities Exchange
on the Record Date, an Unmarketable Parcel was any holding of
88 shares or less. Payment of the sale proceeds were made to participating shareholders on 27
May 2016 in accordance with their payment instructions
as recorded on the share register. Alarming laws and
legislation have been passed in other countries that can significantly impact
people’s lives. Though a few movies without
the most sterling scores sometimes slip through, this section is
a splendid resource on Certified Fresh movies currently streaming on Tubi.
References:
https://blackcoin.co/4-top-tips-for-winning-big-at-online-poker/
The campus is served by buses to Seattle and some Eastside cities at the Overlake Transit Center, operated by
Sound Transit and King County Metro. Microsoft also announced its intention to contain most its
future growth within Redmond, while retaining some offices
in Downtown Bellevue and Factoria. The campus was originally
leased to Microsoft from the Teachers Insurance and Annuity Association, a
pension fund manager, until it was bought back in 1992. Microsoft chose
to move its headquarters from Bellevue to nearby Redmond in January 1985, selecting a 29-acre (12 ha) plot of land that would be
developed by Wright Runstad & Company. Microsoft initially moved onto the grounds of the campus on February 26, 1986,
weeks before the company went public on March 13.
The 1978 win over Marquette was another instance of the Irish defeating the
defending national champion. The 1954 win in the NCAA tournament over Indiana prevented IU from back-to-back national titles after claiming the 1953 NCAA Tournament
Title. They are also the first Big East team to go undefeated at home two straight seasons.
References:
https://blackcoin.co/woospin-premier-pokies-paradise-for-aussie-players-in-2025/
Synonyms for important help you explain value and priority in a clearer way.
Learn a new word every day. Comprehensive resource for word definitions and usage
A school trip may be important for learning, but it is not essential to pass a class.
Important means something matters a lot, yet life can still go on without it.
Both words show value, but essential is stronger. The main idea is that the thing matters more than normal things.
You can show need with essential, impact with significant, urgency
with urgent, and status with influential. Learning synonyms for important helps you explain value and priority
with more precision. Things can matter for different reasons like need, impact, status, or
urgency, so English has many close words.
References:
https://blackcoin.co/safe-online-casinos-in-australia/
If you feel like Lady Luck is on your side, you can make a lot of money fast while playing baccarat.
The goal of the game is to bet on which hand total is going to be higher or if it’s going to end in a tie.
You will get to enjoy quality graphics and sound effects, fast-paced gameplay, and plenty of betting options.
Every operator has several virtual roulette tables prepared for the fans of this traditional casino game.
We deliver everything you need to gamble like a boss – exclusive bonuses,
slot games, new gambling sites, and much more. The best online casinos let you navigate their platform for free, and all the casinos we
recommend allow you to try their games at no cost.
For those looking to play for and win real cash,
real money casinos offer secure transactions, fast payouts,
and a wide range of deposit options. The best online casinos
offer more than just pokies. The best casinos offer transparent, fair, and achievable bonus
terms, giving players real value. We’ve reviewed nearly 100 online casinos that accept Australian players.
This allows for the excitement of substantial wins, with some casinos offering a lower house edge on certain games
to improve favourable outcomes. A high-quality casino offers a wide array of games, including slots, table games,
and live dealer games. The most common payment method, credit and debit cards like Visa, MasterCard, and
American Express are widely accepted by Australian online casinos.
Aussie players have a variety of casino payment methods to choose from when it comes to playing games.
Despite the fact that games have a wide diversity and have
unique features easy to discover at most sites, some are more popular among Australian players and some are less.
References:
https://blackcoin.co/blackjack-tutorial/
casino online paypal
References:
slonec.com
paypal casinos
References:
activeaupair.info
online casino for us players paypal
References:
http://carecall.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=2092656
online casino paypal einzahlung
References:
https://worlancer.com/profile/waylonmeade068
I have been exploring for a little bit for any high-quality articles or blog posts on this sort of space . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this website. Reading this info So i am satisfied to exhibit that I’ve an incredibly just right uncanny feeling I discovered just what I needed. I so much no doubt will make certain to do not put out of your mind this website and give it a glance on a constant basis.
online blackjack paypal
References:
https://bolsadeempregos.com.br/Empresas/top-list-of-australian-casinos-expert-picks-for-2025/
mobile casino paypal
References:
https://jobthejob.altervista.org/employer/top-casino-sign-up-offers-for-new-players-updated-2025/
My brother suggested I might like this blog. He was totally right. This post truly made my day. You can not imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!
It is the player’s sole responsibility to inquire about the existing laws and regulations of the given jurisdiction regarding age limitations for online gambling. It is the player’s sole responsibility to inquire about the existing laws and regulations of the given jurisdiction for online gambling. Featuring a diverse selection of games, including slots, live casino, table games, and more, Casino Rocket combines a sleek design with smooth functionality. We prioritise urgent matters like login rocket casino problems or security concerns.
Some reviewers mentioned that the customer support team is friendly and helpful, while others experienced slow response times. Whether you’re on mobile or desktop, you’ll experience smooth gameplay without delays. Their games feature unique bonus rounds and engaging themes. We partner with industry-leading software providers to deliver top-quality gaming experiences. We’ll verify the code validity and manually credit eligible bonuses to your account. Partner websites and affiliate platforms occasionally feature casino rocket code promotions.
References:
https://blackcoin.co/ufo9-casino-your-place-to-play-your-way/
online casino paypal
References:
https://skilling-india.in/employer/online-casino-australia-top-real-money-casino-list/
paypal casinos online that accept
References:
https://razib.cretechbd.com/employer/die-besten-online-casino-mit-paypal-im-test-2025/
online casinos that accept paypal
References:
https://sigma-talenta.com/employer/our-favorite-paypal-casinos-2025-ranking-update/
us online casinos paypal
References:
https://generaljob.gr/employer/15-best-online-casinos-australia-trusted-sites-for-real-money/
Tauch ein in das spaßige Spielerlebnis und schnapp dir potenzielle Gewinne ohne eigenes Risiko! Alle Neuen dürfen sich über 200 kostenlose Freispiele für den beliebten Spielautomaten Chicken Chase freuen. Die Mindesteinzahlung liegt bei nur €10 – damit kann wirklich jeder diesen fetten Bonus abstauben. Als Neuling bei uns kriegst du ein hammerstarkes Startpaket von bis zu €2.000 Bonusgeld plus 225 Freispiele bei deiner ersten Einzahlung! Du bekommst ein mega großzügiges Willkommenspaket von bis zu 2000 Euro plus 225 Freispiele, sobald du dich anmeldest!
Falls Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) aktiviert haben, geben Sie den Einmalcode ein, den Sie per SMS oder in Ihrer Authenticator-App erhalten haben. Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail mit einem Aktivierungslink. Geben Sie Ihre Handynummer ein und bestätigen Sie diese mit dem Code, den Sie per SMS erhalten. NV Casino operiert unter einer offiziellen Glücksspiellizenz aus Curacao, was den Spielern eine sichere und faire Spielumgebung bietet.
References:
https://s3.amazonaws.com/onlinegamblingcasino/casino%20rostock.html
Um bei HitnSpin Casino mit Echtgeld zu spielen, registrierst du dich, aktivierst dein Konto und tätigst eine Mindesteinzahlung von 10 €. Alles findet in Echtzeit statt, und Sie spielen gegen echte Dealer und Mitspieler. Neue Spieler werden mit einem Willkommensbonus von 800€ und 200 Freispielen begrüßt, der über die ersten 3 Einzahlungen verteilt ist.
Tischspiele waren lange Zeit das Herz von Casinos und auch heutzutage kann man sich viele dieser klassischen Casinospiele nicht aus einer Spielhalle wegdenken. Casino Spiele kostenlos auszuprobieren ist eine hervorragende Methode, um sich an Glücksspiele heranzutasten. So kann man sich sicher sein, dass man eine sichere und innovative Glücksspiele-Erfahrung machen kann, wenn man bei uns spielt. Heute möchten Spieler flexibel sein und auch unterwegs auf ihre Lieblingsspiele zugreifen können. Hit’n’Spin bietet zahlreiche Einzahlungs- und Auszahlungsmethoden, um maximale Flexibilität zu gewährleisten. Für je 10 € Einsatz in unseren Spielen (außer im Live-Casino und bei Instant Games) erhalten Sie einen Treuepunkt.
References:
https://s3.amazonaws.com/onlinegamblingcasino/lotto%20casino.html
Der Gewinn von Echtgeld ist mit diesen Boni dennoch möglich. Gutgeschrieben werden dir die Freispiele für den Slot Fortune Gods von PGSoft. Mit unserem Bonus Code CTOFS100 sicherst du dir 100 Freispiele ohne Einzahlung bei FanSport. Die Freispiele erhältst du exklusiv mit unserem Bonus Code 100VINCI1. Die Freispiele kannst du im Slot Gates of Olympus verwenden.
Viele Casinos bieten spezielle Bonusangebote für Spieler nach der ersten Einzahlung an. Deshalb werde ich euch nachfolgend genau erklären, wie ihr eure erste Einzahlung tätigen könnt und wie ihr von den großzügigen Willkommensboni profitieren könnt. Ihr werdet erfahren, welche Bonusangebote euch erwarten und welche weiteren Vorteile diese Casinos bieten. Online Glücksspielanbieter setzen gezielt auf den Einsatz verschiedener Arten von Casino Boni ohne Einzahlung, um bestimmte strategische Ziele zu erreichen. Je nach Anbieter kann es sein, dass ein Bonus Code für die Freischaltung von Casino Bonusangeboten benötigt wird.
References:
https://s3.amazonaws.com/new-casino/best%20casino%20sites%20spin4bonus.html
Auch die Liebhaber traditioneller Casinospiele kommen nicht zu kurz. Das Unternehmen präsentiert eine umfassende Spielesammlung, die ein maßgeschneidertes Spielerlebnis für die unterschiedlichsten Geschmäcker bietet. Für jede 10 €, die Sie bei Spielen (außer Live-Casino und Instant Games) einsetzen, erhalten Sie 1 Gratispunkt.
Die maximale Auszahlung beträgt das 5-fache des Bonus und du kannst pro Stufe bis zu CHF 300 erhalten. Jede Woche erhalten wiederkehrende Spieler Reloads, Cashback von bis zu 12 % und spezielle VIP-Belohnungen, wenn Sie die Treuestufen erklimmen. Neukunden können allein für ihre Anmeldung bis zu 800 CHF plus 200 Freispiele freischalten. Die Mindesteinzahlung beträgt nur 10 CHF, und dank schneller Auszahlungen und keiner Obergrenze für Auszahlungen haben Sie jederzeit Zugriff auf Ihre Gewinne. Ob Sie klassische Slots, Live-Dealer-Action oder wöchentliche Neuerscheinungen suchen, unsere Plattform bietet Abwechslung für jeden Geschmack und jedes Spielniveau.
References:
https://onlinegamblingcasino.s3.amazonaws.com/vegas%20days%20casino.html
References:
Bally’s casino tunica
References:
https://www.24propertyinspain.com/user/profile/1356535
References:
Mardi gras casino
References:
http://premiumdesignsinc.com/forums/user/tunakarate2/
References:
Hot slots
References:
https://imoodle.win/wiki/WD40_Classic_spray_WD40_Australia
difference between steroids and anabolic steroids
References:
https://support.mikrodev.com/index.php?qa=user&qa_1=frenchclock7
steroids price
References:
http://muhaylovakoliba.1gb.ua/user/coatgym1/
weight gaining stack
References:
https://notes.io/eufYJ
References:
Blood work before and after anavar hdl ldl
References:
http://humanlove.stream//index.php?title=storycause40
I want meeting useful info, this post has got me even more info! .
pill steroids
References:
https://pediascape.science/wiki/Clenbutrol_Alternative_lgale_au_Clenbuterol
References:
Anavar before after reddit
References:
https://elclasificadomx.com/author/voicecare2/
%random_anchor_text%
References:
https://historydb.date/wiki/Top_Natural_Appetite_Suppressants_to_Help_Control_Hunger