2025年8月にオーストラリア通信メディア庁(ACMA)が公表した「Digital platforms’ efforts under voluntary arrangements to combat disinformation and misinformation Fourth report to government」は、デジタルプラットフォームが自主的な規範のもとでどのように偽情報・誤情報に対応しているのかを詳しく記録している。自主規範(Australian Code of Practice on Disinformation and Misinformation)は2021年に導入され、Adobe、Apple、Google、Meta、Microsoft、Redbubble、TikTok、Twitchの8社が署名している。ACMAは毎年、各社の透明性レポートを取りまとめ、政府に提出してきた。今回の報告は、2024年の活動を総括し、2025年以降の課題を整理したものである。
国際的な事例と国内事例
報告書はまず、世界とオーストラリア国内での偽情報事例を取り上げる。
- ルーマニア大統領選挙(2024年)
憲法裁判所が選挙を無効とする異例の決定を下した。背景にはSNS、特にTikTokを通じた外国干渉、資金の違法流入、票操作が疑われる事案があり、欧州委員会はTikTokに対してデジタルサービス法違反の可能性を調査している。 - 英国サウスポート刺傷事件(2024年)
事件直後に拡散した誤情報が反移民暴動につながった。規制当局Ofcomはアルゴリズムの推奨が分断を助長したと指摘し、議会は「ソーシャルメディア、偽情報、有害アルゴリズム」の調査を開始した。Metaの監督機関であるオーバーサイトボードは、危機対応の遅さを問題視し、暴動を煽る危険性がある投稿を削除しなかったMetaの判断を覆した。 - オーストラリア・サイクロン・アルフレッド(2025年)
上陸前に「ブリスベンが時速220キロの風に襲われている」とする偽動画が出回り、「政府が気象を操作して人々の自由を奪おうとしている」という陰謀論も広がった。自然災害時に偽情報が人々の不安につけ込む典型例である。
ACMAは、豪州成人の74%が偽情報を懸念しており、世界でも最も高い水準にあると指摘している。一方でメディアリテラシー教育を受けた人は24%にとどまり、脆弱性が残されている。
プラットフォームの方針の変化
署名企業の透明性レポートからは、二つの大きな傾向が読み取れる。
ファクトチェックの縮小
- Googleはオーストラリア通信社(AAP)との契約を2025年に更新せず、検索やニュースでのファクトチェック表示も取りやめた。
- Metaは米国で第三者ファクトチェックを終了し、「Community Notes」型のユーザー参加方式に移行した。オーストラリアではまだ継続しているが、将来的な見直しが示唆されている。
- TikTokはAAPとの提携を継続し、ファクトチェックを組み込んでいる。
AI生成コンテンツへの対応
- Apple Newsは2024年7月から、AIで生成あるいは補助された記事をラベル付けする方針を導入した。
- YouTubeは2024年3月に、生成AIなどによる合成コンテンツに開示義務を課し、本人に似せた合成コンテンツを削除申請対象に追加した。
- Metaは政治広告や社会的問題に関する広告に対し、AI利用の開示を義務化した。
- Adobe、Microsoft、Google、TikTokはC2PA(Content Provenance and Authenticity)に参加し、透かしや「コンテンツ認証情報」技術を導入している。
これらは、ファクトチェックという事後的な対応から、AI生成コンテンツの真贋をあらかじめ明示する仕組みへと軸足を移していることを示す。
データから見える傾向
報告書は、各社が提供した豪州特化のデータを集計している。
- 誤情報削除件数の減少
Meta、TikTok、YouTube、LinkedInはいずれも、2023年から2024年にかけて豪州で削除された偽情報コンテンツ数が減少した。 - 広告違反の急増
Googleでは違反広告の削除件数が2023年の約3600万件から2024年には6000万件を超えた。Microsoftも同様に急増を記録している。広告分野の取り締まりは強化されている。 - 不正ネットワークの摘発
TikTokは2024年に59件の不正ネットワークを遮断。Metaはロシアの「Doppelganger」作戦を追跡し、6000以上の偽ドメインを摘発した。
これらの数字からは、偽情報コンテンツそのものの削除は減っている一方、広告と偽アカウントへの対策が拡大している傾向が見える。
メディアリテラシーと教育投資
報告書は教育面での取り組みにも注目している。
- MetaはAAPと共同でメディアリテラシーキャンペーンを行い、約253万人に届き、視聴回数は615万回を超えた。
- MicrosoftはOpenAIと協力して「Societal Resilience Grants」を創設し、選挙管理機関や高齢者、ジャーナリストにAIリテラシーを普及。
- Adobeは学校向けにメディアリテラシーカリキュラムを開発。
- TwitchはMediaWiseと連携し、利用者向けの教育資材を公開した。
さらに政府は2025年から初の「国家メディアリテラシー戦略」を策定し、教育・研究機関と連携して進める予定である。
自主規範の課題
報告書は自主規範そのものの課題も指摘する。
- 大手でありながら署名していないプラットフォームが存在する。
- 新規署名者「Legitimate」が2025年に脱退したが、正式な告知がなく透明性に欠ける。
- 月間利用者数100万人未満のサービスは報告義務が免除されているが、その基準が明確でなく、DIGIによる説明も不十分である。
2025年後半には規範の全面的な見直しが予定されており、透明性やガバナンスの強化、署名者拡大、苦情処理の整備などが議論されることになる。
まとめ
今回の報告書から浮かび上がるのは、削除による対応が減少し、AIコンテンツへのラベル付けや教育投資が中心に移りつつあるという方向性である。一方、ファクトチェックの縮小はリスクを高め、自主規制モデルの限界も示している。オーストラリア政府は法規制を撤回し、この自主規範に依拠していく方針を示した。今後のレビューで、透明性と実効性をどう高めるのかが大きな課題となる。
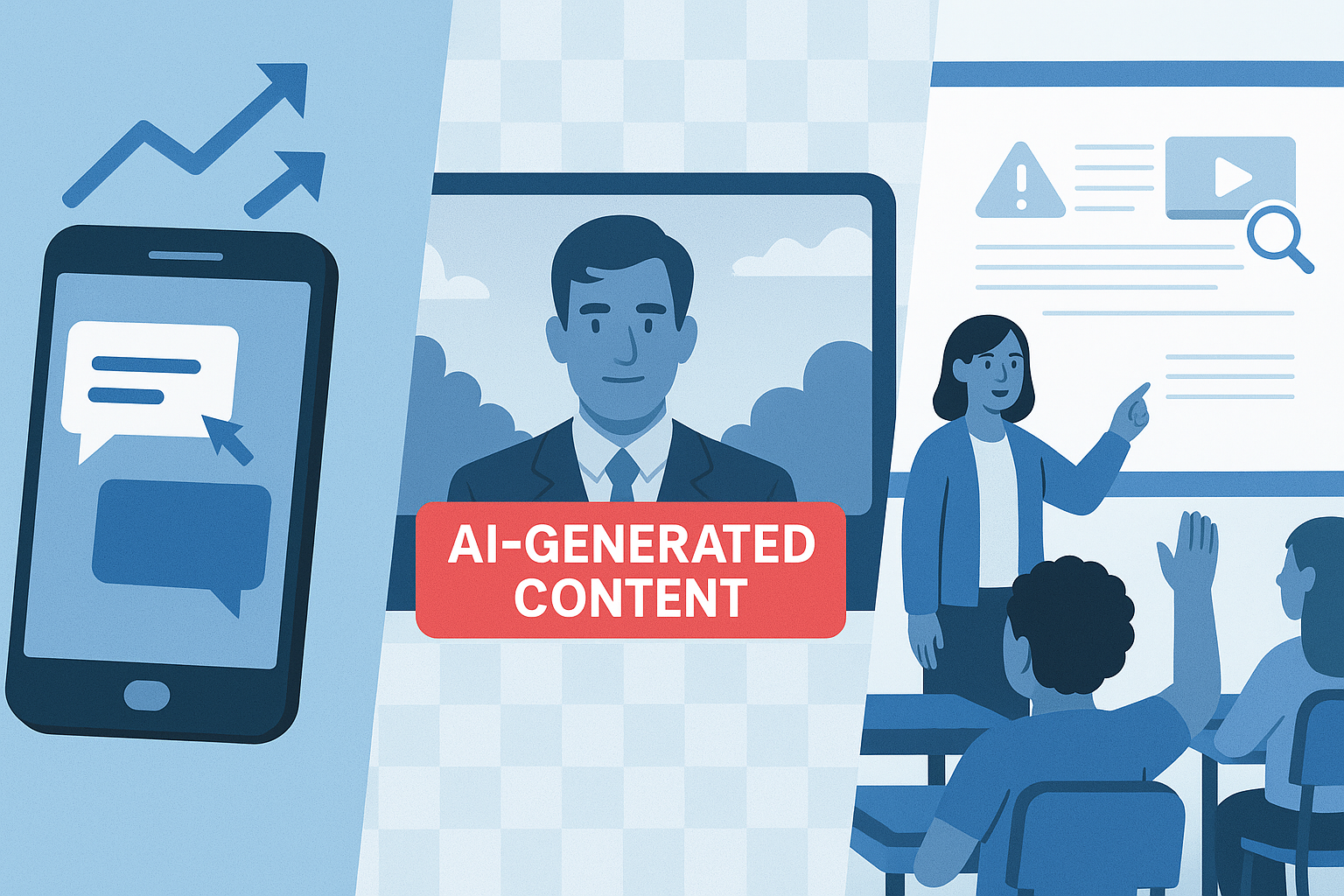


コメント
Throughout this awesome design of things you’ll receive an A+ for hard work. Where you confused us was first on your specifics. You know, people say, details make or break the argument.. And that could not be much more true here. Having said that, let me tell you precisely what did work. Your writing is certainly very engaging and this is possibly the reason why I am taking an effort to comment. I do not really make it a regular habit of doing that. Secondly, although I can certainly see a jumps in reason you come up with, I am not really sure of how you appear to unite the ideas that produce the final result. For now I shall subscribe to your position however trust in the near future you actually connect the facts much better.
Thank you for sharing superb informations. Your site is so cool. I’m impressed by the details that you have on this website. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found just the information I already searched all over the place and simply could not come across. What a perfect web-site.
You are my intake, I have few web logs and infrequently run out from brand :). “Truth springs from argument amongst friends.” by David Hume.
I have recently started a website, the info you offer on this website has helped me tremendously. Thanks for all of your time & work.
Hello! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done a outstanding job!
I am usually to running a blog and i really recognize your content. The article has actually peaks my interest. I’m going to bookmark your site and preserve checking for new information.
I’d have to examine with you here. Which is not one thing I usually do! I take pleasure in reading a post that may make folks think. Additionally, thanks for permitting me to comment!
Mit dem Bonuspaket können Sie sich Bonusguthaben im Gesamtwert von bis
zu 500€ sichern. Dieses Casino ohne Limit wird von den Behörden aus den Philippinen reguliert und hat wirklich einiges zu bieten. Ein vertrauenswürdiges neues Online Casino arbeitet
mit renommierten Softwareanbietern zusammen, die für Fairness und Qualität bekannt sind.
Gerade die Casinos mit EU Lizenz gelten als sicher und seriös.
Seriöse Online Casinos sind in der Regel von anerkannten Glücksspielbehörden lizenziert und reguliert.
Hier finden Sie nicht nur top Boni, sondern auch sichere Zahlungsmethoden und ein vielfältiges Spielangebot.
Die Wahl eines vertrauenswürdigen und seriösen Online Casinos
ist für ein sicheres, faires und angenehmes Glücksspielerlebnis von entscheidender
Bedeutung. Spins of Glory zeigt sich als verlässliche Adresse für alle, die sicher und fair online spielen möchten. Die
deutsche Lizenzierung gewährleistet, dass Spieler in einer sicheren Umgebung spielen, wo Fairness und Transparenz oberste Priorität haben.
Ein Zertifikat von Gaming Labs International bekommen ebenfalls nur faire und seriöse Online
Casino-Anbieter, die im Vorfeld festgelegte Standards zu erfüllen haben. Zu den Dienstleistungen gehören unter anderem Qualitätssicherung, Software Tests, RNG-Zertifizierungen und
Plattformzertifizierung. Es ist das wohl wichtigste Siegel, wenn es um faire und seriöse
Online Spielhallen geht.
References:
https://online-spielhallen.de/tipico-casino-login-ihr-einfacher-zugang-zur-casinowelt/
Your bonus funds are instantly added after redemption and can be used across the
casino’s full range of pokies. The code must be entered in the “coupons” tab that you’ll find in the casino’s cashier
after you’ve registered. A free pokie bonus of A$15 is available to Australian signups
who enter the bonus code “15NEWREELS” at Reels Grande Casino.
Free spins no-deposit bonuses are promotional offers provided by online casinos
that allow new players to play slots for free without making an initial deposit.
If you’re new to online casinos, learning how to claim no deposit bonus code offers enables you to start playing
without risking your own money. Today’s new no deposit bonus offers are
promotions from online casinos that allow players to enjoy games without making a deposit.
You should claim no deposit bonuses to explore Aussie casinos online,
see how they work and how specific games play while having fun with no risk.
Most online casinos let Australian players keep their winnings from no deposit
bonuses after meeting wagering requirements.
You can also play slots for free in demo mode, allowing you to
test games before you decide to play for real money. What is considered the best
online casino is not necessarily the same for everyone. Are you wondering how to
make the most of your no deposit bonus and increase your chances of winning real cash?
All of the casinos featured on our list can be accessed in their
entirety using your mobile device.
RNG audits and third-party checks ensure fairness in slots and table games.
Always confirm the contribution rates for live dealer games
toward bonus wagering. Regular players at WinSpirit earn loyalty points (CPs) for real-money play, predominantly on slots.
WinSpirit Casino positions itself as a comprehensive online gambling platform, distinguished
by its exceptional game variety, flexible payment options, and mobile
accessibility. The platform provides players with various self-management tools designed to maintain healthy
gambling behaviors. Game selection on mobile platforms includes approximately 90% of desktop-available titles,
with only legacy games lacking mobile compatibility.
The Winspirit platform operates within regulations and complies
with all necessary laws of Australia. Agents can check eligibility and guide you through activation or
suggest alternative promotions. WinSpirit supports Visa, MasterCard, local bank options, e-wallets like MiFinity and
vouchers such as Neosurf, plus a broad list of cryptos. We hope
this guide helps you explore WinSpirit confidently — good luck and play responsibly.
It’s especially strong for slot enthusiasts and mobile users
who want PWA convenience. Effective bankroll and bonus management reduce stress and improve long-term enjoyment.
Understanding wagering requirements and game contributions is essential to extract value.
WinSpirit structures bonuses into welcome packages,
weekly promos and VIP rewards. When withdrawing crypto choose the network (ERC20, TRC20 etc.) that matches your wallet to avoid extra fees.
References:
https://blackcoin.co/what-is-free-play/
Very interesting info!Perfect just what I was looking for!
online real casino paypal
References:
https://rhea-recrutement.com/employer/use-paypal-to-play-poker-at-888poker/
online betting with paypal winnersbet
References:
https://cvbankye.com/
I gotta bookmark this site it seems invaluable invaluable
I have been exploring for a little bit for any high quality articles or weblog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this site. Studying this info So i am glad to express that I’ve an incredibly just right uncanny feeling I found out just what I needed. I so much indisputably will make sure to don¦t disregard this web site and give it a glance on a relentless basis.
The website is optimised for iOS and Android, making it
easy to enjoy games on the go. At the same time, if you are unlucky today,
it is not a critical amount to lose. Secondly, you
can make the $10 minimum deposit! First, we have thousands of games with minimum bets of 10 or
20 cents. Each bonus brings fun and high winning potential!
MiFinity is another convenient payment method
for Australians.
It shows the platform genuinely considers Australian players.” For complex issues requiring detailed assistance, players can reach our support team via email at [email protected]. We provide comprehensive responsible gambling tools to help players maintain control over their gaming activities.
Also, if you’re into feature-loaded games, check out hits like “Valley of the Gods” or “Book of Dead” for an adventure through ancient Egypt. Here at Stay Casino, there are tons of online slots, and there are thousands to choose from. On the site, you’ll find games neatly organized into seven categories, including Bonus Wagering, Live Casino, Mini Games, Popular Games, and more.
References:
ufo9
online casino australia paypal
References:
http://play123.co.kr/bbs/board.php?bo_table=online&wr_id=276290
online slot machines paypal
References:
https://jobzee.co.uk/Company/die-besten-online-casino-mit-paypal-im-test-2025/
australian online casinos that accept paypal
References:
https://www.seniorjobbank.ca/companies/paypal-casinos-2025-best-casino-sites-that-accept-paypal/
paypal casino uk
References:
https://supplychainjobs.in/employer/best-real-money-online-casino-sites-worldwide/
NV Casino bietet seinen Spielern eine Vielzahl von sicheren und bequemen Zahlungsmethoden für Ein- und Auszahlungen an. Spieler erhalten abhängig vom eigenen VIP-Level zwischen 3 % und 12 % Rückzahlung auf ihre Nettoverluste. Regelmäßige Spieler können jeden Freitag von einem Einzahlungsbonus von bis zu 700 € profitieren. Auch hier gilt eine maximale Gewinnbegrenzung in Höhe des Fünffachen der Ersteinzahlung. Die Höhe des Bonus ist abhängig von der Einzahlungssumme, der Umsatzfaktor beträgt 40x für Bonusgelder und 35x für Freispiele.
Das NV Casino bietet ein sicheres und vielfältiges Spielerlebnis, unterstützt durch eine Curaçao-Lizenz und einen soliden Sicherheitsindex. Wenn Sie frische Luft bevorzugen, bieten die nahegelegenen Parks eine entspannende Flucht aus dem Trubel der Gegend. Sie werden das Menü des Penny Cafe lieben, das eine Mischung aus mexikanischen und amerikanischen Gerichten bietet. Gemeinschaftsveranstaltungen und Interaktionsbelohnungen bereichern Ihr Erlebnis zusätzlich und bieten Anreize zur Teilnahme. Obwohl bisher keine Benutzerbewertungen eingereicht wurden, bietet das Diskussionsforum des Casinos einen offenen Raum, um persönliche Erfahrungen zu teilen, was Transparenz und Vertrauen stärkt. Darüber hinaus priorisiert das NV Casino die Glücksspielaufklärung, indem es Ressourcen und Informationen über verantwortungsvolles Spielverhalten direkt auf ihrer Plattform zur Verfügung stellt.
References:
https://s3.amazonaws.com/onlinegamblingcasino/casino%20affiliate%20software.html
Laut den vorliegenden Informationen gibt es Promo-Optionen wie 50 Freispiele ohne Einzahlung für Big Bass Splash oder sogar 25 Euro Cash ohne Einzahlung. Gelegentlich bietet HitnSpin spezielle Aktionen wie einen Bonus ohne Einzahlung an. Das Casino bietet eine Vielzahl von Anreizen, die sowohl neue Spieler als auch treue Bestandskunden belohnen.
Danach sollte Ihr Konto aktiv sein und Sie können die erste Slot Maschine spielen und eine Chance auf echtes Geld haben.Vergessen Sie außerdem nicht, sich bei Ihrem ersten Hitnspin Casino Login den Bonus zu sichern. Sie haben genug gehört und wollen anfangen, bei HitnSpin zu spielen? So können Sie bedenkenlos bei uns spielen.Insgesamt sind Ihre Daten und Gelder bei uns zu jedem Zeitpunkt zu 100% geschützt.
References:
https://s3.amazonaws.com/new-casino/casino%20bonus%20ohne%20einzahlung.html
So stellen wir sicher, dass nur die besten und sichersten Online Casinos in Deutschland eine Top-Bewertung erhalten. Ein Online Casino wird von uns nur dann empfohlen, wenn es über die erforderliche deutsche GGL-Lizenz verfügt. BrilliantCasinos.com bietet ausschließlich unterhaltungsorientierte Informationen. Wir arbeiten mit erstklassigen Online-Casinos zusammen, um unseren Besuchern exklusive Boni und Werbeaktionen anzubieten. Unsere Casino-Partner-Website ist bestrebt, Spielern das bestmögliche Online-Spielerlebnis zu bieten. Seriöse Casinos sollten mehrere Kontaktmethoden anbieten, wie z. Wenn Sie beim Spielen in einem Online-Casino in Deutschland auf Probleme stoßen oder Fragen haben, besteht der erste Schritt darin, sich an das Kundensupport-Team zu wenden.
Wir haben die besten Online Casinos getestet und für euch eine Liste der Top-Anbieter im deutschsprachigen Raum zusammengestellt. Bwin Slots, Wunderino und StarGames führen die Liste an und gehören zu den besten Online Casinos mit Paysafecard. Die besten Online Casinos mit PayPal sind Wunderino, Wildz und SlotMagie. Alle Online Casinos mit deutscher Lizenz sind legal und zahlen wirklich aus. Die eine „beste“ Zeit zum Spielen im Online Casino gibt es nicht.
References:
https://onlinegamblingcasino.s3.amazonaws.com/casino%20spar.html
References:
Female anavar before and after pics reddit
References:
https://pad.stuve.de/s/kq89jF8UZ
References:
Women’s anavar before and after
References:
https://morphomics.science/wiki/Anavar_Before_and_After_Results
References:
Winnavegas casino
References:
https://sciencewiki.science/wiki/Speed_Limits_Fees
References:
Cool gaming names
References:
https://bom.so/Wx8zfk
References:
Hollywood casino cincinnati
References:
https://undrtone.com/latexiron2
steroid for weight loss
References:
https://www.giveawayoftheday.com/forums/profile/1571714
where to buy steroid powder
References:
http://theconsultingagency.com/members/billheat3/activity/1547/
anavar cutting
References:
http://theconsultingagency.com/members/giantcheese11/activity/1285/
References:
Anavar alone before and after
References:
https://pad.stuve.uni-ulm.de/s/Gg4gYtb7M
dmaa bodybuilding
References:
https://scientific-programs.science/wiki/Winstrol_Stanozolol_Online_Kaufen
References:
Anavar weight loss before and after
References:
http://09vodostok.ru/user/basscell7/
References:
Before and after using anavar
References:
https://etuitionking.net/forums/users/clockrobert7/
where to get illegal steroids
References:
https://nerdgaming.science/wiki/Nahrungsergnzungsmittel_Was_das_Gesetz_erlaubt
What’s Going down i am new to this, I stumbled upon this I have discovered It positively helpful and it has aided me out loads. I’m hoping to contribute & help different users like its helped me. Great job.
References:
Anavar alone before and after
References:
https://king-wifi.win/wiki/Il_miglior_steroide_anabolizzante_per_le_donne_Oxandrolone_Anavar
%random_anchor_text%
References:
https://socialbookmarknew.win/story.php?title=dianabol-comprar-dianabol-en-espana-hi-tech
References:
Paypal casino
References:
https://socialisted.org/market/index.php?page=user&action=pub_profile&id=291102
References:
Blackjack strategy
References:
http://okprint.kz/user/showmoney57/
References:
Talking stick casino
References:
https://baby-newlife.ru/user/profile/422670
References:
Casino michigan
References:
https://www.24propertyinspain.com/user/profile/1362435
References:
Jackpotjoy slot machines
References:
http://celebratebro.in/birthdays-in-bangalore/index.php?qa=user&qa_1=greasetheory2
References:
Emerald princess casino
References:
https://opensourcebridge.science/wiki/3_Ways_to_Check_Your_Payment_History_on_Candy_Crush
References:
No deposit sign up bonus
References:
https://scientific-programs.science/wiki/Descubre_Cmo_Jugar_en_un_Casino_con_un_Croupier_en_Vivo
References:
Cripple creek casinos
References:
https://socialbookmark.stream/story.php?title=candy96-payment-methods-fast-secure-crypto-friendly
%random_anchor_text%
References:
https://mclaughlin-hamrick-6.thoughtlanes.net/stanozolol-winstrol-tabletten-kaufen-top-preis-online
body builder steroid
References:
http://pattern-wiki.win/index.php?title=mahmooddaugaard2527
how do you inject steroids
References:
https://linkvault.win/story.php?title=symptome-bei-testosteronmangel-diese-warnsignale-kennen-viele-maenner-nicht
%random_anchor_text%
References:
https://lovebookmark.date/story.php?title=where-to-buy-clenbuterol-online-legally-and-safely
street names for steroids
References:
https://graph.org/What-to-Take-After-a-Dianabol-Cycle-Find-out-the-best-PCT-01-25
when to take dianabol
References:
https://theflatearth.win/wiki/Post:Post_Cycle_Treatment_A_Comprehensive_guide_to_a_safe_PCT
References:
Rosemont casino
References:
https://skitterphoto.com/photographers/2176085/stokholm-potter
References:
O l g slots
References:
https://timeoftheworld.date/wiki/Fullsized_Cocktail_Table_Arcade_Game_with_60_Classic_Games
References:
Las vegas slots
References:
https://pediascape.science/wiki/Top_Real_Money_Online_Casino_2026
References:
Play online games games
References:
https://md.inno3.fr/s/0Pxm3cKWK
best muscle growth pills
References:
https://may22.ru/user/cheesebugle97/
dbol reviews bodybuilding
References:
https://pnwsportsapparel.com/forums/users/lipoutput51/
steroids side effects on women
References:
https://hikvisiondb.webcam/wiki/Muskelaufbau_und_TestosteronKick_Der_unterschtzte_Trainingsfehler_den_viele_Mnner_machen
how to use steroids safely for bodybuilding
References:
https://lynn-ottosen-2.hubstack.net/clenbuterol-und-fettverbrennung-dosierung-anwendung-wirkung-und-tipps
References:
Lucky eagle casino texas
References:
https://timeoftheworld.date/wiki/No_Deposit_Bonus_Promo_Codes_Freispiele_fr_deutsche_Spieler
References:
Diamond jacks casino
References:
https://to-portal.com/lizardswamp3
References:
Cache creek casino
References:
https://mathews-pena.mdwrite.net/24casino-24-casino-in-deutschland-jetzt-online-spielen-and-bonus-sichern
References:
Ladbrokes mobile casino
References:
https://wikimapia.org/external_link?url=https://online-spielhallen.de/888casino-im-test-slots-poker-zahlungen-bonus/
References:
Casino maryland
References:
https://gaiaathome.eu/gaiaathome/show_user.php?userid=1833116
References:
Station casinos boarding pass
References:
https://linkagogo.trade/story.php?title=ihr-online-gluecksspielplatz-fuer-sichere-auszahlungen
References:
Online betting in india
References:
http://cqr3d.ru/user/vaseclose3/