IPIE(International Peace Institute Europe)は2025年、テクニカルペーパー「Artificial Intelligence and Peacebuilding: Opportunities and Challenges」(TP2025.3)を発表した。本書は、AIが平和構築の現場でどのように応用されているか、またそこに潜むリスクは何かを、600を超える学術論文・政策文書・市民社会のレポートをレビューして包括的に整理したものである。対象は紛争予測や人道マッピング、市民参加のためのチャットボットや対話プラットフォーム、調停や交渉支援に至るまで幅広い。だが同時に、監視や標的化といった武器化のリスク、環境負荷やエネルギー消費の問題も正面から扱う。本稿では、報告書が描き出す応用分野ごとの具体的な事例と限界、そして提示された勧告を順に紹介する。
AIと情報環境:中立ではないデータ
序論でまず強調されるのは「データは中立ではない」という原則である。AIの成果は、どのように収集されたデータか、誰が保有しているか、どの目的で利用されるかによって大きく変わる。たとえば紛争地のSNS投稿は、都市部からの発信が中心で農村部や通信遮断地域の声は欠落する。これを「社会の全体像」として扱えば、偏った政策判断につながる。
また、情報環境自体がAI活用の行方を左右する。自由なメディア、説明責任を果たす統治、適切な規制やデジタル・リテラシーが存在する環境では、AIは市民のレジリエンスを高める。しかし、権威主義的な環境では、同じ技術が検閲や監視、偽情報拡散に用いられる。したがって、AIの平和構築応用を評価する際には、技術の性能だけでなく、それを取り巻く情報環境の質を前提にしなければならない。
紛争予測:期待と盲点
事例と導入状況
紛争予測はAI応用の中で最も早く導入が進んだ分野である。代表的なのがウプサラ紛争データプログラム(UCDP)と、Armed Conflict Location & Event Data(ACLED)である。これらは暴力事象を詳細に記録した大規模データベースで、死者数、場所、関与主体などをラベル化して蓄積している。これを入力として機械学習モデルを訓練し、人口統計や経済指標を組み合わせて将来の暴力リスクを予測する。
スウェーデンの「Violence Early Warning System(ViEWS)」はその代表例だ。ACLEDとUCDPのデータを組み合わせ、アフリカ諸国のサブナショナルレベルで「来月どの地域で暴力が発生する確率が高いか」を予測するモデルを構築している。このシステムは国連開発計画(UNDP)や一部の人道団体が参照し、資源配分や早期警戒に利用している。
成果と問題点
紛争予測の利点は、従来の専門家判断では把握しきれない大規模データのパターンを分析し、早期警戒やホットスポットの抽出に役立つ点にある。だが、報告はここで手放しの楽観を拒む。
第一に、突発的な「変化点」には対応できない。COVID-19の世界的流行やミャンマーの2021年軍事クーデターは、過去データに存在しないため完全に予測を外した。第二に、紛争データの定義やラベリング自体が政治的に偏る危険がある。暴力と認定するか否かで結果は変わり、入力データの偏りがそのまま予測に反映される。第三に、予測精度が高く見えても、現場の介入設計に落とし込むと齟齬が生じる。AIは「未来を保証する占い師」ではなく、人間の判断を補助するシグナルにすぎない、と報告は繰り返す。
リアルタイム・マッピング:鮮やかな地図と沈黙の領域
実際の活用例
AIはまた、リアルタイムでの紛争や人道状況のマッピングに利用されている。衛星画像やドローン映像、SNS投稿、携帯電話の移動データを組み合わせることで、暴力や避難の動きを「今この瞬間」に近い形で可視化できる。
ハイチの地震後には、国際機関が衛星データと携帯通話記録を組み合わせ、道路の通行可能性を把握し、人道支援のルート計画に利用した。シリア内戦では、国連機関やNGOがSNS投稿を機械学習で分類し、攻撃地点や避難経路を推定した。リモートセンシング企業のPlanetや国連のUNOSATは、破壊された建物やインフラを高解像度で検出し、人道マッピングに提供している。
空白とリスク
一方で「沈黙の領域」が常に存在する。政府が通信を遮断している地域や、農村部などインフラが未整備な場所では、データが存在しない。結果として、都市部を中心に鮮やかに描かれる地図は、最も脆弱な人々を丸ごと欠落させる。またSNS由来のデータは、誤情報や操作に晒されやすい。現地検証が伴わなければ、誤った地図を根拠に誤誘導が生じる危険が大きい。
市民参加ツール:チャットボットと対話プラットフォーム
チャットボットと低帯域環境
AIは市民参加を拡大する手段としても試されている。東アフリカではSMSを使った通報システムが導入され、住民からの暴力被害報告を集めた。南アジアでは自動音声応答(IVR)が災害時の避難情報を配信し、低帯域環境でも利用可能であることが示された。これにより、従来アクセスできなかった住民が参加できるようになった。
しかし同時に、送られた情報が政府や武装勢力に渡れば、住民が危険に晒されるリスクがある。包摂の拡大と監視の危険は常に背中合わせである。
RemeshとPolis
国連政治・平和構築局(DPPA)はRemeshを使い、リビア・イエメン・シリアで市民の意見を収集した。数百人規模の参加者から得られた回答をAIがクラスタリングし、合意可能な論点を抽出した。Polisは台湾やニュージーランドで用いられてきた対話可視化ツールだが、紛争文脈にも応用されつつある。
こうしたツールは大規模対話を可能にするが、「代表性」は保証されない。接続できない人々は排除される。また、発言の安全が担保されなければ報復に直結する危険もある。
調停・交渉支援:効率化と信頼の緊張
PoCの成果
交渉支援においてもAIは実験的に導入されている。ドイツ外務省とAI開発団体OmdenaのPoCでは、膨大な交渉資料をAIに探索・要約させた。その結果、関連文書の検索時間を最大70%削減できたと報告されている。これは調停準備の効率を大幅に改善する成果である。
限界と危険
だが、平和交渉は効率性だけでは成り立たない。交渉の核心は「信頼」と「中立性」であり、AIの要約や提案が偏っていれば、交渉全体が揺らぐ。さらに、交渉記録やメタデータが外部に漏洩すれば、参加者が報復の危険に晒される。報告は、AIの利用は探索・要約といった補助的領域に限定し、「自動交渉」の導入は避けるべきだと明確に線を引いている。
横断的リスク:環境負荷の現実
ペーパーは応用分野を超えて共通するリスクを列挙する。データの偏り、希少事象の予測困難、武器化の可能性に加え、環境負荷が強調される。
大規模言語モデル(LLM)の学習には数百MWhの電力と大量の水冷却が必要である。研究によれば、GPT-3クラスのモデル訓練には数万世帯分の月間電力に相当するエネルギーが使われた。水使用量も莫大で、データセンター周辺の水不足を悪化させる可能性がある。平和構築のために導入したAIが、別の場所で環境不安を引き起こす逆説が突きつけられる。
設計原則と勧告
報告は最後に、各ステークホルダーに向けて具体的な勧告を提示する。
- 設計者:Do No Harmを原則に、人権と同意をライフサイクル全体に組み込む。
- 技術者:小規模LLMと地域言語対応を重視し、住民と共同設計する。
- 政策担当者:人権に基づく規制と資金投入を行い、国際協調を推進する。
- 民間企業:現地組織と直接連携し、環境負荷の低減や誤情報・ディープフェイク対策に責任を持つ。
- 市民社会:人権と参加原則に基づき、モニタリングと実装指針作成を担う。
- 学術界:実地での協働研究と学際的な人材育成を推進する。
- ドナー:短期的なパイロットに偏らず、長期的な知見共有と人材育成を支援する。
結論
IPIEのテクニカルペーパーは、AIと平和構築の接点を応用分野ごとに丁寧に整理し、可能性と限界を具体的に描き出した。紛争予測や人道マッピング、市民参加の拡大、交渉支援といった応用はすでに実験段階に入りつつあるが、同時に監視・武器化・環境負荷といった深刻なリスクを抱えている。AIが平和の資源となるか否かは、設計原則と情報環境次第である。


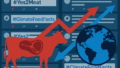
コメント
Mit Wild- und Scatter-Symbolen bietet das Spiel erhöhte Chancen auf große Gewinne.
Das Spiel bietet 10 Gewinnlinien sowie Wild- und
Scatter-Symbole, die Ihre Chancen auf große Gewinne erhöhen.
Shining Crown ist ein farbenfrohes und spannendes Automatenspiel, das ein klassisches Spielerlebnis mit Obst-, Kronen-
und Siebensymbolen bietet. Wir ergreifen angemessene Maßnahmen,
um sicherzustellen, dass Ihre persönlichen Informationen vor unbefugtem Zugriff, Offenlegung,
Änderung oder Zerstörung geschützt sind. Durch die Teilnahme
an unserem Affiliate-Programm bestätigen Sie, dass Sie unsere Bedingungen überprüft und verstanden haben.
Zum Beispiel erhalten Conticazino-Spieler nach einer
erfolgreichen Identitätsprüfung 50 Freispiele.
Spieler, die ihre Identität bestätigen, werden zu
vollwertigen Mitgliedern des Conticazino-Glücksspielclubs und können problemlos Gewinne abheben, an Werbeaktionen teilnehmen und zusätzliche Belohnungen vom Casino erhalten. Um
Ihre Identität zu bestätigen, muss sich der Spieler
in sein Konto einloggen und seine persönlichen Daten in seinem Kontrollfeld eingeben. Die Identitätsüberprüfung im Conticazino Casino ist einfach
und muss nur einmal durchgeführt werden. Auf diese Weise kann das Casino sicherstellen, dass
es sich bei dem Spieler um eine echte Person handelt,
die volljährig und zur Teilnahme am Glücksspiel
berechtigt ist.
References:
https://online-spielhallen.de/evolve-casino-login-ihr-zugang-zum-spielvergnugen/
The platform also supports a Skycrown Casino Australia login, allowing members to manage their accounts efficiently.
The Skycrown Casino Login page is easily accessible from the official
website, where players can enter their credentials and start playing instantly.
You can browse games and play demos without verification. Some live dealer tables
run separate mobile and desktop interfaces, but the underlying game and bets carry over.
Some live dealer tables run separate mobile and desktop interfaces, but the underlying game and
bets carry over seamlessly.
Cash-outs at Skycrown are simple and support a wide range of
options such as Visa, MasterCard, Skrill, Neteller, PayPal, bank transfers,
and cryptocurrencies including Bitcoin and Ethereum.
The casino is recognised for fair payouts, transparent rules, and
responsible gambling practices. Yes, Skycrown Casino is a
licensed and regulated platform. All contact details and procedures listed are current as of 2025 in accordance with the operational standards of the Skycrown Casino platform.
Simply click Log In, enter your email and password, and
start playing instantly.
SkyCrown App Casino is the perfect choice for players
who want to use their devices for endless betting and casino fun. Our app
is optimized for the best gaming experience on the go.
Our app is designed with Australian users in mind, offering a safe and seamless gaming experience.
Whether you’re a frequent player or new to the platform, the app ensures
you can always be a part of the action. If you’re new to the platform, you
can easily create an account directly through the app.
References:
https://blackcoin.co/casino-payments/
Lucky Green Casino’s payment system is designed to make every transaction seamless and worry-free.
Every hand and spin at Lucky Green Casino feels
genuine and exciting, making it a true all-in-one gaming hub.
The more you play, the more benefits you unlock — a
system that makes every spin count. Here,
you can play with real dealers in real-time, streaming
from professional studios in HD quality. Players can explore hundreds of pokies covering every theme imaginable, from adventure and mythology to fantasy and nostalgia.
The platform’s unique mix of modern design, responsive performance, and vibrant entertainment ensures that every visit feels
exciting and rewarding.
For those who enjoy the thrill of live casino games, Lucky Strak and Winfinity bring their expertise to Lucky Green. The casino isn’t limited to slots either – it
also offers a wide variety of instant games and table games to suit different
preferences. With over 1000 options available, including more than 500 pokies, players
have plenty to enjoy. The bonus and free spins have a 45x wagering
condition, requiring players to wager the bonus amount 45 times before
withdrawals are allowed.
References:
https://blackcoin.co/how-to-spot-poker-cheats-and-what-to-do-with-that/
usa casino online paypal
References:
https://pridestaffing.us/companies/online-casino-mit-paypal-einzahlung-die-top-casinos-im-vergleich/
online casino that accepts paypal
References:
http://www.dycarbon.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=564571
online casino mit paypal einzahlung
References:
https://realestate.kctech.com.np/profile/gracielatilton
casino mit paypal einzahlung
References:
https://analyticsjobs.in/jobs/companies/home/
Die Mindesteinzahlung für die Teilnahme an dieser Aktion beträgt 20 €/$/£ (oder entspricht EUR). 100% bis zu 1000€ + 100 Freispiele 50% bis zu 500€ + 50 Freispiele
In den meisten Fällen beträgt die geforderte Mindesteinzahlung 10€. Aber statistisch betrachtet ist eine solche Aussage haltlos, wenn man in einem lizenzierten Casino Einsätze tätigt. Das sind Unterschiede und Nachteile in den Regularien, die bei Offshore-Behörden wie zum Beispiel in Curacao bestehen. Betreiber, die keine solche Lizenzierung besitzen, aber dennoch hierzulande ihre Dienste anbieten, sind Betrüger und landen auf einer Blacklist. Der maltesische Staat hat daher ein hohes Eigeninteresse an der unbedingten Vertrauenswürdigkeit der vergebenen Glücksspiellizenzen! Die Bewerbung auf die Erteilung einer Lizenz und die Verlängerung einer bestehenden Erlaubnis sind mit Kosten verbunden.
References:
https://s3.amazonaws.com/new-casino/boomerang%20casino.html
References:
Blood work before and after anavar hdl ldl
References:
https://hack.allmende.io/s/RNW4dF6ky
References:
6 week anavar before and after
References:
https://able2know.org/user/cobwebelbow64/
References:
Ashley revell
References:
https://mozillabd.science/wiki/WD40_Casino_Review_Bonus_Codes_2026
References:
Casino los angeles
References:
https://www.askocloud.com/index.php/user/stoveiron3
strongest fat burning steroid
References:
https://menwiki.men/wiki/Clenbuterol_Sopharma_at_51_00_Buy_Legal_in_America
anabolic vs catabolic steroids
References:
https://www.hulkshare.com/veilslope5/
how do you make steroids
References:
https://klint-glerup.federatedjournals.com/como-reconocer-un-bolso-falso-segun-los-expertos
References:
Anavar cycle results before and after
References:
https://skitterphoto.com/photographers/2134476/salinas-marks
side effect of bodybuilding
References:
https://oceanflat3.bravejournal.net/where-to-buy-legal-steroids-online-in-2026
buy steroids in mexico
References:
https://doc.adminforge.de/s/SVVvxtAd4_
what is a steriod
References:
https://livebookmark.stream/story.php?title=recensione-dianabol-quali-sono-gli-effetti-di-questo-steroide
References:
Before and after pics of women on anavar
References:
https://www.garagesale.es/author/repairjeff6/