PEN Americaが2025年3月28日に公開したレポート「Exploring How to Build Community-Level Resilience Against Disinformation」は、偽情報に対して“信頼できる人との対話”を起点にしたアプローチを紹介している。AIによる自動生成コンテンツが普及し、プラットフォームの対応も後退するなかで、制度やメディアの外側にある「関係性」そのものに着目している点が特徴だ。
本レポートは2022年から2024年にかけて、マイアミ、ダラス–フォートワース、フェニックスの3都市で行われた実践を中心に構成されている。背景にあるのは、米国社会における政治的分断、制度不信、ソーシャルメディアを介した過激化の進行、そして2024年大統領選挙に向けて拡散した偽情報の数々である。だが、報告書が焦点を当てるのは「何が流れたか」ではなく、それに「誰がどう向き合ったか」のほうだ。
「ニュースを見るのが疲れる」という人に、どう話すか
たとえば、ダラス–フォートワース地域でワークショップに参加した女性、バーバラ・ジェームズは、選挙をめぐる会話が増える中で、ある友人の存在が気になっていた。その友人は、いつも同じニュースチャンネルばかりを見ており、「どうせメディアなんて全部偏ってる」と話すようになっていた。
ワークショップで「trusted messenger」としてのトレーニングを受けたジェームズは、その友人にある日こう声をかけた。
「一緒に、別のチャンネルのニュースも見てみない? どこがどう違うのか比べるの、ちょっとおもしろいと思うんだよね」
この提案は、意見の押しつけではなく、好奇心を共有する形で行われた。ふたりは実際に数日間、異なるニュースチャンネルを一緒に視聴し、話し合いをするようになったという。ジェームズは「自分が説得したんじゃない。情報を比べるという行為を、一緒にやってみただけ」と振り返っている。
「学校で何を教えているのか」という疑念と向き合う
マイアミでは、公教育をめぐる偽情報が広まっていた。「ジェンダー教育が強制されている」「特定の歴史が削除されている」といった話がSNS上で共有され、それを真に受ける保護者や地域住民も多かった。
教育者であり、地方議会選に出馬していたジャクリーン・ギルは、そうした話題を信じる同僚に対し、あえてすぐには否定せず、「それ、どこで見たの?」と質問から入った。
同僚は、「Facebookで見た動画」と答えたが、どの団体が発信元かは覚えていなかった。ギルはその情報を一緒に調べ、「これは州の方針でも、学校の実際の授業でもない」と説明しつつ、**「なんでこういう話が出てくるんだと思う?」**と、さらに別の問いを投げた。
その後、同僚からは「これ、また出回ってたけど、どう思う?」と自発的な問い合わせが届くようになった。ギルは「相手の意見を変えたんじゃなくて、“何かを一緒に調べる相手”になれたことが大きい」と語っている。
WhatsAppのカフェ会話で、疑問を口にする訓練を
フェニックスでは、Conecta Arizonaと連携し、スペイン語話者向けにWhatsApp上での「cafecito(カフェシート)」が定着している。これは、毎朝のように数十人が集まるチャット形式のニュース対話の場で、参加者は自分の疑問や見かけた情報について自由に書き込み、他の住民や専門家が応答する。
ある朝には「州知事が投票IDを廃止する」というチェーンメッセージが話題になった。そこでは実際の選挙管理局の情報が共有され、「IDが必要なのはどの場面か」「なぜそう誤解されやすいか」といった点が整理された。
この場では、「わからない」「気になる」と言っても咎められない空気が維持されており、質問の多さそのものがリテラシーの高さを示す構造になっている。PEN Americaはこの形式に注目し、他地域での応用可能性も検討している。
偽情報対策を「誰と話すか」の問題に戻す
PEN Americaの本レポートは、従来の偽情報対策が重視してきた「情報の正誤」や「プラットフォーム上の制御」といった手法とは異なる、関係性を基盤とした介入モデルを提示している。政治的・制度的対応が困難な局面が増える中、日常的な信頼関係の中で、情報摂取や判断の前提を揺らすことが可能であるという前提に立ち、具体的な支援策を展開した点は注目に値する。
偽情報の流通経路を断つのではなく、それを受け取る側の態度や習慣に働きかけるアプローチとして、本レポートは実践知とともに貴重な素材を提供している。


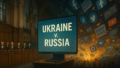
コメント
сколько стоит changan https://changan-v-spb.ru
This is a very good tips especially to those new to blogosphere, brief and accurate information… Thanks for sharing this one. A must read article.
Hi there, You’ve done an incredible job. I’ll certainly digg it and in my opinion recommend to my friends. I am confident they will be benefited from this site.
You made some first rate factors there. I seemed on the web for the problem and located most people will go together with together with your website.
he blog was how do i say it… relevant, finally something that helped me. Thanks
Very efficiently written article. It will be valuable to anyone who utilizes it, as well as yours truly :). Keep doing what you are doing – looking forward to more posts.
Utterly indited articles, Really enjoyed reading through.
I too believe therefore, perfectly composed post! .
It’s difficult to find well-informed people on this
topic, but you sound like you know what you’re talking about!
Thanks
online slots paypal
References:
ninula.com
online slot machines paypal
References:
https://10xhire.io/employer/us-online-casino-reviews-2025/
casinos paypal
References:
advertiseajob.co.uk
paypal casinos for usa players
References:
https://directorio.restaurantesdeperu.com/employer/best-online-casino-australia-2025-top-australian-online-casinos/
Heya! I realize this is sort of off-topic however I had to ask.
Does building a well-established blog such as yours require a large amount of work?
I’m brand new to blogging however I do write in my journal on a daily basis.
I’d like to start a blog so I can share my own experience and views online.
Please let me know if you have any ideas or tips for new aspiring bloggers.
Appreciate it!
Customer Support Chat Job: $25/hr ! This is a job application, open for applicants from all countries, for online customer support workers doing live chat support. This means you will be handling the live chat messages for a business on their website and social media accounts. Full training is provided and we have jobs available to start work on right away. You are able to set your own hours as long as you work a minimum of 10 hours a week. Read more details here : http://chat-assistant.advertising4you.co.uk
References:
Anavar only cycle before and after
References:
schoolido.lu
References:
Vernon casino
References:
https://clashofcryptos.trade
References:
Anavar for women before and after
References:
lovebookmark.date
$600 per week watching movie reviews ! Do you like watching movies? If yes then you might like this job because here, you’ll get a chance to watch movie reviews daily and get paid by doing so. There’s a YouTuber with more than 3 million subscribers who post movie reviews daily. He wants to hire a remote worker because of his busy schedule. Read more details here: http://social-media-jobs.advertising4you.co.uk
References:
Nooksack casino
References:
onlinevetjobs.com
References:
Los angeles casinos
References:
https://kostsurabaya.net/author/latexeight8/
References:
Blackjack bomber
References:
https://canvas.instructure.com/eportfolios/4127172/entries/14560856
I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good.
I don’t know who you are but definitely you’re going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!
I’m really enjoying the design and layout of your website.
It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable
for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme?
Superb work!
bodybuilding steroids side effects photos
References:
https://socialbookmark.stream/
References:
Should i take anavar before or after workout
References:
rentry.co
anabolic usa
References:
https://hateboard58.bravejournal.net/
effects of performance enhancing drugs
References:
imoodle.win
This really answered my problem, thank you!
steroid injections for muscle building
References:
botdb.win