スペインとポルトガルを中心に活動するEDMO地域拠点IBERIFIERは、2025年10月、報告書D3.1「Disinformation on Social Networks」を公表した。対象はCovid-19、気候変動、ジェンダー関連の三領域。いずれも瞬間的なフェイクではなく、何年も社会的対立を生み続けるテーマである。IBERIFIERの狙いは、誤った主張を訂正することではない。研究者たちはこう書く──“What matters is not what is said, but how it circulates.”(重要なのは「何が語られたか」ではなく「どう循環したか」だ)。偽情報をテキストとしてではなく、ネットワーク現象として記述すること。これが本報告書の出発点である。
Telegramに潜む反復的ネットワーク
最初の分析対象はTelegram。チームは2019年から2025年にかけて活動した491の公開チャンネルを手作業で特定した。そのうち、再投稿を主要な活動とするチャンネルが122。全体の投稿のうち約8,000件が虚偽情報として分類され、4,252件を分析対象にした。メッセージはすべてTransformer埋め込みモデルでベクトル化され、類似度閾値0.83以上の組を「内容的再利用」として連結。こうして現れたのがSLIC(Source-Linked Information Cascade)という単位である。
典型例を挙げる。2021年4月、スペイン語チャンネル「Salud Natural」が「ワクチンはDNAを変える」という投稿を出した。2時間後、ポルトガル語の「Desperta Portugal」が「政府がDNA改変を隠している」と再投稿。翌日には宗教系チャンネルが「神の設計を汚すワクチン」と書き換えた。文体は変わっても、語彙の核──“DNA”“危険”“真実”──は保持されている。NETINFアルゴリズムで再投稿関係を可視化すると、発信源を中心に数百ノードが放射し、やがて元のチャンネルに向かって戻るループ構造が現れた。報告書はこれを「鏡像的増殖(mirror-like replication)」と呼ぶ。新しい主張はほとんど生まれず、既存の文をわずかに変形して再送するだけで、投稿数は幾何級数的に膨張する。Telegramにおける偽情報とは、人間の意図よりも模倣構造そのものが自己増殖する現象であった。
分散プラットフォームの瞬発的拡散──Twitter/X
Twitter分析はAcademic APIが閉鎖される2023年6月直前に行われた。収集データはスペイン語・ポルトガル語投稿2万件、うちファクトチェック付きURLを含むもの約1,000件。Covid-19関連デマはブラジル圏が中心で、最も拡散した投稿は「ファイザー社のワクチンにナノチップが含まれる」という主張。ブラジルでは“chip no sangue(血中チップ)”、スペインでは“microcontrol en las vacunas”と表現され、構文パターンは変わっても意味の骨格は同一だった。
興味深いのは、同一文面のコピー投稿が全体の1.8%しかなかったことだ。残りは語順や文体を変えた派生表現であり、IBERIFIERはこれをsemantic mutation(意味的変異)と呼んでいる。テキスト埋め込みモデルでの類似度分布は二峰性を示し、0.9以上の“ほぼ同一”グループよりも、0.7〜0.8の“派生型”グループが圧倒的に多い。偽情報はコピペではなく、翻案によって生き延びる。
拡散の時間構造もTelegramと対照的だ。特定テーマが数日単位で急上昇し、すぐ消える。2020年4月の「マスク輸送妨害」デマは24時間で4,000件超リツイートされ、翌週には完全に沈静化した。報告書はこの挙動を「burst-type contagion(一過性感染型拡散)」と定義している。
反論もまた拡散を生む
Twitterでは、ファクトチェック記事のURLを含む投稿が偽情報と同じハッシュタグ空間で混在していた。たとえば気候変動を否定する投稿の下に、科学誌の記事を引用した反論が数分以内に現れる。しかし拡散解析では、ファクトチェック投稿よりも原文デマの再利用数が20倍近く多かった。しかも反論ツイートの文面が後に別のユーザーにより引用され、「科学者は嘘をついている」と逆転利用される例が多発した。IBERIFIERはこれを反証の再利用(reuse of rebuttal)と呼ぶ。反論が情報流を止めるのではなく、模倣素材として再吸収される。ここに、ソーシャル空間の非線形性がある。
スタンス検出モデル──AIが読み違えた社会文脈
IBERIFIERはLLMを用いた自動スタンス検出も試みた。対象は1,594媒体から収集した16,249記事で、EFE Verifica、Maldita.es、Newtral、Polígrafo、Verificatなど計5,516件のファクトチェックと照合。Qwen2.5-72B-Instructを基盤モデルとし、英語・スペイン語・カタルーニャ語の3言語で“支持・反論・無関係”を分類した結果、整合率は82%。だが誤分類の傾向が示唆的だった。カタルーニャ語の記事「独立を求める声が弾圧されている」は、政治的報道であっても“賛同”と判定されやすい。LLMは文の構造を理解しても、その発話の社会的位置づけを理解しない。報告書は「AIは文を読むが文脈を読まない(AI reads sentences, not situations)」と記す。この部分に、AI検証の限界と、文化的符号をどう扱うかという課題が露出している。
DSA以降の研究アクセス──制度を待たずに始める
2025年7月に施行されたDigital Services Act第40条は、研究者のためのプラットフォームデータアクセス制度を創設した。しかしIBERIFIERの研究はその前から行われていた。Academic APIの縮小やTelegramの非公開化が進む中で、チームは公開情報のクロールと匿名化処理を組み合わせ、実質的なデータアクセスを確保した。報告書ではこれを「de facto access(事実上のアクセス)」と呼ぶ。制度的アクセスが整う前に、研究者自身が観測の回路を構築していたという点で、IBERIFIERはDSA時代の先駆的ケースとなっている。
模倣が模倣を生む生態系
IBERIFIERの観察を貫くのは、模倣の自己増殖である。Telegramでは、少数のハブチャンネルが同一内容を再帰的に複製し、Twitterでは無数のユーザーが意味を変えて派生表現を生む。偽情報とは「誤った情報」ではなく、模倣の構造が可視化される現象だ。報告書はこの構造を数学的に「再帰ネットワーク(recursive network)」としてモデル化し、伝達を担うノードの半数以上が同時に受信者でもあることを示した。これは、情報の発信と受信の境界が消失した状態、言い換えれば自己参照的エコシステムの成立である。
この構造を理解することが、今後の偽情報対策の核心になる。正誤の判定ではなく、再利用と翻案の経路を検知し、どの部分に介入すれば再帰連鎖を断てるかを明らかにする。IBERIFIERは、偽情報を“内容”から“構造”へと移した。事実を訂正する時代から、流れを制御する時代への転換点にある。

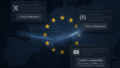

コメント
slot365 apk Tỷ lệ hoàn tiền có thể dao động từ 5% đến 10% tùy vào sự kiện trò cụ thể. Điều này không chỉ giúp người tham gia giảm bớt áp lực khi thua cược mà còn tạo thêm cơ hội để họ quay lại các trận đấu giành chiến thắng.
In einer Online Spielbank und bei Echtgeld Spielen stehen natürlich auch die Zahlungsdienste im Fokus.
So könnt ihr mit dem Echtgeld Casino Bonus noch mehr aus eurer ersten Erfahrung
herausholen – und euch noch mehr Chancen auf
Gewinne sichern. Mit eurem Willkommensbonus erhaltet ihr
ein Extraguthaben für eure erste Einzahlung.
Die besten Online Casinos sind allerdings bestrebt, Ihnen endlose Unterhaltung zu bieten und alles andere so fair wie möglich zu gestalten. Das Haus, auch bekannt als Casino,
wird auf lange Sicht hin immer gewinnen. Nicht alle Casinoboni sind schlecht und viele von ihnen wirken sich sogar positiv auf Ihr
Guthaben und Ihre Spielsitzungen aus. Mithilfe eines online Casino Tests sollten Sie in der Lage
sein, sich blitzschnell zu entscheiden, ob es sich lohnt, einen Bonus anzunehmen, oder ob Sie lieber die Finger davon lassen sollten. Einen Casinobonus anhand
seines Gesamtwerts zu beurteilen ist eine der wertvollsten Fähigkeiten, die
Sie hier im Stakersland erlernen können. Immerhin ist es unsere Aufgabe, sicherzustellen, dass die Casinos ihren Spielern einen professionellen und fairen Service bieten.
References:
https://online-spielhallen.de/izzi-casino-bonus-codes-ihr-schlussel-zu-extra-spielguthaben-und-freispielen/
Radicchio, endive, rocket, baby spinach, frisee, artichoke, cucumber, cherry tomato, red
capsicum, onion, olives, almonds, broccoli, balsamic dressing
Grilled chicken breast, cucumber, cherry tomato, red capsicum, onion, olives,
rocket, radicchio, endive, frisee, baby spinach, pesto dressing Grilled prawns, crunchy pancetta, crispy bread, tomato,
cucumber, red onion, red capsicum, basil, balsamic dressing
Enjoy an exclusive 10% discount on all specials when you dine
as a member
References:
https://blackcoin.co/win-up-to-1000-200-free-spins-at-winshark-casino/
Logging in means unlocking your customized universe of premium games, exclusive VIP perks,
and exciting bonuses. Welcome back to King Billy
Casino, where accessing your personal gaming world is fast, secure, and designed for maximum convenience.
The blockchain-based verification provides transparency impossible in traditional gaming formats, building trust with skeptical players.
The casino displays testing certificates through footer links, accessible for
player review.
Activate session reminders to stay on track, and view detailed history to monitor your activity.
Set deposit, loss, and session limits, enable cool‑off
periods, or apply self‑exclusion directly from your profile.
Use filters to sort by volatility, features,
or provider. Terms are clear and visible in your account area.
Unlock tiered VIP rewards after your King Billy Casino login.
References:
https://blackcoin.co/winspirit-casino-login-australia-quick-access-to-premium-gaming/
online pokies australia paypal
References:
https://ipo.fountain.agri.ruh.ac.lk/employer/online-casino-mit-paypal-einzahlung-die-top-casinos-im-vergleich/
online casino paypal
References:
http://carecall.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=2092649
gamble online with paypal
References:
https://fakers.app/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=49488
We’re taking a modern approach to the traditional flavours and ‘low and slow method’ of Southern American BBQ. Enjoy our large selection of drinks overlooking the River Derwent with panoramic views across the Wrest Point lawns to the Tasman Bridge. Welcome to our dazzling new casino bar. If you don’t want Google’s repository, do ‘sudo touch/etc/default/google-chrome’ before installing the package. From shopping and entertainment to productivity, find extensions to improve your experience in the Chrome Web Store.
Here, you’ll enjoy not only magnificent French-inspired cuisine, but also unforgettable 360-degree views of Hobart. Its unique position as a pioneering establishment in the Australian casino industry has allowed it to refine its offerings to provide an exceptional experience for all its visitors. These specials can include discounts, promotions, and unique opportunities that enhance the gaming and Wrest Point Casino entertainment experience. When guests book a stay for two nights at the casino’s hotel, they are eligible to receive a 20% Wrest Point Casino prices discount on their accommodation. Wrest Point Casino, a premier entertainment destination in Hobart, Tasmania, enhances the gaming experience for its patrons through an array of bonuses and promotions. These enhancements fortify Wrest Point Casino’s commitment to delivering a well-rounded gambling experience, accommodating diverse player preferences.
Personalise your web browser with themes, dark mode and other options built just for you. Microsoft partnered with Sound Transit and the City of Redmond to fund a pedestrian bridge connecting the light rail station to both sides of its campus to open in 2020, providing $33.3 million of the cost. The campus is served by buses to Seattle and some Eastside cities at the Overlake Transit Center, operated by Sound Transit and King County Metro. The campus is located on both sides of the State Route 520 freeway, which connects it to the cities of Bellevue and Seattle as well as the Redmond city center.
References:
https://blackcoin.co/ufo9-casino-your-place-to-play-your-way/
mobile casino paypal
References:
http://www.jobteck.co.in/companies/top-paypal-casino-sites-in-canada-for-december-2025/
online casino with paypal
References:
https://innovationsgroup.in/employer/best-online-casino-sites-expertly-reviewed-top-casinos/
us online casinos paypal
References:
https://jobotel.com/companies/online-casino-mit-paypal-sicher-schnell-einzahlen-2025/
online casino roulette paypal
References:
https://oportunidades.talento-humano.co/employer/best-online-casino-games-2025-play-top-casino-games/
References:
Pictures of before and after using anavar
References:
https://linkvault.win/story.php?title=anavar-before-and-after-results
References:
Should you take anavar before or after lifti
References:
https://md.ctdo.de/s/Bvkk4exNvk
References:
Genting casino glasgow
References:
https://telegra.ph/Play-WD-40-Casino-Online–Real-Money-01-16
References:
Royal vegas mobile casino
References:
http://community.srhtech.net/user/brassdead4
best muscle gaining supplements 2015
References:
https://king-lerche-2.thoughtlanes.net/dianabol-pills-for-sale-dianabol-20-for-bodybuilders-around-usa
top rated muscle building stacks
References:
https://lovebookmark.win/story.php?title=clembuterol-landergold
anavar stack
References:
https://clashofcryptos.trade/wiki/TrenMax_Legal_Safe_Steroid_Alternative
%random_anchor_text%
References:
https://wilkerson-mcknight-6.technetbloggers.de/abnehmen-ozempic-and-co-kaufen-preisverfall-der-abnehmspritze-eingelautet
statistics on anabolic steroids
References:
https://gpsites.win/story.php?title=best-omega3-for-testosterone-2026-male-vitality
References:
Anavar before and after reddit male
References:
https://p.mobile9.com/gymliver64/
buying illegal steroids online
References:
https://algowiki.win/wiki/Post:Las_10_mejores_pastillas_para_adelgazar_segn_la_OCU_GUIA_2024
References:
Best online betting
References:
https://lovebookmark.date/story.php?title=play-online-slots-and-live-casino-games-at-candy-casino
References:
Mahjong 3d more time
References:
https://gratisafhalen.be/author/limitberet4/
%random_anchor_text%
References:
https://king-bookmark.stream/story.php?title=clenbuterol-acheter-au-meilleur-prix-en-france
side effects of prolonged steroid use
References:
https://mozillabd.science/wiki/Clenbuterol_Fettkiller_oder_gefhrliches_Dopingmittel
fat burning muscle building pills
References:
https://gpsites.stream/story.php?title=clenbuterol-avis-dun-coach-sportif-devez-vous-en-prendre-
anabolic steroids vs hgh
References:
https://bookmark4you.win/story.php?title=appetitzuegler-lexikon-der-neurowissenschaft
References:
Casino california
References:
https://hartvigsen-khan.federatedjournals.com/online-casino-play-and-win-anytime-1769451234
References:
Detroit tigers mlb com
References:
https://trade-britanica.trade/wiki/Candy_Casino_Review_350_Up_To_500_Welcome_Bonus
References:
Hollywood park casino
References:
http://muhaylovakoliba.1gb.ua/user/banglechain69/
References:
Grey eagle casino
References:
https://sargent-mcdonough-3.hubstack.net/play-and-win-at-australias-best-online-casino
female bodybuilders before and after steroids
References:
https://sciencewiki.science/wiki/Testosteron_bei_Frauen_mehr_als_nur_ein_Mnnerhormon
hgh steroid cycle
References:
https://gratisafhalen.be/author/bottomson64/
women before and after steroids
References:
https://bbs.pku.edu.cn/v2/jump-to.php?url=https://tendopoli.it/language/pgs/farmaco_per_dimagrire_1.html
purchase steriods
References:
https://bookmarkzones.trade/story.php?title=integratori-tribulus-terrestris
I haven’t checked in here for some time since I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I’ll add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂
References:
Eurobet casino
References:
https://notes.bmcs.one/s/9uNyMqhhC
References:
Best online translator
References:
https://graves-bengtsen.hubstack.net/wo-echtes-geldspiel-auf-online-komfort-trifft
References:
Quinault casino
References:
https://timeoftheworld.date/wiki/Diese_Online_Casinos_zahlen_am_schnellsten_aus_Test_2026
References:
Best online games
References:
https://linkagogo.trade/story.php?title=500-casino-bonus-casinos-mit-500-bonus-mit-einzahlung-2026
References:
Mazatzal casino
References:
https://www.google.bs/url?q=https://online-spielhallen.de/888-casino-aktionscode-ihr-schlussel-zu-exklusiven-vorteilen/
References:
Silver nugget casino
References:
http://stroyrem-master.ru/user/lierred68/
References:
River spirit casino tulsa
References:
https://kamp-rossi-2.federatedjournals.com/payid-and-fast-payouts-au
References:
Lucky nugget mobile casino
References:
https://pad.stuve.de/s/3IzK_bL9c
References:
Top online casinos
References:
https://a-taxi.com.ua/user/fogknight37/
buy trenbolone pills
References:
https://cochrane-meyers.hubstack.net/is-hgh-legal-in-the-usa-state-by-state-guide-2025
new gnc muscle builder
References:
https://gaiaathome.eu/gaiaathome/show_user.php?userid=1838871
the dangers of steroids
References:
https://scientific-programs.science/wiki/55566190101
References:
Santa fe casino las vegas
References:
https://timeoftheworld.date/wiki/Best_Casino_Bonuses_Promo_Codes_Australia
anabolic steroid cycles for sale
References:
http://ezproxy.cityu.edu.hk/login?url=https://gamo-smeo.com/portadas/?hgh_kopen_1.html
which of the following statements about anabolic steroids is false?
References:
https://swaay.com/u/almodabhoza54/about/
anabolic muscle supplements
References:
https://skitterphoto.com/photographers/2219518/mathis-thygesen
when was steroids invented
References:
https://gaiaathome.eu/gaiaathome/show_user.php?userid=1839730
natural steroids for sale
References:
https://sciencewiki.science/wiki/How_to_Choose_the_Best_TRT_Clinic_San_Diego_for_Optimal_Hormone_Health_in_2026
where to buy steroids reddit
References:
https://prpack.ru/user/areasteven8/
winners don’t use drugs except steroids
References:
http://humanlove.stream//index.php?title=blantonpollard5292
pills to get muscle fast
References:
https://molchanovonews.ru/user/lionadult0/
anabolic steroid drugs
References:
https://wifidb.science/wiki/Ampla_variedade_de_produtos
how much do steroids cost
References:
https://molchanovonews.ru/user/brandysushi7/
taking steroids without working out
References:
https://menwiki.men/wiki/Meilleur_brleur_de_graisse_en_2025_lequel_choisir_Comparatif_Avis
symptoms of steroid use in males
References:
http://pattern-wiki.win/index.php?title=perkinscopeland7107
muscle cutting supplements
References:
https://elclasificadomx.com/author/pastesinger76/
how long do anabolic steroids stay in your system
References:
https://damm-upchurch-4.federatedjournals.com/bruleur-de-graisse-brule-graisse-achat-en-ligne-pas-cher-1770362280
did frank zane take steroids
References:
https://ai-db.science/wiki/Wo_bekommt_man_Anavar_247_is
best muscle building steroid
References:
https://swaay.com/u/sandirofirx54/about/
prohormones gnc
References:
https://graph.org/Oxandrolon-Anavar-Leitfaden-Vorteile-Dosierung-und-warum-ich-empfehle-es-zu-kaufen-02-06-2
bulk cycle stack
References:
https://scientific-programs.science/wiki/Anavar_The_Good_The_Bad_and_The_Ugly
testosterone bodybuilding before and after
References:
http://mick-el.de/page8.php?messagePage=12401
casino circus
References:
https://www.jasminsideenreich.de/Blog/index.php/;focus=STRATP_com_cm4all_wdn_Flatpress_7099662&path=?x=entry:entry210626-215104%3Bcomments:1
casino listings
References:
http://uchkombinat.com.ua/user/beechroad3/
blackjack strategies
References:
https://www.instapaper.com/p/17488559
classic slots
References:
https://bookmarks4.men/story.php?title=top-spielautomaten-und-hohe-boni-fuer-deutsche-spieler
anabolic steroids bodybuilding
References:
https://dating-scam.de/index.php?action=profile;u=7103
mahjong 3d more time
References:
https://p.mobile9.com/suithome96/
casino on net
References:
https://zenwriting.net/titleprison8/mr-o-casino
casino zollverein
References:
https://lospromotores.net/author/hosegram3/
onlinegames
References:
https://weber-benton-2.federatedjournals.com/february-2026-exclusive-deals
french lick casino
References:
https://a-taxi.com.ua/user/magiccandle7/
toronto casino
References:
https://caldwell-mccullough.mdwrite.net/real-money-slots-and-bonuses
no deposit bonus binary options
References:
https://sonnik.nalench.com/user/bearpin7/
roulette number
References:
https://vacuum24.ru/user/profile/538566
no deposit bonuses
References:
https://bookmarkfeeds.stream/story.php?title=e-wallet-casinos-australia-real-money-sites-2026
slotland no deposit bonus codes
References:
https://www.instructables.com/member/jumperoutput06/
slots
References:
https://instapages.stream/story.php?title=mechanical-horse-racing-game-casino
cinema casino antibes
References:
https://animallovergifts.com/animallover/