2025年7月に発表されたHCSS(ハーグ戦略研究センター)の政策ブリーフ「FIMI in Focus」は、地政学的に異なる2つの地域——インド太平洋とヨーロッパ——における外国による情報操作と干渉(FIMI)の実態を比較し、その構造的な共通点と文脈的な違いを整理している点で注目に値する。これは、FIMIのグローバル化を捉えつつ、地域ごとに異なるナラティブと手段を戦略的に使い分ける加害者側の柔軟性を浮き彫りにするレポートでもある。
「ワインとロブスターが犠牲に」──中国のFIMIは“硬軟複合”型
まず目を引くのが、中国による「情報操作+経済的威圧」の連携的な手法だ。
たとえばオーストラリアでは、同国がHuaweiの5G参入を拒否し、COVID-19起源の独立調査を提案した直後に、中国は石炭、ワイン、大麦、ロブスターといった主要輸出品目に高関税を課す制裁を実施した。その背後には、単なる経済報復を超えた世論操作の意図があった。豪州の大学やメディア、研究機関への資金依存を通じて「対中批判を避ける空気」を醸成しようとする動きは、FIMIのソフト面とハード面が結びついた典型例である。
さらに台湾では、選挙前にSNSやメディアを通じて民主制度への不信を煽る情報操作が確認されている。そのターゲットは候補者、政党、世論と幅広く、特に「台湾の政府は信用できない」「中国との関係改善が安定につながる」といったナラティブが繰り返し流布された。
このように、中国のFIMIは外交的孤立化・経済的圧力・世論操作をパッケージとして展開する“複合型”である。対象国の構造的な依存関係(研究費・貿易・移民)を巧妙に利用しながら、特にディアスポラや文化機関(例:孔子学院、WeChat)を介してナラティブの浸透を図る点が特徴的だ。
安くて効果的──ロシアの“低コストFIMIモデル”
一方、ロシアのFIMI戦略は、中国とは異なり、比較的低コストで実行可能な「拡散型・混乱型」モデルである。
インドネシアでは、2022年の段階でロシア擁護・ウクライナ批判のナラティブがSNS上で目立つようになった。この背景には、RTやSputnikといった国営メディアの現地語放送や、親ロシア系のインフルエンサーの拡散、さらには現地通信社(マレーシアのBernama)との提携も含まれる。中でも注目すべきは、国家的な投資や軍事プレゼンスがほとんどない地域において、メディアとナラティブ操作だけで影響力を行使している点だ。
ヨーロッパではより攻撃的かつ体系的であり、“Doppelganger”作戦はその代表例。これは、既存の信頼あるニュースサイト(Le Monde、Der Spiegelなど)にそっくりな偽サイトを作成し、そこに親ロシア的・反ウクライナ的な情報を流し込むというもの。SNSで拡散されることで、一部の読者はそれが本物の記事だと信じ込む。
さらに、2024年のモルドバ選挙では、SNSを使った世論誘導と共に、秘密資金による工作資金流入も確認されており、FIMIが選挙干渉と組み合わされている。2025年のポーランド大統領選では、極右系グループとの連携も疑われている。ロシアは情報戦を、既存の社会的分断や過激思想と融合させる形で展開している。
共通項は「プラットフォーム依存のエコシステム破壊」
レポートが強調するのは、中国とロシアのFIMIが戦略目標や手法において異なる一方で、共通して依拠する構造的な弱点が存在するという点だ。
- ソーシャルメディアとエンドツーエンド暗号化チャットアプリの普及により、「検証なき拡散」が容易に
- 民主主義社会の特徴でもある「言論の自由」が、偽情報の温床になる
- 少数派・ディアスポラ・学術機関といった“境界的空間”が操作の入口として狙われる
その結果、表面的には文化・言語・制度が異なるインド太平洋とヨーロッパであっても、FIMIが突いてくる脆弱性は驚くほど似通っている。それは「信頼の欠如」「制度疲労」「情報のフラグメント化」である。
抽象論ではなく、構造の可視化を
FIMIという言葉はまだ広く一般化されていないが、レポートはその概念の不統一こそがFIMI対策の最大の妨げだと指摘している。地域間で異なる用語・法制度・脅威認識が存在する限り、加害者側は「グレーゾーン」を利用して活動を続けることができる。
HCSSはその打開策として、以下の三点を提案している:
- 用語と脅威定義の標準化
- 手法ベースでの共通対策の構築
- 社会全体によるレジリエンス強化
このうち特に重要なのが「手法ベースの対策」であり、FIMIの加害者が中国であれロシアであれ、操作手段が同じであれば防御策も共有可能であるという発想は、実務的な含意が大きい。
おわりに
「FIMI in Focus」は、FIMIの“地政学”を理解するうえで、かなり整理された一冊だ。国単位の比較ではなく、“どのような手法が、どのような脆弱性に作用するのか”という構造論に踏み込んでおり、事例も十分に含まれている。
今後FIMIを扱う分析においては、ナラティブの内容よりもインフラ(資金源、流通経路、共犯者)を可視化する視点が不可欠になるだろう。その意味で、本ブリーフは現在地の確認としても、将来の調査設計の参考としても有効な文書である。

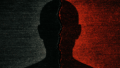

コメント
Um ein klares Bild zu vermitteln, berücksichtigt diese Analyse alle Faktoren, einschließlich Bonusangebot und Sicherheit.
Dank seines guten Rufs in stationären Casinos
und eines Jahresumsatzes von über 20 Millionen Euro bietet das Casino hochwertige Löwen Play-Spiele und komfortable Zahlungsbedingungen. Besonders Krypto-Auszahlungen sind oft innerhalb weniger Minuten auf dem Konto.
Starte noch heute – und spiele mit dem Stolz und der Stärke eines Löwen.
Die Mindesteinzahlung von 10 € bis 29,99 € bringt 25 Freispiele.
Nein, aufgrund der deutschen Lizenzbestimmungen bietet das Löwen Play Casino derzeit keine Live Casino Spiele an.
Zusätzlich gibt es – abhängig von der Höhe Ihrer Einzahlung – bis zu 150 Freispiele für
das Spiel Book of Ra Deluxe. Diese werden Sie übrigens in keinem
offiziellen deutschen Online Casino finden, da die inländische Lizenz das
Anbieten von Live Dealer Spielen nicht erlaubt.
Es gibt 200 Freispiele ohne Einzahlung für das Spiel Big
Bass Splash! Die Freispiele müssen wie immer 75x umgesetzt werden und morgen gibt es einen neuen Bonus.
Lass also auch diese LöwenPlay Freispiele ohne Einzahlung
nicht verfallen und klick auf das Ei um
den Bonus mitzunehmen! An diesem schönen Dienstag bekommst du auf deine Einzahlung von bis zu 100€ von Löwen Play einen Einzahlungsbonus von 66%.
Zu beachten ist auch, dass der maximale Gewinn pro Geschenk maximal 100€
betragen kann, was natürlich trotzdem bedeutet, dass du täglich bis zu 100€ gewinnen kannst.
References:
https://online-spielhallen.de/alles-zur-sg-casino-auszahlung-schnell-sicher-und-unkompliziert/
Swimming pool day passes and cabanas are available for non-hotel guests.
Tier Credits are accumulated when playing on gaming machines and table
games, with your Vantage Rewards card registered. But the only
area of gaming and gambling where we appear to be lacking is in the area of legislation and oversight.
Enhanced by high-definition graphics and responsive interfaces,
the software integration not only elevates gameplay but also fortifies the casino’s commitment
to technological excellence and customer satisfaction. Utilizing software from industry-leading providers, the casino ensures each game runs smoothly across various platforms.
These regulatory bodies are stringent in their requirements, involving
regular audits and checks that guarantee fairness and transparency in all casino operations.
The ville Casino Townsville operates with utmost adherence
to legal and regulatory frameworks, ensuring all gaming activities are conducted in a secure and ethical
manner. This approach ensures that all players can manage their
funds efficiently and securely, according to their individual preferences.
Unlock the benefits of discounted dining and accommodation today.
Join the crew and be first to know about exclusive discounts, new spots, and all things delicious.
If you do not hear back within 24 hours we suggest that you
phone the restaurant as opening times and days may change.
Showcasing the freshest tropical produce, guests can feast
on all you can eat buffet, live cooking stations and made-to-order dishes.
For those who want a residence, not just a hotel room,
the spacious Corner Suites make for a luxurious retreat.
References:
https://blackcoin.co/black-jack-strategy-poker/
Citizens in Australia, therefore, bear no responsibility for gambling online as it
is down to an operator who allows players from Australia to block players and stop them from
gambling on their site. We review the most trusted sites
that offer no deposit bonus codes, free spins, highest
payout percentages, and reliable on-time payouts. Whether you’re a seasoned gambler or new to the online casino scene, these resources and top-rated casino sites are sure to provide
endless entertainment and opportunities to win big.
You are free to pick any of the online casino sites that
we have picked here, or any other that we have reviewed for Australia.
Even with the restrictions of the Interactive Gambling
Act, Aussie players can still join and play at offshore licensed online casinos.
Trusted Australian online casinos are safe, provided
you play at licensed and regulated sites. This is the go-to real money online casino for players who have better
things to do than sit around waiting to win. Many AU online casinos also feature specialty games
for variety. Real money pokies, also known as slot machines, are the most popular choice at Australian online casinos.
Find out more about the best online casinos Australia players recommend
before you make that call.
Unfortunately, Curacao casinos have sometimes been caught taking part in questionable gambling
practices. There are a few gambling authorities in the world that provide licensing to casinos targeting
Australians. Instead, they will need to play at casinos that
are licensed abroad under more universal authority.
References:
https://blackcoin.co/jeetcity-casino-a-comprehensive-review/
paypal neteller
References:
https://dmnsj.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=651612
online casino paypal
References:
http://dwsm.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=273417
online slots paypal
References:
https://jobspaceindia.com/companies/200-trusted-sites-reviewed-pokies-guide/
online real casino paypal
References:
https://pridestaffing.us/companies/online-casino-mit-paypal-einzahlung-die-top-casinos-im-vergleich/
us online casinos that accept paypal
References:
https://fanajobs.com/profile/faustogef55141
online american casinos that accept paypal
References:
https://www.zimskillsglobal.co.zw/employer/40-best-australian-online-casinos-for-real-money-in-december-2025/
References:
Diamond joe casino
References:
https://pikidi.com/seller/profile/airvise23
References:
Anavar steroids before and after
References:
https://doc.adminforge.de/s/YcaikF6O6Z
References:
Le petit casino paris
References:
https://reddy-snyder-2.thoughtlanes.net/wd-40-casino-review-and-bonus-codes-2026
References:
Drive casino
References:
https://gpsites.win/story.php?title=wd40-casino
anabolic steroids for muscle growth
References:
https://ukrajina.today/user/tailsecure9/
pre hormone supplements
References:
https://wifidb.science/wiki/Buy_Clenbuterol_Online_Fat_Burner_for_Lean_Muscle
References:
Lady anavar before and after
References:
https://wifidb.science/wiki/Anavar_Oxandrolone_Choisir_Sa_Cure_Sans_Risque
References:
Woman before and after anavar
References:
https://oren-expo.ru/user/profile/804057
References:
Anavar before and after female reddit
References:
http://ezproxy.cityu.edu.hk/login?url=https://www.valley.md/anavar-avant-et-apr%C3%A8s-ch
why are anabolic steroids illegal
References:
https://rentry.co/e8qafv28
References:
Anavar results before and after female pictures
References:
https://espersen-aggerholm-2.blogbright.net/15-steroide-vor-und-nach-bildern
References:
Women anavar before and after
References:
https://dreevoo.com/profile.php?pid=974974
References:
Trt and anavar before and after
References:
https://dlx.hamdard.pk/user/profile/338239
does steroids shrink your penis
References:
https://hateboard58.bravejournal.net/medikamente-preisvergleich-apotheken-produkte-gunstig-kaufen
symptoms of steroids
References:
https://mensvault.men/story.php?title=clenbuterol-le-clenbuterol-detourne-pour-maigrir
what is the purpose of anabolic steroids
References:
https://securityholes.science/wiki/Trenbolone_Anleitung_AZ_von_einem_erfahrenen_Bodybuilder