2022年のロシアによるウクライナ侵攻は、物理的な戦争にとどまらず、情報空間での戦いを激化させた。爆撃や銃撃と並行して行われたのは、虚偽情報・陰謀論・誘導的なナラティブをめぐる「見えない戦争」だ。そしてその最前線に立ったのが、ミームである。
英国ノッティンガム・トレント大学とデンマーク・オーフス大学の研究者によって作成された報告書『The Complex Web in Memetic Warfare』(2025年7月発行)は、ミームという一見「軽い」表現形式が、いかにして戦時下における政治的・文化的抵抗の武器となるのかを、徹底的に分析している。
本稿では、報告書が示した主要な知見──特に「NAFO(North Atlantic Fella Organization)」という草の根運動がいかにして情報攪乱に対抗し、国際的連帯を築き、戦争の語りを再構成したか──を紹介する。
1|「NAFO」とは何か──シバイヌとサブカルが情報戦の武器になるとき
「NAFO」は「NATO」のもじりであり、中心にいるのは軍隊でも国家でもなく、犬(Shiba Inu)をアバターにした匿名ユーザーたちである。2022年5月、ポーランドのXユーザーが、ウクライナへの寄付と引き換えにシバイヌのアイコンを提供したのをきっかけに発足。以来、NAFOはロシアの偽情報をミームで風刺し、寄付と連帯を促す分散型コミュニティとして急速に拡大した。
組織としての指導部は存在せず、参加条件も「ウクライナ支援」という広範な志向に過ぎない。X、Reddit、Telegram、Discordなどを横断しながら、参加者は自発的に投稿、共有、報告、寄付などを行っている。
2|メメティック・ウォーフェアとは何か──笑いと嘲笑の中の戦争
報告書では、ミームを使った情報戦を「メメティック・ウォーフェア(memetic warfare)」と定義する。これは「情報操作の一形態であり、ミームや視覚メッセージを通じて世論・ナラティブ・敵対的勢力への認識に影響を与える戦略的行為」である。
特にNAFOは、「防御的ミーム戦術」を展開することで、以下の機能を果たしている:
- ロシア発の虚偽情報を笑いと嘲笑で解体する
- ウクライナ支持者の間で感情的連帯を築く
- 戦争のリアルをわかりやすく可視化する
- 寄付や発信を促すきっかけを作る
たとえば、「第二の軍事大国」と称されたロシアが無様に敗北する様子を「ウクライナで第二の軍事力」として風刺したり、「You pronounced this nonsense, not me」など、ロシア側の英語の言い回しを逆手に取ったミームが拡散された。
3|デジタル市民の戦争参加──NAFOの構成と行動
報告書では255名のNAFO参加者に対する調査を実施し、さらにNAFOメンバー18名、ウクライナ市民21名へのインタビューを通じて、NAFOの行動と動機を詳細に描き出している。
● 行動の広がり
- ミームの制作・拡散
- ウクライナへの寄付
- 敵対的投稿の報告(通称「bonking」)
- 情報の翻訳・再発信
- 政治家・メディアへの働きかけ
● 使用プラットフォームの分布(複数回答)
- X(旧Twitter):94名
- Reddit:86名
- Facebook:54名
- Discord:50名
- Telegram:40名
● 参加者の動機(自由記述からの分類)
- 「戦争に対して自分ができることをしたい」
- 「民主主義と自決権の防衛」
- 「ロシアの情報操作に対する怒り」
- 「連帯とユーモアで心を保つため」
4|「笑い」が持つ政治的力──ユーモアとナラティブの戦場
NAFOの戦術の中核にあるのはユーモアと風刺である。報告書では、これが単なる娯楽ではなく、むしろ強力な情報武器であることを強調する。
ユーモアは情報攪乱に対する直接的な反論ではなく、「真剣に受け取る価値すらない」と敵の語りを脱価値化する力を持つ。これによって、ロシアのプロパガンダに対し議論で負けることなく、笑いで勝つという新しい対抗手段が出現した。
あるNAFOメンバーはこう述べている:
「議論に引きずり込まれる必要はない。漫画の犬とやり取りし始めた時点で相手は負けている」
5|ミームの倫理──「笑っていいライン」はどこか
しかし、メメティック・ウォーフェアには倫理的な限界もある。報告書は、グラフィック画像(死体・戦争犯罪)を含むミームの是非について、NAFO内部でも意見が割れていることを示している。
- 「現実を見せるべき」「ショックが必要だ」と主張する派
- 「被害者の尊厳を守るべき」「トラウマを避けるべき」とする慎重派
多くの参加者が「レイプや拷問をネタにすることは許容されない」と述べ、NAFO内には**一定の内的規範(コード・オブ・コンダクト)**が存在することも明らかになっている。
6|可視化された効果──ウクライナ社会からの応答
インタビューに応じたウクライナ市民の証言からは、NAFOの活動が単なる「西側の応援団」ではなく、実際の被害地にいる人々にとっても心理的支えとなっていることが分かる:
「攻撃の直後に見たミームが、笑わせてくれた。世界はまだこっちを見てくれていると感じた」(ウクライナ人インタビュー04)
「私の母は72歳で、テレグラムも使えなかった。でも今は危険な投稿を避ける術を学んだ。リテラシー教育はもっと必要だ」(ウクライナ人インタビュー14)
7|国家にできないことを市民が担う──報告書の意義
本報告書の結論は明快だ。ミームは「冗談」ではない。政治的なメッセージの最前線であり、情報攪乱の攻防線であり、市民による文化的防衛線でもある。
報告書は以下のような政策提言を行っている:
- ミーム拡散の経路可視化技術の開発
- 防御的ミーム戦略の理論化と支援
- AI時代に対応したメディア・リテラシー教育の強化
- SNSプラットフォームの規制強化と自動再生オフなどの設計改善
終わりに──「戦う犬たち」とソフトパワーの再構築
ミームは軽薄ではない。それはナラティブを取り戻す武器であり、国家が発信できない声を届ける手段であり、連帯と批判と希望を同時に表現するメディアでもある。
NAFOは、冷笑ではなく倫理的なユーモアを通じて、ウクライナをめぐる国際世論の空間を再設計してきた。もはや戦争は銃弾と爆弾だけで行われるものではない。メッセージと画像と、そして笑いの力が戦況を変えることもある。


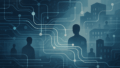
コメント
Hmm is anyone else having problems with the pictures on this blog loading? I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any feed-back would be greatly appreciated.
Life spielen ist ja viel interessanter. Dessen hochgelobte Akustik wissen neben dem hier beheimateten Sinfonieorchester Basel auch das Kammerorchester Basel, die Basel Sinfonietta und zahlreiche internationale
Klangkörper sowie Solisten bei Gastspielen zu schätzen.
Wie im Rest der Schweizerischen Eidgenossenschaft gilt auch im Grand
Casino Basel ein Mindestalter von 18 Jahren für die Teilnahme an Glücksspielen. Bitte spiele
ausschliesslich in sicheren Online-Casinos mit gültiger
Lizenz.
Aus dem ursprünglichen Interesse an traditionellen Glücksspielen und Poker entstand ein Startup, das heute ein erfolgreiches Unternehmen im Glücksspiel-Bereich ist.
Der Zug bietet ebenfalls eine angenehme Alternative – ICEs
rollen direkt von Städten wie Frankfurt oder Mannheim nach Basel
SBB. Über 355 Glücksspielautomaten gibt es im kleinen Spiel, dazu zählen auch Jackpot-Automaten.
Da das Casino direkt neben dem Airport Hotel liegt, hat das
Restaurant Casino Basel den passenden Namen „Hangar 9“ erhalten. Natürlich kannst Du
aber auch mit relativ wenigen Franken bereits spielen. Wer es beim
Roulette im grossen Spielsaal zu stressig findet, kann im Automatenbereich Platz nehmen und
elektronisches Roulette spielen. Baccarat und Punto Banco
konnte ich bei meinem Besuch leider nicht spielen, was angesichts der ansonsten grossen Auswahl aber nicht weiter schlimm
war. „Echtes“ Casino Poker gegen andere Mitspieler
wird leider nicht angeboten. Dadurch ist das Casino in der Lage, über 300 Spielautomaten und eine grosse Auswahl an unterschiedlichen Tischspielen für seine Gäste bereitzustellen.
References:
https://online-spielhallen.de/willkommen-bei-monro-casino-ihr-einfacher-login/
Utterly pent written content, thanks for selective information. “He who establishes his argument by noise and command shows that his reason is weak.” by Michel de Montaigne.
Settle a dinner table debate, or practice a new
language. In July 2024, the American Bar Association (ABA) issued
its first formal ethics opinion on attorneys using generative AI.
On November 29, Rosário revealed that the bill had been entirely written by ChatGPT, and that he had presented it to the rest of the council without making any changes or disclosing the chatbot’s
involvement. In Mata v. Avianca, Inc., a personal injury lawsuit filed in May 2023, the
plaintiff’s attorneys used ChatGPT to generate a legal motion. In November 2025,
OpenAI acknowledged that there have been “instances where our 4o model fell short in recognizing signs of delusion or emotional dependency”, and reported that it is working to improve safety.
A 2025 Sentio University survey of 499 LLM users with self-reported mental
health conditions found that 96.2% use ChatGPT, with 48.7% using it specifically for mental health support or
therapy-related purposes.
Rivaling patient care in some of the finest hospitals, AirMed air ambulances are equipped for virtually every critical care scenario.
AirMed offers unparalleled medical care and bedside-to-bedside transportation on a worldwide basis
and boasts the most experienced air medical crews in the
industry. AirMed International is the leading air ambulance and medical transport company in the United
States, with 25,000 total missions and counting. There are a lot of misperceptions about the cost of air medical transport.
Air Methods has a talented workforce of over
4,500 team members, which includes the best in the air medical industry.
References:
https://blackcoin.co/ripper-casino-login-australia-complete-guide/
These games offer life-changing payouts with jackpots often reaching
millions of dollars. If for some reason you decide to stop playing on the LevelUp casino Australia, we recommend
that you do not rush and close your account, but simply set a cooling-off period.
Thanks to casino Level Up functionality, a player can limit the amount they can spend
per day, week or month. If for some reason you no longer
have access to the email that is tied to your LevelUp account,
you can contact LevelUp’s customer support department to help
you. Any attempt to open multiple accounts is prohibited and such accounts plus the money that has been deposited will be closed immediately.
However, to ensure there are no trickery in the game, Australian LevelUp Casino has a Know Your Customer (KYC) policy.
References:
https://blackcoin.co/black-jack-strategy-poker/
I’ve been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any fascinating article like yours. It is pretty worth sufficient for me. Personally, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before.
online casino paypal
References:
https://cybernetshell.com/employer/best-paypal-online-casinos-real-money-deposits-withdrawals-al-com/
paypal casino online
References:
https://macrorecruitment.com.au/employer/paypal-casinos-best-online-casinos-that-accept-paypal/
I wish to express thanks to you just for rescuing me from this crisis. Right after searching throughout the the web and seeing principles which are not pleasant, I was thinking my entire life was gone. Being alive devoid of the strategies to the difficulties you have sorted out as a result of your main article is a crucial case, and the kind that could have adversely affected my career if I hadn’t discovered your blog post. That ability and kindness in handling a lot of stuff was helpful. I don’t know what I would have done if I hadn’t come upon such a solution like this. I can now look ahead to my future. Thanks for your time very much for this specialized and effective guide. I won’t hesitate to refer your blog to anyone who desires care on this subject matter.
I am no longer certain where you are getting your info, but good topic. I must spend some time finding out more or understanding more. Thanks for great info I used to be searching for this info for my mission.
I am not positive where you are getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning more or figuring out more. Thanks for magnificent info I was searching for this info for my mission.
us online casinos that accept paypal
References:
dev.yayprint.com
online casinos mit paypal
References:
https://externalliancerh.com/employer/best-payid-australian-online-casinos-and-pokies-december-2025
Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish only about gossips and net and this is actually irritating. A good blog with exciting content, that’s what I need. Thank you for keeping this site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.
online casino with paypal
References:
jobstak.jp
online casino paypal einzahlung
References:
http://www.recruit-vet.com
References:
Casino mississippi
References:
https://mozillabd.science
References:
When to take anavar before or after workout
References:
funsilo.date
References:
Female anavar before and after
References:
chessdatabase.science
References:
Used slot machines
References:
09vodostok.ru
References:
Rincon casino
References:
https://web.ggather.com/firbait3/
legal anavar alternative
References:
https://socialbookmarknew.win/
best muscle supplements at gnc
References:
https://scientific-programs.science/wiki/How_to_Get_Trenbolone_Your_Ultimate_Guide_for_Safe_Acquisition
rich piana steroid
References:
mclaughlin-hamrick-6.thoughtlanes.net
Very interesting information!Perfect just what I was looking for!
steroid body vs natural body
References:
https://dokuwiki.stream/wiki/TESTOVIRON_Foglietto_Illustrativo
anabolic medical definition
References:
coolpot.stream
pictures of bodybuilders on steroids
References:
output.jsbin.com
References:
Hi tech anavar before and after
References:
gpsites.stream