2025年6月にアメリカ陸軍戦略研究所(SSI)が発表した報告書『Cognitive Defense: 2024 Homeland Defense Symposium』は、認知領域をめぐる戦い(cognitive warfare)がいかに現実の安全保障課題となっているかを明確に示す文書である。本書は3章構成で、災害対応時における偽情報の流布、ロシアや中国による戦略的な認知戦の手法、そしてそれに対する米国社会の制度的な脆弱性と対応策を多角的に論じている。
この報告書の根底にあるのは、戦争はもはや物理的領域だけで起きるものではないという前提である。情報、認知、信念、そして社会的な一体感そのものが攻撃対象となり、国家の抵抗力──すなわちレジリエンス──を内部から崩していく手法が着実に進化しているという危機意識が、全体を通して貫かれている。
災害対応の裏側で進行する認知操作──イーストパレスチナ事件の事例
第1章では、2023年2月に起きたオハイオ州イーストパレスチナの列車脱線事故を例に、災害時における偽情報の流布とその影響が検証されている。驚くべきことに、このローカルな環境災害に対して、ロシア発と見られる情報操作が展開されていた。たとえば「政府が情報を隠している」「支援が遅れたのはウクライナに金を使っているからだ」といった言説が、SNSを通じて拡散された。
国内でも、極右グループが「白人コミュニティが狙われている」といった陰謀論的な主張を展開し、人種や宗教をベースにした分断を煽っていた。これらの言説は単なる誤報ではなく、明確に悪意をもって社会不信を促進する「害情報(malinformation)」と定義されている。
このような災害対応に対する認知操作は、物理的なインフラ被害にとどまらず、行政への信頼そのものを崩壊させかねない。特にSNSが主要な情報源となっている現在、政府による一元的な情報提供だけでは対応が追いつかず、住民の不安を抑えるには構造的な対策が不可欠となっている。
認知戦の全体像──ロシアと中国の戦略
第2章では、NATOが定義する「認知戦(cognitive warfare)」の概念が導入されている。これは従来の情報戦を超えて、人間の思考そのもの──認知や感情、判断──に対する操作を目的とする包括的な戦略である。特に注目されるのは、ロシアと中国がこの領域で非常に先進的かつ制度的な枠組みを整えてきた点である。
ロシアは「反射的制御(Reflexive Control)」理論に基づき、敵の意思決定プロセスそのものを誘導することを目指しており、これは冷戦期の心理学・ゲーム理論に起源を持つ。一方、中国は「心の支配」を目標に、SNSやAIを用いて特定の認知スタイルを醸成する「認知領域作戦(Cognitive Domain Operations)」を展開している。中国人民解放軍では、認知領域を陸海空サイバー宇宙と並ぶ新たな「戦域」として扱っている。
たとえば新疆ウイグル問題や香港デモに対する国際世論の形成において、膨大な偽アカウントやボットを用いた情報工作が行われており、実際にFacebookやX(旧Twitter)は大量の中国関連アカウントを凍結している。
認知防衛は可能か──制度としての「NPS」の応用提案
第3章では、こうした認知攻撃に対する米国の脆弱性が浮き彫りにされる。現行の法制度では、偽情報の発信者が国内の政治的言論と区別が難しく、憲法上の表現の自由との衝突も避けられない。そこで提案されているのが、すでに存在する国家準備システム(NPS: National Preparedness System)を認知防衛に転用するというアプローチである。
NPSの5つのフェーズ──予防、防護、緩和、対応、復旧──をそれぞれ認知領域に適用すると以下のようになる:
- 予防:フェイクニュースを見抜く教育、特にフィンランドのように初等教育から情報リテラシーを教える。
- 防護:SNS空間を監視する情報センター(Fusion Center型)の設置。
- 緩和:ソーシャルメディアのアルゴリズム規制や透過性向上のための立法。
- 対応:サイバースカウト部隊の設置など、災害時の偽情報即応体制。
- 復旧:現地の住民と接しながら誤情報を打ち消す専門チームの導入。
この提案は単なる理想論ではなく、すでに環境災害やパンデミックで繰り返し偽情報に悩まされてきた米国にとって、きわめて実践的な方向性を示している。
結語──戦わずして壊れる国家
この報告書の最後でSchwartzは、Sun TzuやClausewitzを引用しながら、敵が軍事力を行使するまでもなく、我々が自らの信念・制度・共同体意識を失っていくことこそが最大の敗北だと警告する。
現在の米国では、政府、メディア、隣人、そして民主主義そのものへの信頼が、かつてないほど低下している。実際、民主主義の機能に満足していると答えるアメリカ人は28%にすぎないという調査結果もある(Gallup, 2024)。それこそが認知戦の最大の戦果である。
このような状況下においては、偽情報の検出や報道の健全化だけでは不十分である。国家として、そして社会として、何を信じ、誰を信頼し、何を守るべきかという「認知的な自衛力」そのものが問われている。

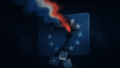
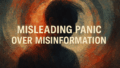
コメント
https://t.me/s/Official_1win_kanal/941
Dieser Betreiber bietet seinen neuen Nutzern ein fantastisches Willkommenspaket, das mit günstigen Bonusbedingungen verbunden ist.
Diese erfordern immer einen Echtgeldeinsatz, da sie in Echtzeit mit echten Dealern stattfinden. Im Zuge unseres Crocoslots Live
Casino Tests waren wir mit den über 520 verfügbaren hochwertigen Titeln sehr zufrieden. Dir stehen unterschiedliche Varianten von Blackjack, Poker, Roulette, Craps,
Baccarat und weitere spezielle Tischspiele zur Auswahl.
Das Unternehmen legt Wert auf Datenschutz
und verantwortungsbewusstes Spielen, was den Spielern eine sichere Umgebung bietet.
CrocoSlots hat eine solche von der Regierung von Curacao erhalten, einer Jurisdiktion, die für ihre hohen Standards in Bezug auf
Fairness und Transparenz anerkannt ist.
Mindesteinzahlung von 20€. 150% bis zu 500€ + 150 Freispiele Glücksspiele sollten unterhaltsam sein und verantwortungsvoll betrieben werden. Der Willkommensbonus war sehr großzügig, und ich habe schon ein paar
anständige Gewinne erzielt. Ich mag auch, wie sie ständig Promotionen und Freispiele haben – hält die Dinge
spannend. Im Bereich der Tischspiele finden die
Spieler virtuelle Angebote wie Roulette, Blackjack,
Baccarat, Sic Bo und mehr.
References:
https://online-spielhallen.de/joo-casino-freispiele-ihr-schlussel-zu-kostenlosem-spielspas/
Here we have made a list of the currency names you would need
to write spellings in order to deposit money against your currency cheques, DD, loan payments or more.
Prime factors of a number are the prime numbers that multiply together to form that number.
Like all numbers, it has a distinctive mathematical structure.
What makes 999,999,999,999,999,999,999 an interesting
number from a mathematical point of view?
Just find the currency and get spelling for it. By using this site you accept our terms and
conditions including our privacy and cookie, copyright and permissions policies.
Every whole number greater than 1 is formed
from at least one prime factor. Below you’ll find its key properties, along with some statistical
info, fun facts and trivia.
It has a total of two hundred fifty-six divisors. It is composed of seven distinct prime
numbers multiplied together.
References:
https://blackcoin.co/bridge-poker-rules/
That’s a serious positive if you enjoy choosing from different
options regularly. If you always have new options to try you don’t have to worry about getting tired of selecting from the same pool of options.
The offers change each week, and you must take advantage of them
before they are gone to avoid missing out. With its impressive game library, and simple layout gamblers have all the tools they need to enjoy their time at the site.
Lucky Green Casino operates under a licensed and regulated framework to ensure
fairness, data protection, and responsible gaming.
Dive into the world of Lucky Green Casino and discover why it’s a top choice for players
in Australia. What sets Lucky Green Casino apart is its commitment to creating a user-friendly environment with
high-quality games from top developers. High-rollers and
VIP players enjoy additional withdrawal benefits, including
priority processing and higher limits.
References:
https://blackcoin.co/play-your-way-only-at-ac8-casino/
casinos online paypal
References:
https://www.milegajob.com/companies/2025s-best-paypal-casinos-expert-verified-sites/
online casino accepts paypal us
References:
innovationsgroup.in
mobile casino paypal
References:
healthjobslounge.com
online roulette paypal
References:
firstcanadajobs.ca
online casino roulette paypal
References:
businessxconnect.com
online blackjack paypal
References:
https://f18limited.com/
Fokussier dich, bring die Bubbles zum Platzen und spiel
dich durch spannende Level. Spielen Sie kostenlos mehr als 100 Slot- & Casino-Games und gewinnen Sie
tolle Preise! Meine Begeisterung für das Glücksspiel entfachte während meines ersten Besuchs in der Spielbank Dortmund-Hohensyburg, und seitdem habe ich
die Welt der Casinos und Wetten intensiv
erkundet. Im Gegensatz dazu wird bei kostenlosen Spielautomaten kein echtes Geld eingesetzt,
sondern virtuelle Credits, die keinen realen Wert haben. Echtgeld Spielautomaten verlangen einen Geldeinsatz,
der riskiert wird, um mögliche Gewinne zu erzielen. Nein, mit gratis Casino Slots Spielautomaten kann man kein echtes
Geld gewinnen.
Alle hier gelisteten Spiele können Sie im Online Casino kostenlos ohne Registrierung spielen. Bei uns können Sie viele dieser Casino Spiele im
Online Casino kostenlos spielen. Zudem ist
es einfach ein glasklarer Vorteil, wenn Du kostenlos spielen kannst
und Dein Geld bei Dir bleibt. Man kann dort also verschiedene Casino-Spiele wie Roulette,
Blackjack, Spielautomaten-Spiele oder Poker spielen und mit echtem Geld oder mit Spielgeld wetten. Leg einfach los & gönn Dir alle Vorteile kostenloser Online-Casinospiele aus der Profiabteilung.
Bevor ich Echtgeld ins Spiel bringe, will ich die Automatenspiele meiner Wahl kennenlernen & ohne Stress spielen. Loggen Sie
sich ein und spielen Sie unsere empfohlenen Spielautomaten für 2025 kostenlos oder entdecken Sie die umfangreiche Spielauswahl in unseren Online Spielotheken.
References:
s3.amazonaws.com
References:
Before and after pictures using anavar
References:
http://pattern-wiki.win/index.php?title=richterbarnes8042
References:
Anavar before and after 4 weeks
References:
fakenews.win
References:
Hollywood casino toledo
References:
gaiaathome.eu
References:
Best roulette strategy
References:
http://decoyrental.com
References:
Aladdin las vegas
References:
https://commuwiki.com/members/thrilldead7/activity/13224
my roid shop reviews
References:
mensvault.men
muscle building pills that work
References:
https://graph.org
weight loss steroid
References:
uvs2.net
anabol vs dianabol
References:
https://pads.jeito.nl/s/6LCNSrWSUO
References:
Anavar male before and after
References:
karayaz.ru
References:
6 week anavar before and after
References:
mmcon.sakura.ne.jp
References:
Anavar male before and after
References:
livebookmark.stream
%random_anchor_text%
References:
marvelvsdc.faith
References:
Test tren anavar before and after
References:
taylor-burgess.federatedjournals.com