2025年6月、Cato InstituteのDavid Inserraは「The Misleading Panic over Misinformation(誤情報に対する誤ったパニック)」と題したポリシーペーパーを発表した。副題には “And Why Government Solutions Won’t Work(なぜ政府の解決策は機能しないか)” とあり、本書は明確に政府主導の誤情報対策に批判的な立場を取る。しかし、その批判は単なる政治的反対ではなく、誤情報という概念自体の不確かさ、影響の測定可能性、そして歴史的・制度的な意味に至るまで、非常に広範で精緻な議論を展開している。
誤情報という言葉が抱える根本的問題
レポートは、まず現在の誤情報 discourse が前提としている用語の曖昧さに焦点を当てる。米国国土安全保障省、EU、OECD、国連など各国・国際機関が定めた「misinformation」「disinformation」「malinformation」の定義を列挙した上で、次の点を指摘する。
- 定義が一貫していない:意図の有無、事実性、被害の有無といった基準が組織ごとに異なる。
- 「misinformation」は主観的判断に依存する場合が多い:特に「誤解を与える」「文脈を欠く」「部分的にしか正しくない」といった理由で広義に分類されると、人間のコミュニケーションの大半が対象となり得る。
これにより、「誤情報」とされる範囲が広がりすぎた結果、言論空間全体が検閲可能な対象に変わってしまっているとする。
誤情報の影響は本当に大きいのか?
次に、Inserraは「誤情報は深刻な社会的被害をもたらしている」という前提に対して実証的に疑問を投げかける。以下のような主張が中心となる。
1. 拡散性は限定的である
SNSの利用データやコンテンツ共有に関する研究から、一般ユーザーのメディア消費に占めるフェイクニュースの割合はわずか0.15%程度であり、しかもそれは特定の層に偏在しているという。
2. 人々は簡単には騙されない
誤情報に接したからといって信じるわけではない。Altayらの研究を引用し、共有が必ずしも信頼を意味しないことや、「他人が騙されやすいと信じる人ほど誤情報を問題視する」という心理メカニズムがあることを指摘する。
3. 行動変容にはつながりにくい
誤情報により信念が変わり、さらに行動にまで至るという因果関係はきわめて証明が困難である。むしろ、信じる人はすでにその誤情報に親和的な態度を持っていた(congenial misinformation)というケースが多い。
こうした分析により、著者は「誤情報によって社会が大きく変わってしまう」という広く共有された危機感に対し、冷静な再検討を促している。
歴史的な構造としての「エリート・パニック」
このレポートの特異性は、社会理論的な再解釈にある。Inserraは、誤情報をめぐる現在の議論を、「新たな言論技術(印刷、放送、インターネット)が登場するたびに、支配的エリート層が大衆の表現力を恐れてきた」という長期的構図に位置づける。
- 古代ローマの元老院による言論統制
- 宗教改革期の異端審問
- 植民地支配下での出版検閲
- 冷戦下のプロパガンダ取締り
これらすべてが「不正確な情報」への恐怖を口実にして、市民の言論を制限してきた。誤情報への国家的対応は、こうした歴史的「エリート・パニック」の現代版に他ならないという。
政策介入への具体的な懸念
実際に政府が誤情報対策を名目として行っている活動についても、Inserraは複数の事例を挙げて批判している。
- 米国科学財団(NSF)による政治的バイアスを含む誤情報研究への資金供与
- COVID-19関連の言論統制(たとえばラボ起源説を「根拠のない陰謀論」と断じた初期対応)
- SNS企業に対する「jawboning」(政府が非公式に削除を要請する行為)
- カリフォルニア州のAIディープフェイク規制とその憲法訴訟
これらの例は、一見正当化可能な誤情報対策が、実際には政治的意見の封じ込めに使われているのではないかという疑問を提起している。
代替としての「自由主義的知の制度(liberal inquiry)」
レポート終盤では、Jonathan Rauchの『Kindly Inquisitors』を引きつつ、「知の創出は、批判的で誰でも参加可能な討論プロセスによってのみ成立する」という制度的視点を提示する。
- 「誰も最終的な真理の担い手ではない」
- 「主張の正しさは、出所や肩書ではなく、誰が検証しても同じ結果になることによって評価されるべき」
この原理に照らせば、政府が誤情報の監視者となること自体が制度的矛盾であるとする。むしろ、SNSにおけるCommunity Notes、Redditの評価システム、Wikipediaの編集履歴といった「分散型チェック」こそが知の民主主義的管理にふさわしい、と主張される。
最後に──この主張の意義と限界
このレポートは、単なる「表現の自由」擁護論にとどまらず、誤情報にまつわる一連の言説を、定義・影響・歴史・制度という複数の次元から再評価しようとする意欲的な試みである。
とりわけ、誤情報の「影響」をめぐる定量的研究の解釈と、公共政策との接続方法については、専門的な読者にとっても参考になる点が多い。言論の自由をめぐる制度的議論に、自由主義的知の制度という視角を持ち込んでいる点も評価に値する。
もっとも、本レポートがほとんどすべての政府介入に対して懐疑的である点は、例えば公共保健や選挙制度の安定といった領域における「知的ガバナンス」への課題を過小評価しているとも言える。そこには「制度不信」のリバタリアン的前提が強く影を落としている。
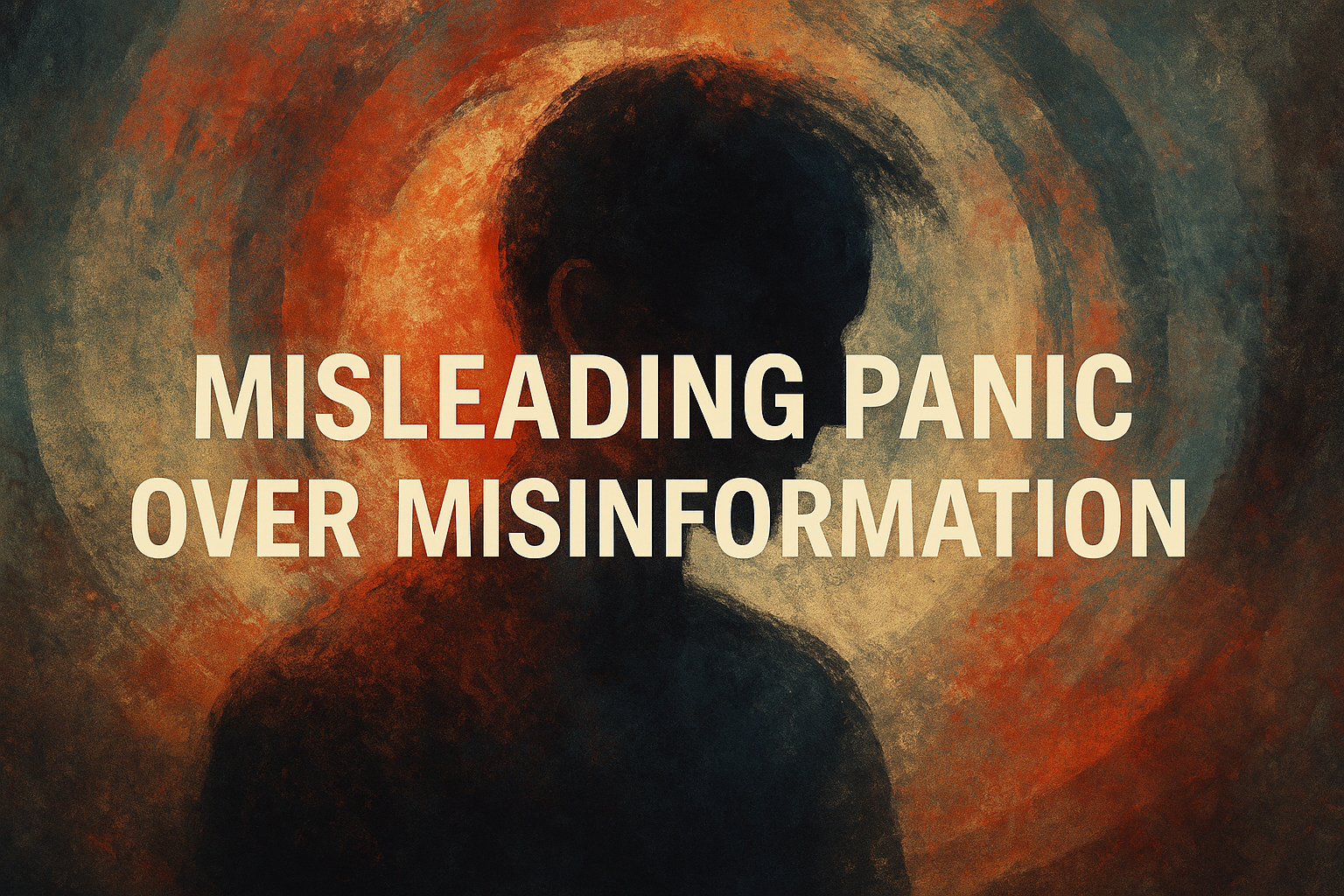


コメント
Ein historisches Erlebnis, das Familien und Kulturinteressierte gleichermaßen fesselt und zu den Highlights der Ausflugsziele zählt.
Eine Attraktion, die in der Region Heerlen für Begeisterung sorgt und unvergessliche Momente unter freiem Himmel
verspricht. Hier erleben Besucher nicht nur einen einzigartigen geographischen Punkt in Europa, sondern genießen auch die hügelige Umgebung und
die seltene Möglichkeit, innerhalb weniger Minuten drei Länder zu beschreiten. Bekannt
als der Dreiländerpunkt, wo sich die Grenzen von Deutschland, Belgien und den Niederlanden treffen, ist dieser Ort ein Fest für
Radfahrer und Wanderer. Es ist diese Vielfalt, die zahlreiche Besucher
Jahr für Jahr zurückkehren lässt, um neue Erinnerungen in diesem limburgischen Juwel
zu schaffen.
Die Herren sollten zum Klassischen Spiel mindestens ein Hemd und Sakko tragen, während
sich die Damen bei ihrer Kleiderwahl für nicht zu freizügige Garderobe entscheiden sollten. Wie es sich für eine
noble Spielbank gehört, gelten bei der Kleiderordnung etwas strengere
Richtlinien (Dresscode Ratgeber – Was in der Spielbank tragen?).
An den eleganten Bars werden derweil edle Weine, Champagner,
Whisky oder auch Softdrinks ausgeschenkt. Darüber hinaus werden im Kurhaus verschiedene andere Unterhaltungsformate geboten. Modernes
Entertainment hat das Casino Baden-Baden in Hülle und Fülle zu bieten und wem das trotzdem nicht reicht, der
sollte die Spielbank an speziellen Themenabenden aufsuchen. Eine Besonderheit ist das Gambling im Pavillon, den es seit 2016
gibt und der dank seiner sich öffnenden Glasfronten das Spielen von Roulette und Blackjack nahezu unter freiem Himmel ermöglicht.
References:
https://online-spielhallen.de/meine-umfassenden-jet-casino-erfahrungen-ein-tiefer-einblick/
Lucky Ones Casino is your all-access pass to a massive collection of real-money games across
every major category. With over 14,000 games, verified payout structures, and intelligent bonus scheduling, you’re never gambling blind.
We encourage players to set personal limits
on their gaming activities, take regular breaks, and seek help if gambling starts to
impact their well-being. The platform encourages responsible gaming by providing tools and resources for players
to manage their gambling activities and seek help if needed.
For poker enthusiasts, the dedicated poker room proudly boasts two standalone poker
tables, where amateurs and pros alike can test their skills and
apply their strategy amongst like-minded individuals.
The atmosphere, gaming options, and hospitality will leave lasting impressions.
If you’re planning a trip to Chile, be sure to include this casino on your must-visit list.
References:
https://blackcoin.co/oshi-casino/
At RocketPlay, we pride ourselves on offering a premium online casino
experience tailored specifically for Aussie players.
With our extensive selection of casino games, exclusive bonuses, and secure
payment options, RocketPlay has established itself
as one of the top Australian online casinos in 2025.
Welcome to RocketPlay, where Aussie players can enjoy
the ultimate online casino experience. With an extensive library of over 3,000 games,
including slots, table games, and live dealer options, players
are sure to find something that suits their preferences.
What languages does the platform support? Players at Rocket Play casino can easily
link multiple wallets, creating a tailored and seamless transaction process.
Every 30 AUD wagered on slots earns you 1 CP, and as you accumulate CPs, you advance to higher levels and
unlock even more rewards. Categories include Popular, New, Recommended, and High Volatility slots, plus cryptoslots for those who prefer
to use cryptocurrency. Explore an array of slots, from timeless classics to innovative video slots with unique themes and features.
Enjoy real-time roulette with dealers or place wagers on sports for an added adrenaline rush.
online casino roulette paypal
References:
http://urikukaksa.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=302179
us poker sites that accept paypal
References:
https://jobs.cntertech.com/employer/us-online-casinos-that-accept-paypal-2025/
online casino paypal einzahlung
References:
https://saudiuniversityjobs.com/employer/best-online-sports-betting-sites-in-the-us-2025/
online slots uk paypal
References:
https://candidates.giftabled.org/employer/best-online-casinos-in-australia-top-casino-sites-for-2025/
References:
Anavar before and after female pictures
References:
https://pad.karuka.tech/s/NdeC6uADt
References:
Women’s anavar before and after
References:
https://fakenews.win/wiki/Anavar_Results_Complete_Timeline_Week_by_Week_How_Long_To_See_A_Change
References:
Planet7 casino
References:
http://mozillabd.science/index.php?title=bowlfarm4
References:
Lotus casino las vegas
References:
https://opensourcebridge.science/wiki/WD40_Casino
References:
Do you take anavar before or after workout
References:
https://skovbjerg-ploug.federatedjournals.com/8-steroids-before-and-after-picture-and-results-bodybuilding-blog
sunestron for sale
References:
https://hikvisiondb.webcam/wiki/Darf_der_Arbeitgeber_einen_Drogentest_am_Arbeitsplatz_verlangen_engineering
why you should take steroids
References:
https://postheaven.net/violaskate2/vitaminas-para-aumentar-la-testosterona-en-los-hombres-que-se-necesitan
steroid source reviews
References:
https://ai-db.science/wiki/Acheter_Hgh_livraison_rapide_en_ligne
References:
Anavar before and after 1 month women
References:
https://www.udrpsearch.com/user/pastawinter7
anabolic steroids medical uses
References:
https://lovebookmark.win/story.php?title=testosterone-difficile-trovarlo-nelle-farmacie-italiane