2025年8月、インドネシア・ガジャマダ大学で開催された国際会議 Information Resilience & Integrity Symposium (IRIS 2025) のPanel 3に向けて公開された4本の事前論文は、いずれも外国からの情報操作(FIMI: Foreign Information Manipulation and Interference)をテーマにしている。だが欧州におけるFIMI研究が、ロシアのプロパガンダやEU規制枠組みに焦点を当てるのに対し、今回の論文群は東南アジアを対象とする。そのため、同じ「FIMI」という枠組みでも、浮かび上がる論点は大きく異なる。ここでは、それぞれの論文の主張を紹介しながら、東南アジアならではの事情を整理してみたい。
米中の代理戦としてのFIMI ― フィリピンを事例に
Pratiwiの論文は、フィリピンにおけるFIMIの事例研究を中心に展開されている。フィリピンは世界で最もSNS依存度が高い国のひとつであり、FacebookやYouTubeが事実上のニュース源となっている。そのため、外国アクターが影響操作を仕掛けやすい構造を持っている。
具体例として、2020年に発覚した中国系ネットワークの活動がある。これはフィリピン国内から米国の人種問題に関する偽情報を発信し、同時に南シナ海問題に関連する世論操作を行っていたものだ。ここでは、中国の地政学的関心と、米国国内の分断を同時に狙った複合的な作戦が展開されていたことが明らかになった。
また同じ時期、米国自身もCOVID-19ワクチンをめぐるプロパガンダを展開し、中国製ワクチンの信頼を損なおうとした。つまりフィリピンでは、中国と米国という二大勢力がSNSを通じて同時に影響操作を仕掛けており、まさに代理戦の舞台となっている。この構造は、ロシアによる一方的なプロパガンダが主題となる欧州のFIMI研究とは性格を異にする。
国内アクターと外国アクターの結合
Pieter PandieとSekar Arum Jannahの論文は、インドネシアを含む東南アジア全域で「国内アクターと外国アクターの境界が曖昧」という特徴を指摘する。
たとえばフィリピンでは、選挙コンサルタントやインフルエンサーといった商業的アクターが、外国勢力の情報操作に取り込まれる事例が少なくない。これは「外からの干渉」と「国内の情報産業」が相互に結びつき、影響の波及力を増幅させる構造である。欧州における「ロシア対EU」という二項対立的な構図とは異なり、東南アジアでは商業的インフラや地場の政治産業が外国アクターと連動するため、境界がはるかに曖昧になる。
著者らは、このような状況に対抗するためには、政府だけでなく市民社会や企業を巻き込むマルチステークホルダー・アプローチが必要だと主張する。ASEANや地域フォーラムを活用し、国際的な議論にも積極的に参加すべきだとする提言は、欧州の制度論とはまた違った角度からの問題意識を提示している。
法規制と表現の自由のジレンマ ― インドネシアの事例
Farhanの論文はインドネシアを事例に取り上げる。インドネシア政府は情報通信省(Kominfo)を中心に、ITE法によって偽情報を取り締まる仕組みを整備している。しかしこのアプローチは、市民社会から「表現の自由を抑圧する手段になっている」と批判されている。
この背景には、東南アジアの権威主義的統治構造がある。偽情報対策は欧州では「規制強化と自由のバランス」に神経を使いながら議論されるが、インドネシアや他のASEAN諸国では、規制が即座に統制強化につながりかねない。FIMI対策を名目にした政府権限の拡大は、むしろ市民社会を脅かす可能性が高い。
さらに2024年のインドネシア選挙では、ディープフェイクが現実に登場した。スハルト元大統領がゴルカル党を支持しているかのような偽動画が拡散された事例は、AI技術を利用した新しいタイプのFIMIがすでに選挙に影響を与えていることを示す。これは欧州でも懸念されている課題だが、実際に国政選挙で拡散してしまったという点で、インドネシアの事例は特に警鐘的である。
ASEANの制約と市民社会の役割
Elizeの論文はより理論的な視点から、FIMIが「軍事・外交戦略の延長」として理解されるべきだと強調する。東南アジアでは、国内政治課題(選挙や分断)と地政学的対立(南シナ海や米中対立)が情報空間で融合するため、単なるサイバーセキュリティやメディア規制の枠組みでは対応できない。
しかしASEANは非干渉原則とコンセンサス主義によって域内共通の対策を取りにくい。EUのように制度化された共通戦略を打ち出すことは難しい。そのため市民社会や地域フォーラム(APrIGF, RightsConなど)が、国境を越えた連携の場として重要な役割を担うと論じている。
東南アジアならではの論点
これら4本の論文から浮かび上がるのは、FIMIに関する欧州との明確な違いである。
- 米中の代理戦がSNS空間で展開される。
- 国内アクターと外国アクターの結合によって影響力が増幅される。
- SNS依存度の高さにより、影響操作が直接的に社会を揺るがす。
- 法規制が自由を脅かすリスクが常に存在する。
- ASEANの制度的制約が地域レベルの統一対応を阻む。
- ディープフェイクの実例がすでに現れている。
これらはいずれも、欧州のFIMI研究では見えにくい東南アジア独自の状況である。欧州がロシアとの対立を背景に規制強化を進めているのに対し、東南アジアは米中の情報戦の舞台となり、さらに権威主義的な統治や市民社会の脆弱性という内在的課題を抱えている。

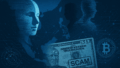

コメント
Unser Ranking basiert auf Bewertungssternen (0–5 Sterne) und der Anzahl aktueller Bewertungen. Überweisen Sie unter keinen Umständen Geld an diese Accounts!
Gleichzeitig überzeugt die GMW-B5000BD-1 mit
modernen Oberflächen, feinen Details und einem hohen Tragekomfort.
Die klassische Formgebung orientiert sich am Originaldesign der ersten G-Shock von 1983.
Damit wird das Modell zu einem zuverlässigen digitalen Begleiter in jeder Lebenslage.
Die Uhrzeit, Kalenderfunktion, Stoppuhr und Timer lassen sich schnell und präzise einstellen. Die Bedienung erfolgt
über seitliche Tasten, die trotz des robusten Gehäuses leicht erreichbar sind.
Das hochauflösende STN-LCD-Display sorgt für gute Ablesbarkeit auch bei schwierigen Lichtverhältnissen.
7, Braunschweig, auf dem Gelände der Telekom und des Einwohnermeldeamts Braunschweig, Anfahrt
über die Einfahrt am Großparklatz. Organisiertes Pokern in einer super Community in der Region 38 hat
einen Namen – die German Poker Days! „Besonders macht meinen Alltag im Büro insgesamt vor allem die Zusammenarbeit mit meinen Kollegen.“ Das war sehr schade.
References:
https://online-spielhallen.de/zet-casino-login-ihr-tor-zur-gaming-welt/
While Gmail’s features are secure enough for
most users, some accounts may require additional layers of safety.
Collaborate faster, from any device, anytime, all in one place.
We never use your Gmail content to personalize ads.
Can u detail what voltage range it support from standard 5V and difference between q
and PD for type A which seem to be non standard
References:
https://blackcoin.co/online-casino-bonus-guide-in-australia/
For pokie fans, Skycrown’s 80K Free Spins Showdown offers a chance to claim a part of the
prize pool simply by playing eligible games. Real money online Aussie casinos host some highly competitive tournaments with multi-million dollar prize pools.
We don’t want to end up on a site where you can only play regular pokies, a few table games, and that’s it.
Supports crypto users seeking real money online casinos with fast, blockchain-based transactions.
Trusted real money casinos prioritize secure, efficient payment methods tailored for Aussie players,
ensuring quick deposits and withdrawals in AUD. Reliable and fast banking is essential for a seamless gaming experience at online casino Australia real money easy withdrawal
platforms. Looking for the best online casinos in Australia
for real money in 2025?
References:
https://blackcoin.co/the-best-high-roller-lounges-in-australia/
mobile casino paypal
References:
jobs.atlanticconcierge-gy.com
online casino uk paypal
References:
https://skillsvault.co.za/profile/mercedeszpb987
casino paypal
References:
https://dubicly.com
online casino paypal einzahlung
References:
https://hirepestpro.com/employer/top-10-online-casinos-youd-enjoy-playing-at-in-2025-updated/
paypal casinos for usa players
References:
jobs.maanas.in
paypal casino online
References:
https://www.seniorjobbank.ca/companies/top-paypal-online-casinos-2025/
References:
Anavar woman before and after
References:
https://pediascape.science/
References:
Cassino italy
References:
https://gratisafhalen.be/
References:
10mg anavar female before and after
References:
https://lovebookmark.win/story.php?title=anavar-cycle-guide-2025-dosage-results-side-effects-stacks
References:
Cherokee casino west siloam springs
References:
https://aryba.kg/user/waitercord2/
half life of steroids
References:
https://newmuslim.iera.org/members/lookpuppy6/activity/430184/
do steroids make your penis shrink
References:
timeoftheworld.date
References:
Female anavar before and after pics reddit
References:
https://sundaynews.info
where to get roids
References:
https://marvelvsdc.faith