ニュージーランド安全保障情報局(NZSIS)が2025年8月に公表した 「New Zealand’s Security Threat Environment 2025」 は、国家を脅かす主要リスクを総合的に示した報告書だ。扱うテーマは暴力的過激主義、外国干渉、スパイ活動、インサイダー脅威など幅広く、偽情報を単独の章として立ててはいない。だが、実際の記述を追うと、情報操作や偽情報がどのように安全保障上のリスクに転化しているかが随所に具体例とともに現れてくる。
SNSと急進化 ― 若者が「燃料」を得る過程
NZSISは、最も現実的なテロのシナリオを「オンラインで過激化した単独犯による身近な武器を使った攻撃」と定義している。ここで重要なのは、過激化の入口はほとんどネット上だという点だ。
例えば、ある調査事例では、若い人物がイスラム国(IS)のプロパガンダを継続的に視聴し、その宗教的正当性を強調する言説に引き込まれていった。この人物はさらに宗教的助言を求め、結果的にISの暴力的イデオロギーを支持するに至った。ここで使われた「証拠」は、いわば 偽情報として作られた宗教的権威の演出 である。
別の事例では、若者がクライストチャーチのテロ犯やナチスの象徴に強い関心を示し、ネット上で過激なコンテンツを共有していた。NZSISと警察が調査した結果、暴力に及ぶ意図は薄く、生活上の保護要因も確認されたため脅威とは認定されなかったが、偽情報や極端な言説が「アイデンティティの一部」として消費されている様子が浮き彫りになった。
こうした事例が示すのは、偽情報は単なる「間違った情報」ではなく、若者の不満や孤立感を裏付ける燃料として機能し得ることだ。
外国政府による「レッテル貼り」と越境弾圧
外国干渉の章では、最も活発な行為者として中国を挙げつつ、複数の国家がニュージーランドで活動しているとされる。その典型が トランスナショナル・リプレッション(越境弾圧) である。
ここで見られる偽情報の手法は、虚偽のラベリングだ。外国政府が「在NZの団体や人物はテロリストだ」「過激派だ」と根拠なく主張し、現地社会での信用を失わせようとする。NZSISはこうした「意図的な誤認」が使われている事例を複数確認している。
実際に2024年には、ある外国政府がニュージーランドに住む難民申請者に関心を持ち、その人物がLGBTQコミュニティに属することを理由に監視対象とした。これは単なる個人情報収集ではなく、性的少数者を社会的に脆弱な立場に追い込むための情報操作に当たる。
また別のケースでは、外国の公務員がNZ国内の協力者に接触し、特定の「反体制的」なグループを地域イベントから排除するよう要請していた。表向きは「コミュニティの和を乱す危険性がある」という理由が与えられたが、実態は偽情報による印象操作である。
信頼できる助言者の顔をした「偽情報源」
NZSISが警告するのは、外国政府が「信頼できる助言者」を装ってニュージーランドの意思決定層に入り込む手口だ。
あるケースでは、影響力のある決定権者が、長年信頼してきた人物から重要な判断材料を与えられていた。しかしこの「助言者」は実際には外国政府の協力者であり、受け取っていた情報は操作されたものだった。本人は全くその意図を疑わず、結果的に誤った判断を下してしまった。
これはまさに、偽情報がエリート層の意思決定を歪める現実例である。一般的に偽情報というとSNSや大衆への拡散が注目されがちだが、国家安全保障上は「個人の意思決定を誤らせる情報操作」の方がはるかに深刻な影響を持つ。
AIが変える偽情報の質
報告書は、生成AIの利用についても強い懸念を示している。AIはプロパガンダを「本物らしく」見せかけ、大量かつ高速に拡散する能力を持つ。過激派が攻撃計画の調査に利用するだけでなく、外国の情報機関もオープンソース情報の自動収集や操作コンテンツ生成に活用している。
従来の「粗雑で見破りやすい偽情報」とは異なり、AIによって生成された偽情報は、受け手にとって 信じやすく、疑いにくい 形に変わりつつある。NZSISは、これが今後の安全保障環境に大きな影響を与えると予測している。
偽情報は「副作用」としても危険
NZSISの分析で特徴的なのは、「ニュージーランド自体が必ずしも狙い撃ちされていなくても、外国発の偽情報の副作用を日常的に浴びている」という視点だ。
つまり、偽情報は直接のターゲットではなくても、社会の分断を深め、過激化の燃料を供給し、意思決定を誤らせる。その構造的リスクを可視化している点で、この報告は偽情報研究者にとって貴重な資料になる。
まとめ
- 若者がオンラインの偽情報を「自分の不満の裏付け」として受け入れる具体例がある。
- 外国政府はディアスポラを狙い、虚偽のラベリングや嫌がらせで抑圧を図っている。
- 信頼できる助言者に偽装した協力者が意思決定を誤誘導する事例が確認されている。
- AIは偽情報の質を高め、見抜きにくい形で拡散を加速させている。
このレポートは「偽情報対策」を正面から掲げたものではない。だが読み込めば、偽情報が安全保障にどのように組み込まれ、現実の脅威として立ち上がっているか を具体的に知ることができる。抽象的な「偽情報の危険性」論では見えてこない、生々しいケースが並んでいるのが最大の特徴だ。


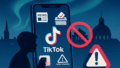
コメント
Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!
You actually make it appear so easy together with your presentation however I in finding this topic to be really something that I think I’d by no means understand. It kind of feels too complex and very wide for me. I am having a look forward on your subsequent publish, I will attempt to get the grasp of it!
Does your blog have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to shoot you an e-mail. I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it grow over time.
Really superb visual appeal on this web site, I’d rate it 10 10.
Hey, you used to write fantastic, but the last few posts have been kinda boring… I miss your super writings. Past several posts are just a little out of track! come on!
Cool blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog shine. Please let me know where you got your theme. Kudos
Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I’ll make sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thanks for the post. I’ll definitely comeback.