米ワシントンD.C.に拠点を置く研究機関Center for the Study of Organized Hate(CSOH)が2025年に公表した報告書「AI-Generated Imagery and the New Frontier of Islamophobia in India」は、インドのソーシャルメディアにおいて拡散しているAI生成の反ムスリム・ヘイト画像を大規模に調査したものだ。調査対象は2023年5月から2025年5月にかけてX、Instagram、Facebookに投稿された1,326件の画像や動画、発信アカウントは297にのぼる。分析は国連の定義するヘイトスピーチ基準に従って行われ、エンゲージメント総数は2,730万を超えたという。
報告書の中心は、生成AIがヘイトに使われるときの「4つの典型的ナラティブ」の解明である。すなわち、①陰謀論的物語、②非人間化、③ムスリム女性の性的対象化、④暴力の美化である。以下、その具体例を紹介する。
事件を宗教対立へとすり替える
生成AIの使い方で最も目立つのは、本来は宗教とは関係のない事件を「ムスリムの犯行」に変えてしまうやり方だ。
- 西ベンガル州の殺人事件では、容疑者にイスラームの頭帽をかぶせる加工が行われ、「イスラーム的暴力」として再解釈された。実際の捜査では宗教的動機は確認されていないにもかかわらず、SNSでは宗教対立の証拠として扱われた。
- ナヴサーリーの駐車場トラブルは、近隣の揉め事にすぎなかった。しかしAIによって「石を持つムスリム群衆」の画像が作られ、地域暴動=宗教暴動として拡散した。事実に即さない「可視化」が、虚構の物語を補強していく。
陰謀論に“証拠”を与えるAI生成物
従来から極右言説で語られてきた「ジハード陰謀論」は、生成AIによってさらに説得力を帯びる。
- 「ラブ・ジハード」
ムスリム男性がヒンドゥー女性を欺き改宗や結婚に誘い込むという言説は、現実の根拠が乏しい。だがAI生成物では、祭礼の場でヒンドゥー女性がムスリム群衆に取り囲まれる光景が繰り返し描かれる。こうした画像は「女性は常に狙われている」という印象を視覚的に刷り込む。 - 「人口ジハード」
ムスリムが大量の子どもをもうけ、人口で多数派を脅かすという物語も古くからある。これもAIで、妊婦や多数の子どもに囲まれた女性の生成画像が繰り返し拡散された。統計的には既に否定されている言説だが、感情に訴える画像は容易に広まる。 - 「レイル・ジハード」
鉄道事故を「ムスリムの破壊工作」と見せるために、線路に岩を置く人物や、斧を構えて列車をにらむ男の画像が合成された。現実の事故映像ではなく、検証困難な合成画像が「自明の証拠」として拡散する。
非人間化の記号
報告書は、ムスリムを動物に見立てる表現がAIで再生産されていることを指摘する。
- 蛇のモチーフが代表的だ。頭帽をかぶった蛇は、欺瞞・毒性・駆除対象という三つの意味を同時に含み、見た瞬間に「敵視すべき存在」と理解させる。
- 家畜への残虐行為を誇張した画像もある。イスラームの宗教的屠殺を、血にまみれた刃物や苦しむ動物で描き、「野蛮な宗教」とする。
こうしたイメージは論理ではなく感覚で敵意を煽る。
ムスリム女性の性的対象化
最も多く確認されたカテゴリーは、女性を性的に対象化する生成物だった。
- アバヤやヒジャブ姿の女性が、ヒンドゥー男性の「戦利品」のように描かれる。女性本人の同意も主体性も欠いたまま、宗教的記号とミソジニーが結びつく。
- 報告書は、GitHub上で発生した「Sulli Deals」や「Bulli Bai」といった女性オークション事件を引き合いに出し、AIによる量産がその延長線上にあると述べる。
この種の画像は、イスラモフォビアと女性蔑視の二つを同時に拡大させる危険を持つ。
暴力を美化するアニメ調の表現
さらに深刻なのは、過去の宗教的暴力を「美学化」する生成物だ。
- 1992年のバブリー・マスジド破壊は、柔らかなジブリ風アニメ調で描き直される。残虐さはノスタルジーに変換され、暴力は英雄的行為として再演される。
- また、過去の虐殺がコミカルなキャラクター(野菜のカリフラワーなど)で描かれ、犠牲の重みが嘲笑に変わるケースも確認された。
美しい絵柄やユーモアがモデレーションの回避にもつながり、受け手の心理的抵抗を下げる。
極右メディアによる拡散の回路
個人アカウントにとどまらず、既存の極右系メディアもAI生成物を利用している。
- OpIndiaは、強制改宗や拉致といった物語を合成画像付きで記事化。編集幹部の個人アカウントも動員し、大規模な拡散を実現した。
- Sudarshan Newsは鉄道事故を「レイル・ジハード」と断定し、斧を持つムスリムの合成サムネイルを利用した。
- RSS系のPanchjanyaは、モスク屋上で投石する姿をAIで作り、「反逆の証拠写真」として扱った。
こうして制作と報道と拡散が循環し、生成物は単なるデマではなく政治的言説の一部として機能する。
まとめ
この報告書は、生成AIが反ムスリムの物語を視覚的に強化する仕組みを、具体例とともに示している。事件の宗教化、陰謀論の“証拠化”、女性の対象化、暴力の美化──いずれもテキストだけでは説得力を持たなかった物語に「リアルな証拠」を与えてしまう。しかもそれは検証しづらく、反証しても拡散の勢いに追いつかない。
「蛇の頭帽」「線路に斧の男」「ジブリ風のマスジド破壊」といった印象的なイメージは、一度流布されると消すことが難しい。報告書は、このような生成AIによる視覚的ヘイトが、インドにおける少数派の安全や社会的信頼を深刻に揺るがしていると結論づけている。

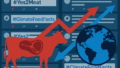
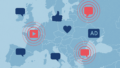
コメント
It is really a nice and helpful piece of info. I am glad that you shared this helpful information with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.
Only a smiling visitor here to share the love (:, btw outstanding style and design.
I do not even know the way I finished up here, but I believed this put up was great. I do not recognize who you’re but certainly you’re going to a well-known blogger should you are not already 😉 Cheers!
Howdy very cool blog!! Guy .. Beautiful .. Superb .. I will bookmark your blog and take the feeds alsoKI am glad to find a lot of useful info right here within the put up, we’d like work out more strategies in this regard, thank you for sharing. . . . . .
I am impressed with this site, rattling I am a big fan .
Dafür gibt es aber einen Willkommensbonus ohne Umsatzbedingungen! Spielern ohne Englischkenntnisse wird es somit erschwert, Unterstützung zu
erhalten. Auch unseren Sicherheitscheck hat
das Casino bestanden und bietet nun auch eine Seite zum verantwortungsvollen Spielen. Eine
App musst du dafür nicht herunterladen, stattdessen rufst du
einfach die mobil optimierte Webseite über den Browser des Mobilgeräts auf.
Das Casino sollte leicht verständlich und bonifreundlich
sein. Jeder kann jederzeit über Chat und E-Mail Hilfe erhalten. Die Leute, die Ihnen auf Deutsch helfen, können lokale Details bestätigen und sicherstellen, dass Sie alle für Sie geltenden Grenzen verstehen. Wenn Sie
einen Gratis-Spin-Code für 50 Spins erhalten, verwandelt sich das Geld, das Sie durch die Spins gewinnen, in Bonusgelder, die Sie einmal
einsetzen müssen. A €50 deposit gets you €50 in bonus funds
at Wolfy Casino if a code gives you 100% bis €200.
Slots zählen für 100 % unless they are excluded, while table
and live games count for less.
Das Willkommenspaket beinhaltet einen erheblichen Bonusbetrag, begleitet von einer großzügigen Anzahl an Freispielen, was es zu einem
verlockenden Angebot für Neuankömmlinge macht.
Mit seiner riesigen Auswahl können Sie auf Ihre Lieblingssportarten wetten oder
Ihr Glück mit Spielautomaten, Tischspielen und Live-Dealern versuchen. Außerdem kannst du blitzschnelle Auszahlungen, zuverlässigen 24/7-Support und erstklassigen mobilen Zugang genießen, der es dir ermöglicht,
überall und jederzeit zu spielen. Die Mission von Wolfy Casino basiert auf der Bereitstellung
eines außergewöhnlichen Spielerlebnisses, mit einem Fokus auf Innovation und spielerzentriertem
Design. Die schwache Optik verhindert allerdings nicht, dass Du alle regulären Spiele und Slots
flüssig und ohne Unterbrechung spielen kannst. Hierbei handelt es sich
um ein sehr ansprechendes Sortiment an klassischen Karten- und Tischspielen,
welches von insgesamt fünf Providern betrieben wird.
References:
https://online-spielhallen.de/myempire-casino-freispiele-alles-was-sie-wissen-mussen/
Diese Online Casinos bieten eine vertrauenswürdige Plattform mit einer Vielzahl diverser Spiele.
Die besten Online Casinos in Deutschland werden von erfahrenen Casino-Testern auf Basis von Spielauswahl,
Sicherheit, Boni und Zahlungsmethoden bewertet.
Hier finden Sie eine umfassende Liste der besten Online Casinos, die in Deutschland legal und
sicher sind.
Wenn Sie also ein Spiel ausgesucht haben, bei
dem Sie gern echtes Geld einsetzen wollen, schauen Sie sich die Casinos an, die Sie unterhalb des Spielangebots finden können. Am Glücksspiel ist grundsätzlich nichts auszusetzen, vor allem dann, wenn wir uns an die Prinzipien des verantwortungsvollen Spielens halten.
Wenn Sie also einige der Spiele auf unserer Liste nicht
aufrufen, finden oder starten können, liegt das möglicherweise an Ihrem gegenwärtigen Standort.
Mit der Blockchain können jene Casinos, die diese Technologie einsetzen, ihren Spielern ein nachweislich faires Spielerlebnis bieten und sicherstellen, dass die Ergebnisse der Spiele völlig zufällig und manipulationssicher sind.
References:
https://online-spielhallen.de/cosmo-casino-bonus-codes-und-mehr-ihr-ultimativer-guide/
Powerhouses like Microgaming and Evolution guarantee a top-shelf spin every time.
If baccarat is your game, don’t miss this thorough baccarat strategy guide to gain an edge.
Gambling addiction can ruin lives, and there’s no shame in reaching out
for help if you feel you’ve lost control. Minimum deposit and withdrawal amounts for Bitcoin and other crypto banking methods
often vary based on the current state of the market
for that currency. Deposits are almost always free, while withdrawals might incur a small fee from the casino or
payment processor. Popular Australian banking methods for
gambling include a wide variety of payment styles, such as credit cards,
crypto, and Neosurf.
There are two main types of Aussie online casinos you might consider, depending on what fits your needs and preferences.
Get ready for lots of fun and the chance to win big with real money casino games.
Our team has compiled a list of the best Australian online
casinos in the table below. All online casinos in Australia regularly run promotions.
The table below shows the Best Australian online casinos with excellent reputations
and a Trust rating of over 8.
References:
https://blackcoin.co/gamdom-online-casino-trusted-by-players-across-australia/
No deposit bonuses are great, but the promotions that follow at Casino Fair Go are even better!
Australian players can actually withdraw funds by utilizing this bonus
without even having to deposit! Fortunately, all new players
are eligible to claim a no deposit Fair Go Casino bonus!
Each deposit can provide a 100% match up to $200, making this a great way to start your gaming experience.
Fair Go Casino welcomes all new players with a substantial bonus.
Your account’s sitting there with all your favorite games ready to go.
New games are being routinely added to this casino’s library.
The software developer is noted for continued dedication to
fairness and transparency, which means all Realtime Gaming games were tested for randomness.
FairGO casino only works with one game maker, Realtime Gaming.
References:
https://blackcoin.co/about-ozwin-casino/
Many live games contribute differently to wagering requirements — always consult bonus T&C before using live
tables to clear a bonus. WinSpirit’s live casino offers classic
table action and game-show formats streamed in HD.
With roughly 2,500 titles, winspirit offers an expansive library.
The platform balances variety, mobile convenience, and promotional value
— three pillars Aussie players often prioritise.
This summary table gives a snapshot of WinSpirit in plain terms so Australian players can quickly
assess the platform before diving into our full review.
Responsible gaming tools, including various limits and connections to support organizations, show care for
player wellbeing.
It provides a secure environment with trusted payment options and generous promotions.
Compared to other Aussie-friendly casinos, WinSpirit’s loyalty program sits in the middle tier.
These aren’t just marketing gimmicks – the cashback hits your account
every Monday morning without requiring claims or minimum loss
thresholds.
Solid lineup of pokies and a really polished live casino.
Transparency on bonuses will always stay a priority.
Huge range of games and the app didn’t freeze once. Its simple design makes finding games and promotions quick, giving you the same great rewards as the desktop site, wherever you are.
Once registered, the Win Spirit casino login process
is simple, requiring just your credentials to access your account instantly.
The support team is available to help with account questions, payments,
or technical issues.
References:
https://blackcoin.co/login-to-your-spin-city-account-the-official-site-2025-updated/
If you or someone you know has a gambling problem, call GAMBLER.
Deposit-match bonus of $2,500. New users and first deposit only.
As soon as your account is up and running, head to the Cashier section and make a deposit using your preferred payment method.
Our team at Casino Guru takes advantage of the fantastic community we’ve built over the years when conducting our casino reviews.
Only the sites that rate the highest in these evaluations make it
onto our list of recommendations.
Yes, online casinos are legal for players within Australia.
A top Australian casino online in 2025 offers a wide range of games at the
click of a mouse, and it takes just minutes to sign up for a
real money casino Australia account. At Casino.com.au, we take a
comprehensive approach to reviewing and rating online casinos for Aussie players.
We have been reviewing online casinos and gambling sites for
over 15 years so we know how to spot the good ones, but also how to spot the bad ones.
Quickly compare Australia’s top online casinos, find winning strategy
guides and reviews from Australian players. Any of the real money online casino sites on our list are worth checking out, so dig in and
find the one that best fits your style.
When playing on the BetRivers casino desktop site, players can navigate to
the usual casino sections, including table games and several slots libraries.
Bet365 Casino on both the US and UK sites combines slot games, table game favorites,
jackpots, and a live casino. It’s perfect for players in New Jersey
looking for a quality casino gaming experience. Sky Vegas, part of the Sky Betting
& Gaming family, is predominantly a slots site but also offers tables games
and a live casino. You can get involved in this bonus by playing a number of different games across casino and poker.
You can also check out our guide to the Best Online Casinos available in Ontario
right now, including where to find the best real money slots, and table games like Blackjack, Roulette, and
Craps!
References:
https://blackcoin.co/what-is-a-high-roller-best-high-roller-online-casinos/
online casino that accepts paypal
References:
https://hirenhigher.co.nz/companies/online-casinos-that-accept-paypal/
us poker sites that accept paypal
References:
https://hootic.com/profile/laurelmaas834
online betting with paypal winnersbet
References:
https://careers.universalair.aero/employer/best-paypal-casinos-2026-uk-casino-sites-accepting-paypal/
online slot machines paypal
References:
https://externalliancerh.com/employer/paypal-online-casinos-best-us-casinos-accepting-paypal-payment-method/
us poker sites that accept paypal
References:
infuline.co.kr
online casino paypal einzahlung
References:
https://hyojun.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=46
online blackjack paypal
References:
https://adm.astonishkorea.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=3619
paypal online casino
References:
https://jobstaffs.com/employer/top-paypal-casinos-in-canada-2025-best-paypal-gambling-sites/
online casino usa paypal
References:
https://chefstaffingsolutions.com/employer/best-online-casinos-australia-top-10-australian-casinos-2025/
paypal casino
References:
https://jobshop24.com/employer/list-of-casinos-in-australia/
References:
Anavar before and after female
References:
https://dlx.hamdard.pk/user/profile/321361
References:
Black jack no yuuwaku
References:
https://musicvideo80.com/user/bowlpimple5/
clenbuterol side effects hair loss
References:
https://oiaedu.com/forums/users/captempo40/
injectable steroids names
References:
https://securityholes.science/wiki/Winstrol_Stanozolol_Online_Kaufen
Thanks for any other informative blog. The place else may I am getting that kind of information written in such an ideal manner? I have a undertaking that I am just now running on, and I’ve been at the look out for such info.
References:
Anavar cycle results before and after
References:
https://bookmarkingworld.review/story.php?title=essen-vor-oder-nach-dem-sport-das-sagt-die-wissenschaft
References:
Anavar cycle results before and after pics
References:
https://buyandsellhair.com/author/ruthgoat9/
%random_anchor_text%
References:
https://www.mapleprimes.com/users/mathbubble9
order steroids online
References:
https://urlscan.io/result/019bcb8d-dfef-733e-a913-da0b527008af/
steroids and testosterone
References:
https://ai-db.science/wiki/GUIA_COMPLETA_OXANDROLONA_ANAVAR