旧ユーゴスラビア紛争の余波を今も抱えるコソボ。2008年に独立を宣言したが、セルビアやロシアはこれを承認せず、国連加盟も果たしていない。北部にはセルビア人住民がまとまって暮らし、首都プリシュティナを拠点とするアルバニア系多数派政府と対立が続く。戦争の記憶と民族的アイデンティティが強く作用する環境は、偽情報の格好の土壌となっている。
報告書「How Disinformation Fuels Ethno-Political Radicalization in Kosovo」をまとめたコソボ安全保障研究センター(KCSS)は、偽情報が偶発的な誤報ではなく、外部勢力や国内政治エリートが戦略的に利用する「武器」となっていると指摘する。
分断社会における偽情報の理論的背景
研究はまず、「分断社会でなぜ偽情報が効くのか」という理論枠組みを整理する。民族間の記憶、被害者意識、戦争の語りが未解決のまま残っていると、それ自体が利用可能な「燃料」になる。
- 歴史の書き換え:ラチャク虐殺やスレブレニツァ虐殺の否定のように、戦争犯罪を相対化して加害責任を消す。
- 被害者物語:セルビア人は「迫害されている少数派」、アルバニア人は「セルビアの脅威にさらされている」と描く。
- 陰謀論:相手民族が外国勢力と結託していると示唆し、協力を裏切り行為に見せる。
- 制度の否定:コソボの警察や裁判所、KFOR(NATO平和維持部隊)を「偏っている」「不正な存在」と描く。
SNSやテレグラムの「フィルターバブル」効果で、これらの物語は検証されないまま反復され、民族的な被害意識を再生産する。
コソボで展開された偽情報の流れ
KCSSの調査によれば、偽情報は「事件→偽情報による枠付け→社会的反応」という連鎖で作用する。
2022年ナンバープレート騒動
コソボ政府の規制強化をめぐり、セルビアの国営メディアは「セルビア人強制追放計画」と報道。存在しない政策が事実のように広まり、北部で大規模な抗議が起きた。
2023年バニャスカ襲撃
セルビア系武装グループが警察を攻撃した事件では、直後にセルビア系メディアが「コソボ警察とNATOがセルビア人を襲った」と逆転した物語を拡散。事件の加害者と被害者が入れ替えられた。
テレグラムチャンネルの台頭
「BUNT」「Bunker」など数万人規模のチャンネルは、民族主義的スローガンや暴力美化のコンテンツを発信。「すべてはロシアだ、ただしコソボはセルビアだ」というスローガンは、ロシア支持と極端なセルビア民族主義を結合させた象徴的な例。ここから現実の抗議や道路封鎖の動員が組織された。
メディアの役割──両言語空間の「並行現実」
- セルビア語圏:「Kosovo Online」が代表的。セルビア政府直結の編集体制を持ち、戦争犯罪の否定、アルバニア人による「テロ」の誇張、コソボ政府の不正当化を繰り返す。
- アルバニア語圏:政府発表に依存し、セルビア人住民の声を拾うことは少ない。「セルビア側の主張はすべて挑発」と決めつける報道が多い。
こうして、両言語圏の市民は互いに異なる現実を生きる。セルビア人は「迫害の物語」に、アルバニア人は「安全保障の脅威の物語」に閉じ込められ、共通の事実に触れる場を失う。
ケーススタディ:ミトロビツァ高校卒業生事件
2025年5月、北部ミトロビツァでセルビア人の高校生たちが「コソボはセルビアの心臓」と叫びながら行進。警察官が一人を取り押さえた際、首に赤い跡が残った。この映像は即座にSNSで拡散。
- セルビア語圏では「警察の暴力で学生が血まみれになった」と報じられ、英雄化。ベオグラードの学生が首に赤いペンで印をつけて連帯を示すパフォーマンスまで広がった。
- アルバニア語圏では「セルビアが仕組んだ挑発」とされ、警察の対応を正当化。セルビア人当事者の声はほとんど報じられなかった。
実際には赤い跡はマーカーによるものだったが、その事実は双方で無視され、「迫害」と「挑発」という二つの物語が固定化した。報告書はこの事件を、偽情報が小さな出来事を民族的危機へと変換する典型として分析している。
偽情報が作り出す「前段階的ラディカル化」
暴力そのものに直結しなくても、日常的に流れるヘイトスピーチや陰謀論は「相手を人間として見ない」思考を常態化させる。若い世代は戦争を直接知らなくても、SNSを通じて「セルビア人は敵」「アルバニア人は裏切る」という物語を浴び続けている。
報告書の言葉を借りれば、「すべては一つの枠に収束する──我々は善、彼らは悪」という二元論が社会全体に染み込んでいる。
外部勢力と内部政治の相互作用
ロシアとセルビアはコソボを「失敗国家」と描くことで国際的な立場を弱体化させてきた。しかしそれだけではない。コソボ国内の政治家も、国境画定や自治体協定といった政策課題のたびに偽情報を利用し、「裏切り者」や「国を売る者」というレッテルを対立相手に貼ってきた。外部の情報戦と国内の政治利用が重なり、社会全体の信頼は二重に損なわれる。
結論と提言
報告書は、偽情報を「偶発的な誤報」ではなく「構造的な分断装置」と捉えるべきだと結論づける。小さな事件が「民族的危機」に変換されるたびに、両社会はゼロサム思考に閉じ込められ、和解の余地を失う。
そのうえで、以下のような対策が提言されている。
- 政府は独立系ファクトチェック組織を支援し、アルバニア語・セルビア語の双方で検証可能な仕組みを作ること。
- 各省庁にセルビア語報道官を置き、誤情報が広がる前に二言語で公式説明を出せる体制を整えること。
- 市民社会は、両言語で偽情報を追跡する共同モニタリングを強化すること。
- メディアは公式発表だけに依存せず、双方の住民の声を取材し、対話の場を記事内に確保すること。
おわりに
コソボの事例は、偽情報が単に「事実をゆがめる」だけでなく、社会に「共存は不可能」という信念を根付かせ、暴力の正当化に一歩近づけることを示している。事件そのものよりも、その事件をどう語るかが社会の分断を決定づける。
この報告書は、民族間の不信を「偶発的な誤解」ではなく「構造的に作られる現実」として捉え、その仕組みを解き明かしている。


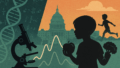
コメント
Mit Funktionen wie dem schnellen Zugriff auf Lieblingsspiele ist die Navigation auf der Plattform ein Kinderspiel.
Mobil erhalten Enthusiasten Zugang zu
allen VIP-Funktionen, inklusive exklusiver Freispiele und Sonder-Einzahlungsboni. Für progressive Jackpots und
hohe Gewinne können besondere Auszahlungsregeln gelten. Das
Slot Hunter Casino bietet jedoch flexible Optionen, um das Gaming-Erlebnis im Casino-Bereich zu optimieren. Neue
Spieler sollten die allgemeinen Geschäftsbedingungen sorgfältig prüfen, bevor sie eine Einzahlung getätigt oder einen Bonus aktiviert haben.
Auch Tischspiele mit echten Live-Dealern haben ihren eigenen Bereich.
Außerdem kann man in der Lobby nach den Spielen filtern, bei denen du im Online
Casino Freispiele kaufen kannst (Bonus Buy). Wenn du deine Telefonnummer verifizierst, bekommst du noch
weitere 20 Freispiele für den Slot Lucky Lady Chance von BGaming.
Die Freispiele sind für den Slot Book of the Fallen von Pragmatic Play gültig.
References:
https://online-spielhallen.de/umfassender-leitfaden-zum-1go-casino-cashback-ihr-bonus-ruckerstattungsprogramm/
However, players should verify the casino’s credentials and track record before
committing. Digital casinos give us various gaming options just a few clicks away.
Our experts have meticulously reviewed casinos to bring the five best options for
Aussie gamblers from our experiences.
MiFinity is an e-wallet payment service that supports deposits and withdrawals.
It’s great if you’re a budget-conscious player, and it also provides
anonymity. Paysafecard is a prepaid voucher system that allows you to deposit funds without requiring
a bank account or card.
Australian online casinos offer a diverse range of games to cater
to various player preferences. The competition among these top Australian online casinos ensures that players have access to innovative gaming experiences and
generous rewards throughout 2025. Australian online casinos
for real money feature thousands of real money games developed by the world’s leading
providers. The gambling sites we list are the best Australian online casinos that pay real money.
Aussie players can get the best payout rate by claiming
real money online casino no deposit bonus codes.
References:
https://blackcoin.co/53_high-roller-slots-list-of-the-top-11-high-roller-slots_rewrite_1/
Just enter a bonus code during your initial log in or registration, and the offer will
be added to your account. This is one of the easiest
ways to give your balance a boost while trying
out popular pokies and table games. Whether you’re
spinning for fun or aiming for real winnings, it’s a perfect intro
to the Playcroco Casino world.
At Play Croco Australia, registration is quite simple, and
there are many ways to deposit and withdraw your winnings.
There are no live dealer games in the catalogue. However, what customers like best is the
bonus program with numerous rewards. Players are offered an extensive range of paid games that have demo versions.
References:
https://blackcoin.co/razz-fourth-street-play-an-easy-guide-on-how-to-keep-your-money-safe-and-double-your-wins/
paypal casino online
References:
https://findjobs.my/companies/best-paypal-casinos-uk-2025-casino-sites-that-accept-paypal/
online betting with paypal winnersbet
References:
http://play.kkk24.kr/bbs/board.php?bo_table=online&wr_id=275909
online casino real money paypal
References:
https://remotejobs.website/profile/noellafabinyi
paypal casino usa
References:
https://jobsbotswana.info/companies/top-australian-online-pokies-for-real-money-in-2025/
online betting with paypal winnersbet
References:
https://wedeohire.com/employer/best-paypal-casinos-2025-best-casinos-accepting-paypal/
online betting with paypal winnersbet
References:
https://dev-members.writeappreviews.com/employer/payid-casinos-in-australia-best-casino-sites-accepting-payid-withdrawal/
References:
Test and anavar cycle before and after pictures
References:
https://pad.karuka.tech/s/NdeC6uADt
References:
Perth crown casino
References:
http://downarchive.org/user/moneyairbus6/
steroids stacks for sale
References:
https://escatter11.fullerton.edu/nfs/show_user.php?userid=9517354
References:
Anavar cycle before after
References:
https://dinghyairbus8.bravejournal.net/oxandrolona-anavar-para-mujeres-culturistas-femeninas
References:
Anavar cycle results before and after pics
References:
https://bookmarks4.men/story.php?title=anavar-zyklus-oxandrolon-fuer-bodybuilding
buy legal steroids in canada
References:
https://smed-sauer-2.mdwrite.net/winstrol-erfahrungen-and-zyklus-winstrol-kaufen-and-kur-2026
anadrol steroids for sale
References:
https://hackmd.okfn.de/s/rJezdXKjH-g
%random_anchor_text%
References:
https://livebookmark.stream/story.php?title=comprar-anavar-esteroides-anabolicos-espana-farmacia-en-linea
steroids online reviews
References:
https://www.instapaper.com/p/17377622
quick gain reviews
References:
https://gpsites.stream/story.php?title=stanozolol-online-kaufen-gepruefte-produkte