「洗脳」や「プロパガンダ」という言葉に、暴力的な全体主義国家の姿を思い浮かべるのは、もはや時代遅れかもしれない。現代では、民主主義国家であっても、権力者がSNSやAIを駆使して世論を操作し、有権者が自ら進んで偽情報に身を委ねる現象が起きている。
2025年2月28日に発表されたAUTHLIBワーキングペーパー『Brainwashing of the People, by the People, with the People』(著:Péter Krekó)は、このような新しい情報操作の形を、制度的・心理的側面の両面から理論化し、スピン独裁や協力的洗脳といった概念を通じて解明している。
スピン独裁とは何か
本論文は、21世紀型の権威主義体制を「スピン独裁(spin dictatorships)」として位置づけている。従来の恐怖政治的な弾圧とは異なり、スピン独裁は暴力ではなく情報操作を主要な支配手段とする。これらのリーダーは選挙を通じて権力を得ており、世論調査やSNSのモニタリングによって有権者の反応を読み取りながら、人気とパフォーマンスによって正当性を維持する。
事例として挙げられるのは、ハンガリー、ロシア、トルコ、シンガポール、インド、エクアドル、ペルーなどで、特にハンガリーのオルバン政権やロシアのプーチン政権は代表的なスピン独裁のモデルとされている。
「騙される大衆」ではなく「協力する大衆」
本稿の主張のひとつは、偽情報が単に上から押し付けられるものではなく、受け手である市民が能動的に「信じたい物語」として受け入れる側面があるという点である。その背景には、部族的なアイデンティティの強化、自己正当化の欲求、政治的・感情的な快感といった心理的動機が作用しているとされる。
また、投票行動や世論形成においては、事実性よりも「象徴的な物語」や「仲間意識」が重視される傾向が指摘され、受け手自身が情報操作に「協力」している状況が分析されている。
真実より面白い物語:なぜ嘘が勝つのか
偽情報が事実よりも広まりやすい理由として、本論文では以下のような非制度的要因が挙げられている。
まず、カリスマ的リーダーの魅力や個性が、伝える物語の信頼性や拡散力を高めること。次に、政治的ナラティブが「悪の他者」「迫りくる危機」「被害者としての自民族」といったわかりやすい構図を提供し、人々の道徳的感情や不安を喚起する仕組み。そして、娯楽性の高い偽情報や陰謀論が、真実よりも受け手にとって魅力的であるという指摘がある。
これらの要素が組み合わさることで、真偽を超えた「信じたい物語」として偽情報が支持されるメカニズムが論じられている。
民主主義 vs スピン独裁:境界の崩壊
本稿はまた、情報操作の技術が民主主義国家でも利用されており、もはや民主主義と非民主主義の境界は情報環境の面では有効でなくなりつつあるという視点を提示している。
たとえば、ドイツ、イタリア、英国、米国といった民主国家においても、政治的権力を持つアクターがボットやトロール、フェイクアカウントを用いて偽情報を拡散する事例が確認されており、これらは制度的な検閲とは異なる形での情報支配とされている。
対抗策の再設計へ:制度ではなく心理への介入
情報操作への対抗策として本稿が提案するのは、従来の「制度による検閲防止」や「啓蒙的な情報提供」に加え、心理的要因に基づいたアプローチである。
とくにメディアの多元性を保ちつつ、デジタルリテラシーを強化することが重要とされているが、その際も「上から目線の指導」ではなく、社会的関係性に根ざしたエンパワメントが有効だとされる。
具体的な実験としては、参加者に「デジタルリテラシーに疎い親戚に向けた手紙」を書かせる介入研究が紹介されており、これによってフェイクニュースへの耐性が向上したという結果が示されている。
まとめ
このワーキングペーパーは、現代の情報操作が「強制されるもの」ではなく「自ら進んで受け入れられるもの」になっているという視点から、プロパガンダや洗脳の概念を再定義している。人びとは「騙される」のではなく、「信じたい物語」を自ら選び取っている。そこにこそ、21世紀型の情報操作の本質がある。
もはや「民主主義だから安心」という前提は通用しない。偽情報と向き合うためには、制度やファクトチェックだけでなく、社会心理そのものへの理解が求められている。

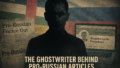

コメント
It’s actually a nice and helpful piece of information. I’m happy that you shared this useful info with us.
Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.
Can you tell us more about this? I’d care to find out
some additional information.
We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community.
Your website provided us with valuable information to work on.
You have done a formidable job and our entire community will be thankful to you.
Viele Casinos bieten nach dem No Deposit Bonus großzügige Einzahlungsboni an.
Du erhältst dann nach Abschluss der Registrierung eine festgelegte Summe Bonusgeld, die Du frei
oder mit kleinen Beschränkungen im Online Casino einlösen kannst.
Eine weitere Möglichkeit für einen Online Casino
Bonus ohne Einzahlung sind Auszahlungen von Bonusgeld. Ein Online Casino Bonus ohne Einzahlung zeigt sich oft als Freispiele.
Ein klassischer Einzahlungsbonus bietet meist mehr Wert.
Strenge Regulierungen führen dazu, dass viele Anbieter
lieber auf klassische Einzahlungsboni setzen.
Genau wie der Name schon sagt, handelt es sich dabei um einen Bonus,
den Sie erhalten und für den keine Einzahlung erforderlich ist.
Es bringt Ihnen nämlich nichts, wenn Sie einen attraktiven Bonus erhalten und an diesem schwer zu erfüllende Umsatzanforderungen haften. Alle unsere Bonusangebote
sind von unseren Experten ausgiebig getestet. Wir prüfen dabei die Qualität, Quantität und Vielfältigkeit der
Spiele, die Bonusangebote und ihre Bedingungen sowie den angebotenen Service wie die Zahlungsmethoden und den Kundensupport.
Du kannst mit 50 kostenlosen Freispielen viel Spaß haben und,
wenn das Glück dir hold ist, einen attraktiven Echtgeld-Gewinn
erzielen. Glücksspielanbieter, die Freispiele ohne Einzahlung zur Verfügung
stellen, haben meist mindestens noch einen Einzahlungsbonus zusätzlich im Programm.
Vielmehr bedeutet es, dass man kein Echtgeld benutzen muss, um in diesen Casinos
zu spielen.
References:
https://online-spielhallen.de/bruno-casino-freispiele-ihr-weg-zu-kostenlosen-spins-und-gewinnen/
If you’re having a bad streak of luck, cashback offers return a percentage
of your losses in the form of a bonus credit. We’re
not saying to bet pennies on your favourite games, but don’t spend all your cash in one place (or on a
single spin). Managing your bankroll is the key to sustained gameplay and big wins down the line, so it’s worth stretching every dollar as far as it’ll
go.
You can easily find information about bonus rules, payment conditions, and other essential aspects.
Make a deposit of at least 48 AUD every week from Friday to
Thursday. You will receive a 50% reload bonus with a maximum limit of 3251 AUD.
Once per month, deposit at least 162 AUD with the HIGH5 promo code.
The VIP program in the casino is not specified.
Note all bonus terms and read detailed conditions in the “Bonus Terms” on the official website.
And with top software providers like NetEnt and Evolution, you’re guaranteed
a high-quality gaming experience.If you’re after a well-rounded online casino that blends modern features
with trusted service, SkyCrown is definitely worth checking out.
SkyCrown regularly updates their promotions page with reload bonuses, free spin drops, cashback offers, and exclusive rewards for VIPs. Ready to start playing and claim your welcome
bonus? SkyCrown prioritizes exceptional customer support to ensure a seamless experience for players.
SkyCrown partners with over 50 reputable game studios to deliver a diverse and
high-quality gaming experience. In addition to slots,
table games, and poker, SkyCrown offers a diverse selection of other casino
games to cater to different preferences. The
live casino games, provided by Evolution Gaming and Pragmatic Play Live, include popular titles like Live Roulette, Live Blackjack, Live Baccarat, and Live Dream Catcher.
References:
https://blackcoin.co/woo-casino-review-all-games-promotions/
New pokies are added on a regular basis at the casino giving the player something to look forward to each month.
The pay table of each pokies game details for the player the
winning options and all special bonus options that are offered such as wilds that substitute for other symbols and complete winning payouts by doing so.
There are games with progressive and random progressive jackpots
and there are games where the player can gamble his winnings by guessing the color or suit of a card to be turned over or
by tossing a coin and guessing if it will land on heads or tails.
Customer support interactions were generally positive, with
responsive and helpful staff. While I haven’t independently verified their RNG certification,
the game play seemed fair during my time on the site.
The fairness of the games is another point of interest.
This review cuts through the marketing spiel to
deliver an unbiased, expert analysis of Ozwin Casino.
References:
https://blackcoin.co/10-minimum-deposit-casino-bonuses-in-australia-2025-guide/
mobile casino paypal
References:
https://cyltalentohumano.com/employer/paypal-gambling-sites-where-its-accepted/
online casinos that accept paypal
References:
https://jobthejob.altervista.org/employer/paypal-betting-sites-2025-gambling-sites-that-accept-paypal/
casino online uk paypal
References:
https://bio.rocketapps.pro/utakillian
paypal casinos online that accept
References:
https://interior01.netpro.co.kr:443/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=139
casino paypal
References:
http://www.thehispanicamerican.com/companies/2025-australia-legal-online-casinos-aussie-online-casinos/
You can view your current loyalty points in your account overview, located in the top right-hand corner. Once this wagering has been completed, your bonus and winnings from the bonus will be converted into real money that can be cashed out. Keep in mind that $3 is the maximum bet allowed while using bonus funds. The free spins can be played on Witch Treasures by GameBeat. You can get 50 free spins every Monday, as long as you make a deposit of $30 or more.
Whether you’re a casual player or a high-stakes enthusiast, the bonus system ensures that every session comes with added value and excitement. Every player can dive into a diverse gaming portfolio tailored to different preferences. The platform’s commitment to fair play is demonstrated by its Curacao eGaming license, which holds the operator to strict standards. Player trust is paramount, and the platform employs robust measures to ensure a secure and fair gaming environment.
To keep the momentum going, SkyCrown offers a Second Deposit Bonus that rewards players for their continued loyalty. On top of that, new players often receive free spins on selected pokies, giving you additional chances to win without putting more money on the line. As a new player, you can take advantage of a generous 100% match bonus on your first deposit, which means if you deposit AUD 100, you get an extra AUD 100 to play with! The support team is knowledgeable about all aspects of the casino, making sure you have the best possible experience.
References:
https://blackcoin.co/ufo9-casino-your-place-to-play-your-way/
online casino for us players paypal
References:
https://skinforum.co.in/employer/payidcasinoau-top-payid-casinos-guide-for-aussies/
casino online uk paypal
References:
https://kaymack.careers/employer/online-casino-welcome-bonuses-2025-casino-sign-up-offers/
online casinos mit paypal
References:
https://pharmakendra.in/employer/best-paypal-online-casinos-accepting-us-players-2025/
online casino paypal einzahlung
References:
http://play123.co.kr/bbs/board.php?bo_table=online&wr_id=276497
best online casino usa paypal
References:
https://prefereplus.com/employer/best-paypal-casinos-2025-online-casinos-accepting-paypal/
References:
10mg anavar female before and after
References:
https://justpin.date/story.php?title=anavar-vorher-und-nachher-bilder-shocking-transformations
References:
Blood work before and after anavar hdl ldl
References:
http://premiumdesignsinc.com/forums/user/brownsystem55/
References:
Anavar womens results before and after
References:
https://pikidi.com/seller/profile/sharkankle78
References:
Four winds casino michigan
References:
https://www.instapaper.com/p/17371234
References:
Jackpot capital casino
References:
https://www.marocbikhir.com/user/profile/526137
anabolic steroi
References:
https://jokumsen-fogh.blogbright.net/testosterone-cypionate
tren steroid side effects
References:
https://justpin.date/story.php?title=lvl58-boost-not-working-yet-the-burning-crusade-classic-world-of-warcraft-forums
anabolic steroids before and after pictures
References:
http://thethoughtfodder.com/members/numberbite9/activity/31446
do steroids make your voice higher
References:
https://gpsites.win/story.php?title=clembuterol-sin-receta-compra-facil-y-segura-online-en-espana
bodybuilder steroids vs. natural
References:
https://pad.stuve.uni-ulm.de/s/sCIGKPdyh
References:
Before and after test cyp 500 week and anavar
References:
https://trade-britanica.trade/wiki/Anavar_Cycle_Guide_Safe_Dosage_Best_Results_2025
References:
Cycle anavar female before and after
References:
https://nerdgaming.science/wiki/Lifters_Lounge_Anmelden
References:
Best time to take anavar before or after workout
References:
https://urlscan.io/result/019bd421-f176-73ef-a3bd-78fa08f3da9f/
best pills to take to gain muscle
References:
https://ai-db.science/wiki/Bururan_en_Colombia_Precio_Opiniones_y_Dnde_Comprar
References:
Women’s anavar before and after
References:
https://nerdgaming.science/wiki/Anavar_gewichtsverlust_vor_und_nachher