中国による偽情報工作をどう捉えるべきか──NATO議会が2025年4月に公開した報告書『Protecting Allied Societies from Chinese Disinformation』は、その問いに対して明確な視点を提示している。中国が展開するのは、従来のように政府発信で一方的な主張を流すやり方ではない。むしろその本質は、「国家が語っているとは見えない形で」「制度の信頼や認知の基盤を揺るがす構造をつくる」ことにある。
本報告書の出発点にあるのは、偽情報を「真偽」の問題としてではなく、「構造」や「制度」への介入として捉える視点である。中国共産党が国内で確立した検閲・宣伝・統制の手法が、そのまま輸出され、NATO加盟国を含む他国社会の情報空間に向けて適用されているという現実がある。
偽情報はどこから来ているのか
報告書がまず指摘するのは、中国の偽情報活動の主体が「国家」そのものでは見えなくなっているという点である。現在の手法では、外国人インフルエンサー、協力的なメディア、買収された情報発信者、さらには生成AIによるコンテンツ生成などを通じて、表面上は第三者の声として発信される。その語り口も、「西側の主張は行き過ぎでは」「中国をもっと正確に見るべきでは」といった相対化の形をとる。報告書では、こうした構造を“国家的プロパガンダのアウトソーシング”と呼び、誰が何を意図して発しているかが分からないことそのものが、情報操作の仕組みであるとする。
このような言説は、国家による正面からの主張ではないが、結果的に中国の立場を下支えするナラティブとして機能する。特定の主張が拡散されるというよりも、「西側にも問題があるのでは」といった疑念が、さまざまな場所から断続的に提示されることで、全体として西側社会の認知環境をずらしていく。信頼の分散、判断の保留、確信の喪失──それがこの戦術の意図する成果である。
NATO加盟国に対する攻勢
こうした戦術は、すでに複数のNATO加盟国において実際の影響をもたらしている。報告書はリトアニアの事例を詳述している。同国は台湾代表部の設置に踏み切ったことで、中国からの経済制裁のみならず、外交的圧力と並行して情報工作の標的にもなった。リトアニア国内の政治家に関する偽のスキャンダルや、EU内部の孤立を演出する報道などが出回り、SNS上でも一貫して政府の外交姿勢に疑義を投げかけるアカウントが活動していたという。
また、カナダにおいては、特定の中国語メディアを通じた選挙干渉の疑惑が報じられた。これは中国系移民社会を対象とするメディア空間が、検証困難なまま操作されているという問題であり、報告書ではその構造的危険性が指摘されている。
さらに、情報操作の連携という観点では、報告書は中国とロシアによるナラティブの相互強化にも言及する。両国はそれぞれのプロパガンダを直接引用・増幅しながら、ウクライナ、台湾、新疆、イスラエル・パレスチナなどの国際問題において「西側批判」を繰り返す。単独では強調できない主張が、他国の言説によって補強される構造は、単なる偶発的連携ではなく、戦略的配置である可能性が高いと報告書は見ている。
対抗策は“遮断”ではなく“制度の強化”
では、これに対して何ができるのか。報告書は「遮断」や「検閲」のような直接的対抗策を推奨していない。むしろ、メディアの透明性、発信主体の開示、編集方針の公開、そして市民のリテラシーの底上げといった、社会側の“耐性”の強化を中心に据えている。
とくに注目されるのは、中国語話者のコミュニティにおける独立報道機関の必要性である。現地語で中国政府寄りの情報だけが流通する状況では、ディアスポラ社会が外部から見えないかたちで国家ナラティブに包囲されてしまう。その空白を埋めるには、報道機関への支援や、信頼できる情報源の育成が不可欠だと報告書は指摘している。
また、AI技術を活用した自動検出やトレーサビリティの強化も重要な柱となっている。誰が、何の目的で情報を発しているのかが可視化されないまま流通する状況を放置すれば、制度的信頼そのものが崩れていく。報告書の問題意識は、まさにその一点に集中している。
認知空間の防衛という課題
本報告書は、中国の偽情報活動を“脅威”として煽る意図では書かれていない。むしろ、情報が「どのように流通するか」、そして「その流通構造が制度にどのような影響を与えるか」という設計上の問題を明示するものである。情報空間が透明であること、信頼に足る根拠が示されていること、多様な視点に裏打ちされた議論が成立していること──そうした前提が壊れていくとき、民主主義の意思決定もまた内側から浸食されていく。偽情報とは、主張ではなく構造の問題なのだという本報告書の立場は、今後あらゆる情報政策の出発点となるべきものである。
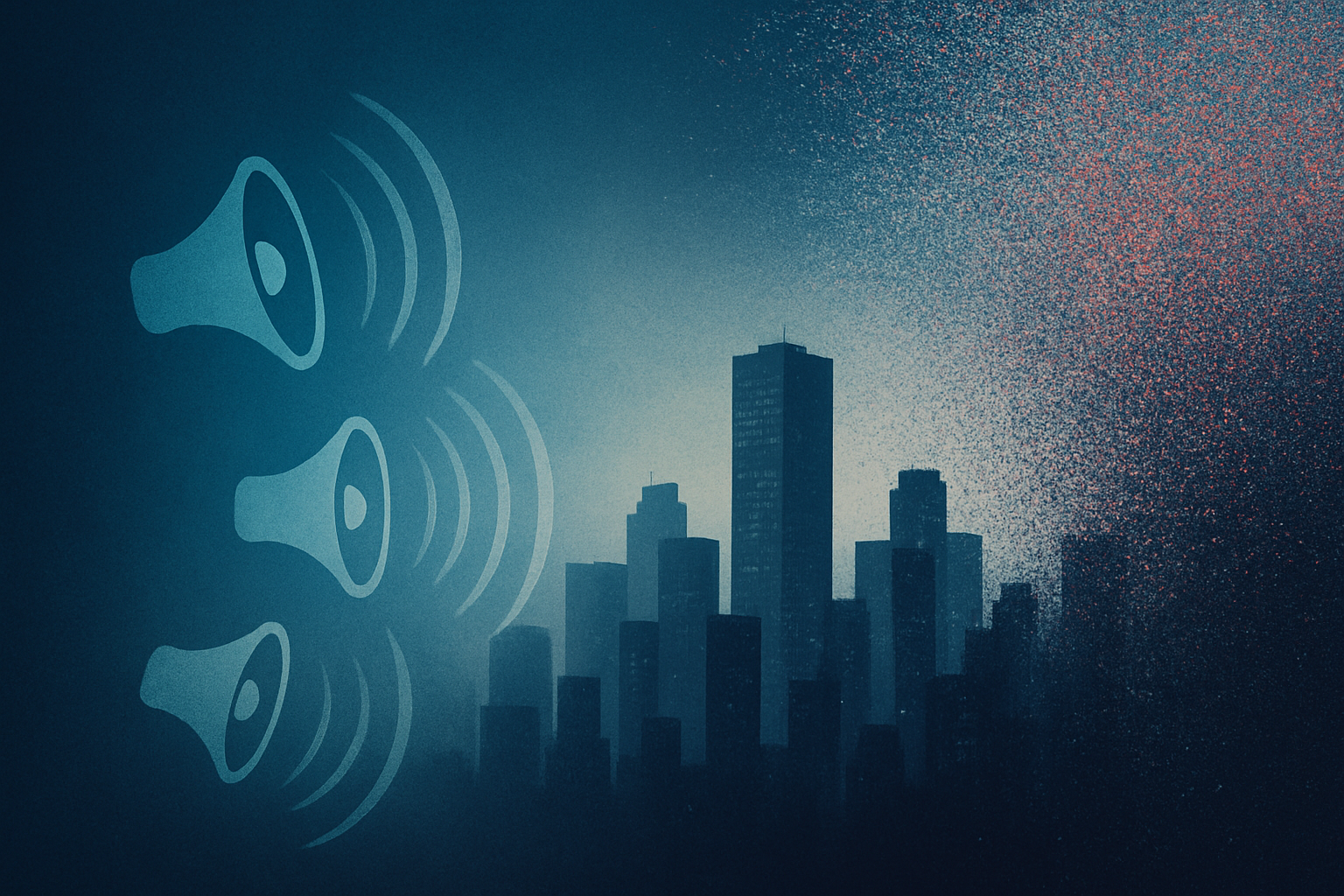
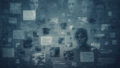
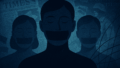
コメント
jzxfpfqxwtkpvrshewdsgjjkinsfyg
Professional ac clean, more details here ac clean
Лучшие девушки для теплого общения и встреч, подробнее тут дешевые проститутки
paypal casino uk
References:
https://jobsspecialists.com
online casino australia paypal
References:
https://alfacareers.com/employer/australian-online-casinos-that-accept-paypal-2025/
online pokies australia paypal
References:
sigorta.jobs
best online casino usa paypal
References:
https://jobsrific.com/employer/best-online-slots-to-play-in-2025-the-ultimate-guide-to-slots/
supplements that contain steroids
References:
millippies.com
legal steroids information
References:
timeoftheworld.date