暴力的過激派による偽情報拡散の実態は、これまで主流の偽情報研究の射程から外れがちだった。特に国家主導のFIMI(Foreign Information Manipulation and Interference)に焦点が当たりがちななか、ICCT(国際テロ対策センター)が2025年5月に公表した政策ブリーフ『Violent Extremist Disinformation: Insights from Nigeria and Beyond』は、このギャップを埋める意欲的な試みである。本稿では、同報告書の中核的な知見を紹介しつつ、偽情報が暴力的過激主義の中でいかに用いられ、何を目的とし、どのような影響を及ぼしているのかを詳しく検討する。
非国家アクターによる偽情報の本質的危険性
報告書の最大の貢献は、国家ではなく非国家アクター、特に武装過激派が偽情報をどのように戦略的に活用しているかを、実証的に明らかにしている点にある。調査対象となったのはイラク、ナイジェリア、セルビア、ジョージアの4カ国。中でもナイジェリアにおけるボコ・ハラム系の二派閥──ISWAP(イスラム国西アフリカ州)とJAS(ジャマーアト・アフリス・スンナ)──を軸に分析が進められている。
偽情報の内容として最も顕著だったのは、「民主主義否定ナラティブ」である。これは4カ国すべてに共通して観測された唯一のナラティブであり、過激派が民主主義体制を「西洋の腐敗」「不信仰」「偽りの秩序」として糾弾する点で一致している。ナイジェリアの事例では、選挙を「多神崇拝(shirk)」と断じ、参加者を「背教者」とみなすビデオが配信された。視覚的にも、ナイジェリア国旗や政治家と並列で米国のシンボルを配し、西洋民主主義との同一視を促す演出が施されていた。
完全な虚偽ではなく「文脈の歪曲」による戦略
調査対象となった383件の偽情報のうち、完全な虚偽は全体の6割にとどまり、むしろ8割以上が誇張や歪曲、あるいは誤解を誘発するようなミスリード情報で構成されていた。特にナイジェリアやイラクのような紛争地域では、現地報道が乏しいこともあり、過激派は実際の事件を「再構成」するかたちで、攻撃の戦果を過大に伝える傾向が顕著だった。死者と負傷者を一括して「死者10名」と記すなど、曖昧な表現が用いられる。動画でも、標的が特定できないまま発砲する場面だけを示し、「作戦成功」を主張する構成が多く見られた。
なぜナイジェリアでは動画が主流なのか
他国ではテキスト中心の偽情報が支配的であるのに対し、ナイジェリアでは動画が最多形式となっている。その背景には、識字率の低さと強固な口承文化がある。ナイジェリア北東部の識字率は全国平均(63%)を下回るとされ、これに対応するかたちでISWAPやJASは動画や音声を主要媒体として利用している。報告書によれば、ボコ・ハラムによる偽情報のうち、テキスト単独による発信はわずか16%に過ぎなかった。
また、Telegramなどの暗号化プラットフォームで発信された動画が、WhatsAppを通じて通信環境の不安定な地域でも再拡散される。最終的には、口頭伝承を通じて偽情報が「預言者の言葉」のように再解釈されるプロセスも報告されており、オンラインとオフラインのハイブリッド型拡散が際立っている。
「怒り」と「誇り」が動員を促す
偽情報が単なるプロパガンダにとどまらず、実際の暴力や勧誘へと結びつく要因として、報告書は「感情トリガー」に注目する。ナイジェリアの事例では、偽情報の86%が「恐怖」、67%が「誇り」、40%が「怒り」に訴えていた。恐怖は外部の脅威を過大に伝えることで住民の沈黙を誘い、誇りは戦果誇張によって組織内の士気を高め、怒りは敵対者──政府、宗教指導者、メディア──への敵意を煽るために使われる。
さらに、直接的な行動呼びかけも少なくない。JASが「憲法を捨ててコーランを受け入れよ」「国旗(緑白緑)を捨てよ」と語る動画は、国家制度からの離脱を明確に求めていた。
偽情報による“緩慢な制度破壊”
暴力的過激派による偽情報がもたらす影響は、即時の暴力や混乱だけではない。むしろ報告書が強調するのは、制度への信頼を徐々に浸食する“緩慢な破壊”である。政府や宗教指導者のみならず、市民団体やNGOまでもが「外国の手先」「スパイ」と中傷されることで、住民の協力が得られず、P/CVE(暴力的過激主義対策)プログラムが機能不全に陥るという。特に若者や女性の参加を得ようとする取り組みが、こうした偽情報によって妨害される構造は各国に共通して観測された。
介入の前提は「文脈理解」
報告書が最後に強調するのは、偽情報への対抗策は単なる情報訂正(デバンク)では不十分であるという点である。たとえばナイジェリアでは、SNSを主戦場とする西洋的アプローチは効果が限定的であり、むしろラジオ放送や地域指導者との連携といったローカルな戦術が不可欠とされる。
対策は以下の3層で構築すべきと提言されている:
- 一次介入:長期的レジリエンス構築(メディア教育、透明性向上など)
- 二次介入:脆弱地域への事前対応(感情的耐性、問題意識の形成)
- 三次介入:既に影響を受けた地域への個別支援(トラウマ対処型メッセージ、代替ナラティブの提示)
まとめ:暴力的過激主義の情報戦を見逃すな
本報告書が示すように、暴力的過激派による偽情報の拡散は単なる“副次的脅威”ではなく、それ自体が過激主義の戦略の中核をなす存在である。誇張、歪曲、感情操作を通じて社会的亀裂を深め、制度と市民社会の信頼を削ぎ、支配の空白を作り出す。その構造を理解せずして、情報空間の安全保障は成立しない。偽情報対策の議論において、国家主体だけでなく非国家主体の動向に目を向けることの重要性を、本報告書はあらためて強く示唆している。


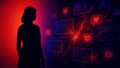
コメント
Das Publikum ist bunt gemischt und es macht Spaß, an den Slotmaschinen zu spielen.
Mit verschiedenen Tischspielen wie Blackjack oder auch Roulette
versuchen. Ja, Sie können in den Online-Casinos in Las Vegas um echtes Geld spielen. Auch hier gilt jedoch, verantwortungsvoll mit dem Glücksspiel umzugehen und nur bei seriösen Anbietern zu spielen. Auch hier ist
es wichtig, nur bei seriösen Anbietern zu spielen und verantwortungsbewusst mit dem Glücksspiel umzugehen.
Die meisten Casino-Resorts bieten auch spezielle Angebote für Nicht-Spieler und Familien an. New
York, San Francisco oder Chicago bieten zahlreiche Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten.
Wer den Trubel einer Großstadt sucht, aber nicht unbedingt nach Las Vegas möchte, kann auch andere Städte in den USA besuchen. Einige Casino-Resorts bieten auch Bungalows oder
Villen an, wie das Encore oder das Four Seasons, die einen privateren und exklusiveren Aufenthalt ermöglichen.
Eine der berühmtesten Attraktionen ist der Bobby’s Room, in dem sich Profi- und Amateur-Pokerspieler treffen. Las Vegas ist die größte Stadt im Bundesstaat Nevada,
und Sie finden dort Luxushotels mit verschiedenen Themen, aber vor allem ikonische und unvergessliche Casinos.
Besonders legendär ist Bobby’s Room, wo Pokerspieler auf höchstem Niveau antreten.
References:
https://online-spielhallen.de/bizzo-casino-cashback-ihre-ruckerstattung-leicht-gemacht/
Er erlaubt Online-Slots und Poker, während Tischspiele und Live-Casinos grundsätzlich verboten bleiben. Damit soll verhindert werden, dass deutsche Spieler mehr für das Spielen ausgeben, als sie sich leisten können zu verlieren. Außerdem sollten renommierte Softwareanbieter, transparente Bonusbedingungen und schnelle Auszahlungen vorhanden sein. Hier zu Spielen ist nicht strafbar, allerdings entfällt der offizielle deutsche Spielerschutz.
Solange man nicht versucht, Verluste einzuklagen, bleibt der deutsche Gesetzgeber ohnehin außenvor. Mehrfach wurde versucht, gegen Nutzer von Casinos ohne deutsche Lizenz vorzugehen. Anders als deutsche 5 Euro Einsatz Casinos haben seriöse Casinos ohne Einsatzlimit zum Beispiel eine Lizenz aus Curacao.
References:
https://online-spielhallen.de/evolve-casino-cashback-ihr-weg-zu-wochentlichen-ruckerstattungen/
We sort out top slot games that are highly rewarding. If you are looking for the best payout online slots,
you are on the right page. The best online slots at 7Bit guarantee an outstanding reeling action. We
recommend you only the best paying online slots that
guarantee a solid income.
Usually, the volatility is not explicitly specified in the specifications of bitcoin slot machines.
Immediately upon registration on the 7Bit website,
the player has the opportunity to receive a Bitcoin bonus and 100
free spins. Modern casino games can boast of many additional features.
Most online Bitcoin slots have special symbols such as Wild, Scatter, and Bonus.
Playing slots with cryptocurrency is legal,
even in countries where gambling is prohibited by local authorities.
But, some prefer to play bitcoin slots in which there are many different features.
New players who do not know much about slots should
start with Low Volatility slots and look at what percentage of RTP is in the slot.
By the way, volatility and RTP are the most important parameters that a
player who play slots with crypto should pay attention to.
And, in every online crypto casinos, this figure
will be identical for the same slots. Basically, all BTC
slots consist of three or more reels that
rotate from top to bottom and have additional features such as bonus mini-games.
References:
https://blackcoin.co/mind-boggling-facts-you-didnt-know-about-online-casino-gaming/
Because of these complaints, we’ve given this casino 17,427
black points in total, out of which 14,100 come from related casinos.
We currently have 10 complaints directly about this casino in our database, as well as 34 complaints about other casinos related to it.
In T&Cs of many casinos, we come across certain clauses,
which we perceive as unjust or overtly predatory. If a casino is included on a blacklist such as our Casino Guru blacklist, this could
hint that the casino has committed some kind of misconduct
towards its customers. To our knowledge, Fair Go Casino is absent from any significant casino
blacklists. Therefore, as we discovered some serious issues
with fairness of this casino’s T&Cs, we advise seeking a casino with fairer T&Cs or at least approaching this casino with caution.
Still, Fair Go Casino does not remain indifferent to other important aspects from the players’ perspective, such as security,
payments, bonuses and the availability of the casino on mobile devices.
The best casino bonuses are reserved for the most loyal players.
Regular players can take advantage of several consecutive free bonuses and promotions.
Launched in 2017, Fair Go has emerged as a premier online casino destination for Australian players.
Free professional educational courses for online casino employees aimed at industry best
practices, improving player experience, and fair approach to gambling.
We had explained to the player that casinos have the right to restrict or revoke bonuses and changed the disputed amount from A$3,000 to A$0 as no real funds were
deposited.
With round-the-clock customer service, smooth
mobile gaming, and rapid transactions, SkyCrown Casino distinguishes itself.
SkyCrown Casino invites Australian gamers to plunge into an exciting world of quality gaming pleasure.
Casino accepts players only over 18 years of age. Whether you use iOS or Android, you can access the entire Skycrown experience right in your browser —
no installation required.
SkyCrown is a fresh face in the online casino industry, having launched in 2022.
Dive into our expert review, crafted using a
comprehensive casino rating system, to discover more about
what this platform has to offer! As you accumulate points, you can climb the ranks and enjoy exclusive bonuses, cashback, and more.
Skycrown Casino rewards its loyal players through a VIP loyalty program.
Regular players can climb tiers, unlock cashback, free spins,
and get a bit more edge over time. You won’t waste time digging through broken links or weird game menus — everything
runs smooth across desktop and mobile. The live casino is
stacked too, with real dealers from Evolution and
Ezugi. Everything works straight away, and the vibe is clearly built for players, not just a flashy
homepage. The welcome bonus is generous and split across five
deposits, each with free spins and bonus cash.
References:
https://blackcoin.co/asino-play-online-casino-games/
Our streamlined registration process takes less than 2 minutes, getting you from
download to gameplay with minimal delay. It has been specially optimized for smartphones with various performance levels to guarantee
a smooth gaming experience without interruptions.
Players can enjoy free games and benefit from a variety of secure payment options.
Over 1,200 slot games from top providers including progressive jackpots
and classic favorites. The SkyCrown App Casino
for Android is lightweight and quick to download on virtually any device,
providing a premium gaming experience without compromising
on performance. Deposit and withdraw funds with ease using multiple payment methods tailored
for Australian players.
A quick sky crown login, and you’re ready to
hit the games — no lag, no drama, just smooth action from start to payout.
Real dealers, real-time action — roulette, blackjack, baccarat,
and game shows streamed in full HD. Logging in is simple — one click from
sky crown casino online login and you’re
ready to grab your next promo or spin the reels. The welcome
package includes up to five deposit bonuses, stacking up free spins and bonus cash
with each round.
References:
https://blackcoin.co/this-is-vegas-casino-review/
online casino australia paypal
References:
http://dwsm.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=273430
online pokies australia paypal
References:
https://page.yadeep.com/tanyabrace
online pokies australia paypal
References:
https://karierainsports.gr/employer/top-paypal-casinos-in-the-us-2025/
online casinos that accept paypal
References:
https://aidesadomicile.ca/employer/best-online-casinos-in-australia-top-casino-sites-for-2025/
online casino accepts paypal us
References:
https://chefstronomy.co.za/employer/newest-aussie-casino-sites/
online casinos that accept paypal
References:
https://okbolt.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=310077
online real casino paypal
References:
https://ftwjobfinder.com/companies/liste-bester-paypal-casinos-2025-aktuelle-situation-in-deutschland/
online casinos that accept paypal
References:
https://ipcollabs.com/companies/online-casinos-australia-best-aussie-casino-sites-of-2025/
casino with paypal
References:
https://noarjobs.info/companies/best-real-money-online-pokies-in-australia-for-december-2025/
online casino australia paypal
References:
https://swifthire.co.za/companies/best-new-online-casinos-australia-2025-recently-launched/
Alle neuen Spieler erhalten von unserem Casino einen besonders attraktiven Willkommensbonus, der oft aus einem Einzahlungsbonus und zusätzlichen Freispielen besteht. Das Casino bietet eine sichere und faire Spielumgebung und ist bekannt für seine zahlreichen Boni und Aktionen, darunter der begehrte NV casino bonus. Die Einzahlungsboni bieten Ihnen eine perfekte Mischung aus zusätzlichem Guthaben und Freispielen, sodass jede Einzahlung doppelt spannend wird. Promo-Codes bei NV Casino, einschließlich keine NV casino bonus code ohne einzahlung, wenn sie verfügbar sind, eröffnen Ihnen die Chance auf exklusive Boni und spannende Vorteile! Unser Casino bietet Spielern aus Deutschland die Möglichkeit, ohne Einschränkungen zu spielen, da wir nicht an OASIS oder LUGAS gebunden sind.
Wenn Sie Unterhaltung auf Casino.NV auswählen, erhalten Sie Zugriff auf moderate Roulette-, Blackjack-, Baccarat- und Pokertische. Das RNG-Tischspielangebot wird im Casino NV durch von Live-Dealern moderierte Spieltische ergänzt. Der Großteil unseres Spielangebots fällt in die Kategorie Online-Slots. Bleiben Sie auf dieser Seite und informieren Sie sich ausführlich über unser Angebot oder besuchen Sie NV.casino und starten Sie Ihren Spielspaß. Wir sind überzeugt, jedem deutschen Glücksspielfan etwas zu bieten. 2025 © Casinosdeutschlandonline.com.
References:
https://onlinegamblingcasino.s3.amazonaws.com/casino%20fast.html
Nichts ist verlockender, als einen kostenlosen 10 Euro Bonus ohne Einzahlung im Online Casino zu erhalten. Hier muss das Bonusgeld zunächst freigeschalten werden. Hierzu gehören die Lizenz, der Kunden-Support, die Spieleauswahl sowie die Bonusangebote.
Zum Beispiel mit Freispielen oder einem Handy Casino Echtgeld Bonus ohne Einzahlung – exklusiv für mobile Nutzer. Statt Freispiele gibt es hier echtes Bonusgeld (meist 5–10 €), das Sie auf mehreren Slots oder sogar Tischspielen verwenden können. Insgesamt ist die Seite übersichtlich und gut durchdacht, sodass sowohl neue als auch erfahrene Spieler sich wohlfühlen können, wenn sie bei VulkanSpiele online spielen. Diese wöchentliche Ausstellung präsentiert Ihnen die besten von allen aktuellen Freispielen mit und ohne Einzahlung, die in Stakersland angeboten sind. Man kann auch mit Echtgeld spielen und mehr Freespins, Casino Bonus ohne Einzahlung und Promotionen – inklusive unserer Monday Reload Packung – in vollem Umfang nutzen.
References:
https://onlinegamblingcasino.s3.amazonaws.com/zet%20casino.html
References:
Test e and anavar before and after pics
References:
https://postheaven.net/carpqueen05/anavar-before-and-after-what-to-expect-from-this-popular-performance-enhancer
References:
Pittsburgh casino
References:
https://lassiter-beebe-3.blogbright.net/contact-us-wd-40-australia
steroid stanozolol
References:
https://fakenews.win/wiki/7_proven_benefits_of_taking_a_testosterone_booster
different steroids and what they do
References:
https://marvelvsdc.faith/wiki/Clenbuterol_Wirkung
steroids before and after 1 month
References:
https://broch-munk.technetbloggers.de/buy-clenbuterol-online-safely-from-a-legal-supplier
where did anabolic steroids originate from
References:
http://king-wifi.win//index.php?title=gardenknee50
References:
Before and after anavar cycle
References:
https://mapleprimes.com/users/thumbspace7
dicks on steroids
References:
https://sciencewiki.science/wiki/HGH_Human_Growth_Hormone_Supplements_for_Men
References:
Anavar results female before and after
References:
https://pediascape.science/wiki/Buy_Anabolic_Steroids_USA_Domestic_Shipping_Lab_Tested