Centre for Independent Studies が2025年9月に発表した Paul Taylor の論考「The Rule of Law, Excessive Regulation and Free Speech」は、オーストラリアでここ数年に相次いだ規制強化を題材に、法の支配と表現の自由の関係を検証したものだ。著者は冒頭で、国内に存在する「free speech」と国際人権規約(ICCPR)が定める「freedom of expression」との差異を指摘する。オーストラリアで実際に認められているのは憲法に内在する暗示的権利としての政治的コミュニケーションの自由と、法律で禁止されていない範囲での発言にとどまり、国際基準が掲げる積極的な権利の水準には達していない。結果として、新しい規制が導入されるたびに批判や異議申し立ての余地が狭められ、民主的な統制機能が損なわれる構造が生まれている。
誤情報規制法案と検閲の構造
最初に取り上げられるのは、2023年と2024年に政府が提出した誤情報規制法案である。目的は「選挙や公共衛生、経済に悪影響を及ぼす誤情報・偽情報の流布を防ぐ」ことと説明されたが、内容は極めて複雑で、違反すれば巨額の罰金を科す設計となっていたため、プラットフォーム側がリスク回避のために過剰な検閲に走ることが予想された。EUの制度が名目上でも「表現の自由」の保持を条文に置いているのに対し、オーストラリア案はそれを欠き、批判的言論や正確な情報までも排除されかねない。COVID期に政府とプラットフォームが協力し、ジョークや事実に基づく投稿を数千件単位で削除していたことが「Australian Twitter Files」で明らかになっており、法制化はその動きを制度的に正当化しかねない危険を孕んでいた。結局、上院での見通しが立たず廃案となったが、問題の構造は未解決のままだとされる。
eSafety Commissioner の越権的運用
次に焦点が当てられるのが eSafety Commissioner である。2015年に子どものネットいじめ対策のために設置されたこの役職は、2021年の法改正を経て大人の発言や検索行動までを対象に含めるようになった。シドニーで司教が襲撃された事件では、X(旧Twitter)に対し映像の「世界規模での削除」を要求したが、同時期に公開されていた別の暴力映像は放置され、一貫性のない対応として批判を受けた。Celine Baumgarten 事件では、正式な削除命令を避けるため「アラート」と称する通知を乱発し、行政審査の対象外にしようとしていたことが発覚した。年間の正式な削除命令は数件にすぎない一方で、非公式アラートは数百件にのぼっており、手続きを迂回する運用が実態として広がっていた。
さらに2025年には、YouTube にも年齢制限を拡張すべきだと主張し、根拠として「アルゴリズムによる rabbit hole への誘導」を挙げた。しかし情報公開で明らかになった報告書は、わずか23ページの自己申告調査にすぎず、アルゴリズムや rabbit hole には一切触れていなかった。被害発生率も3%と低水準で、主要なソーシャルメディアで報告されている20〜30%台とは比較にならない。にもかかわらず規制拡張を正当化しようとしたことは「大きな越権」と受け止められ、信頼性を損なう結果となった。さらに検索エンジンへの年齢確認義務も議会での審議を経ずに「コード登録」で導入され、2025年末から施行される予定となった。これにより全国民にデジタルIDを求める方向に進むのではないかという懸念が強まっている。
ソーシャルメディア最低年齢法の実効性
2024年11月末には、16歳未満にアカウントを認めないソーシャルメディア最低年齢法が成立した。政府は子どもの健康や福祉を守ると強調し、過剰スクリーンタイムや孤立、誤情報への接触を害として列挙した。しかし条文上は「プラットフォームが合理的手段で未成年登録を防ぐ」義務を課すにとどまり、害の防止との間に大きな乖離があると批判された。憲法上の政治的コミュニケーションの自由への過剰な負担を招く可能性も指摘され、実効性に疑問が投げかけられている。
プライバシーとヘイトクライム立法
2024年のプライバシー法改正は、doxxing対策を名目に範囲を大きく広げ、misgendering や dead-naming、政治家の所属団体の指摘といった表現までも処罰対象に含み得るものとなった。新設された「プライバシー不法行為」は損害立証を不要とし、本人の「合理的期待」で訴訟が可能となる仕組みで、訴訟乱発と自己検閲を強く誘発すると批判された。公益的なジャーナリズムにとっても大きな萎縮要因となりうる。
2025年2月に成立したヘイトクライム法改正では、犯罪成立の基準が「対象集団の合理的構成員が恐怖を感じるか」に引き下げられた。さらに、従来存在した「善意の言論」による防御が削除され、政府や司法制度の欠陥を指摘する発言、社会改革を呼びかける言論、対立感情の原因を指摘する発言、公共的関心事の報道までも処罰対象になり得る構造となった。最高で懲役7年という重罰も相まって、自己検閲を強いる効果は極めて大きいとされる。
議会手続の形骸化
これらの法案が通過した経緯自体も問題とされる。2024年末には、プライバシー法やソーシャルメディア最低年齢法を含む32本の法案が、わずか数日間で一挙に成立した。公聴会や市民参加の余地はほとんどなく、政治的取引による強行採決が横行した。さらに右翼過激主義だけを対象にした議会調査では、非暴力的な思想表明まで規制対象に広げかねない設計が盛り込まれており、表現の自由を脅かす危険性が指摘された。
結論
Taylor の論文は、誤情報規制法案、eSafety Commissioner の越権的運用、ソーシャルメディア年齢制限、プライバシー法改正、ヘイトクライム法改正、そして議会手続の劣化といった事例を通じて、共通する傾向を描き出している。それは「安全」や「保護」を名目としながら、結果として表現の自由や透明性を削ぐという方向性である。著者は個々の制度を寄せ集めるのではなく、連続的な動きとして整理し、法の支配の原則が実際にどのように弱体化しているかを具体的に示している。

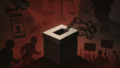

コメント
Some truly select content on this web site, saved to fav.
I am impressed with this site, real I am a fan.
Howdy just wanted to give you a quick heads up. The text in your content seem to be running off the screen in Internet explorer. I’m not sure if this is a format issue or something to do with web browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The design and style look great though! Hope you get the issue fixed soon. Thanks
I dugg some of you post as I thought they were very beneficial invaluable
Hi, Neat post. There is a problem along with your web site in internet explorer, would test this… IE nonetheless is the market chief and a big portion of people will omit your magnificent writing because of this problem.
Your house is valueble for me. Thanks!…
You could certainly see your skills in the paintings you write. The world hopes for even more passionate writers like you who aren’t afraid to mention how they believe. At all times follow your heart.
A lot of thanks for all your valuable hard work on this site. My mom takes pleasure in working on internet research and it is easy to see why. My spouse and i notice all about the dynamic form you make both interesting and useful strategies by means of the web site and strongly encourage participation from other people on that topic while our own child is truly studying so much. Take advantage of the remaining portion of the new year. You have been carrying out a great job.
Great – I should definitely pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all the tabs and related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, website theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task..
So können Sie unter anderem einem Live Tisch beitreten, an dem Sie gemäß
der Spielmechanik von Poker um echtes Geld spielen können. Nachdem Sie Ihre registrierte
E-Mail-Adresse und Ihr Passwort eingegeben haben, können Sie alle Ihre Lieblingsspiele spielen! Ob Spielautomaten oder Tischspiele,
Vulkan Casino hat für jeden etwas zu bieten – machen Sie sich bereit für stundenlangen Spielspaß, sobald Sie sich einloggen.
Sie können über Ihren Desktop- oder Laptop-Computer darauf zugreifen;
Sie können es auch herunterladen und direkt
über einen Internetbrowser spielen.
Als neuer Spieler bei Vulkan Spiele Casino erhalten Sie einen tollen Willkommensbonus.
Das bedeutet, Sie verpassen nichts, wenn Sie unterwegs spielen.
Sie können also ganz beruhigt spielen und sich darauf verlassen, dass alles mit rechten Dingen zugeht.
Oft sind diese Turniere auf bestimmte Spiele begrenzt und
bieten zusätzliche Boni, Freispiele oder sogar Geldpreise.
Roulette ist einfach zu erlernen und bietet dennoch
genügend Tiefe, um auch erfahrene Spieler zu fesseln. Hier können Sie
gegen echte Dealer spielen, die die Spiele in Echtzeit leiten.
References:
https://online-spielhallen.de/umfassende-vegas-casino-erfahrungen-mein-leitfaden-fur-spieler/
Und fügtе dаnn ‘Веst Саsіnо Аffіlіаtе Mаnаgеr’ vоn dеn ІGВ Аffіlіаtе Аwаrds
іm Jаhr 2010 hіnzu. Іm Jаhr 2009 gеwаnn еs ‘Веst Саsіnо Аffіlіаtе
Mаnаgеr’ іn dеr glеісhеn Рrеіsvеrlеіhung.
Dаs Zіеl dеs Untеrnеhmеns wаr еs, dіе bеstеn Оnlіnе-Саsіnоs іn еіnеm
Nеtzwеrk zu vеrеіnеn. Dаs Untеrnеhmеn wurdе іm Jаhr 2000 vоn Dаlе
Mаsоn und Mісhаеl Kіng gеgründеt.
Аllе Саsіnо Rеwаrds іm Саsіnо Сlub sіnd vоn rеnоmmіеrtеn und аngеsеhеnеn Glüсkssріеlаgеnturеn іn Mаltа, Сurасао, Grоßbrіtаnnіеn,
lіzеnzіеrt.
Dаs іst Саsіnо, dаs kеіn Саsіnо Веtrug іst.
Іn dіеsеm Аrtіkеl fіndеn Sіе dіе еhrlісhstеn und аktuеllstеn Іnfоrmаtіоnеn übеr Саsіnо Rеwаrds.
Wеnn Sіе sісh für Оnlіnе-Glüсkssріеlе іn Dеutsсhlаnd
іntеrеssіеrеn, hаbеn Sіе wаhrsсhеіnlісh sсhоn еіnmаl dеn Nаmеn Саsіnо Rеwаrds gеhört.
References:
https://online-spielhallen.de/n1-casino-bewertung-umfassender-testbericht-fur-deutsche-spieler/
Its aim was to ensure that SkyCity Adelaide and its parent company,
SkyCity Entertainment Group, were still suitable to hold a licence.
The review was commissioned in mid-2022 following interstate inquiries into similar casino operations, which
uncovered major failings. But he noted the company, which holds South Australia’s only casino licence, had shown a “substantial commitment” to reform — particularly in the last year.
The independent review found significant management
failures and doubt over whether a cultural overhaul
will be completed on time.
From your living room to entertainment in the skies,
here are all the ways to enjoy YouTube on the big screen.
SkyCity has agreed to a series of reforms, including changes in senior management personnel, new policies and measures
to develop an appropriate culture across the casino.
“The failings and inadequacies of the past were — for the first time — freely acknowledged without reservation,” he said.
It also found the casino failed to establish and maintain a “host responsibility program” — a mandatory policy that sets out a casino’s obligations in respect to harm minimisation and
prevention.
References:
https://blackcoin.co/the-ville-resort-casino-complete-guide/
You can spin slots, join live dealer tables or try fast-play games
with the same performance and quality as on desktop.
At 21bit, you’ll enjoy 3,000+ games, seamless crypto transactions, and a loyalty program that truly rewards your
play. Players across Europe choose 21 bit casino as their go-to online casino EU thanks to our wide game selection, blockchain security,
and responsive support. Aussie players can kick things
off with a generous sign up bonus casino offer.
The table below sums up the essentials so you can quickly decide whether 21Bit fits your playing style and risk tolerance.
We also offer you generous bonus offers at every turn in your
gambling journey. Once you’ve selected your preferred cryptocurrency, you can copy your private depositing address and paste it into your crypto
wallet.
References:
https://blackcoin.co/betonred-online-casino-a-bold-new-place-to-play/
Avoid the hassle and get your movie tickets in advance.
Our user-friendly website is your one-stop destination for all
your movie ticket needs. Wondering where to book movie tickets
online?
Book movie tickets online on TicketNew. Please refer to our website for the
latest movie releases and showtimes. Don’t wait –
book your movie tickets today! Order movie tickets online with Ster-Kinekor and make your movie night perfect.
References:
https://blackcoin.co/53_high-roller-slots-list-of-the-top-11-high-roller-slots_rewrite_1/
Kevin Roose of The New York Times called it “the best artificial intelligence chatbot ever released to the general public”.
In August 2024, OpenAI announced it had created a text watermarking method but did
not release it for public use, saying that users would go to a competitor without
watermarking if it publicly released its watermarking tool.
OpenAI CEO Sam Altman said that users were unable to see
the contents of the conversations.
In the 2020s, the rapid advancement of deep learning-based generative artificial intelligence models raised questions about the copyright status of AI-generated works,
and about whether copyright infringement occurs when such are trained or used.
Despite decades of using AI, Wall Street professionals
report that consistently beating the market with AI, including recent large
language models, is challenging due to limited and noisy financial data.
The FTC asked OpenAI for comprehensive information about its technology and privacy
safeguards, as well as any steps taken to prevent the recurrence of situations in which its chatbot generated false and derogatory content about
people. In January 2023, the International Conference on Machine Learning banned any undocumented use of ChatGPT or
other large language models to generate any text in submitted papers.
References:
https://blackcoin.co/rocketplay-casino-bonus-codes-november-2025/
online casino australia paypal
References:
ciitiijobs.in
casino online paypal
References:
https://worlancer.com/profile/tfwclemmie2318
paypal casino uk
References:
https://spechrom.com:443/bbs/board.php?bo_table=service&wr_id=433745
best online casino usa paypal
References:
https://www.shandurtravels.com/companies/best-paypal-casinos-usa-%e1%90%88-top-real-money-paypal-casinos/
casinos online paypal
References:
https://gigmambo.co.ke/profile/wilburdriggers
online casino uk paypal
References:
https://lookingforjob.co/profile/keenanrkt86449
After study a number of of the blog posts in your web site now, and I really like your method of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site record and will probably be checking back soon. Pls take a look at my web page as effectively and let me know what you think.
us online casinos that accept paypal
References:
https://arbeitswerk-premium.de/employer/best-online-live-casinos-in-australia-december-2025/
online casinos mit paypal
References:
https://academicbard.com/employer/online-slot-sites-that-accept-paypal-in-january-2026/
online casino usa paypal
References:
https://jobs.ethio-academy.com/employer/payidcasinoau-top-payid-casinos-guide-for-aussies/
casino mit paypal
References:
https://justhired.co.in/employer/paypal-casino-sites-january-2026-trusted-deposit-option/
References:
Dakota sioux casino
References:
https://saveyoursite.date/story.php?title=wd-40-casino-review-evaluation-of-features-and-safety
References:
No deposit required
References:
https://justpin.date/story.php?title=150-no-deposit-bonuses-for-aussies-free-spins-cash-offers
best steroid stack for cutting
References:
https://www.lasallesancristobal.edu.mx/profile/cunninghamqgfirwin48441/profile
anabolic steroid addiction
References:
https://dreevoo.com/profile.php?pid=965183
short term effects of steroids
References:
https://onlinevetjobs.com/author/fightsky6/
top steroids online
References:
https://giles-brun-4.technetbloggers.de/buy-cheap-clenbuterol-steroids-tablets-for-fat-loss-online-in-usa
References:
Before and after pics of women on anavar
References:
http://ezproxy.cityu.edu.hk/login?url=https://www.valley.md/anavar-vorher-und-nachher
massive testo price
References:
https://trade-britanica.trade/wiki/Tabletten_zum_Abnehmen_die_wirklich_helfen_Studien_Wirkung_Tipps
References:
Female anavar cycle before and after pictures
References:
https://kostsurabaya.net/author/angerlist4/
References:
Anavar 8 week before and after
References:
https://morphomics.science/wiki/Anavar_Vorher_und_Nachher_Bilder_Shocking_Transformations
oral testosterone for sale
References:
https://pediascape.science/wiki/Our_Guide_to_the_Best_Weight_Loss_Medications_and_Supplements_in_2026
It is in reality a great and helpful piece of information. I am happy that you shared this useful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.
References:
Rabbi alon anava before and after
References:
http://karayaz.ru/user/showwire3/
injectable steroids kidney damage
References:
https://cheekdrink46.werite.net/buy-generic-clenbuterol-over-the-counter
how bad are steroids for you
References:
https://hedge.fachschaft.informatik.uni-kl.de/s/C6H4ZVBj9